

こだまする光の中で爆竹の踊り乱れる涙も乾く
無に向かい一筋走る爆竹の歓声あげて現よ去らす
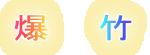
「ボン」という鈍い音がしたと思うと、福来のおじいちゃんの新しい綿入れの右ポケットには一輪の綿の花が咲いた。見るとポケットの縁が焦げ、真っ白な花びらが灰色の布地から浮びあがり、立体感のある油絵のようにも見えた。縁のには方にちかちか点滅する赤い斑点が蚕のように白い花を蚕食している。おじいちゃんは慌てて手でそこを叩き、火を消そうとした。花は押し花になってしまった。
その花は、ポケットに入っていた「二両響」の仕業だった。「二両響」とは長さ15センチぐらいのロケット型の爆竹で、いろいろな爆竹の中で親分的な存在であった。点火されると、一回目の爆発で2、30メートの高さまで飛び、空中で更に大きな音を立てて玉砕する仕組みとなっている。普通は地面に置いてやるのだが、肝試しをしようと手の上でやる子もいた。また、下にレンガなど敷いて、斜めにして、ベランダにいる子を狙ってやる子もいた。
しかし、その「二両響」は空中で爆発するはずなのに、なぜ、おじいちゃんのポケットで爆発しただろうか。それはこういうわけだった。
誰かが打出した「二両響」は空中に高く飛んだが、うんともすんとも言わず、あっけなく地面に引き還してきた。
この世によっぽど未練があるのか、壮絶な死は何も役に立たないと悟ったのか、そのどちらかなのだろう。しかし、すぐその残骸を拾う子はいなかった。突然生き返って、暴れ出さないとも限らないからだ。しかし、福来のおじいちゃんはそれを素早く拾い、ポケットに入れた。「二両響」をばらして、中の火薬を取り出し、孫のため自家製の爆竹を作るつもりだったのだ。それが、新しい綿入れのが遭遇した悲惨な運命の導火線だった。
福来の家は六人兄弟だった。父方の祖父母も一緒に住んでいるが、部屋は10平米ぐらいしかなかった。彼のお父さんは労働者で、給料が安く、お母さんは仕事がなかった。生活は苦しく、子供の名前に「福来」とつけても、福はなかなか来ない。それどころか、女の子が次から次と生まれてきて、生活は一層苦しくなった。一家で紙箱作りの内職をやっても賃金は知れたもので、倹約家のお母さんはいるおかげで子供達はすくすく育った。おじいちゃんはよくごみ拾いに出かけ、拾ったものを分類して、廃品収購站(不要品回収所)に売って家計の足しにしていた。「ごみ拾い」の渾名がついても一向に気にせず、家族のために精を出していた。僕の物心がついてから福来のおじいちゃんは、ずっと繋ぎはぎだらけの服を着ていたが、初めて新しい服を着た姿を見たかと思ったら、驚く間もなく、おじいちゃんのポケットに花が咲いてしまったのだ。その可笑しさに思わず笑ってしまったが、おじいちゃんの悲しそうな後ろ姿を目にして、後味が悪かった。孫のための勇ましい行動は、咲くべきではない綿の花となり、空しく散った。おじいちゃんの後ろ姿は子供達の無邪気で残酷な笑いの波に呑み込まれた。
しかし、おじいちゃんの何年かに一回しか新調できないこの 新しい綿入れは、お正月に撮る「全家福」の晴れ舞台から姿を消すことはなかった。最前列の真中に座り、右膝に孫娘を坐らせているおじいさんの笑顔は幸せそのものだった。
綿の花が咲いた日から30年あまりの春夏秋冬が過ぎた。
先日、僕はほぼ20年ぶりに故郷で旧正月を迎えるため天津に帰った。大晦日に従兄弟夫婦の招きで、両親と一緒に彼らの家に行った。
従兄弟は「爆竹をやる?」と聞いた。一瞬タイムマシンに乗って十何年前に戻ったような気がした。心中やるかどうか決め兼ねているのに、「やるやる」という言葉が口をついて出た。彼が買ってきたのは「鞭砲」と呼ばれている爆竹で、結婚式や開店祝い(そう言えば葬式も)よく使われている、鞭の形をしている長い爆竹だった。包装紙は大変立派になったものの、その中身は相変わらず鮮やかな赤だった。
小さいとき、その「鞭砲」は丁寧に解いて、バラバラにし、我ら腕白少年の「爆竹合戦」の格好の武器にしたものだ。不良はタバコで、そして、不良候補(補欠)や我ら「善良」な子供たちは線香で爆竹に火をつけ、10メートルぐらい離れている敵に思い切って投げつける。敵陣で開花した小さな爆竹は、吾らに大きなスリルを満喫させ、その響きは単純でありながら、あの時代に聞き飽きた「毛沢東語録」「八個様板劇」と違うリズムとメロディーがあるだけに、余計に幼い琴線に触れた。
爆竹合戦をやりたいと思った。しかし、二人しかおらず、従兄弟を敵に廻すわけにはいかないし、眼科の先生のお世話になるのも格好が悪いので、やめることにした。
何十年ぶりかに爆竹に火をつけた。アメリカ映画の「タイムトラベル」のワンシーンのようだった。
爆竹は昔の単純な作りと違って、クライマックスが来るように作られている。あの最後の一発からもたらした静寂な一瞬は、死の喜びさえ感じさせる。
地面に桜の花びらのような爆竹の残骸をしばらく見ていたら、従兄弟の娘が「ご飯できたよ」と呼びに来た。
大宴会が始まった。従兄弟の奥さんは腕を振舞って、何品もの料理を作ってくれた。テレビのカウントダウンが始まった。それと同時に外の爆竹の音が一段と激しく響いた。
大地を震撼する空気の震え、無の世界に連れ込まれそうな火薬の香り、そして、星と月の輝きを失い、ただただその無としか言いようがない時空を彷徨う魂、何も考える必要も感じられず、身も、魂も無心の境地を行き来する。ジャズのリズム、バイオリンの調べ、音楽に陶酔する心地よさ、寒々とした夜空の下で一抹の暖かさに包まれ、刻々と変化している空の色を眺め、新年を迎える前奏曲に聴き惚れる。
しばらくすると、爆竹の音がピタット止まった。皆餃子を食べる時間だった。
それまで静かに「かいてんばん」に寝ていた餃子は、爆竹に起され、白い花が咲き乱れる鍋の中で湯気のベールに覆われ、思う存分に踊り出した。鮮やかで軽快な「輪廻転生」の舞だ。
爆竹のような人生も一つの選択、いや、選択させられる人生の一つだと思える。静かな「春蚕到死方尽、蝋燭成灰涙始干」も立派な終焉だが、爆竹のような華やかな死に方も人生の舞台を退場する仕方の一つではないだろうか。
今は、多くの都市ではいろいろな理由で爆竹は禁止になっている。天津でもいずれ禁止になるだろう。爆竹は、あの無邪気な少年時代にタイムトラベルさせてくれ、人の心を震えさせる感動を与えてくれる。そして、なりよりも、僕に忘れかけた福来のおじいさんの優しい笑顔を見せてくれる魔法の道具である。
爆竹合戦は記憶の中にだけ繰り広げられるだろう。爆竹なしの新年は、なんとしても切なく、虚しい。