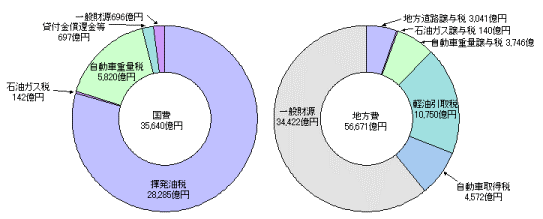道路特定財源問題についての私見
安部政権の重要課題としての「道路特定財源の一般財源化」が世間を賑わせている。
最近の報道では、 財源に余剰が出た場合に、その分を一般財源化の方向で決着が付きそうである。
この問題も郵政民営化における郵政族と同様に、道路族と呼ばれる族議員の反撃に会って事態は難航しそうであったが、先の小泉前総理の国会運営方法(衆議院解散)や、安部新総理のリーダーシップの不足もあって、両者打開点を見出す方向で 決着したようである。
社会環境が変化している中にあって、ここでも既得権を守ろうとする集団の政治姿勢に、うんざりしているのは私だけだろうか?
「余剰が発生しているのであれば暫定税率を下げるのが先決だ。」「受益者負担の原則に反する。」「ガソリン税を払っているのに消費税を払うのは税の二重徴収だ。」とか、この問題についてマスコミや評論家の間で様々な議論が展開されている。
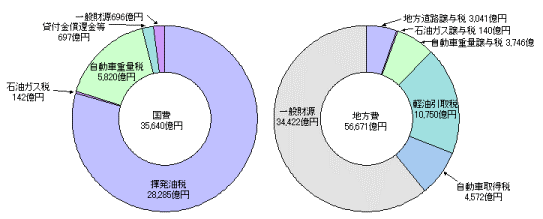
現状を把握する為に上図をご覧頂きたい。これは、昨年度の道路整備に費やされた財源の実績である。
ご覧のように、特定財源以外に約3,5兆円が一般財源から支出されている。これは国が管理する道路特定財源とほぼ同額である。
問題はこの国が管理する「道路特定財源」具体的には、「揮発油税」及び「自動車重量税」に在ることが判る。
何のことは無い、 国の予算を地方がおねだりしている構図がここでも見えてくる。 地方交付税と同様、国が地方に対して発言力を強化する枠組みは、これには留まらないが、過去の国全体が貧しかった時代の枠組みが綿々と続いている現状がここにもある。 地方分権は何時になったら実現するのだろうか?
尤も、最近の相次ぐ知事の官製談合事件は「大丈夫かいな?」と思う反面、国(中央官僚)の地方分権に対する弾圧の姿勢が見え隠れするが。ここでも官僚の保身が象徴的に現れている。
話が少しそれたが、「道路特定財源」が受益者負担の原則により道路のみに使用が限定されているのであれば、なぜ地方費の一般財源が道路費用に使用されているのか?」
細部に目を転じれば、種々の問題が見えてくるが、それでは事の本質を見誤ることになる。
問題は、国、地方において現在の借金を如何に、次世代に残さないか、が最大且つ緊急の状況にある時に税の公平性、透明性を確保しつつ、如何にこの借金状況を解消するかにある。
以前、塩爺(元塩川財務大臣)が「母屋(一般財源)が借金で茶漬けを食っているときに、離れ(特定財源)ではすき焼きを食べている。」と発言し、特定財源の課題を見事に表明されていたが、今、この議論が再燃しないのは不思議と言うしかない。
また、今後の消費税アップの理由を高齢化社会に対応する為の財源として「特定財源化したい」旨の発言があったが、私は全ての税を「一般財源」にすべきであると判断する。
その理由は、税の公平性、透明性を確保する上で、その使用について選挙で選ばれた議員によって決定されるべきであると判断するからである。「特定財源」の最大の課題は、この公平性、透明性 が現状では確保されていないからである。
「何に、いくら使うか」 納税者にとっては、これが現政権を評価する最重要な基準となる。民主主義が発展する為には、国民自らがもっと政治に関心を持つ事が必要であり、「政治家の質が悪いのは、国民の質が悪いからである。」とは、よく言ったものである。
増税の手段として発生してくる「特定財源」や、その一方で官僚の天下り先への税金の垂れ流しの現状を放置する現政権は、一体何を考えているのか。
「自分さえ良ければ」の発想が蔓延している状況が、今の日本の政治を体現していると言っても過言ではない。