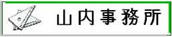|
| こんな場合には 必ず遺言書をお作り下さい。 |
子供がいない場合 相続人が存在しない場合 内縁の妻や未認知の子供が存在する場合 生前お世話になった人に財産を贈りたい場合 遺産相続で争いが起こりそうな場合 |
| 贈与はメリットがあるんですか? |
相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減されます。一度に多額の贈与をすると重い贈与税がかかりますが毎年120万円づつ贈与すると。 ※わざわざ110万円ではなく120万円にするのは、申告して納税しておくと贈与の実績がつくられ、のちに税務署から贈与そのものを否認されないための知恵です。ちなみに贈与税は、基礎控除を差し引いた10万円の税率10%ですから1万円です。 |
|
生前贈与? 相続時精算課税制度とはどんな制度ですか? |
いわば 生前相続 のような制度です。 この制度を選択すると、2500万円までは贈与税を支払うことはなく、これを超える部分について、一律20%の贈与税を納めることになります。そして相続発生時に、その贈与価格を相続財産に加算して相続税を計算します。 ただし、この贈与価格はその贈与時の価格によります。なお、既に納付した贈与税額は相続税から差し引かれます。 要件は60歳以上の親から20歳以上の子(父母又は祖父母から20才以上の子又は孫)への贈与であること、年齢はいずれも贈与の年の1月1日現在です。また、その人数に制限はありません。 適用を受ける人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、同制度を選択する旨の「選択届出書」、「戸籍謄本等の関係が分かる書類」を「贈与税の申告書」に添付して税務署に提出しなければなりません。 |
| 遺産もあれば、借金もあります、どうしたらいいですか? |
限定承認という手法があります。 また限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に提出し、限定承認の申述をしなければならない。 |
| 贈与か遺言か相続放棄?どんな方式がありますか |
今では相続人は共同で相続する建前になっていますから、完全な方法というものはありません。贈与か遺言か相続放棄の3つの方法があります。 1. 生存中に贈与してしまう方法があります。農地の場合は農地法の許可を要すること、相続の場合と比べ贈与税が高いことの難点があります。 2. 遺言で決めておく方法があります。遺言書は「相続分(割合)の指定」と「分割方法(土地は誰に、建物、現金は誰に)の指定」との2つの方法があるといえます。また、遺言書には「自筆証書」、「公正証書」、「秘密証書」の3種があります。それぞれ、その形式は法律で定まっています。令和2年には各法務局で自筆証書遺言書保管制度が始まり、法務居に保管して頂くことで検認が不要となり、更に紛失の恐れもありませんので、公正証書と比較は出来ませんが利用しやすくなりました。 3. あなたの死後に相続人に相続の放棄をしてもらうように頼んでおく方法があります。放棄は、死後3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申述書を出さねばなりません。 |
| 相続に必要な書類は何ですか? |
相続登記に必要な書類は ・ 死亡された方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 ・ 相続人の戸籍抄本 ・ 相続人の印鑑証明書、住民票 ・ 固定資産税評価証明書 ・ 残高証明書 などが必要になります。 |
| 相続人と相続順位について教えてください。 |
相続財産の分配にはルールがあります。配分の割合は民法で決められています。一般に「遺族に配偶者と子供がいるケース」では、配偶者が遺産の2分の1を相続し、配偶者に配分された以外の遺産を、子供の数で均等に配分します。 ・ 配偶者は例外なく相続人になります。 ・ 配偶者と子供がいないときに限り、後順位である親や兄弟姉妹が相続します。 |
| 相続税の申告期間は?相続税はどれくらいかかりますか? |
相続税の申告書提出期限と納付税期限は、相続人が、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
申告書の提出先は、被相続人の死亡のときの住所地の所轄税務署です。 相続人が全員で共同して1つの申請書を作成し、連署で提出することが原則です。このように共同提出が原則です。 相続または遺言によって贈与を受けた人は、死亡した人の総財産額が、課税最低限(3000万円+法定相続人×600万円)以下の金額であれば、申告する必要はないのですが、そうでなければ、申告する義務が生じます。(申告は提携先の税理士事務所で致します) 申告が必要な場合は期限内に必ず処理してください、場合によっては過小申告加算税、重加算税、懲役や罰金の刑事罰まで課せられることもあります。 |