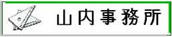|
| 収集運搬業の許可をとるのに必要な書類は? |
新規(更新)許可申請 1. 安全に産廃を運搬できる車両等が必要であること。 2. 関係者は、禁治産者及び関連法規の違反者等が排除されていること。 3. 経営者(法人の場合は、原則として登記簿上の役員)が知事等の認定講習会の受講終了証の添付が必要なこと。 4. 許可の有効期限は、5年間であるが、終了前に更新許可の手続きをしなければ当然失効となります。 なお、講習会は、産廃の運搬課程「新規許可」・「更新許可」と特別管理の運搬課程「新規許可」と「更新許可」の4種類に分かれています。 ・運搬課程新規許可…行政機関に新規許可申請をするときに添付するもので、受講後5年間のみ使用できます。 ・運搬課程更新許可…許可を受けた行政機関に更新申請をするときに添付するもので、その許可期限満了の2年以内に受講すること。 |
| 認定講習はどんなものですか? |
認定講習の受講 1. 講習会は、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが知事等の指定を受けて各地で実施されています。年間スケジュールがあり、何時、何処でも受講できるわけではありません。 また、許可申請人(法人の場合は、業務を行なう役員1名)が受講しなければならないとされています。 2. 受講は、各地域の産業廃棄物協会が受付窓口であり、地域振興局又は窓口の協会にあらかじめ受講資料を請求し、申込をすることになります。 |
| 事業者とはどんな人ですか? |
事業者(法第12条)とは、事業を営んでいる全ての人が該当します。 事業者は、自らの責任で産業廃棄物(以下「産廃」という。)を処理基準に従って適正に処理しなければなりません。 しかし、自分の施設で産廃を適正に処理できる事業者は、極く稀で殆どの事業者は許可業者に委託してその責任を果たすことになりますが、違反すると5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰則があります。 従って、産廃を委託して処分する場合にも違反が無いように共通事項を参照してください。 |
| 産廃を保管する土地にも規則があります。 |
保管基準 産廃を委託処分するまでは、次の保管基準を守らなければならない。 ① 保管場所から、廃棄物の飛散流出・地下浸透・悪臭の防止、ねずみの生息・はえの発生防止等必要な措置を講ずること。 ② 保管場所は、構造耐力上安全な「囲い」(道庁指導高さ1.5m以上)をすること。 ③ 保管場所には、その旨の「表示」をすること。 |