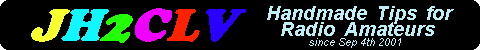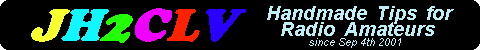簡易RFサンプラーについて
 送信機やリニアアンプの特性を見るときに欲しくなるのが、出力の一部を取り出すための装置。
送信機やリニアアンプの特性を見るときに欲しくなるのが、出力の一部を取り出すための装置。
業務用には方向性結合器などが使われるが一般には高価で入手が難しい。
アマチュア的に簡易でそれなりと特性が得られる手法に抵抗器による分圧方式がある。
方向性は持たないが、単純に出力の一部を微弱電力として測定用に取り出すにはこれで十分である。
左はその実例で下は回路図と応用を示したものである。電力が通過する同軸ラインから、抵抗器2個による分圧で測定用微弱電力を取り出す仕掛けである。
この分圧比を1/1000000〜1/100000程度に設定できれば-60〜-50dB程度に低下させることが出来る。
この程度の電力なら同軸ラインへの影響は無視できる。
しストレー容量やストレーインダクタンスはハイフレでは無視できないので、抵抗器は高周波用を持ちい、配線は極力短くしている。
そして筐体内部からの漏れが無いように、TAKACHI製のアルミ・ダイキャストボックスに組み込んでいる。
 自作RFサンプラーと測定
自作RFサンプラーと測定
左は自作サンプラーをダミーロードに直付けしサンプル出力を取り出している様子。この出力は測定器(スペアナやオシロスコープetc)で50Ω終端され測定環境が整う。サンプラー出力・同軸ケーブル・測定器入力の各Zが整合していないとf特を持ち高調波が正常なレベルにならない。抵抗器によるサンプラーだが、実装時のストレーや抵抗器自身のストレーがあり基本的にf特を持つ。同軸ケーブルもf特を持つので、特に高い周波数では減衰分を補正して読む。測定器の入力まで十分な整合を心掛ける。
参 考
50Ω負荷に1KWが供給されている場合、信号を正弦波とするとP=E二乗/RでE=√PRとなる。
この場合、Eは実行値だから最大値は更に√2倍になる。したがってEmax=√2・√PR=√2・√1000・50=1.41・224=317(V)。
Emaxから抵抗1MΩと50Ω及び測定器50Ωにかかる電力を計算すると・・・P=E二乗/R=317・317/1000000+25≒0.1W・・・となり、発熱を考慮して0.5W程度もあれば十分。結合度は抵抗比で決まり、サンプル出力も測定器50Ωにつながっている状態で見ると、25Ω/(1000000Ω+25Ω)となり凡そ0.0000249程度(-54dBで1KW時なら2.5mW)になる。
 参 考:BIRDのRFサンプラーについて
参 考:BIRDのRFサンプラーについて
右はBIRDのサンプラー4275-20、周波数帯は20-1000MHzとなっているがHFローバンドでもサンプル出来る。
上部に見えるツマミを回す事により結合度を可変できる。またツマミの横に見えるレバーはツマミのロック機構。スルーラインには方向性は無い。
サンプル機構は単純にスルーライン(Nコネ)とサンプル出力(BNCコネ)間の静電結合を可変するものと思っていたが、測定すると結合度を可変しても静電容量は47PF程度で一定だった。
またスルーラインとサンプル出力間には直流的な結合は無い。では一体どのような仕掛けになっているのだろうか?。
サンプルコネクタの信号源Zや整合の概念はどうなっているのだろうか?。分解するまで疑問が解けそうにない。
関係資料:CM型方向性結合器について・・・方向性結合器及びRFサンプラーの紹介・製作