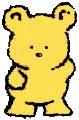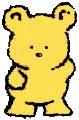家庭の窓 家庭の窓
|
人間とは,身の安全のために,適当な間を周りに置いて他と関わっていることを表していますが,その間は虚無ではなく,実有でなければなりません。
間接は間を置いて接していること,間隙はその空間距離,間合いは,人が意図して設定する間の取り方,間違いは,それぞれの間が関わりを持てないほどずれていること,間に合うとは,関わりが成り立つ間の向き合いを,間抜けとは,愚かな間のずれを,それぞれ表しています。
人のつながりは,お互いの間の絡み合いです。お互いにつながりたいという状況で,間がつながります。一方がつながりたいとの間を持ちだしても,他方が間を合わせてつながろうとしなければ,成立しません。無理につながろうとすれば,それはお節介になり,拒否されるでしょう。無理強いをしないで,つながろうという情報を届けながら,間を保って,必要なときにつながるようにするしかありません。
人のつながりを生み出す間として,何らかの補助的な役割を持った間にすることが有効です。その例が,品物の提供と受容が機能する間合いです。売り場という空間を設けて,品物を通してつながりが生まれます。商店のような物理的な実態のあるモノに限らず,集会所のような抽象的な情報の交換も,つながりを生む間合いになります。
人のつながりについて,言ってくれないからつながらない,言っても聞いてくれないからつながらないという間違いが起こります。間の設定準備が不完全な場合で,つながりの間ではなかったのです。今からここでつながります,という状況が設定されていなければ,つながりは結ばれません。ただし,突発的に生まれる事故のようなよほどの強い間の発生の場合には,つながりへの願いと受け入れが最大限に発揮される間に変わります。
最近,人の間が冷ややかになってきました。冷えすぎて冷淡になることもあります。その理由は間が虚空間になり心理的に間遠くなって,人の温もりを保てなくなってしまったからです。冷え切った間合いでは,ハラスメントに染まったものにしかなり得ません。
振り返ると,かつての暮らしでは,地域という狭い実空間での間合いが主流でした。間近な間では,人の温もりが直に伝わり合うことになります。間近であるから,お互いの実情を分かり合えて,間合いが取りやすくなります。今更に求めようとしている自助から互助への間合いが取りやすかったのです。間というものの温もりを取り戻すことに早く気付かなければなりません。
|
|
|