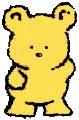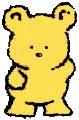『子育ちは 安心すれば 進み出す』
『子育ちは 安心すれば 進み出す』

■子育ち12資質■
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
『子育ち第3資質』
【居所を見つけ安心できる】
《まえがき(毎号掲載)》
子育て羅針盤では,子どもの育ちを6つの方向と2つの領域から考察します。6つの方向とは,「誰が,どこで,いつ,何が,なぜ,どのように育つのか」という問題視座です。また,2つの領域とは,「自分の育ち(私の育ち)」と「他者と関わる自分の育ち(私たちの育ち)という育ち」の領域を表します。6つの方向にそれぞれ2つの領域を重ねた12の論点が「子育て羅針盤」の基本的な考察の構成となります。
この第95版では,こどもができるようになっていく資質という面から育ちを考えていきます。こどもの健全な育ちというものの中身を具体的なできることに表してみます。それぞれが程度に違いがあってもそれは個性になりますが,そのことを自覚しておけば,幸せに生きていくことができます。何となく育っているように思えても,生きる喜びをしっかりと自覚する視点を身につけて欲しいのです。もちろんこれまでのように,健全な育ちを実現する羅針盤としての全方位を見届けることができることを再確認していただけたらと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《安心するのは誰ですか?》
子どもは育つ場を必要としますが,それは安心できる居場所です。もし不安な場に置かれたら,自分を守るために,もう一人の自分は閉じこもり,育ちは滞ります。
子どもが安心して育つ居場所とは,特殊な場所ではありません。例えば,夕食後に子ども部屋に追いやられると,隔離されてひとりぽっちになり,窓際の不安にさいなまれます。家族とつながるリビングが安心の場になります。
家庭でお手伝いをする子どもは,親から認められることから,自分がいて欲しい人であるという確かなつながりを実感し安心することができるでしょう。
人とのつながりが豊かであることが居場所です。豊かなとは? それは多様性です。今,子どもたちはクラスメートとの横のつながりに片寄っていて,育ちの場が貧弱になっています。
いろんなタイプの友達の輪を持つようにしなければなりません。たとえクラスで友達関係がこじれても,他に友達の輪を持っていれば,落ち込みは少なくて済みます。地域の子ども会やスポーツ仲間,クラブ仲間などがあります。同年齢にこだわらず,年上や年下の関係も大切です。
育ちには大人とのつながりが欠かせませんが,親や先生との縦のつながりは指導という色合いがあって,子どもにとってはどちらかと言えば見張られているという関係に思われています。
また,近所や地域の大人たちとの斜めのつながりがほとんどありません。このつながりは子どもを見守る温かなつながりです。親がご近所とのつながりを大切にする姿を見せてやってください。地域の温かなつながりに安心があるのです。
いじめのパターンは,まず,同質の人間としてグループの内部に取込み,次に些細な違いを理由に「境界域」に排除します。決していじめられっ子をグループの「外」に追放はしません。完全に排除されればその方がすっきりするのですが,グループと付かず離れずの所に追放するだけです。いじめが陰湿に見えるのは,飼殺しの状態においているからです。いじめられっ子は,剽軽な明るい子に多いように見えることがあります。もう一人の子どもは剽軽に振舞うことで不安定な自分のソゴを埋めようとしているからであり,大人はその剽軽さにいじめを見落すことになります。
母親にとっては,わが子は出来が良かろうと悪かろうと,器量が良かろうと良くなかろうと,唯一無二の存在です。ところが,園や学校に行き出すと,序列化され,○番だ,出来ない,怠けるという比較個性の目で見られるようになります。そうしないと,やがて我が子が爪弾きされて生きていけないのではと不安になっていきます。塾,先生の管理下に差し出され,他人から評価される存在と,親としての唯一無二の存在というアンビバレンスが生じ,わが子を見る視点が分裂していきます。親は親の目を曇らせないでください。
小学生の登校拒否では,「学校が恐い,不安」を訴えることがあります。授業では「時間内に」,給食は「食べ残してはいけない」というように,学校は緊張の空間です。いろんな能力及びその発達段階の子どもがいるのに,皆が出来るはずであるという画一的教育の場では,居場所が無いと感じる子どもが出てきます。もう一人の自分が,付いていけない,落ちこぼれている自分を認めさせられるのは苦痛なはずです。学校という場が居場所ではなくなるのです。
★落書き★
商売などが流行らなくてお客さんが来ない状態を「閑古鳥が鳴く」といいます。ところで,閑古鳥とはどんな鳥でしょうか。芭蕉の歌に「憂きわれをさびしがらせよ閑古鳥」と詠まれているように,悲しい鳴き声をする鳥のようです。その鳴き声は「カッコー」です。閑古鳥とはカッコウのことだそうです。その寂しい鳴き声が寂しい店を連想させるということのようです。カッコウには何の罪もないことです。
|