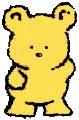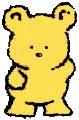『子育ちは 自分の弱さ 一時耐え』
『子育ちは 自分の弱さ 一時耐え』

■子育ち12資質■
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
『子育ち第9資質』
【現実を直視し忍耐できる】
《まえがき(毎号掲載)》
子育て羅針盤では,子どもの育ちを6つの方向と2つの領域から考察します。6つの方向とは,「誰が,どこで,いつ,何が,なぜ,どのように育つのか」という問題視座です。また,2つの領域とは,「自分の育ち(私の育ち)」と「他者と関わる自分の育ち(私たちの育ち)という育ち」の領域を表します。6つの方向にそれぞれ2つの領域を重ねた12の論点が「子育て羅針盤」の基本的な考察の構成となります。
この第95版では,こどもができるようになっていく資質という面から育ちを考えていきます。こどもの健全な育ちというものの中身を具体的なできることに表してみます。それぞれが程度に違いがあってもそれは個性になりますが,そのことを自覚しておけば,幸せに生きていくことができます。何となく育っているように思えても,生きる喜びをしっかりと自覚する視点を身につけて欲しいのです。もちろんこれまでのように,健全な育ちを実現する羅針盤としての全方位を見届けることができることを再確認していただけたらと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《忍耐するのは何故ですか?》
自分の能力の正しい使い道を見極めることが,子育ちの第8の能力でした。ただ,能力を生かすことが簡単ではないことが普通です。そのようなときに簡単にあきらめないことが大切です。
しなければならないことがあるとき,自分の気持ちにそぐわないからと逃れることなく,きちんと直視し自らの力で受け止める忍耐が必要です。今は何をするときかという状況をもう一人の自分が理解し,自分にできることをすればいいのです。今は食事のとき,今は黙ってお話を聞くとき,今は楽しく遊ぶとき,そのような生活のリズムを身につけることから忍耐は始まります。
あきらめないためには工夫する力が必要です。遊んでいて何かが足りないとき,学校の授業で持ってくるものを忘れたとき,急に雨が降ってきたとき,道に迷ったとき,立ち往生してしまうのではなく,何とかならないかと可能性を探すことが工夫するということです。手近なものから代用になるものを探して間に合わせようとすれば,今この場でできることを見つけることができます。現実を見る力とは目的を持って真剣に見つめることであり,その結果として工夫する力が培われます。
物事はすんなりとは進みません。気持ちは焦りますが,焦ってうまくいくことはありません。焦りを押さえ込む忍耐が働けば,状況を見ざるをえないようになります。できることを見極め,自分の力を信じてやってみます。やっていけば状況は変わってくることを信じることです。その途中の忍耐は可能性を産み出す陣痛のようなものです。
他人に迷惑をかけないように気をつけることは,確かに立派なことです。そうしている人は,他人から受ける迷惑を許せないと思うことがあります。自分は迷惑をかけないように努力しているのに,あなたは私に迷惑をかけてばかり,そう非難することになるでしょう。人は存在しているだけで他人に迷惑を掛けているものです。その現実を弁えて,他人からの迷惑をある程度は受け入れる忍辱(にんにく)が必要です。順番を待つということから始めましょう。
勉強,スポーツ,趣味,遊び等,どの場でもそれなりの尺度があります。多様な尺度を持ち,強い弱い評価を一元化しないようにします。例えば,教科や種目の得意不得意があるはずです。他と比べるのではなく,自分の中でもできることもあればできないこともあります。弱さの自覚がない子どもが,他人の小さな弱さをかぎ出すようになり,それがいじめにつながっていきます。同学年という横社会では弱さが見えにくいものです。異年齢の縦社会では,弱さが大きく目につくので,気にならなくなります。それが現実なのです。
三人兄妹の真ん中の子が知恵遅れでした。二つのケーキを,母親は兄妹に半分,真ん中の子に一個を与えました。贔屓をしたのです。その子は食べようとしません。それに気付いて,母親は自分と半分にしました。喜んで食べました。普通であれば大きい方が欲しいはずですが,その子は兄妹が半分,自分は一個という現実に気付いて,食べる気にならずに我慢しました。世間は知恵遅れと呼びますが,知恵は遅れていないのです。ただの「知識遅れ!」と呼ぶべきかもしれません。知識は遅れても,人の知恵があればいいのです。
学校とは,外部からの取締を受けなくても,自己管理できる人間を作る所です。いじめ,盗み,器物損壊,喫煙や飲酒などのルール違反や性的乱脈などをすることは,人として卑劣な行為であり,本当の弱虫であるという基本概念を植え付けることが期待されています。してはいけないと知っているだけではなく,したら気分が悪くなるという感情を育まなければなりません。強いということは悪しきことに走ろうとする衝動に耐えられることであり,人を助けることであると,徹底して教育すべきです。
エミールに,「子どもを不幸にする一番確実な方法はなにか。それをあなたは知っているだろうか。それはいつでも何でも手に入れられるようにしてやることだ」と書かれています。子育てのあり方は古今東西で変わらないようです。「皆が持っている,仲間外れにされる」という子どもの声に,親は弱いものです。欲しがるものを与えれば,子どもは喜びますが,それは一時のことでしかありません。すぐに,次の新しいものがねだられます。我慢とは欲望を断つ抑制力であり,それは「後で」という言葉で,先の可能性につなぐことができます。
★落書き★
スマホの普及によって,新聞が読まれなくなっているようです。ところで,新聞は読むものなのにどうして聞くというのでしょう。新聞とは中国語でニュース,つまり新しく聞くことの意味でした。ラジオもテレビもない明治時代にニュースを伝える印刷物に中国語でニュースの意味の新聞と名付けられました。そのご新聞と名付けられた印刷物が発刊されて呼び名が定着したのだそうです。
|