Nゲージ蒸気機関車>蒸機の工作>夕張鉄道11号機の組み立て(ワールド工芸)
夕張鉄道11号機の組み立て(ワールド工芸) その1
昨年(2016年)8月に発売されたキットです。色々な事情でずっと着手できず、今更手を付けました。
今までのワールド工芸のエンジンドライブ機と同様の構成です。何か形態がツボにはまりまして、楽しく進められました。
2017.6.6/2020.11.23
説明書の手順のとおりに組み立てました。新しい機関車の場合、戸惑いがちな上廻りの組み立てについては、かなり詳しい手順が箇条書きされていたため大変助かりました。
いつもこうだといいのですが、難しい機関車でも説明がないものもあって、説明の粒度は毎回同じではありません。
説明書1/4 テンダーの組み立て
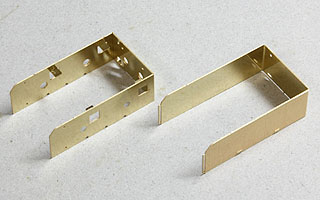
テンダー側板は2枚重ねです。外板は曲げ済みです。
内板の4箇所のツメと、後部のラグを引き起こし、外板とぴったり重ねて貼り合わせました。
何か所かのハンダ穴からハンダを流して付けますが、上下の断面にもハンダを流して固定しておきました。→あとでヤスリ掛けなどをするとき、引っ掛けてめくれたりしないようにするため。
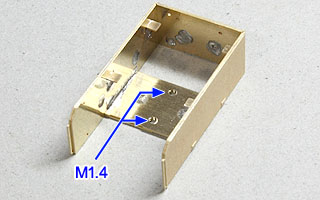
床板を取り付けました。
中央2箇所の穴は、あとで下廻りをネジ留めするため、M1.4タップを立ててネジを切っておきした。
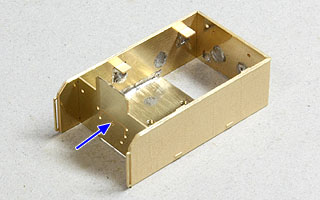
妻面の仕切り板を挟み込んでハンダ付けしました。
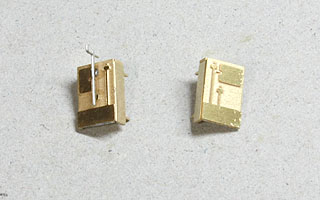
妻面の左右部分(工具箱などが付いているところ)を組み立て、一方にはブレーキハンドルを付けました。
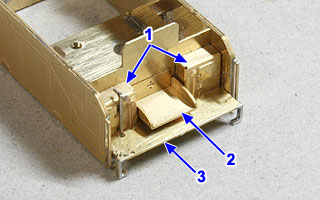
1. 組み立てた左右の箱を取り付け。
2. 石炭皿を取り付け。
3. 前方の床板を取り付け。下側の足も曲げてハンダ補強しておきました。
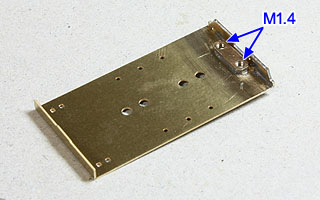
床板を折り曲げ、後ろの端梁部分は模様が表に出るように折り返して固定しました。
カプラーをネジ止めする台座を固定し、M1.4ネジを切っておきました。
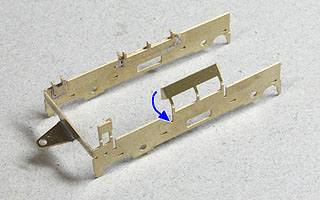
下廻りの外枠を折り曲げました。
前方と中央付近にある出っ張りは、端の三角の部分を直角に曲げ、そのまま内側から180度折り返します。
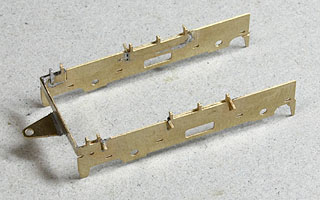
折り返したところです。三角の部分が外枠の溝から外側に顔を出します。
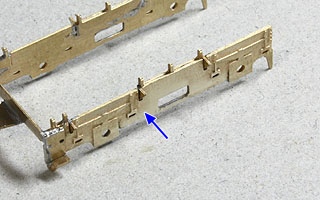
台車枠外側に、もう一枚外板(A2-2)を貼り合わせました。前側のステップ部分は折り返して曲げておきました。
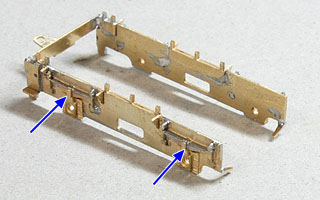
さらに4箇所の板バネを折り重ね、貼り合わせました。
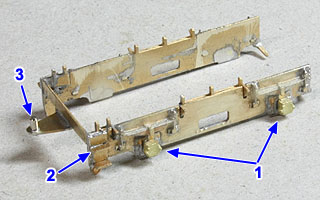
1. ロストワックスの軸箱を固定。
2. ステップ中段を取り付け。
3. ドローバーピンを取り付け。
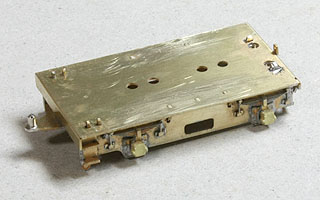
でき上がった台車枠を、床板に差し込んで固定しました。上側の出っ張りで邪魔になるものは削り取っておきます。
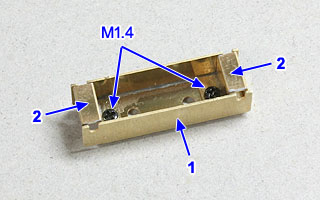
軸受けを組み立てました。
1. 2箇所に、車輪押さえをネジ留めするためのM1.4ネジを切ります。写真ではすでにネジ留めしてあります。
2. 車輪押さえを折り曲げ。これは仮に取り付けたもので、実際には塗装後、車輪を軸受けに置いてから車輪押さえをネジ留めします。
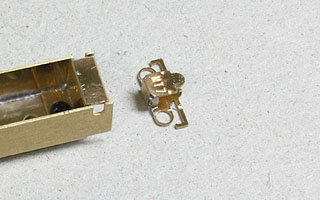
カプラーポケットを折り曲げました。
塗装後、MT-7マグネマティックカプラーを取り付け、床板にネジ留めします。
アーノルドカプラーの場合は、カプラーの根元に少々の加工を施すようです。
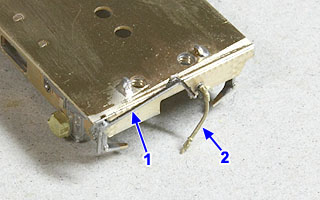
1. カプラー解放てこを固定。
2. ブレーキホースを固定。
実は根元のハンダ付けが不十分で、塗装後に外れて空回りするようになってしまいました。何か、しっかり付かなかった感触はありました…。
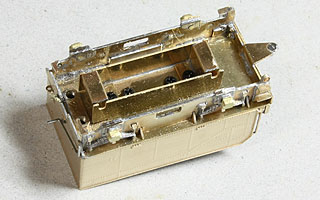
軸受けの底の穴から、上下をネジ留めしました。
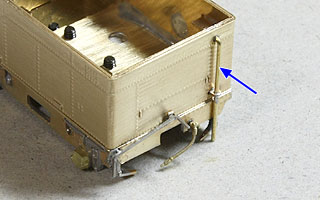
付属の0.5mm真鍮線を曲げ、後部妻板の上部の穴と、下部のラグの穴に差し込んで固定しました。
これの長さを決めるため、先に下廻りを組み立てて合体したものです。
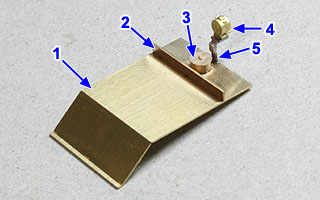
1. 炭庫底板を折り曲げました。
2. 仕切り板を固定。
3. 給水口を固定。
4. ライトを取り付け座に固定。
5. 取り付け座を最後部に固定。
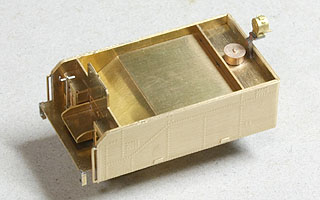
いったん下廻りを外し、組み立てた炭庫底板をはめ込んで、下側からハンダ付けしました。
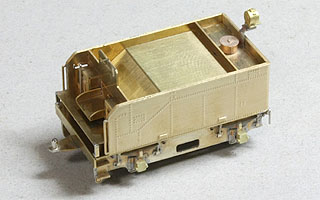
再び下廻りをネジ留めしました。おそらく取り外すことはないだろうと、このまま塗装しました。
テンダーはこれで終わりです。台車周りは立体表現のため、ちょっと部品の貼り重ねが多めですが、特に難しいところはないと思いました。