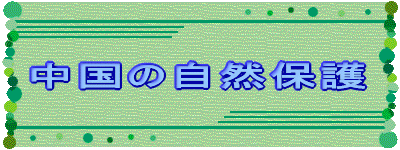

2004年9月13日。山海関〜北戴河。39キロ。晴れ。
102号国道は、大部分がポプラの防風林に囲まれている。
ときに、それが二重三重と重なり、地平線まで一直線に緑の谷間を作っている。
樹齢はみな若く精精30年だろうか。それでもこの樹は成長が早く、高さは40メートルほどある。
両脇は唐黍畑。以前中国の風景を代表した高粱は珍しい。都市近郊は、蔬菜果物もあるが、一面と言っていいほど唐黍畑である。河北省に入るとさつま芋畠もあった。遼河流域には水稲も多く見られた。
やはり都市近郊に限られるが、ビニールハウスもある。
昔の撫順は、公園や高級住宅街には樹木も並木もあったが、一歩郊外に出ると、ボタ山とオイルセール(石油を含む頁岩)で灰色一色だった。柳はそれが目印になるほど少なかった。
徐さんが、私が自然保護に関心があるのを知って自然保護の看板があると、隊列を停めて写真を写すように勧めてくれるが、あまり多いので止めた。
昨年黒龍江省を旅行したとき、北大荒の農地に「退耕還土」(耕すのを止めて、土に戻そう)というスローガンを、数多く見た。北大荒はハルピン、牡丹江など黒竜江省北地の荒れたツンドラ(永久凍土)地帯を開拓した、国営農場である。面積はほぼ四国の三倍ある。そこは、世界的にも貴重な沼沢地を多く抱え、日本から鶴など渡り鳥の中継基地としても有名である。そこが開拓で失われたのだが、遅ればせながら、いま保存に乗り出している。
野鳥といえば、雀や燕が減った。白米のご飯が黒くなるほど居た、蝿が居ない
新中国建国以後55年の大変化は、こんな所にも及んでいる。
今度、北戴河の入り口で初めて蛇を見た。1メートルを越える青大将で番だった。それまで見た蛇の屍骸が一匹。日本ならこの時期山道を自転車でいくと、至る所で蛇に出会う。車に轢かれた屍骸も珍しくない。
犬、猫の屍骸は言うに及ばず、ときには狸や兎の屍骸にも出会う。今回は羊が車に撥ねられたのを見たのが一回だけだった。
蛇はある意味で、自然保護の物差しである。蛇が居るということは、蛙のようは小動物が居るということ。それは、そこが農薬に汚染されていない、または汚染度が低いことを意味する。
中国の道路で、蛇を見かけないことは、色々な原因が考えられる。
一 蛇が減った。
二 道路で分断されても、生態系が乱されないほど、生活圏が広い。
果たして蛇は減ったのか。中国の料理屋では、蛇はよく見る。日本の生簀の魚みたいに、籠の中の蛇の現物を見て注文する。延吉では、道端で姿焼きにしてうじゃうじゃと売っていた。蛇の絶対数が減ったとは思えない。
もし蛇が減ったのなら、これはやはり大きな問題である。農薬の汚染が進んでいることを意味するから。
二は、十分に考えられる。とにかく中国は広い。今回沿線は人口密集地帯と聞いていたのだが、行けども行けども唐黍畑。それでも20キロも走れば確かに集落はあるから、中国では人口密集地帯というのかもしれない。
中国の蛇が、危険を冒してまで道路に出る必要がないほど豊かな自然に恵まれているのなら、幸せである。
中国でも自然保護は大きな問題になっている。今回自転車は自然にもっとも優しい乗り物ということで、新居浜のエコロジー、エネルギー、フォーラム(代表者三宅和雄)というNPO団体が、この旅行を支援して下さった。
中国側は同じくベンチャービジネスで、この方面に関心がある、宮涛さんという人が受け皿になって協力して下さった。宮さんの名前は、正式には龍の下に共と書く。この字は日本にはないので、中国語で発音が同じ宮を当てている。
三宅さんと、宮さんは、太陽発電電池、廃材を利用した、エコロジーエネルギーストーブ、庭園設計などが、互いに共通する営業品目である。二人ともまだ30才台。ビジネスチャンスを求めて、活発に動く。
経済発展と、環境保全は矛盾する面がある。仮にクリーンなエネルギーを人類が手にしたとしても、全て解決出きるとも思えない。エネルギーの消費そのものが問い直されている。限りなき富の追求を是とする価値観そのものが問い直されなくてはいけないと思う。
日本は先進国と言われる。先に走って、先に富を得た者が、後から来る物に同じ道を来ることを拒むことは出来ない。失敗の経験を生かすべく教えることはできる。
もっと大事なことは、これ以上先進国が地球を苛めないことではないだろうか。
車社会の中で、私は車を捨てた。実は高尚な理念に基づいたものではない。事故を起こして、これ以上運転したら、人を傷つけるかもしれないと思って、車を捨てただけである。
車を失って得たものは、足の筋肉と、快眠である。食も美味しい。
この旅で、私は質素な生活をした。それは、かつて日本が先進国を目指して辿った道を遡ったに過ぎない。
「人はどれだけの土地が必要か」トルストイにこんな小説があったと思う。起きて半畳寝て一畳。主人公に最後に必要だったのは、息絶えて横たわる一畳だけだった。
人は生きていく上に最低何が必要か。それが問い直された旅でもあった。

