| GLORIES | ||
 ゲルマ・ラジオとレフレックス (懐かしのビギナーズ・ラジオ2題。昭和は遠くなりにけり。) 今でこそ「1個15円。20円。」みたいなお安い感じのトランジスタですが、1960年代はじめ当時は、新技術を用いたハイテク・デバイスでした。たとえ小さく壊れやすくても、子供には高嶺の花。ここでご紹介するレフレックス・ラジオは、この貴重なトランジスタが、1個で2個分に働くという、まさに魔法のようなラジオです。 作ってみました。懐かしのビギナーズ・ラジオ2題です。 2003年10月20日 マリオ ゲルマニウム・ラジオ。別名ゲルマ・ラジオ。 おそらくこれについてはあまり説明の必要がないかも知れません。SD-46とかのゲルマニウム・ダイオードを用いたこのラジオは、当時、ラジオ製作の第一歩であり、実に多くの人が製作経験を持っています。 私も、例にもれずはじめてのラジオはこのゲルマ・ラジオでした。最初は兄が作ってくれて、待ちかねるうち、ようやく手にしたそのラジオのイヤホーンからラジオ放送が聞こえたときは、びっくり、大感激でした。 私はこれをラッカーで固めたちっちゃな手製の箱に作り直して、いつもそのラジオを持ち歩き、夜もアンテナを外に出せる2階の廊下に寝て、蚊の鳴くような小さな音のこのラジオを楽しんだものでした。 もう一回り古い時代の人は鉱石ラジオでしょうか。やはりこれも同じ原理のラジオです。  ゲルマ・ラジオをわかりやすい回路図で書くと、おおよそ右図のようなものです。サムネイルをクリックしてみてください。 ゲルマ・ラジオをわかりやすい回路図で書くと、おおよそ右図のようなものです。サムネイルをクリックしてみてください。アンテナがとらえた放送電波は、コイルとバリコンで作る同調回路の両端にその強さに応じた高周波電圧を生じます。その電圧によって生じた電流が、ゲルマニュウム・ダイオードでできた整流式の検波器を通り、コンデンサと抵抗器を組み合わせたCRフィルターの両端に音声に応じた低周波電圧を生じます。そしてその電圧がイヤホーンを鳴らす。 このように、ゲルマニュウム・ラジオは、アンテナがとらえた電波のエネルギーで直接イヤホンを鳴らす仕組みです。ですから電池などの電源なしでラジオ放送が楽しめる利点がある反面、ちょっと銅線を張った程度の小さなアンテナや伸縮式のロッドアンテナでは、イヤホーンを小さく鳴らすのがやっとで、とてもスピーカをならすところまではゆきません。放送局の送信所の近くに住んでいて大きなアンテナをかまえた人が『スピーカーを鳴らした。』という話は、本で読んだことがありますが、こんなのはやはり特別な例だろうと思います。 さて、ゲルマ・ラジオは簡単でも、蚊の鳴くように小さな音ではラジオとしてはいかにも不足です。同じビギナーが作るにしても、「もう少し大きな音で聞きたい。」ということがおこります。そしてそういうことになると、やはり増幅作用のあるトランジスタのお世話にならなくてはなりません。当然電池も必要です。そしてそこで登場するのが、タイトルのレフレックス・ラジオです。 今でこそ「1個15円。20円。」みたいなお安い感じのトランジスタですが、60年代はじめ当時は、トランジスタは新技術を用いたハイテク・デバイスです。たとえ小さく壊れやすくても、真空管と同じぐらい高価な部品。子供のお小遣いから見たら、トランジスタはまさに高嶺の花でした。 ところがこのレフレックス・ラジオは、その貴重なトランジスタが、なんと1個で2個分に働くというのです。まるで魔法のような話。ですから、私にとってこのレフレックス方式のラジオは、その頃のビギナー向けラジオのなかでは、もっとも印象深いラジオです。「1個で二個分。」いかにもつましく、まさに時代の産物だと思います。  まず参考までにトランジスタ1個を用いたベーシックな1石ラジオを紹介したいと思います。サムネイルをクリックしてみてください。 この場合も、ゲルマ・ラジオと同じく、コイルとバリコンでできた同調回路で目的の放送を選ぶのですが、その同調回路からの出力は、トランジスタの入力特性(低インピーダンス)に合うよう、特に工夫されています。そしてここで、バリオームを操作して、トランジスタのベース電流をコレクタ電流が止まる<カットオフ点>付近まで下げてゆくと、トランジスタの増幅作用は、単なる信号の増幅から、ダイオードとよく似た、検波作用を伴ったものに変わり、トランスのある出力側にゲルマニウム・ラジオよりもずっと大きな音声電圧が現れます。これでイヤホンを鳴らす。音量調節も付けられます。 こうなると、弱い信号でも増幅されるので、邪魔になるアンテナも、同調コイルと一緒になった内蔵型のバー・アンテナみたいなものでことが足り、たとえば高知市内なら、普通は外付けアンテナは不要です。 さて、一工夫あるのがレフレックス・ラジオです。 トランジスタはベース電流(コレクタ電流)を小さく絞るとそれだけ増幅力が細ります。つまり、今お話ししたようなベース電流を絞り込んで検波する普通の1石ラジオの場合、「増幅する。」とは言っても、そこではトランジスタの増幅力のすべてが発揮されているわけではありません。やっぱり「トランジスタの増幅作用を十分生かした、より有利な使い方はないものか。」という考えが起こります。 賢い人はいるものです。ラジオ放送の高周波信号と、その検波出力である低周波信号の両方を、一個のトランジスタで増幅すればよいと考えた。 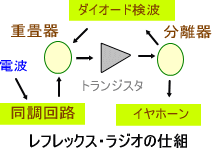 つまりこうです。まずラジオの信号をトランジスタで高周波増幅し、それをゲルマニュウム・ダイオードで検波する。つぎに、取り出した音声信号を再び入力側に戻し、もとのトランジスタでより大きく増幅する。<レフレックス>、つまり<反射式>という意味が、これでなんとなく分かると思います。 ラジオの放送信号と、その検波出力である音声信号の重畳・分離はいとも簡単です。トランジスタの入力側に重畳装置。出力側に分離装置を置けばよく、かくしてレフレックス方式は完成です。当時トランジスタのことを『石』と呼んでいましたが、これはまさに一石二鳥の妙案です。 ちなみに、レフレックス・ラジオは真空管でも簡単に作れます。しかし、たかだかイヤホーン鳴らす程度のことに、大きな電源を用意し、ヒーターを点けて、250ボルトで働かすなんていうのはどんなもんでしょう?気分は大正昭和ですが…。 さて、中学校のときは中古の真空管しか持っていませんでした。5球スーパーを作ったら興味の中心は短波放送へ移り、無線局を開けば、課題はさらに送信機やアンテナへと広がります。結局、中学高校時代の私は、このレフレクス・ラジオを試すことはありませんでした。 しかし、そうこうするうち、大人になってみればいつの間にやらトランジスタは安くて便利なディバイスです。回路は銅箔を貼った基盤に組むから大がかりな金属加工がありません。加えて低い電圧で働き、しかも真空管のようにヒーターを点灯する必要がないから、大がかりな電源は必要なく、トランジスタなどの半導体回路は、電池一つで簡単に実験が楽しめます。  ご覧ください。レフレックス・ラジオです。ある時たまたまラジオ・キットのカタログでこのラジオを見つけて購入し、試しに作って遊びました。 構成は、お話ししたような1石レフレックス回路の後ろに、スピーカーを鳴らすためのアンプが一つ付いた、ちょっと贅沢な2石レフレックス・ラジオです。まず説明書に目を通し、組み立ては一時間あまりです。 電源を入れると「ゥワン。」とスピーカーが鳴りだして、「してやったり。」なかなかたいした迫力です。 「ところがどっこい。」 聞いているNHK第一の背後に、しっかり負けずに、高知放送とNHK第二が聞こえます。 「ウーム。やっぱり。」 所詮レフレックス・ラジオはゴジラになったゲルマ・ラジオに過ぎません。音は大きくなっても、選択特性はゲルマ・ラジオそのままです。  さてここで、私の枕元にある、時々深夜放送を聞くラジオを紹介したいと思います。写真に見る、ソニーの学習用ラジオ・キットです。基盤上のラジオ用ICのまわりに部品を配置したり、必要な工作を自分でするもので、値段は2000円ほど。ラジオICのピンまわりのように特に難度の高い部分はハンダ付け済みで、<小学校高学年用>と書いてあります。 さてここで、私の枕元にある、時々深夜放送を聞くラジオを紹介したいと思います。写真に見る、ソニーの学習用ラジオ・キットです。基盤上のラジオ用ICのまわりに部品を配置したり、必要な工作を自分でするもので、値段は2000円ほど。ラジオICのピンまわりのように特に難度の高い部分はハンダ付け済みで、<小学校高学年用>と書いてあります。現代のビギナーズ・ラジオは、スピーカーがガンガン鳴る、実用にも耐える、便利なICラジオです。スーパー・へテロダイン方式。セラミックフィルター付き。初心者用ラジオが蚊の鳴くようなゲルマ・ラジオであった時代とは、月とスッポン。まったく隔世の感ですねぇ。 なお、スーパー・ヘテロダイン方式のラジオは、感度と受信安定性に優れ、現代の標準的なラジオです。そして、これに用いられるセラミックやクリスタルでできたフィルターは、それを用いることですぐれた選択特性が得られます。つまり、異なる周波数で放送されるNHK第一と第二が、同時に混ざって聞こえるということは、もう起こらないということです。それはそれで、また味があったのだけれど・・・。それではまた。つぎの話をお楽しみに。 2003年10月20日 マリオ |
||
| GloriesTopへ | ||