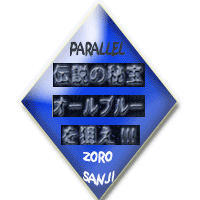
◆
100
◆
目の前にある美しい宝石はきらきらと輝き、見るものを飽きさせない。
スーツ姿のロロノア家当主は、
二つの宝石をずっと見つめ続けていた。
私は・・・、
これを知っている・・・。
おれは・・・、
これを・・・。
ずっと見つめていると、
後見人であり会社の専務であるミホークがあらわれた。
「厄介なことになった。
クロコダイル時期国王より、
オールブルーを見せて欲しいという達しがあった。
同意して見せれば、おそらく所望され、
断れば反逆罪で、それは持ち去られる。
麦わらのルフィの生存は確認され、
わが会社に疑いの目が向けられている。
反逆者、ロロノア・ゾロに瓜二つの社長にも疑いの目は向けられている」
「オールブルーを差し出すしかあるまい」
クロが分厚い書類を片手にあらわれた。
「すべてはこの宝石、オールブルーから始まった。
処刑された麦わら海賊団とオールブルー事件に関する記事だ。
どれだけクロコダイルが活躍したかをほめたたえるものばかりだ。
我々は、今まで、オールブルーはすでにクロコダイルの手中にあるものとばかり思っていた。
しかし、真実は奇なものだ。
泥棒は目的を果たし、生き延びていた。
奇跡的にオールブルーは我々の元に戻って来た。
だが、ここからが正念場だ。
敵は、以前の比ではない。
本気で戦わねばならん」
ロロノア家当主は、じっとそれを見つめた。
「二つあるから、一つ差し出せばいい」
ゾロの言葉にミホークが渋い笑いを浮かべた。
ロロノア・ゾロなら、簡単にそんなことは言わなかったはずだ。
だが、ロロノア家当主としての選択は正しい。
クロコダイルとたかが宝石のことでもめごとを起こすのは馬鹿げているから、
その方法しかないことは分かる。
「これを持って行く」
ゾロが示した宝石は、
時としてきらきら淡い光を浮かべる石のほうだった。
・・・あの時も、
差し出したのはこの宝石のほうだった。
そして手元に残したのは、
同じ石。
誰かと同じような目をした深く青く輝く石。
オールブルーは何も語らない。
すべてを知っている宝石は、
静かに輝き続けていた。