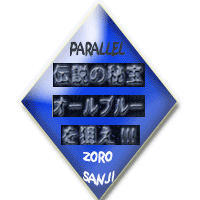
◆
103
◆
クロコダイルの館に戻ってからも、
アルビダの脳裏からはゾロの姿が消えなかった。
サンジは放心したように、
ぼんやりとベッドの上に座っていた。
生きている人間には見えなかった。
よくできた人形のようだ。
クロコダイルは、城という名の要塞を作った。
あの奥に入ったら、
多分もう生きて出ることはできない。
けど、どうすることもできやしないさ。
クロコダイルに従うしかない。
そうするしかないんだ。
・・・ゾロ。
あれは、ゾロだった。
でも、アタシの事が分からないみたいだった。
無言で部屋の掃除をし、
部屋の整頓をした。
サンジはもうアルビダが部屋にいても、
何一つ話かけることもない。
アルビダがサンジに話かけることは禁じられている。
部屋には、いくつかのレタスやサボテンの鉢があり、
サンジがクロコダイルに頼んで買ってもらった料理の本や性的な本がきちんと並べられている。
アルビダは知っていた。
サンジがその中の真っ黒い本をよく見ている事を。
ニコ・ロビンに何かを頼んだことを。
その先に何があるのか、とうに気づいている。
どうすれば、いいんだい?
アルビダは、サンジのいる場所から逃げ出した。
サンジは殉教者のように、
しずかに座り続けていた。
ゾロと一緒にいた時は、
なんてがさつで下品でバカな男かと思ったものだ。
クロコダイルといる時は、
恐ろしく淫らで妖艶な顔を見せる。
でも、今は・・・。
誰も触れることのできないほど高貴で無垢な美しさに満ちている。
誰にも助けを求めず、
誰をも傷つけず、
たった一人で耐え続けている。
いつまでもこんなことは続かない。
アルビダは顔を覆った。
「時期国王は、今日は10時23分ごろお越しになるわ」
いつの間にか背後にニコ・ロビンが立っていた。
アルビダは、いつもなら従うだけだが、
どうしても知りたくて言った。
「今日、サーの城でゾロを見た。
あれは、ゾロだった!!」
ニコ・ロビンの表情は全く変わらなかった。
「ロロノア・ゾロは確かに死んでいるわ」
「それは・・・どういう・・・?」
「知らないほうが身のためよ。
貴女にもミスター・プリンスにも関係のないことだわ。
もう、心が死んでいるのよ。
プリンスにこれを」
心が死んでいる?
では・・・身体は生きている?
・・・ゾロが・・・生きている?
もう・・・あれはゾロじゃない。
・・・でも・・・生きてる?
ゾロは・・・生きている?
アルビダはロビンから渡された袋をにぎりしめたまま、
いつまでも立ち続けていた。