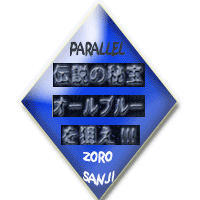
◆
113
◆
サンジは、捨てようと思って、ごみ箱にこっそり押し込んでおいた、
腹巻をにぎりしめて、
すわりこんでいた。
どうして?
アルビダおねえさまは、
どうしてこれを捨てなかった?
どうして、これをおれに渡した?
だれに、渡せと?
もう・・・ゾロはいないのに・・・。
茫然とすわりこんでいると、
近くで誰かが騒ぐ声や、
怒鳴る声が聞こえてきた。
うるさかったけれど、
サンジにはそんなことはもうどうでもよかった。
どこかで、誰かの絶叫が聞こえた。
誰かの苦しむ声が聞こえた。
それでも、
サンジは何の反応も示さなかった。
近くで、
大きな物音がして、
荒々しい足音と、
誰かが戦う音が聞こえてきた。
それが何であっても、
もうサンジにはどうでもいいことだった。
何の感情も動かなかった。
「侵入者が!!
王の間に!!」
誰かの叫び声が聞こえた。
「その男を殺せ!!」
誰かが怒鳴っていた。
「ぐぁあああああ!!」
叫びはだんだんサンジに近づいてくるけれど、
サンジは動こうとはしなかった。
もう、何がどうなってもいい。
どうでもいい。
ぼんやりすわりこんでいるサンジの近くの壁に、
ひとすじの光が射し込み、
ゆっくりと壁が二つに割れた。
その壁の向こうには、
血だらけの刀を三本持った男が立っていた。
その男が刀をふるうと、
警備兵がばたばたと倒れた。
力の差は歴然としていた。
兵たちは、何か叫びながら、
刀の男に飛びかかっていくが、
まるで相手にならなかった。
その男は、
兵たちを一人のこらず斬りすてると、
サンジに近づいてきた。
明るい光が、その男を照らし出していた。
サンジは大きく目を見開いた。
息をするのも忘れて、
その男を見た。
物騒な刀、
ミドリの頭、
趣味の悪いオヤジシャツ、
それから・・・、
世界広しといえども、
誰一人身につけないようなミドリ色の腹巻。
・・・ゾロ?
・・・ゾロなのか?
ゾロは死んだはず。
なら、オレは夢を見てるのか?
それとも、オレも死んだのか?
どっちだっていい。
ゾロがここにいたら、もうどっちだっていい。
サンジの目から涙がこぼれおちた。
ゾロは、サンジの目からこぼれおちた涙がきらきらと輝くのを見た。
涙をためたサンジの目が、
深い青でなく、
淡い青にきらきらと輝くのを見た。
オールブルーだ。
淡いオールブルーと同じ。
濃いオールブルーもこいつと同じだった。
両方とも・・・こいつだ。
おれの、オールブルー。
やっと、気づいた。
どれだけ、てめえが大切か。
どれだけ、オレが愚かだったか。
てめえこそ、オレの宝。
てめえなしで生きていても、
なんの値打ちもねえ。
オレは、ヨサクとジョニーが残していた腹巻を見て、倒れた。
それからまる三日も仮死状態で昏倒していたらしい。
無の境地でいた時に、
誰かがオレを呼んだ。
愛をこめて、
オレを呼んだ。
心をこめて、
オレを呼んだ。
サンジ、お前は、オレを呼んだ。
生きることから離れた、
オレの魂を呼び覚ませた。
オレはてめえから、奪うばかりで、何一つ与えてやれなかった。
それなのに、てめえは、オレに愛をくれた。
オレには愛など必要ないし、
興味もない。
くだらないたわ言にしかすぎないはずのものだった。
意識を取り戻し、すべてを思い出したオレは、
サンジがクロコダイルに監禁されたままなのを知った。
その時、あの麦わらの一味のナミに言われた。
「あんた、自分がどれだけサンジ君のことが好きか考えたことがある?
どれだけサンジ君のことを愛してるか、知ってる?
あんたのしあわせって、何?」
ムカつく女だが、
核心を突かれた。
「答えは、直接サンジ君に言いなさい」
オレはすべてに感謝しねえといけねえ。
オールブルー作戦をたてたナミに、
オレにここにこさせたルフィやウソップやチョッパーに。
後方支援と称して、
雑魚どもと戦っているヨサクとジョニーに。
何よりも、目の前のこいつに。
オレを見て、
ぽろぽろ涙をこぼしている。
どんな宝石よりも美しい涙。
にぎりしめているミドリ色のものは・・・、
腹巻?
腹巻なのか・・・?
ゾロは胸がしめつけられる気がした。
「サンジ」
サンジはゾロが泣いていることに気づいた。
これは、夢?
だってよう、ゾロはオレの名前なんて呼ばねえ。
オレを見て泣いたりなんかしねえ。
けど・・・、
今、
オレをぎゅってしてるのは誰だ?
無駄に筋肉があって、
ミドリの腹巻してて・・・。
他に・・・誰がいる?
ゾロ以外に、誰がいる?
「ゾロ?」
サンジは小声でその名を呼んだ。
名を呼んでも、
ゾロは消えなかった。
消えるどころか、
ますますサンジのことをぎゅっとした。
・・・まさか・・・。
そんなことが・・・。
でも・・・。
・・・本物?
本物の・・・ゾロ・・・?
クロコダイルに幾度となく抱かれた時、
記憶の中にゾロはあらわれ、
目覚めるといつも消えていた。
まぼろしを見すぎていたから、
真実が何か、もう分からない。
ゾロは流れ落ちる涙をぬぐいもせずに、
サンジを抱きしめた。
よかった。
こいつは、ちゃんと生きてた。
礼を言う。
これ以上に、しあわせなことはねえ。
喜びに身体が震える。
抱きしめる手が震える。
「ゾロ?」
サンジはもう一度、その名を呼んだ。
やっぱり、ゾロは消えなかった。
本物?
本物だ!!
会えたら文句をいっぱい言ってやると、
いつも思っていた。
けれど、サンジは、何も言えなくなって、
ゾロの腹巻をぎゅっとにぎりしめた。
うれしかった。
ゾロがここにいるだけで、
信じられないくらい、
しあわせだった。
言葉もでないくらい、
しあわせだった。
二人の心がぴったりとよりそっていたから。