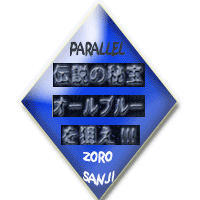
◆
60
◆
「それで、貴様はおめおめと帰ったきたわけか」
ボン・クレーはどくどくと血を流して、
床に横たわっていた。
ここは警察の特別室だ。
もうここの警察はクロコダイルに乗っ取られたといえる状態だった。
すべての権限をクロコダイルが握っていた。
クロコダイルは冷酷な視線をボン・クレーに投げかけた。
「使えないやつだ」
そう言うと、
ボン・クレーの身体に義手である、
鍵爪を刺した。
「あがぁっっっ」
ボン・クレーは朦朧とした意識の中、
己の任務の失敗を呪った。
・・・・あちしとしたことが、
情けをかけてしまったようよう。
ここで息の根をとめられてしまうのかしら。
・・・オカマ道(ウェイ)半ばにして志を断たれるのねい。
もうだめよう。
あちしはまさしく瀕死のスワン・・・。
今なら、どのプリマドンナにも負けない踊りをすることができるわようっっっっ。
ううっ・・・無念。
クロコダイルは動かなくなったボン・クレーには見向きもせず、
新たな部下を呼んだ。
「お呼びですか、サー」
陰のようにクロコダイルに従う、
腹心の殺し屋。
どんな汚いことでも、
無表情に行い、
殺す相手は老若男女容赦しない。
「ミスター・プリンスを見つけた」
クロコダイルの言葉に、
隅に控えた男は無言でうなずいた。
「つれて来い」
くり返される指令に、
男は無表情にうなずき、
機械的に情報の入ったデータを見た。
ミスター・プリンスを幾度となく連れて来ては、
幾度となく消した。
ミス・プリンセスに関しても同じだ。
そのたびに、
クロコダイルの嗜好にある傾向があることには気づいていた。
記憶の中にある誰かににた容姿。
誰かににた表情。
忘れられない、ただ一人の人。
その人にどこか似ている男や女たち。
自分が抱いている懸念が現実になることはない。
そう思っていた。
連日世間を騒がす、宝石盗難事件。
容疑者にその名を見た時、
心臓が止まるかと思った。
・・・サンジさん、どうして?
そして、
サー・クロコダイルが、
盗難事件の直接の担当になった。
・・・サーがあの人に興味を持ちませんように。
自分が死にかけていた時、
すべての人間は冷たく接した。
オレはひとびとに忌み嫌われ、蔑まれながら死ぬのだと覚悟した。
血まみれで、
ボロボロで、
近寄るのも見るのも嫌なような有り様だった。
闘争に破れた自分を助けようとするものは誰もいなかった。
自分の中には「鬼」がいる。
憐れみも感情も持たない鬼が。
人の死に対して何の感情もわかない。
死を向かえて感情的になるやつらの言葉などたわごとだ。
自分の死であっても意味があるものではない。
やつらと等質な死で充分だ。
だが、近づいて来た死は、
傷での死ではなく、
飢え死にだった。
あふれるほど人はいるのに、
みな敵でしかなかった。
人を憎んで生きる者には、
人も憎しみしか返さない。
当然の報いだった。
なのに、
ただ一人、
手を差し伸べてくれた人。
それがサンジさんだった。
厨房の裏で、
食い物をくれた。
うまかった。
涙が、出た。
オレの目から涙が。
「生まれた時から泣き声もあげず、涙も流さなかった」と言われるオレが。
「ギン、お前はこの男を知っているのか?」
クロコダイルの言葉が背中に浴びせられた。
悟られてはいけない。
サンジさんを知っているということは。
「記憶にありません」
嘘だ。
一日たりとも忘れた事のない人。
この人にうけた恩は言葉ではいい表せねえ。
クロコダイルに命じられるまま、
多くの男や女を攫って来た。
どこかにサンジさんを感じさせるような相手ばかりだった。
クロコダイルは、
すぐあきて、
彼らを処分した。
オレはこの手でサンジさんに良く似た男や女を殺して来た。
犯せと言われたら、
犯した。
あの人をここに連れてこねえといけねえ。
クロコダイルにおもちゃにされるために。
サーの命令は絶対だ。
オレはそれを守る。
オレがサンジさんを・・・、
サンジさんを連れて来る。
「はやく連れて来い。
気が強そうで、楽しみだ」
クロコダイルはそう言うと、
もうその話題からは興味をなくし、
別の部下にボン・クレーを処理するように告げた。
ギンはひっそりと「ミスター・プリンス」のデータを見た。
自分が出会った後のサンジさんの経歴。
今は、
ロロノア・ゾロとデキてるらしいのか・・・。
画面の中で文句を言う姿。
キレて暴れている姿。
サンジさん、
サンジさん。
焦がれて、
欲する心と、
不安と、
いらだち。
会いたかった。
あんたに、
会いたかった。
でも、
オレは命じられることをやる。
「鬼人」としてしか生きられねえから。