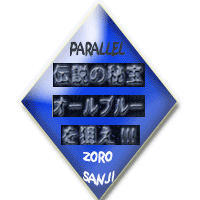
◆
96
◆
「サー、そのお召し物は!!!!!!
儀式用の服がっっっ!!!!!」
クロコダイルの側近たちは、
顔色を変えてかけよった。
「うまい言い訳を考えるのも貴様たちの知恵だろうが。
頭を使わせてやるのだ」
クロコダイルは悠然と御用車に乗り込んだ。
「サー、出られる前に濡れたということで・・・」
汗を流しつつ、策を労じる男を、冷静な女の声がさえぎった。
「いいえ、いい案があるわ。
子どもに水をかけさすのよ」
クロコダイルはそれまで無言でついてきていたその女を振り返った。
たしか、ニコ・ロビンといったか。
ひとくせありそうな女だが、有能だから手元に置いている。
くだらない権力主義や力のみを過信する男どもより、
よほど知に長けている。
「それでいい」
クロコダイルが許可をあたえると、
それを実行すべく
部下が駆け出してゆく。
人々は偉大なるクロコダイルの姿を一目みようと、
クロコダイル邸の前で待ち続けていた。
クロコダイルを乗せた車が、
閉ざされた門から姿をあらわすと、
待ち構えていた民衆は一斉に歓声をあげた。
クロコダイルは窓を開け、
笑みを浮かべて人々に手を降った。
民衆は最初から濡れているオレには気づかない。
そして、愚かな子どもの失態に驚き、恐れ、
それをとがめないオレを賛美する。
なかなかいい方策だ。
ミスタープリンスは昼間から湯あみとは結構なことだ。
あやつは自分にいくら金がかかっているかなど知りはしまい。
あの青い瞳にうつるものは、
仕切られた空間と、
オレしか必要ないのだ。
あれはこのクロコダイルのものだ。
人々の歓声は、
奥深い館の中まで届く事はない。
クロコダイルの館では、
街の喧噪がうそのようにひっそりと静まりかえっていた。
アルビダは情事の跡もそのままに床で眠っているサンジを見つけ、
顔を背けた。
アタシにどうしろというんだい。
あんたのためになんか、
何一つできやしない。
それでも手にとった毛布をそっとかけ、
クロコダイルが投げ捨てた書物を手にして、
ため息をついた。
サンジに与えられたのは料理の本と、
性的な営みやその歴史について書いた本。
それらを手にしていたアルビダは、
背後に人の気配を感じて、
あわてて振り向いた。
そこには黒髪の背の高い女が立っていた。
床に倒れているサンジを、
無言で見下ろしている。
「貴女、ここから逃げたくはない?」
アルビダは身体を強ばらせた。
この女は、確かニコ・ロビンというクロコダイルの腹心で、
暗殺の名人という噂だった。
これまでに顔を会わすことはあったが、
言葉を交わしたことはない。
その女が、どうしてここに?
ニコ・ロビンは味方?
それとも敵なのか?
「このままでは、貴女も私もいつかクロコダイルに消されるわ。
その前に先手を打つのはどうかしら?」
罠かもしれない。
でも、命運つきたのであれば、
もうとっくに死の国に着いているはずだ。
「アタシだって、このままでいいとは思っちゃいないよ。
・・・でも、どうやって?」
「そう、私たちにはあの男は殺せない」
ロビンはそう言うと、
視線をサンジに戻した。
「サーはそのコにご執心」
そう言って、
ロビンは一冊の本をアルビダの手に手渡した。
タイトルのない真っ黒な本。
アルビダは震える手で、
その本を受け取り、
サンジの側にそっと置いた。
変わらないものなど、
この世にはない。
それが光に向かって進むか、
闇に向かって進むか、
知っている者など誰もいない。
何かを変えたければどうすればいい?
じっとしていても何も変わらない。
全てを賭けて進むしかない。
全てを信じて進むしかない。
アタシは間違ってなんかない?
なのに何故こんなに苦しい?
誰か。
閉ざされた扉を開いておくれ。
アタシのために。
そして、
このコのために。