| MIDIって何? |
| MIDIとはMusical Instrument Digital Interfaceの略で、世界共通の 電子楽器の規格です。MIDI規格が、出来る前は、電子楽器のメーカーが違ったり、同じメーカーでも機種が違うだけて、データの互換性が失われていました。つまり、制作音源以外で演奏するときは、いちいちデータの変換をしなければならなかったのです。MIDI規格の登場により、メーカーや楽器の種類が違っても、 それぞれの機器の性能に応じて演奏情報を伝えることができます。つまり、データの変換が必要なく、メーカーの違いや音源の違いがあっても、それなりに同じ演奏が出来るようになりました。 インターネットでは普通、演奏情報をスタンダートMIDIファイル(SMFと省略されることもあります)という データ形式に変換してやりとりします。つまりスタンダートMIDIファイルを ダウンロードして音源とプレイヤーさえあれば手軽に音楽が楽しめるわけです。 (ただし著作権に注意) |
イメージ図
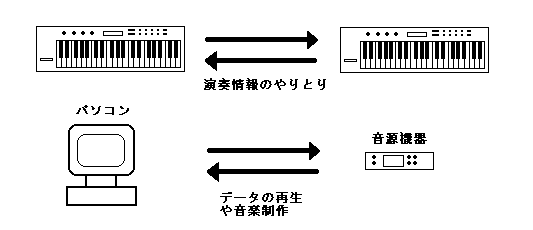 |
|
| MIDIとMP3やWaveデータなどの音声ファイルの違い |
MIDIとMP3やWaveなどの音声ファイルの違いを挙げると、
音声ファイル
- 音そのもののデータである。(いわゆる波形データ。これはとても容量がいる。)
- 早送りをすると音程が高くなる。(その反対も)
MIDIファイル
- 音そのもののデータは音源に任せ、音の高さ、長さ、強さ、発音タイミングなどの情報が記録され それを音源に送ることで音楽が演奏される。
- 早送りをしても音程が変わらない。
- 特定のパートを自由にコントロールできる。
とまあ他にもいろいろ挙げることができるでしょうけど、MIDIが優れている所はなんと言っても ファイル容量が軽いことが挙げられます。それゆえ手軽に音楽を伝えることができ、 ネット上で流通しているのもこのためだと言っても良いでしょう。 |
| 今はもうパソコンだけでMIDIが楽しめる! |
| 最近はソフトシンセというものが出てきてパソコンだけでMIDIが楽しめる ようになっています。ソフトシンセとは文字どうりハードの音源をソフトの 形にしたもので、今やその音はハードの音源と聞き比べてもたいして変わりの 無いものとなっています。(価格も手ごろ)今のパソコンには大抵何らかの ソフトシンセが入っていて、Windows98にも簡単なソフトシンセが標準で 入っています。だから今やわざわざハードの音源を買わなくても、 手軽にMIDIを楽しめる時代となっているのです。 |
| |
| GM、GS、XG |
| MIDIにはもともとGM(ジェネラルMIDI)という規格がありました。 GM規格とは音色数128で、その音色配列を統一しメーカーが違っても GM対応の音源なら同じ演奏表現ができるようにしようというものです。 しかしこれだけでは音色数、表現等に限界があるため、GM規格を拡張し、より高度な 演奏表現を目指すために作られたのがRoland社のGSとYAMAHA社のXG という規格です。両者はGM規格をベースに作られているので、GM規格で 作られたデータも演奏することができます。そしてGSやXG対応のデータを それぞれの対応音源で演奏させればより高度な演奏ができるというわけです。 代表的な音源にGSではSC(サウンドキャンバス)シリーズ、XGでは MUシリーズがあげられます。 |
イメージ図
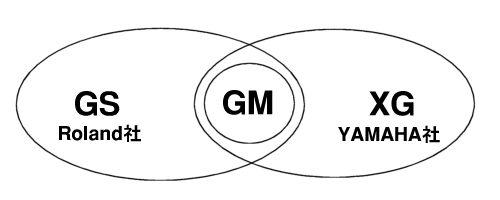 |
|
| |
| MIDIの弱点 |
| これだけ便利で流通しているMIDIですが、弱点もあります。先ほど触れたように 音そのものの情報は各自の音源に頼っているので、音源が違えば当然演奏も違ったものと なってきます。それを少しでもなくそうとGM規格などが出てきたわけですが、やはり メーカーの違いなどで音色の微妙な違いがありデータ制作者の意思とは違った演奏に なってしまうことがよくあるのです。特に作りこめば作りこむほど音源固有の機能を 使うことになり、労力をかけたデータほどますます互換性が無くなってしまうというような悪循環になる場合 もあります。(全く同じ音源なら問題は無いのですが・・・) |
| |
| 著作権とMIDI |
MIDIにも立派な著作権があります。それぞれのMIDIによって扱いが違いますので、個別に説明します。
■オリジナルMIDI(当サイト→「オリジナルMIDI」「投稿オリジナルMIDI」)
著作権は、データ制作、及び作曲者にあります。オリジナルMIDIに関しては 自由にお使い下さいとの記載がされているHPもありますが、HP等のBGMに使いたいという場合は、原則、 メール等で直接製作者に尋ね、使用許可をもらわなければなりません。
■オリジナル以外のコピー、アレンジ等のMIDI
(当サイト→「久石譲MIDI」「スタジオジブリ作品主題歌MIDI」「その他のMIDI」)
いわゆるプロの楽曲ですが、著作権を管理しているのは作曲者や製作者ではなくJASRAC(日本音楽著作権協会)がすべて一括管理をしています。ただし、2002年から著作権の管理形態が変わり、JASRAC以外の民間団体でも、著作権を管理できるようになりました。 原則、その管理団体(JASRAC等)の承諾が無ければHP等に掲載することはできません。MIDIは関係無いと思われる方もおられますが、2001年7月から、個人HP上のJASRAC管理曲(プロの楽曲ほぼ全て)のMIDIに関しても、JASRACの承諾が無ければ掲載することが出来なくなりました。 |
| |