犬養写真館 別館
5月3日より5日まで関西に旅行に出かけておりました。
ここではその一部を「日常雑貨店」と「犬養写真館」と合同にて
その内容をお届けしたいと思います。
ただし非常に個人的趣味に偏った内容なのでお気に召すかどうか…
今回の関西めぐりのテーマは
「
広いところ・見晴らしのいいとこへ行こう!」![]()
![]()

到着したときの曇りの天気が晴れに変わったので、近鉄吉野線飛鳥駅より自転車を借りて明日香村を探索すると相成りました。
樫原(字が違うんだけど漢字がないのでごめんなさい)神宮前駅からリュック担いだ人たちが沢山いたので、「皆明日香行くのかなぁ〜。混んでいたらいやだなぁ…」と思いつつ電車に乗りました。2つめの飛鳥駅についたときにどどどーーーーんと大量に人は下車し、駅前のレンタサイクル屋各社は客取り合戦を繰り広げていました。いままで何度も飛鳥には訪れていましたが、こんなに混んでいることは今まで一度たりともなかったので
 2.天武・持統天皇陵の事実
2.天武・持統天皇陵の事実
先ほどの道から鬼の雪隠・俎という不思議な石跡(飛鳥には不思議な石の史跡が沢山あります。ここからちょっと行った所にある亀石は一番有名でしょう)を通り過ぎると右手の奥に丘があります。
(ここら辺で木がうっそうとした小高い丘はほとんど古墳と考えていいと思います。)その丘はかの有名な天武・持統天皇陵なのです。この写真は陵を登りきったところにある門を撮ったのですが
右手の松の隣にある立看板は天皇・皇族陵には必ずある宮内庁の注意書きなのです。一時天皇陵フリークだった私はいろんな天皇陵に行きましたが、ここはちょっと不思議な事実があるんです。
天皇陵はその性格上中の確認とかは一切されない(できない)そうなんです。なので天皇陵の中には伝説にもとづいて定めているのもあります。ところがこの天武・持統天皇陵は実際のものだと確認ができています。何故かって?それはですね、昔この陵には盗賊が入りまして、そのおかげでここは中の状態とかすべてわかっているんですって。
普通天皇陵なんて私のような物好きくらいしか行かないものなんですが、さすがに今日は人がけっこう来ておりました。

天武・持統天皇陵から亀石をぬけて数分行った所に川原寺跡があります。跡なんでこのように野原の中に石とか設置されているだけで、かろうじて「ああここがそうなんだ」とわかるようになってます。川原寺は弘法大師ゆかりのお寺でこの後ろには現在の川原寺があります。正面の建物は聖徳太子が生誕した馬小屋のあった橘寺です。ここにも二面石といわれる石跡が境内にあります。
今回はとにかく広い所に行きたかったので、真ん中に立った時はなんともいえない感動がありましたね。本当に周りは何もないんですよ、ここって。

川原寺跡より北西にちょっといったところに伝板蓋宮跡という名前のところがあります。ここも川原寺のように跡地として石畳などがあるだけなのです。しかも頭に「伝」とついていることから現在もここがその場所だとは断言していないようです。板蓋宮は天智天皇(当時は中大兄皇子)が藤原(中臣)鎌足と共謀して大臣蘇我入鹿を殺害した場所です。千年も時を経た今では歴史の複雑な事実を微塵も感じさせない気持ちのよい場所ですが、ここに立つといにしえの人たちはどんなことを思いながら立っていたのかなとちょっと千年昔に思いを馳せてしまいます。できることならドラえもんのどこでもドアでその時代を覗いて見たいです。
 こうなっているんですよ
こうなっているんですよ
有名な石舞台古墳は裏手から古墳内に入ることができるようになっているんです。といっても中は石棺などはありませんけどね。広さは人が20人ほど入ることができるくらい広いのです。さすが蘇我馬子の墓だろうといわれているだけあって規模は大きいです。当時は岩の上には土が盛ってあっていたといわれています。千年の間にすっかり土はなくなっちゃいましたようですね。ちなみに岩の上に昇ることはできません。念のため。(誰もそんなことしないか…)

石舞台古墳の側面です。人と比べると古墳の大きさがよくわかると思います。本当に大きいんですから。

石舞台古墳の隣は石舞台公園という憩いの場となっていました。(数年前はなかったぞっ!)ちょうどお昼時でしたので家族連れの人たちがお弁当を広げていました。古墳入り口前に割と大きい売店がありますからそこでお弁当買って食べている人もいたようですし。真ん中の建物は宮殿の入口のような形をしたものなんですが、何でこのような建物にしたかちょっと???。宮跡でもないのにねぇ…。
GW中だからこんなに人がいますけど平日にはほとんどいないんですから!この辺て。

石舞台古墳の次に行った飛鳥寺の入口売店で売っていたおにぎりなんです。赤米という珍しいお米でできてます。赤米は明日香で作っているお米だそうです。ちょうどお寺についたのが12時過ぎていた頃なので小腹がすいた人たちが次から次へと買い求めていました。私のお昼もこれで済ませてしまいました。1個100円で売っていたのでとても安く済んじゃいました。
ああよかった♪

飛鳥寺は聖徳太子の頃の創立の寺で、その後天智天皇が藤原鎌足と初めて会った場所として知られています。
金堂に奉られているこの仏像は百済系の止利仏師作で、作られた当時のものは顔と指の一部だけですが、実は日本最古の仏像なんです。東大寺の仏像よりも150歳も年上です。
創立当時のお寺の敷地は現在の25倍の規模で(遺跡発掘により確認がとれています)、何度も何度も火災などに遭いながらも仏像だけは吹きさらしの火事跡に残っていたそうです。発見されたときはこの同じ場所にぽつんと置き去りになったような状態で、すすだらけの姿だったと。
数年前ウスイさんとこのお寺に訪れたとき、ウスイさんは仏像が建物もなくたった一体だけで残されたという話をお寺の人から聞きながら感極まって泣いてしまったんです。
そのときはウスイさんの気持ちが分からなかったのですが、今回この場に座って合掌した時にやっと分かった気がします。千年以上も時を経てこの場で仏様と遭えたことがとてもすばらしいことだと胸が熱くなりました。
きっとでかいだけの東大寺の大仏では、一生こんな気持ちになることはないんだろうな。
 ちょっと変わった面立ち
ちょっと変わった面立ち
飛鳥大仏の正面ですが、この仏像の表情ってちょっと面白くなっているんです。向かって右から見ると怖い顔で、左から見ると優しい顔なんです。これは本当ですよ。実際にお寺の方の説明受けてから両方の側で見てみましたから。
からくり好きな止利仏師らしいなぁと感心してしまいました。

飛鳥寺の庭にあるこの岩は礎石として使っていたもので、仏様と同じ年だけこの場所にあります。岩だって馬鹿に出来ません。飛鳥は岩だって立派な遺跡として成り立っているんですもん。

飛鳥寺の裏にあります蘇我入鹿の首塚です。といってもこれも「言われている」ものなんです。飛鳥板蓋宮で暗殺された入鹿の首はここに葬られたという言い伝えのもと、今も訪れる人は絶えません。
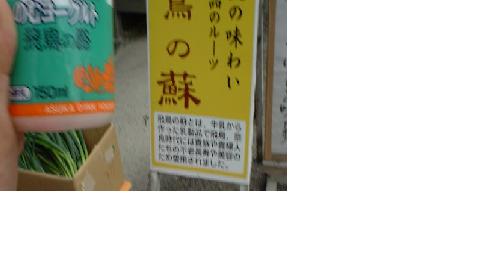
左の飲むヨーグルトが「何でこのシリーズに??」と思われたでしょう。飛鳥寺の売店で赤米のおにぎりと一緒に売られているものです。
ヨーグルトのルートである「蘇」という乳製品が大陸から最初に伝わったのが実はこの飛鳥で、しかも聖徳太子が生きてきたときには既に食されていたのです。今と同じ美容食だったとか。