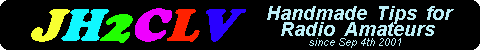
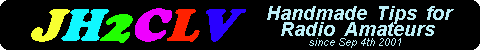
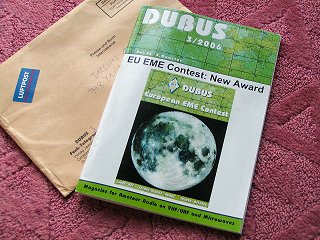
|
今日は大晦日。時間不足でやり残しがいっぱいあって落ち着かない中、庭の草むしりをやっていたら郵便屋さんが国際郵便を届けてくれた。身に覚えの無い差出人だが宛名は間違いなく自分である。恐る恐る開封すると何とDUBUSの3/2006号(写真)だった。知人の福島氏(JH6RTO)が拙作3-500Z/144MHzアンプの紹介を同号の中で行なっている。併せて編集部に当該誌の配布をお願いして頂くなど、粋な計らいに感謝している。氏とは今年の5月27日、FEDXPとSDXRAの合同ミーティングで初めてお逢いしたもので、その際私の持ち込んだ資料の利用を申し出て来られた。 さてこのアンプは1997年(CQ誌1998年10月号掲載)の作品である。f-max=110MHzの3-500Zを144MHzで使うと言うことで、当時ちょっと話題になった。ところが、中々理解して頂けず水面下では色々と物議を醸し出した記憶がある。プレートタンク回路はLC集中定数による直列共振、即ちλ/2線路共振と等価な回路を3-500Z側面に配し無理の無いRF経路を構成。信号源に対して直列共振であるから、動作はIp最大点が出力最大点になる。並列共振(λ/4線路共振)に慣れ親しんだOM諸氏には、この怪しげな直列共振とプレート電源供給は中々理解されなかった。 |

|
28日の御用納めは22時頃仕事が明けた。早々実家に向かい正月準備に励んだ。生活拠点を名古屋から実家に移した事や母の他界もあり、例年にない年の瀬の忙しさだ。家の掃除は言うに及ばず、喪中向きの正月準備や餅つき、お寺や関係各所への挨拶回りetc・・・あっという間に時間が過ぎて行く。何気なくこなしていた母の存在をあらためて感じている。その中、犬の散歩中に声が掛かりBS受信相談にのった。時々映らなかったのが完全にNGになったらしい。チューナーとANTを持参し調べると、受像機はOKだがアンテナを含めたそれ以前がNGと判明。子供達が興味津々の様子だったので、アンテナ前に立つと電波が遮断されTVが映らなくなる実験を披露し好評だった。また地上デジタル放送の受信方法についても尋ねられ説明を行った。既に暗く途中で作業を打ち切ったが多少の案内にはなったものと思う。更に別件だが、四国の知人より「文豪ミニ7RX+HDシステム」のリクエスト。空き時間を使いディスクの作成や動作確認を行った。久しぶりにMS-DOSと格闘したが、自作メニューに1991年と記してあり物持ちの良さに呆れている。写真は喪中では飾らないはずの鏡餅とオンマウスはHDイメージコピー中のMS-DOSマシン文豪ミニ7RX。 |

|
毎年この季節になると実家の南側にある柿木に小鳥たちがやってくる。柿や畑のミカンが目当てなのだが、12月も終わりに近づくとその柿やミカンは収穫が終わり既にない。それでお人好しの我々は小鳥たちが可愛そうだと言うことで、ミカンやふかしたサツマイモ等を柿の木の枝に差し込んでおく。すると小鳥たちも事情を良く知っていて毎日柿の木に舞い降り、我々の目を楽しませてくれる。 写真は今日13時頃の柿の木の様子。メジロがやってきて美味そうにサツマイモを突いている。メジロが立ち去ると直ぐ別の鳥がやってきて突つく。オンマウスカーソルすると見える小鳥は入れ替わりにやってきたヤマガラ。 この日は小鳥目的の撮影ではなかったのでサイズが十分でない。たまたま目に入った小鳥を見てルーズ気味のサイズでシャッターを押しただけ。このため写真は320x240(pix)にトリミングしてある。 ところでこの日のメニューサツマイモだったが、ミカンの半切りを差しておくと今度は図体のでかいヒヨドリも降りてくる。この場合、大きさではかなわないメジロやヤマガラは遠慮しながら遠くでヒヨドリの立ち去るのを待っている。何とものどかで楽しい光景だ。 |

|
カミサンからの電話で、次男が川崎から自転車で帰ってきたと伝えてきた。冗談だろうと思いつつ実家に帰るとそれは本当だった。 夜中の2時に川崎市多摩区を出発し、主にR246経由で御殿場を越え凡そ10時間かけて昼頃着いたらしい。この季節なのに手袋を装備するのを忘れ、手は日焼けした様に真っ赤になっていたようだ。自転車は自前で調達した物のようだが、オヤジ達が乗っている(いた)ロードレーサーとは趣が異なる。 一体何を思ったのか・・・と尋ねてもまともな答えなど返ってこない。それはオヤジが最も良く知っている。同じ年頃の30年程前、名古屋から帰ってきたり、箱根を越えたり、富士山を一回りしてきたりと色々やったが、考えてみれば大した理由など無かった。敢えて理由を探せば「走ってみたかった・・・」程度しか見つからない。 丁度実家に戻る頃、今度は3男が豊田から帰ってきた。それも名鉄やJR在来線を乗り継いできたらしい。そして顔を見たら丸坊主で、話を聞くとスキンヘッドから始ったらしい・・・こちらも何処か似たようなところがあって面白い。写真は翌日撮影した次男の自転車(黒)とオヤジのロードレーサーのツーショット。 |

|
ミカン切りも終盤。16日は前夜の雨が露として残り、作業するとビショビショに濡れる状態だった。天候は回復しているので露が消えるまで待つのがベターと思っていた。ところが7時半頃、気の早い親父は小さい木から切ると言い出し作業を始めてしまった。それに連られ作業がスタートした。しかし、始めると直ぐ軍手が、30分もすると靴の中も濡れだした。朝は8時半にならないと陽が差さない土地だから、指先はかじかみ大変な状況になった。そんな事はお構い無しの親父は黙々と切っている・・・どういう神経構造かと感心する。指先がふやけ感覚がおかしくなり、途中から軍手と靴下を交換し長靴に履き替えて作業を続けた。15時半、日没で撤収が始り作業は16時に完了。翌17日は朝から曇天で寒い朝だったが午後になると雲がはけ好天になった。天気が良いと会話が弾み活気が出てくるのが面白い。両日の収穫量は約2トン。叔父さんや姉夫婦をはじめ親戚の皆さんの応援を頂き感謝に耐えない。青島の他に少量だがはるみ(写真)と太田ポンカンも収穫した。16日夜は名物秋葉羊羹(みのや栗田菓子店販売)目当てで秋葉さんの祭りを覗くが中々の人出で驚いた。しかし羊羹は既に売り切れゲット出来ず類似品を買い求め帰宅。 |
| オンマウスすると、「きょうの清水」サイトの「みのや栗田菓子店写真」へ、クリックすると清水事情に詳しい「きょうの清水サイト」へリンクします。なお秋葉羊羹は、秋葉さんのお祭りが行なわれる毎年12月15-16日にしか販売されない貴重な品です。 |

|
昨日の雨は夜まで降ったようだ。露が残りポンカン切りの作業が出来ない朝を迎えた。それで貯蔵用の箱を準備をしたりで露が乾くのを待った。藤枝の姉夫婦・聖一色の叔父さんも手伝いに見え様子を伺っていた。 10時頃になって中河内の従兄弟夫婦が携帯ブロア持参で来られ梅雨を払い出した。暫くすると天候の回復に併せ気温も上昇し作業が出来る状況になった。10時半頃、本日の作業についての説明会(切った後の仕分け方について)を行なった後待ちかねたポンカン切が始った。仕分けの作業は3種類(2L以上・2L未満・不良)に分けて箱に並べ積み上げる。不良は色が来ていない物や形が悪いものなど・・・貯蔵段階で色や甘みが付くので復活する場合もある。 この日は昼食や休憩(カミサンの「しるこ」が出た!)を挟んで16時頃まで作業を行い、屋敷南側の約8割を切り取った。皆さんお疲れ様。 太田ポンカンとは、地元の太田敏雄さんが発見した庵原ポンカンの枝変わりが発展した品種で、昭和58年5月に登録されている。親父と太田氏は親しい間柄で、昭和50年頃から栽培を続けている。 写真はポンカンの枝越しに見るタワーとアンテナ群。 |

|
まだ少年だった頃に夢見た真空管に国産最後の7F管(プレート損失1KW~5KW未満の4極管)7F71Rがある。最初に手にしたのは19歳の頃(1973年)だったが、その容姿に圧倒され初対面にも関わらず「7F71R」の名称を一瞬にして覚える事になった。当時は813や3-500Z等のガラス球を指をくわえて眺めていた時代で、自前のアンプはTV受像機の水平出力管をかき集め4~5本パラッた物がせいぜいの時代だった。
したがって、こんな球を使うのは夢のまた夢だろうと決め付けて30数年が経過した。その辺りの話と製作を7F71R HPA Makingコーナーで紹介している。 さて写真は、7F71Rのフィラメントに通電した様子。さすがに直熱管で白熱電球を燈すのと同じ位のタイミングで明るくなる。東芝の規格表によれば余熱時間は15秒とされている。余熱のための待ち時間を嫌うDXingや、業務用途の障害対応(予備)用には最適と言えよう。余熱時間が3分もあるアンプなんてとても使えないのも、この様子を見ると良く分かる。 フィラメントの光がセラミックを通して外に伝わってくる様子が分かるように、オンマウス映像は前明かりを落として撮影している。ピンクセラミックは東芝製であるが、NEC製は白セラミックである。 |

|
左はギョッとするようなヘビの写真。カミサンが実家の通称「漬物小屋」の整理のために器を移動していたら発見。携帯電話のカメラで撮影して送って来た。
漬物小屋は暖房がある訳でもなく外気温度と変わらない状況なので、このヘビは冬眠準備でもしていたのだろうか・・・そのためか動きが悪かったらしい。それにしても携帯電話カメラのレンズはワイドだから、このサイズにするには随分と近くまで寄ったに違いない。普通ならヘビもビックリして逃げ出すはずであるから、ここではカミサンの好奇心にも拍手したい。 ところでこのヘビの種類は何?・・・実家周辺で子供の頃から良く見たヘビは①アオダイショウ②ヤマカカシ③シマヘビ④マムシ等が思い浮かぶが・・・このヘビは見たこと無い。でも色が違うがマムシの気もあるか・・・しかし皮膚に照りがある。分かる方のご教示をお願いしたい。 いずれにしてもこの珍客は好まざる客なので、尋ねてきた親戚の叔父さんに棒に引っ掛けて外に放り出して貰ったとの事。 しかし外は寒いからやっぱりここに戻ってくるかもしれない。もしそうなら、動物達も住んでいる人間を見ているのかも知れない・・・。 ・・・皆様メールやBBSへの書き込み有難うございます。「シロマダラ」が正解のようです。家の親父は「イモガラヘビ」と呼んでいましたが、めったに見ることは無いようです。 |

|
今年も既に師走。12月1日は母が亡くなってから49日の区切りであった。実家の南側にあるお墓で白木の門牌や七枚塔婆等を焼却した。また実家の床の間に仮設してあった祭壇を片付け、この間閉ざしていた神棚類を空け、ようやく普通の状態に戻った。
仏具はめったに取り出す事が無いため、何処にしまったか分からなくならないように一ヶ所に整理して収納した。今までは殆ど母任せで、他の者は何が何だかサッパリの状況だったが、これで少しは改善出来たと思う。 写真は今朝7時頃、HanaとPiggの散歩で家の南側にある小道を通った時の様子。一面に白い霜が降りていたが分かるだろうか?。犬たちはこの程度の霜では何も寒さを感じないらしく普通に歩き回っていたが、自分は今年最初の霜であり思わずシャッターを押した。 天気予報は今日と明日月曜は冷えると伝えていたが、8時半頃になると朝日が差し込み霜は融け穏やかな日本晴れとなった。 今年は、7月の固定局変更検査までは順調なペースだったが、後半は引越しや母の他界など随分と人生を感じさせる出来事が多かった。取り組み中の製作・研究課題の進捗も遅れ気味だが徐々に片付けて行く予定である。 |
| 以前から同僚に奨められていた、サーバー(ネットワークハードディスク)がようやく完成した。実家には複数のPCでLANが構成されている。どのPCでネットワーキングするかはその日の気分だったりする。それだとデータは各PCのローカルディスクに分散されてしまうため、後で覗こうとした時に探すのが大変であった。と言うことで、複数のPCでデータやファイルを共有するためのサーバーを立ち上げた。このために新規に部材を購入するのは芸が無いので手持ちの小型PCを生かす事にした。またこの目的に最適なソフトが最近マニアの間で人気のあるFreeNAS Server。USBメモリやCDにインストールしそのまま起動、設定は他のPCからIPアドレスを指定してWebリモートで行なうスグレモノ。使い出すとこんなに便利なものかと感心する。 写真は玄関欄間に設置したPC(左)とルーター群(右)。PCは4年程前の秋葉ツアーで購入したEzGo+(セレロン1.1GHz)。 | 
|