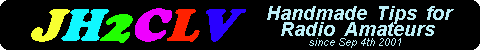
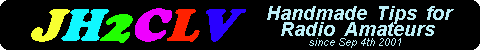
| 21日夜、ネットにつながらなくなった。PCの故障かと思ったらLANが可笑しい。ルータ・HUBのCOREGA/CG-BARMX、夏は高温で不具合多発のため、裸にしファンを付け6年も生きながらえたが、潮時か・・・。ipconfigコマンドを打ったり、PPPoE設定をPCへ移そうと努力していた。ところが24日朝、何事も無かった様に復旧している。絶対にCOREGAが悪いと、発注したBUFFALO/BBR-4MGがこの日届いた・・・。ネット依存甚だしい生活に天罰だったのかも知れない。 5日、7MHzで懐かしい友人の声。呼ぶがANT同調NGで交信に至らず。直前まではOKだったのに、電源投入だけで同調OKになってしまう。26日、雪の舞う中、屋上のATU/SG-230を外すと中に水(オンマウス)。乾かすが全くNG。投入した予備機もまたNG・・・一昨年雷でやられた事を忘れていた。これらを突きだすとドツボは間違いないので早々に修理出し。 FL-2100シリーズでロシア球改修を行った(写真)。3台やったが内2台でバンドSWが溶解。1台はFL-2100Bで未使用接点を移植し技ありの復旧。ところがもう1台のFL-2100Z、ローターごと溶解し接点移植は不可能。友人のハムショップへSWを打診するが有るかどうか・・・。不具合があると手を入れたくなる性格はどうしようもない。 | 
|

|
今日は半休を貰い三男の卒業式(修了式)に赴いた。既に学生用アパートから実家へ引き揚げていた三男は、カミサンの運転で豊田を目指した。こちらは6時半に起床し7時前に福井を発った。休日ではないので高速道路のETCは100Km までの通勤割引を利用。100Kmまで半額だからETCカード2枚でつなげば豊田までの凡そ200Kmを半額で行ける。米原ICが丁度中間点で下車。素早くETCカードを入替えて高速へ戻ろうとするが遮断機が開かない。よく見るとETC装置がカードを読みに行ったままでLEDが点滅している。こりゃまずいと思ったら担当の方がインターホンで呼んできた。データの読み取りがNGだったので、後ろの装置から出る紙カードをとり、降りる時に料金所へETCカードと共に提出すれば割引が受けられられるらしい。半信半疑だったが三好ICで指示通にすると無事半額割引が成立。9時半にカミサンと合流。天気も良く桜が咲き、辺りは卒業式らしい雰囲気に満ちていた。10時から式が始まり約50分…卒業していよいよ社会人かぁ。子供の頃や過去の入学・卒業などのシーンがまぶたに浮かんできて感慨深い。本当に早いものだ。この日は所用のため14時過ぎ福井へ戻った。写真は開式直前の会場、オンマウスは帰路の日野山。 |
| 18日20時半頃福井ICへ入り清水ICを下り帰宅すると24時半。途中北陸道を北上する消防の隊列や、その他支援車とすれ違った。名神・東名をつないで東京を経由するより、西日本なら日本海側を通った方が東北は早く確実なのだろうか。名神・東名ではその種の隊列を見ることは無かった。道中の安全と現地での活躍を祈る。今回の帰省は、20日、孫の顔を三男と見に行こうと企てた。ところが、19日にミカンの間伐木をチェンソーで刻んでいたところ、一部に残っていた枯木に当てた瞬間に跳ね左手首の軍手に接触。この際左手皮膚を浅く切ってしてしまった。治療後の大事をとり名古屋行きは見送ることになった。全く不注意も良いところでお恥ずかしい。幸い傷は浅く回復を早めるために縫ったが、傷口はバンドエイド1枚で覆える程度だった。三男は4月から就職するため、東京から帰省した次男も加わり夕食は送別と壮行の会になった・・・早いものである。20日は初孫の命名書を書き神棚に掲示。最近毛筆など試したことが無いのに、カミサンからPCはダメと念を押され何とか筆書き。お世辞にも上手とは言えないが、字は踊っていても気持はこもっている。13時福井への帰路に就き17時帰還。GSは20㍑給油制限の連続だった。 | 
|

|
11日発生した大震災、TVで流れる津波映像はこの世のものとは思えない。あの中に避難できなかった人が居たのかと思うと言葉もない。何とか時間を逆戻しできないものかと床で祈った。迷っていた翌12日、3男の引越しを敢行。卒業・就職のため家財を豊田から実家へ引き上げた。カミサンも来る予定が、大津波警報が継続し親父が心配で急きょ休止。7時に福井を発つと、名古屋の長男から東名とR1が通行止で大渋滞だから止めとけと電話。しかし、何とかなるとそのまま走る。三好ICを降り豊田に着くと9時半。積むばかりかと思いきや、出来ていたのは本の段ボール詰めだけ。本棚やコタツは分解し積み易くしたが、それ以外に梱包し難い物がごろごろ。何とか車に積むと未だ衣装や生活用品が散在。すると3男、15日もう一度運ぶから大丈夫…この日が最後かと思っていのにぃ。まぁいいやと区切りをつけ出発すると11時。豊田ICから先は予想外に快適だったが静岡ICで下されR1を走る。清水へ入るとR1も旧R1も大渋滞。裏道を抜け14時過ぎに帰宅。荷物を下し昼食を取り15時半福井への帰路に就く。カミサンが手料理とはるみを持たせてくれた。そう言えば昨晩、嬉しい初孫が誕生し遂に爺になった。写真は出発前、前日の雪を被った愛車。 |
| 週末の空き時間はFL-2100Bの改修にあてた。ソケット穴が油圧パンチで開けられるようになったら作業が格段に早い。単身赴任と言えど家事洗濯に食事の支度などで意外と時間がない。点けっ放しのTVも誘惑する。作業が終盤に入ると手作り部分も多くなる。FL-2100Bを眺めつつFL-2100Zでの経験を含め改修イメージを固める。オリジナリティは尊重したいが、あまり個性を出しても…と葛藤、似て非なりの2台だから。Esg回路は自作で決まり。Ecg用はオリジナルでは不足なのでこれも自作。FL- 2100Zと同じ3倍圧回路をEsg基板に同居させる。そして形になったものを後部箱へ実装。そんなこんなで気づくと22時半。こりゃまずいと早々に電源投入し電圧確認。ここまでは良かったが問題はその後。エキサタをつなぐと漏電NFBがトリップ。おかしい。調べるとAC側巻線の一つが地絡。そんなことがあるものかと何度も電源を入れ直すがその度に部屋は真っ暗に…。電圧設定端子で地絡していた。そう言えば、頭の取れたビスが残りにっちもさっちも行かない状況だったのを掘り出していた。端子の中に金属屑が残っていたのだ。なってこったぁ!だったが、これで見事動作。時間は25時。写真は800Wで連続60分キーイング中の改修FL-2100B。 | 
|

|
早いものでもう3月。今日は桃の節句だと言うのに昨晩から冷え込み雪が積もった。帰宅した22時頃は横殴りの雪であおられて寒く、傘が逆さまになる状況だった。 さて、転がり込んでいるFL-2100Zの2号機改修作業は極めて順調に進んでいる。受電電圧を200Vに変更し、7MHz/CWで動作テストを行うと40Wのドライブで約800Wを出力する。ちなみに1KW出力を得るためには70Wの入力が必要になる。この場合はすでに飽和領域に達している。これらの数字は1号機とほぼ同等であり、極めて再現性が高い事が分かった。ただ残念なことに1.9MHzと3.5MHzバンドで、プレート補助コンデンサを開閉するバンドSW接点が溶解しており、現在同調点が得られない状況。おそらく前オーナーがハイバンドでチューニング中にVHF帯で寄生発振が起こり、放電した熱で溶解したと推測される。なお2号機には50MHzを組み込む予定はない。 写真は凡そ1ヶ月振りに雪が降り積もった福市内。雪は日中に融けてしまった。オンマウスはいよいよ改修の始まる3号機FL-2100B。FL-2100Zの兄貴分にあたるリニアアンプで友人からの依頼品。改修サイトを立ち上げているのでご覧頂きたい。 |