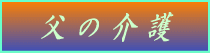|
|
|
|
| 父は100才を迎えてもなお元気で殆ど毎日東京界隈までバスと電車を乗り継いで一人で出掛けるのが日課であった。一方母は10年程前に子宮がんの手術をし、一時可成り落ち込んでいたが、早期発見のため転移することもなく、その後快復し、自分たちの食事も作っており、また時々二人で食事に出掛けるなど、有難いことに介護とは縁遠いものであった。しかし、父はある日突然の事件から「味覚障害」となり、食事が摂れなくなり入退院を2年間程繰り返すこととなった。また一方、母は父の事件ショックでそれ以来自分の食事が作れなくなり、妻の協力の下に食事の世話をすることとなった。 |
|
|
| 突然の出来事 |
|
平成8年(1998)年4月1日は朝からしとしとと雨が降り、コートを必要とする様な肌寒い日であった。父はいつものように江東区太平町にあるお寺(父はこの寺の総代をしていた)にお詣りに出掛けた。夕方5時頃になっても「まだ返ってこない。」と母が不安げに言い始めた。お寺に訪ねたところいつものように3時頃帰途に着いたとのことである。しかし7時になっても帰宅せず、警察に行き、『110番』通報に届けをし、通報をして貰った。再びお寺に連絡したところ霊断の結果「身体には問題を生じてはいない。11時頃帰宅するだろう。」とのことであった。しかし、無駄とは思いながら、8時頃JRの蒲田駅まで行き「京浜東北線沿線で老人の事故などなかったか」訪ねてみたが、何もそのような情報はないとのことであった。
11時近くになり母親宅を覗くがまだ帰っていない。11時に先の寺の住職より「まだ帰宅していませんか」との心配の電話があり、状況を説明し始めた所、「ガラガラ」と玄関の戸が開く音がしたので、電話を待って貰いながら玄関に出てみると父がタクシーで帰ってきた。
タクシー運転手の説明によると「霞ヶ関から乗ったとのことであった。また、父の話す言葉がハッキリ聞き取れないので、やっとたどり着いた。」とのことであった。
父は多くを語らないため、「お寺を3時頃出て何処をどのように彷徨っていたのかは分からない。」が、母にポツポツと語った所から想像すると「普段、昼間行きつけている大手町にある農協ビルの(夜で人影のない)階段を上り下りしていたらしい。その後、ビルの外に出てうずくまっていたところを、通りかかった人が親切にタクシーを止めて乗せてくれたようである。お礼の言いようもないのですが、声を掛けて頂いた方に感謝する次第です。 |
|
|
| 長期介護の始まり |
|
無事帰宅し、一安心したが、翌日両親宅を覗くと何時もように写経をしている様子もなく居間で横になっていた。疲れが出て横になっているが、食事などは普段通り摂れているのだろうと思っていた。
1週間ほどすると母が「食事を全然食べないのだ」と言いだした。早速、掛かり付けの病院に行き、入院して点滴を受けることになった。頭部のCTを含めて、諸機能の検査をして貰ったが、特に異常はなく1週間か10日程で退院出来るだろうとのことであった。点滴と併用して食事が少し食べたり、食べなかったりで変動したが、10日程で退院の日の昼食は全部食べることができこれで一安心と退院した。
しかし、退院後も食事時には食べさせに行くが、なかなか食が伸びず、1週間程してこのままではどうしようもないので、病院と相談し、再入院させて貰った。 |