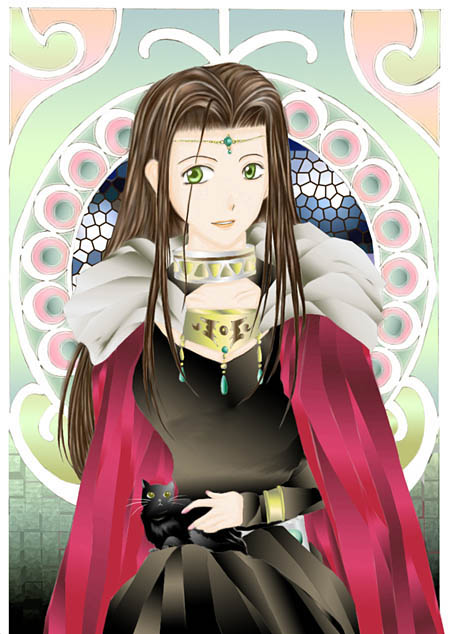
<Illustration by きっかわ様>
「おーーっす!」
と、俺はいつものように『飛翔亭』の扉を押し開けた。
まだ朝のうちなので、客の数は少ない。
カウンターの奥から、店主のディオがこちらを向き、軽くうなずく。
俺は、毎朝の指定席になっているカウンターの端の席につき、ディオに軽く手を振る。
「いつものやつ」
すぐに、エールの入ったジョッキがカウンターを滑ってくる。
なみなみと注がれたエールを、半分ほど一気に飲み干す。
寝起きでいささか鈍かった身体が、しゃきっと目を覚ます。これだから、朝の1杯はたまらない。
2杯目のエールに取りかかる頃、朝食が出てくる。
この店の看板娘のフレアさんが焼いてくれる、あつあつのマフィン。それに、タマゴを2個使った目玉焼きだ。俺の好み通り、黄身は半熟になっている。
「景気はどうだい、ルーウェン」
朝食をたいらげるのを見計らったかのように、ディオが声をかけてくる。
「ああ、良くもなし、悪くもなし、さ」
俺は肩をすくめて答える。本当は、良くない度合いの方が強いんだが、冒険者たるもの、弱みを表に出すわけにもいかない。
「なんか、適当な仕事はないもんかな? 護衛でも、怪物退治でも、何でもいいんだが・・・」
ディオは、あごに手を当てて考え込む。
「そうさな・・・。ここんとこ、その手の仕事はめっきり減っちまってるからな。戦争もない、怪物が出たという噂も聞かない。騒ぎと言えば、そら、例のデア・ヒメルの事件くらいだが、王室騎士隊が束になっても解決できないときては、冒険者の出る幕はなさそうだしな」
「そうか・・・」
「ま、世の中が平和になるというのはありがたいこったが、あんたら冒険者にとってはつらいことかも知れんなあ」
予想していたことではあったが、やはりがっかりしてしまう。
実を言えば、俺の財政状態は行き詰まっている。仕事がなければ、来月の下宿代も払えないのだ。
仕方がない。気は進まないが、やはりここは、彼女の仕事に頼るしかないか・・・。
「ごちそうさん」
数枚の銀貨をカウンターに置く。
そして、顔を上げ、なにげなくディオに尋ねる。
「そういえば、マ・・・」
言いかけたとたん、ドアが勢いよく開いて、金色の疾風が飛び込んでくる。まさに、噂をすれば影、だ。
「おっはよーございまーーっす!!」
金色に見えたのは、その長い髪だ。波打つ豊かな金髪をいくつかに分けて束ね、青く丸い髪飾りでまとめている。緑を基調にした錬金術服を身に付けているが、そのいでたちは、いささか涼しげだ・・・というか、露出度が高い。本人はまったく気にしていないようだが。
錬金術師のマルローネ・・・通称マリーは、そのままつかつかと店の奥に並んだ酒樽に歩み寄る。そして、空色の瞳で樽をじっと見つめ、右手を伸ばし、
「たぁるっ!!」
と叫ぶと、何事もなかったようにカウンターに戻ってくる。
おまじないかなにかのつもりなのだろうか、これは今や『飛翔亭』の名物ともなってしまっている。
「はい、ディオさん、約束の『燃える砂』。期日通りだよ」
マリーは布袋を取り出し、ドスン、と勢いよくカウンターに置く。
とたんに・・・
布袋の一部が発火した。
ボフッ!!
鈍い爆発音がし、黒煙がたちのぼる。
俺は急いで窓を開けに行き、マントで煙を払った。
煙が窓から出て行くと、残ったのは、すすで黒く染まったマリーとディオ、そして焼け焦げのできたカウンターだった。
ぬれタオルを手にしたフレアさんが、あわてて厨房から飛び出してくる。
ディオは、目をぱちぱちさせたが、感情を押し殺した声で、
「マリー・・・。期日に間に合わせてくれたのは結構だが、危険物の扱いにはもう少し注意を払ってほしいものだな」
一方、マリーは袖でごしごしとこすり、ますます真っ黒になった顔で、
「あ、あははは、またやっちゃった・・・」
と悪びれる様子もない。
フレアさんから受け取ったタオルで顔をぬぐいながら、ディオは、
「やり直しだな。期限は10日間延期する。ただし、賃金はカウンターの修理代の分を差し引かせてもらう。いいな」
フレアさんがにっこりと言い添える。
「それと、今日の件は、イングリド先生には報告しない方がいいわよね」
「ひ、ひぇぇ・・・」
一瞬、泣き笑いのような表情になったマリーだが、すぐに、
「ま、いっか」
とすすだらけの顔で笑う。
この立ち直りの早さ、切り替えの早さは驚異だ。
タオルで顔をぬぐい、マントについたすすを大雑把に払い落とすと、マリーははじめて俺がいるのに気付いたようだった。
「あ、ルーウェン、いたんだ。ラッキー! ちょっと手伝ってよ。これからアカデミーに買い物に行くんだけど、荷物が多くなりそうなんで、運ぶのを手伝ってほしいの。もちろんお礼はするわよ」
これは、俺にとっては渡りに舟だった。本来は、町の外に採取に出る時の護衛の方が賃金が高いのだが、金欠の今は、どんな半端仕事だってありがたい。
だが、俺は言った。
「ま、いいか。あんまり半端な仕事はしたくないんだけどな。ちょうど暇だし、手伝ってやるよ」
こちらを見ているディオに片目をつぶってみせ、マリーに続いて俺は『飛翔亭』を出た。
おっと、ここで自己紹介をしておこうか。
俺の名はルーウェン・フィルニール。数年前から、この王都ザールブルグを根城に冒険者稼業をしている。
生まれはドムハイトとの国境に近い村だ。このあたりのところはいろいろと込み入った事情があるのだが、それはおいおい明らかにしていくとしよう。
今は、職人通りの一画にある下宿屋に住んでいる。家主はハドソン夫人という口やかましいおばさんだが、それなりに居心地はいい。ひとりで暮らすには広すぎるくらいの部屋だ。もっと家賃の安い屋根裏部屋に移ってもいいのだが、あいにく今は空きがないそうだ。
俺の前をアカデミーに向かって、石畳の道をずんずん歩いて行くのは、錬金術師のマルローネ。みんなはマリーと呼んでいる。職人通りに工房を開いて自活しているが、実は錬金術を教える魔法学院アカデミーの特別試験を受けているところなのだそうだ。
聞くところでは、錬金術師としての才能は悪くないのだが、先ほどの事件でもわかるように、あまりにもあわて者でアバウトな性格のため、良い成績が取れず、アカデミー始まって以来の劣等生というレッテルを貼られてしまったのだという。そして、5年間の試験期間でどんな作品を作り出すかで、卒業できるかどうかが決まるのだそうだ。
その試験期間も、3年目を迎えようとしている。
しかし、マリーの態度は堂々としたものだ。
アカデミーの門を入ると、正門前広場の向こうに威圧感のある建物が姿を現す。
昼間なので正面の大扉は開け放されており、学生たちが行き来しているロビーが見える。
中に入ると、正面には寮棟や研究棟に通じる扉が、右側には図書室の扉が見える。何度もマリーに付き合わされて足を踏み入れているために、冒険者の俺もアカデミーの内部にかなり詳しくなってしまった。
ロビーの右手の奥が、アカデミーのショップになっている。ショップでは簡単な錬金術の材料や薬品をはじめ、高度で専門的な器具や参考書まで売っている。今日の目的地はそこだ。
カウンターの中には、栗色の長い髪をした上品そうな女性が控えている。店員のアウラさんだ。
「こんにちは!」
マリーが元気に挨拶する。
「あ、いらっしゃい・・・」
低い、落ち着いた声でアウラさんが応える。
「あら?」
マリーが声を上げる。
「きゃあ、かわいい!」
目ざとく、アウラさんの左腕に抱かれた生き物に気付いたのだ。
「どうしたんですか、その子猫」
「ええ、1ヶ月ほど前に、アカデミーの裏門に捨てられていたのよ。職員のひとりが拾って、それ以来アカデミーで育てているのだけれど、この子ったら、すっかりショップのカウンターが気に入ってしまったみたいなの。でも、元気がいいから、悪さをしないように抑えておかなければならなくて・・・」
「そうですよね、子猫なら、元気が良すぎるくらいじゃないと」
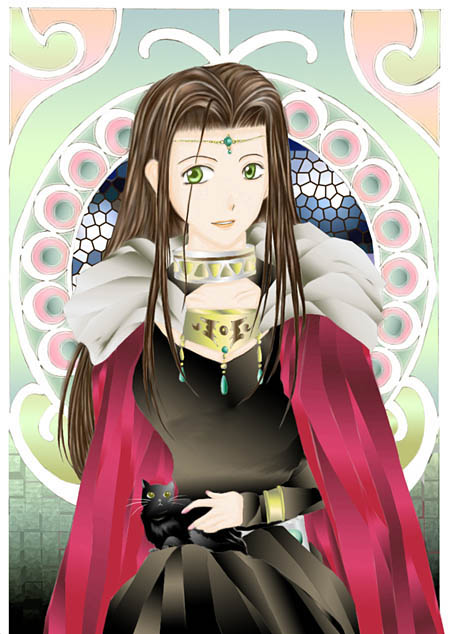
「あんたみたいに元気が良すぎるのも問題だけどな」
俺が口をはさむ。マリーは無視して、
「運動とかは、どうさせているんですか?」
「夕方になると、勝手に外に出ていくのよ。そのために、建物にこの子専用の出入り口まで作ってもらったのよ」
そうこう言っているうちに、当の子猫はアウラさんの腕を逃れ、空き箱やかごが積まれているショップの片隅で、丸くなって寝てしまった。
「あ、ごめんなさい。すっかり無駄話をしてしまったわ。今日は何がほしいのかしら」
「ええとね、今日は買いたいものがたくさんあるのよね。『祝福のワイン』を10本と、『ほうれんそう』を20でしょ、それから『塩』と『竹』と、遠心分離器も新しいのが必要だし、妖精さん用の乳鉢もひとつ・・・」
まくしたてるマリー。アウラさんはあわてず騒がず、言われた品物を棚から取り出して来ては、カウンターに揃える。無言で、伏し目がちに・・・。
俺は、おや?と思った。いつも口数の少ないアウラさんだが、今日は普段に増して元気がないように見える。先ほど、子猫の話をしていた時も、なんとなく無理に元気な声を出していたように感じられた。身体の具合でも悪いのだろうか。
買った品物を箱や袋に詰め込むのに、ああでもない、こうでもないと騒いでいるマリーの背後から、冷ややかな声がかかった。
「やれやれ、うるさいうるさいと思ったら、やはりマルローネさんでしたか。図書室まで声が聞こえていましたよ。ここは神聖なアカデミー、静かに落ち着いて、研究や思索にふける場所です。はた迷惑なことはやめてほしいものですね」
マリーの動きが一瞬、止まる。そして、ゆっくりと後ろを振り向く。
声の主は、どうやら図書室の方から歩いてきたらしい。
アカデミーの主席を4年間続けている秀才クライスは、白を基調とした錬金術服を無造作に着こなし、小脇に分厚い参考書をかかえて自信たっぷりな表情をしている。銀色の髪に銀縁眼鏡をかけ、眼鏡の奥の青い瞳には涼しげな光がある。襟の赤い記章で、彼がアカデミーの最上級生だということがわかる。
ちなみに、マリーが付けている記章の色は灰色で、これは特別試験を受験中という意味らしい。
マリーをまっすぐに見据えると、クライスは口元に冷ややかな笑みを浮かべ、右手で眼鏡の位置を整える。そして、うんざりした口調で、
「どうやら今日の私は本当についていないようですね。こんなところで疫病神に出会ってしまうとは・・・」
これを聞いたマリーが、つんと口をとがらす。
「な、なによ、いきなり! ひとのことを疫病神呼ばわりして! あたしは買い物をしていただけなんですからね。そりゃ、少しは騒がしかったかも知れないけどさ。クライスこそうるさいのよ、小姑みたいにぎゃあぎゃあちくちく・・・」
「おや、自覚がないようですから言っておきますが、あなたとの妙な賭けに乗せられて、先日もあんな西の果ての港町まで引きずり回されたばかりですよ。マイスターランク進学を控えた大事な時期だったというのに・・・。これが疫病神でなくて、何だと言うのです」
「な、何ですってぇ!」
「まあまあおふたりさん、その辺にしておきなよ。それこそはた迷惑だぜ」
見かねて、俺が割って入る。すでに、俺たちはロビー中の注目を集めてしまっていた。
こういった騒ぎに慣れておらず、目を丸くして見ている下級生。いつものことと、無視を決め込む上級生。眉をひそめる女生徒に、今日はどちらが勝つか賭けをしている男子生徒。反応は様々だが、落ちこぼれのマリーとアカデミー主席クライスとの舌戦は、今やアカデミーの名物になってしまっていると言ってもおかしくない。
もう2年の付き合いになる俺も思う。いったいこのふたり、仲がいいんだか悪いんだか。
先日、西の港町カスターニェまで採取旅行に行った時もそうだった。毎日のように、些細なことで口論の連続。止めるのはいつも俺の役目だった。
護衛やら何やらで、マリーとクライスに付き合うのは、確かに疲れる。でも、依頼があれば、俺は引き受けてきた。
なぜか。
このふたりを見ていると、とにかく飽きないのだ。放っておけない、という気持ちも、少しはあるかもしれない。ま、ディオの旦那に言わせれば「ルーウェンはお人好しだからな」で片づけられてしまうのだが。
ぷいと横を向き、マリーは買った品物の梱包作業に戻る。クライスのことは無視することに決めたようだ。俺も手伝って、祝福のワインのびんを、割れないように箱に詰める。
だが、クライスは立ち去ろうとしない。
カウンター越しに、アウラさんをじっと見つめている。
やがて、クライスが口を開く。
「顔色が悪いようですね。なにかあったのですか、姉さん」
「えええええーーーーーーっ!!」
クライスの言葉を聞いたマリーが、素っ頓狂な声を上げる。
「今、何て言ったの? 姉さんって聞こえたけど」
クライスは再び冷ややかな表情でマリーに流し目をくれ、
「おかしな人ですね、あなたは。自分の姉を姉と呼んで、何がおかしいのですか」
「だって・・・だって・・・」
驚きのせいか、マリーは言葉が続かない。驚いたという点では、俺も同じだった。この、似たところがほとんどないアウラさんとクライスが、姉弟だったとは・・・。
「そうなの。知らない人も多いけれど、クライスはわたしの弟なのよ」
知的な顔に穏やかな微笑みを浮かべ、アウラさんが言う。
「え・・・、じゃあ・・・」
と、ショックから立ち直りかけたマリーが問い掛ける。
「本当に、同じご両親から生まれたんですか」
「そうよ。まちがいないわ」
アウラさんの返事を聞いたマリーが、ふと考え込む。そして、納得したような表情を浮かべ、
「そうだったの・・・。クライス、かわいそうに・・・」
「妙なことを言いますね、マルローネさん。なぜ、私がかわいそうなのですか」
「だって、お姉さんに、性格のいいところを全部取られてしまったんでしょう? だから、そんなに嫌みな性格に・・・」
「そ、そんなわけはないでしょう! 余計なお世話です!」
クライスは、気を取り直したように姉に向き直った。
「で、先ほどの続きですが、姉さん・・・」
心配そうな弟の言葉に、アウラさんはひとつ小さなため息をついた。
「普通にふるまっていたつもりだったけど、あなたには隠せなかったようね。実は・・・」
低い声をさらにひそめて、
「アカデミーに、泥棒が出没しているのよ。ここ何週間か、ショップの品物が、次々と何者かに盗まれているの」
「ええっ!?」
俺たちは異口同音に叫んだ。アカデミーに泥棒だなんて、前代未聞の話だ。
「それでね、アカデミーでもひそかに調査を続けていたのだけれど・・・」
目を伏せ、アウラさんは言葉を続ける。
「わたしも、犯人ではないかと疑われているのよ」
「何ですって!?」
今度の言葉はクライスとマリーの口から同時に出た。こういうところは、このふたりの呼吸はぴったり合っている。
「外部から人が侵入した形跡はないし、ショップの鍵を預かっているのはわたしでしょ? 商品をこっそり持ち出して、横流ししているのではないかって・・・」
「そんな、ひどい・・・。アウラさんに疑いをかけるなんて!」
怒りのこもった声でマリーが言う。今にもアカデミー当局にどなりこみそうな雰囲気だ。
クライスの方はと言えば、眼鏡に右手を当て、目を閉じて何やら考え込んでいたが、やがて目を開く。
「わかりました・・・。話を聞いたからには、黙っているわけにはいきません。姉さん、この事件、私が必ず解決します。そして、姉さんの疑いを晴らしてみせます」
クライスの声には、決意がこもっていた。
「あたしも協力するわ!」
マリーが叫ぶ。
クライスは肩をすくめ、
「ま、仕方ないでしょう。協力するのはマルローネさんの勝手ですが、邪魔だけはしないようにしてください」
俺も言った。
「よし、乗りかかった船だ。俺も一枚かませてもらうぜ」
そして、心の中で付け加えた。
(あんたらふたりだけでなにかをやらせたら、何をしでかすかわからないからな)