|
|

|
�A�Y�B�A�[�S�E�_�b���[���H(DOP)�@100������630�~�@
�������A
�����M����^�C�v�AM.G.�Œ�34%�@���F�l�g�B�A�g�����e�B�[�m�E�A���g�E�A�f�B�W�F�B
�A�Y�B�A�[�S�ɂ�2��ނ���A�n�����Ԃ̒Z���u�v���b�T�[�g�v�Ən�����Ԃ������u�_�b���[���H�v�ł��B���|�I�ɗ��ʗʂ������̂̓v���b�T�[�g�B�Ⴂ�͏n�����Ԃ����łȂ��A�������Ⴄ�̂��Ƃ��B����̂͏��K�͂Ȃ������Ă����_�b���[���H�A�E�����ł�������n�������Ă��邽�߃A�~�m�_�̌�������������B�������͌����v�`�v�`������B�l�`�b�Ƃ��������ł͂Ȃ��A�{�\�{�\�Ƃ�����������B�|���͂��邪�������Ȃ��̂ŁA���Ă���Ƃ���A���ł��H�ׂ���`�[�Y���Ċ����B(2006.1.7)
|
|
|

|
100������850�~�@12�����`24�����n���̃A�Y�B�A�[�S�E�_�b���[���H�B�n���������������A�A�~�m�_�̌����������o�Ă���B�H�ׂĂ݂���p���~�W���[�m�E���b�W���[�m�̂悤�ȃW�����W�����Ƃ����H���ł͂Ȃ��A�v�`�v�`�Ƃ����u��������v�̗������Ƃ��̂悤�Ȓe����悤�ȐH���B�A�~�m�_�̓A�~�m�_�ł��l�X�Ȏ�ނ�����̂ŁA�p���~�W���[�m�E���b�W���[�m�Ƃ͂܂�������A�~�m�_�Ȃ̂��낤�B�A�~�m�_�̌������o�Ă遁�|�݂������Ղ�Ǝv���������������A���ׂẴA�~�m�_���|�݂�������킯�ł͂Ȃ��������B���������e�����āA���N�����l�i�������Əオ���Ă��܂��ˁB(2007.12.1)
|
|
|

|
�t�F���~�G�ōw���̃_�b���[���H�A100����987�~�B�n���^�C�v�Ȃ̂œ��R�v���b�T�[�g��艩�F���B�����������Ă��čd���B���ނƂՂՂƁu��������̗��n�v�̃A�~�m�_������B�n���̎Ⴂ�v���b�T�[�g�������b����44���ɑ��āA�n���^�C�v��34���ƒႢ�̂́A�n�����Ă����Ɠ����b������̂ł͂Ȃ��A���Ƃ��Ɠ����b�����炵�č���Ă���̂������ł��B�Ȃ̂Ńv���b�T�[�g���_�b���[���H�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��A�Ƃ������ƁB���Ƃ��p���~�W���[�m�E���b�W���[�m�Ȃ����������ǁA�����n����������̂͒E������MG��߂ɍ��̂́A�����ɏn������Ă���ԂɎ��b�����_���L��������̂�h�����߂炵���B(2008.5.30)
|
|
|

|
�搶�̃C�^���A�E���F�l�g�B�̂��y�Y�`�[�Y�B�_�b���[���H�̒��ł�����ɏn�������āA�Ȃ��4�N���̃X�g�����F�b�L�I�B�n���̓x�����ɂ���āA�u���b�c�@�[�m�v�u���F�b�L�I�v�u�X�g�����F�b�L�I�v�ƌĂѕ����Ă��邻���ł��B�{��C�^���A�̃`�[�Y�V���b�v�ł́A�n���Ⴂ�������ƕ���ł��āA���낢��H�ה�ׂĂ���4�N����Ԑ搶�̂��D�݂������Ƃ������ƂŁA�����Ă��Ă������������́B�d���g�D�̒��Ƀ|�c�|�c�Ɗۂ��`�[�Y�A�C������A���̒��Ƀ`�[�Y�̗܂ƌ����鐅����������ƁB�`�[�Y�̗܂�����͔̂��������؋����Ă�������ˁ`�B�H�ׂĂ݂�ƁA�|�݂�����[���ƔZ�k����Ă��邯��ǁA���b�������Ƃ��Ə��Ȃ��������_���L���S���Ȃ��A�ƂĂ����킢�[���B�������A�~�m�_�̌����́u��������̗��n�v�B���̐H���ʼn��̃A�~�m�_����������ʔ����˂��Đ搶�Ƙb���Ăāu�ł�����A�l�͈�����E�E�E�v���āB�͂́B�}�j�A�̊Ԃ����̉�b�ɂ��Ă����܂��傤�B(2008.9.6)
|
|
|
|

|
�A�Y�B�A�[�S�E�v���b�T�[�g(DOP)�@100������630�~�@
�������A�����M����^�C�v�@M.G.44%�@�C�^���A�E���F�l�g�B�g�����e�B�[�m�E�A���g�E�A�f�B�W�F�B
�u�A�Y�B�A�[�S�v�͕W���烁�[�g���̍����n�тɂ��鑺�̖��O�Łu�v���b�T�[�g�v�Ƃ͉����̈Ӗ��B�n���H���O�Ƀv���X�����̂������ŁA�n�����Ԃ͂�20�`40���B���Ƃ��Ƃ͗r�����������̂��A16���I���ɋ������ɕς�����Ƃ��B
�s�K���Ȍ������������܂����A����͂��Ƃ��ƃA�Y�B�A�[�S�ɂ͂���C�A�Ȃ̂ł��傤���A����Ă����J�j�J���z�[���ł��傤���B�킩��܂���B���`�b�Ƃ����e�͂�����A�Â݂Ǝ_�����قǂ悭����D���������B�r�̂����Ă�Ƃ����Z�����Ȃ��ƂĂ��H�ׂ₷���B����p�̃`�[�Y�Ƃ�������ہB(2007.11.10)
|
|
|

|
�t�F���~�G�ōw���A100����746�~�B������ۂ��N���[���F�Ƃł��\���܂��傤���B�O��͔��������C���ł����A���͊������Ă܂���B�ՂՂƃ��J�j�J���z�[���������܂��B�C�^���A�̐��Y�ʑ�5�ʁB(2008.5.30)
|
|
|

|
�A�l�y�c�@
�������A���M����^�C�v�@���{�E�k�C�����S�l����(����q��)
�A�l�y�c�Ƃ̓A�C�k��Łu�ׂ���v���Ӗ����Ă���B���䂲�v�Ȃ͓�������ڏZ�g�B��4��All
Japan�i�`�������`�[�Y�R���e�X�g�ŋ��܂���܂��ꂽ�̂����̃A�l�y�c�B�����ڂ������R���e�Ɏ��Ă��āA�i�b�c�̕���������܂��B�L�����ׂ����ƂĂ����������B�ق��ďo���ꂽ��R���e���Ɠ����Ă��܂������B�v���t�B�[���ɂ͏����ĂȂ��������ԈႢ�Ȃ����M����^�C�v�ł��ˁB(2009.6.6)
|
|

|
14�����n���̂��́B�i�b�c�̕����������A�_���͍T���߂ŃA�~�m�_�̌����������A�|�݂Ƃ̃o�����X���悭�A���{�l���D�ރ^�C�v�̃`�[�Y���Ǝv���܂��B�R���e�Ɏ��Ă���̂ł����A����̂͐�G�肪��U���b�Ƃ��Ă���悤�ȋC�����܂��āA�A�b�y���c�F���[�ɂ����Ă���ȂƎv���܂����B���S���Ĕ�������{�̂����߃`�[�Y�B(2010.09.04)
|
|

|
12�����n���̂��́B�I�ɍ����Ŕ����Ă������́B���H�ׂĂ����i���̈�ۂ̃A�l�y�c�ł��B�ց[�[���i�b�c��ӓ��̃��[�X�g���������܂��������������悭�āA���������`�[�Y�ł��B�L�����ׂ����̂������ł��ˁB�����s���Č������H�[�̂ЂƂł��B(2011.07.31)
|
|
 |
�k�C���E���S�ɂ���`�[�Y�H�[�u����q��`�[�Y�H�[�v������`�[�Y�A���O�́u�A�l�y�c�v�B�q��߂��̏���̖��O�������ł��B�O��̐F�A�����f�ʂ̔������N���[���F�A�����ăi�b�c�̂悤�ȍ��������肪���܂��B�H�ׂĂ݂�ƁA�L���ȃR�N�ƔZ���ȃ~���N�̎|�����������ς��ɍL����܂��B���������������`�[�Y�����ʂɓ��{�ō���Ă��āA�������Ƃ��o���邱�Ƃ��f���炵���ł��B(2018.3.18)
|
|
|
|

|
�A�{���_���X(AOC)�@100������630�~
�������A���M����^�C�v�@M.G.48%�@�t�����X�@�T���H���n��(���[�k�E�A���v).
�A���v�X�R�[�̎R�̃`�[�Y�B���O�̗R���͋��̕i��A�{���_���X�B�n�����Ԃ�90���B���ʂ��ԗ֏�ɔ����Ă���̂������ŁA�̂͂��̂��ڂ݂ɓ�������ĎR����ӂ��Ƃ̒��܂ʼn^�������肵���炵���B�����悤�ɑ��ʂ��ԗ֏�ɔ����Ă���{�[�t�H�[����荂�������a���������T�C�Y�B����͉Ă̍��n���q�́u�G�e�E�A���p�[�W���v�B�R�N������i�b�c�̂悤�Ȗ��킢�B�\��͎���ĐH�ׂ��ق��������ƌ���ꂽ���ǁA�O�̂��ߐH�ׂĂ݂���H�ׂ�ꂽ�B(2004.11.6)
|
|
|

|
�O��̓r�X�P�b�g��Œ��F�A���g�͉��F�݂̋����A�C�{���[�B����ɂ̓A�~�m�_�̌����͌�������Ȃ��B���H���Ă݂�ƁA���C���K�x�ɗ����Ă��āA�R�N������|�����\���A���Ȃ���������B���C�����~�����Ȃ�B
�v���t�B�[���ɂ͌ÒЂ��̂悤�ȍ���Ƃ����̂����邪�A������������͊������Ȃ������B(2007.3.3)
|
|
|

|
�i�b�c�̂悤�Ȃ����Ă肵�Ă��āA�������قǂ悢�����ŁA���S�ł��閡�B(2007.8.4)
|
|
|

|
�����͏n���m(MOF)�N���X�`�����E�W���j�G���̎肪����`�[�Y�̌����B�N���X�`�����E�W���j�G���̎肪�����A�{���_���X�B�\��͂��Ȃ苭�߂Ȋ���������ł��܂��B���͌Â��Ɖ��̔[���Ƃ��q�ɂ̂悤�ȓ����Ǝv���܂������A�l�ɂ���Ă͌C�̒��̓����Ƃ��A�ʂ��Ă��Ă�����҂̍���Ƃ��A�����̍���Ƃ��A�����Ȉӌ����o�Ėʔ��������B�H�ׂĂ݂�ƁA��ʓI�ȃA�{���_���X�Ƃ���Ȃɂ��Ⴄ���̂Ȃ̂��Ƌ������B�������ς��ɖI���̕����Ɩ��A�����Ă���[���Ɩ���Z�k�����悤�Ȗ��x�̂��閡�ł��Ȃ�������B�Z���Ȃ̂ő����͐H�ׂ��Ȃ����A�ԃ��C���Ƃ��т��т��Ȃ���H�ׂ�͍̂ō��ł��B�Ă��N���X�`�����E�W���j�G���̃A�{���_���X�ɏo�������A�܂��H�ׂĂ݂����Ǝv���B(2008.10.4)
�����B�N���X�`�����E�W���j�G���̃`�[�Y�́u���E�`�[�Y����(��)�v����̎戵�B
|
|
|

|
�p���؍ݒ��Ƀ}�_��HISADA�̃`�[�Y�u�K�ł����������A�{���_���X�B�����1�N���炢�̏n����Ԃł��B����̃J�r���O��Ɋۂ��V�~�����Ă��܂��B�i�b�c�̍��肪���āA�������قǂ悭���S�ł��閡�B(2012.6.30)
|

|
|
|

|
�X�C�X�Ƃ̍��������ɂ��郌�E�W�F���œ������{�l�̃`�[�Y�E�l�̎R�����v�����ꂽ���́BY�q�搶�����n�̔����Ŕ����Ă��Ă������������̂ł��B�ȑO�A�R������A�����ɃZ�~�i�[�ōu�t�����ꂽ�ہA�`�[�Y���Ԃ�����ɃA�{���_���X���������������ƕ����Ă����̂ŁA���҂��Ă��������Ă݂܂����B�����ڂ͏�����߂̊������ȁH�Ƃ�����ۂł����B�H�ׂĂ݂�ƁA��H������Ǝv���Ă��������ƈႤ�B�A�{���_���X�炵�����������Ȃ��B�ÒЂ����ۂ��������Ȃ��A��������Ƃ��Ă��Ė�������Ă��Ȃ��B�搶�����������Δ����̐l�����肽���Ȃ������������E�E�E�ƌ����Ă��̂ŁA�����炭�u���̋ʁv���ǂ��Ȃ������̂ł��傤�B������Ǝc�O�B���Ɋ��ҁB(2013.6.1)
|
|
|

|
�A�|���_���X�B
�t�����X
���[�k���A���v��(�T���H���n��)�̋������̃`�[�Y�ŁA���ʂ̃J�[�u�������ł��B�t�����X�̎R�̃`�[�Y�̑�\�i�̃`�[�Y�Ƃ����Ă����ł��傤�B����̃R���͐h���]���������l�����܂������A���́u�܂��܂����ʁv�B�|�݂͂���ȂɂȂ���������Ȃ����A���Ƀ_������Ȃ����B���Ă��āA�n��������������A�����͔Z���ق��������A�|�݂��ǂ��ق��������A�ƃ`�[�Y�D���͎v�������ł����A�����H�ׂ�`�[�Y������ȂɔZ���|�݂ł���K�v�͂Ȃ��A�������肵�Ă�������O�����ɂ����Ƃ������Ƃ�����B�p�r�Ƃ������H�ׂ�V�`���G�[�V�������l���āA�`�[�Y��]�����邱�Ƃ��厖���ȂƊ����Ă���B(2015.1.25) |
|
|
|

|
���@���e�b���[�i�E�J�[�[��(DOP)
�������@MG34���@�C�^���A�E�����o���f�B�A�B
�C�^���A�̃����o���f�B�A�B�̍Ŗk���ɂ������@���e�b���[�i�k�J�ō���鋍�����̃`�[�Y�ł��B������DOP�`�[�Y�Ŋ��Ԍ���(6/1�`9/30)�̊��l�̂���u�r�b�g�v�ƎY�n�͔���Ă��܂����A���̃`�[�Y�͈�N����邱�Ƃ��\�ł��B�Ȃ̂����̊��ԈȊO�́u���@���e�b���[�i�E�J�[�[���v�𖼏�邱�ƂɂȂ�܂��B�H�ׂĂ݂�Ƌ����͒E������Ă��邽�߂�������Ƃ��Ă��āA����������y���ėD���������B���n�̐l�̕��i�g���̃`�[�Y�ł��傤�B(2013.12.23)
|
|
|
|

|
�������[�E�m���[��
�X�C�X�̃t���u�[���B�ɂ��鏬���Ȓ��̉Ƒ��o�c�̏����ȍH�[������Ă���`�[�Y�uMont Vully�����E�������[�v�̕\�ʂ��A�s�m�E�m���[���̃��C���Ŗ����Ă�����́B�X�C�X�̃G�e�B���@�̃`�[�Y�������Y�q�搶���w���B�����ȃ`�[�Y�A�C�Ȃ̂����J�j�J���z�[���Ȃ̂������Ȍ��������������܂��B�s�m�E�m���[���̕����͑S�������܂����͔Z���Ŗ�������Ă��܂��B(2013.6.1)
|
|
|

|
�G�_��(BOB)�@�@Edam
�������A���M����^�C�v�@M.G48���@�I�����_
�I�����_�k���G�_���n���̃`�[�Y�B�S�[�_�Ƌ��ɃI�����_���\����`�[�Y�B�Ԃ����b�N�X���R�[�e�B���O����Ă���̂ŁA�ʏ́u�ԋʁv�ƌĂ�邪�A����͗A�o�p�B�����p�̓R�[�e�B���O�Ȃ��B�Ԃ����̓����炢�̑傫���B�O���͍d���A�Ԃ����b�N�X���͂����Ă��A��������Ԃ��F�f���`�[�Y�Ɏc���Ă��Ă��B�����̓N�Z�̂Ȃ��D���������������͎���Ȃ���ۂŊO���ɋ߂Â��ɂꌰ���ɁB�����炩���`�[�Y�Ƃ��ė��p����Ă���悤���B(2006.07.01)
|
|
|

|
�A���S�C���[�E�x���N�P�[�[(PDO)�@Allgäuer
Bergkäse
�������A���M����^�C�v�@M.G 45���@�h�C�c�E�o�C�G�����n��
�A���S�C�Ƃ̓A���v�X�̂��ƂŁA�A���v�X�̎R�ŕ��q�������̖��E�ۓ���������`�[�Y�ł��B�W��900���`1800���̎R�����ō���n�����Ԃ�4�����ȏ�ł��B����̂��搶���h�C�c���甃���Ď����A�������́B�n�����Ԃ�24�����ŁA�傫�߂̃A�~�m�_�̌����������܂��B�H�ׂĂ݂�ƃW�����W�����A�|�݂����������R���e�Ƃ��O�����C�G�[���Ɏ��Ă��āA����݂Ȃǂ̃i�b�c�̕���������܂��B(2011.11.19)
|
|
|
|

|
�G�e�B���@
Etivaz (AOC)�@
100������630�~�@
�������A���M����^�C�v�AM.G.45%�@�X�C�X�E���H�[�B
�O�����C�G�[���̒��ԂŐ��@���قƂ�Ǔ��������ǁA�ď����ō���邽�߁A�F���Z���A���킢���Z���Ȃ̂������B�����̂͂P�W�����n���Ȃ̂ŁA���Z�����ŃM���`���ƒ��܂��Ă銴���B�A�~�m�_�̌������傫���A�W�����W�������Ă�B���C���Ƌ��ɂ��������ɂ͂������ǁA���H�ɂ̓L�c�C�ˁB(2006.2.4)
|
|
|

|
5/10�`10/10�܂ł̊��ԂɃA���v�X�ŃA���p�[�W���ɂ���č����B�����ɂׂ͍����K�肪����A�����̓�ŁA�d���g�p�����`���I�Ȑ��@���`���ƂȂ��Ă��܂��B70�����x�̔_�Ƃł̂ݍ���Ă��āA���Y�ʂ����Ȃ��B30�����ȏ�̏n���̂��̂����r�[�u(Rebibes)�ƌĂԁB�S���Y�ʂ�2�`3�������r�[�u(Rebibes)�B
����̊��z�́A���肪�����k���ł݂�ƒЕ��̂悤�ȍ���ŁA�悭�悭�v���o���Ă݂�Ɓu�L���[���̂p�����v�̍���ł��B�W�����W�����ƃA�~�m�_�������������[���`�[�Y�ł��B�t���{�f�B�̃��C������{���̂����ɗǂ������ł��B(2008.3.1)
|
|
|

|
�G�e�B���@(AOC)
�X�C�X�̃��H�[�B�ɂ���C��1172���̃G�e�B���@���ō����`�[�Y�B�ꏊ�⎞����5��10������10��10���܂łƌ����A���@���d���g���ē���łȂ���Ȃ�Ȃ��Ȃǂ̓`���I�Ȃ��̂����ʂ��Ă��āA�n���ꏊ���G�e�B���@���̏n���ɂɌ��邽�߁A���Y�ʂ�380�g���Ə��Ȃ��B����̃G�e�B���@��Y�q�搶�����n�̃G�e�B���@���ōw�����Ă������������́B�O��͍���͍������b�k�ށA�g���Č����Ɩ��É��́u��p�̂䂩��v�̍��肪���܂��B�Ȃ�ł��낤�B(2013.6.1)
|
|
|
|

|
�G�����^�[���@(AOC)
�������A���M����^�C�v�AM.G.45�`49%�@�X�C�X
�X�C�X�ň�Ԃ̐��Y�ʂ��ւ�B�g���ƃW�F���[�ɓo�ꂷ��A�����ɂ��`�[�Y�Ƃ����e�p�����Ă���B���_�ۂ̈��ł���v���s�I���_�̓����ŁA�G�����^�[���̑傫�ȓ����ł��鑽���ȋC�A����R�ł���B����͂킴�ƌ�����낤�Ƃ��Ă���킯�ŁA23�x���炢�̏n���ɂ�1�T�Ԃ��炢����Ă������ƂŁA�傫�Ȍ��ɐ�������B�O������ۂ̗͂Ŗ����`�����Ă����̂ł͂Ȃ��A�����Ƀv���s�I���_�����y���邱�ƂŁA�Ɠ��̂ق�ꂢ���������܂��B�H�ׂĂ݂�ƁA�ȂD�������Ƃ��������A���������Ă��镗���Ƃ�����ۂł����B�ǂ������̓v���s�I���_����閡���D������Ȃ��݂����B(2006.11.4)
|
|
|

|
���A�̒��ŏn���������������n���̃G�����^�[���̃u���b�N���x���B�ʐ^�ł͔���ɂ������F���ӂ��̃G�����^�[�����Z���Ȃ��Ă���B�����������Ȃ��Ă��邪�A����ς肠��܂�D������Ȃ������B�g�[�X�g�ɏ悹�ĂƂ��Ƃ�������Ⴄ�̂��ȁB(2006.11.4)
|
|
|

|
�F�������������������ƐH�ׂĂ����G�����^�[���B���Ȃ��Ԃ��ǂ����̂ȂƂ������Ƃ͕�����̂����ǁA���͂ǂ������܂�D���ł͂Ȃ��B���ʂɐH�ׂ邯��ǁA�v���s�I���_�Ɠ��̕������ǂ����˂��B�����Ĕ����Ă܂ŐH�ׂ����Ƃ͎v��Ȃ��`�[�Y���B(2007.5.12)
|
|
|

|
�t�F���~�G�ōw���A100��452�~�B�^��p�b�N�ɂȂ����u���b�N�Ƃ̂��ƂŊO��͂Ȃ��B�^��Ŕ���ɂ̓A�C�z�[������������ƁA�ׂ�Ă��܂��̂ŁA���܂茊�������Ă��Ȃ����̂����{�ɂ͓����Ă��Ă���炵���B����̃G�����^�[���A���Ɋ��蓖�Ă�ꂽ���̂ɂ́A�ЂƂ����Ȃ��B������Ȃ̂��A�v���s�I���_�ۓƓ��̕������ア�B���Ƃ��Ƃ��̖������Ȃ̂ŁA���������D���������̃G�����^�[���Ȃ�܂����������B(2008.6.6)
|
|
|
|

|
�G�����^�[���E�h�E�T���H���@�@
�������A���M�����@M.G.45%�@�t�����X�E�T���H���n��(���[�k�E�A���v)
�X�C�X�̑�\����G�����^�[���`�[�Y�ł����A�����A���v�X�̎R�A�t�����X�̃T���H���ł�����Ă��܂��B�X�C�X�̃G�����^�[���ɔ�ׂ�ƁA�`�[�Y�A�C���傫���̂������B�����Ƀv���s�I���_�ۂ������A�n�����Ԓ���1�����قǁA�`�[�Y��22�`23���̊��ɒu���Ă��ƁA�v���s�I���_�ۂ̊����������ɂȂ�A���̂Ƃ��o��Y�_�K�X�ɂ���āA�`�[�Y�A�C������܂��B�X�C�X�̂��̂����`�[�Y�A�C���傫���Ƃ������Ƃ́A�v���s�I���_�ۂ̊֗^���傫���Ƃ������ƂȂ̂ŁA�����v���s�I���_�ۂ̉e����傫�������Ă��܂��B���H�������z�́A�{�\�{�\���Ă��āA�����փS���Ƃ�����ۂŁA�ꖡ������������B��͂�M�������ĐH�ׂ�`�[�Y���Ƃ�����ۂ��������܂����B�������搶��F�̈ӌ����ƁA����̂͂��Ȃ��Ԃ̂悢�����������������ł��B(2007.3.3)
|
|
|
|

|
�J�X�e���}�[�j���iD.O.P.�j�@ �@100������1000�~�ʁ@�����M���� �@100������1000�~�ʁ@�����M����
������(�r���E�R�r���̃~�b�N�X������)�@MG�@34���@�C�^���A�@�s�G�����e�B�N�[�l�I��
�N�[�l�I���̃J�X�e���}�[�j�����Ƃ��������ȑ��ŁA�Ă̕��q���ɂ����������ꐶ�Y�ʂ����Ȃ��̂Ō��̃`�[�Y�ƌĂ�Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ��H�ׂ邱�Ƃ��o���Ȃ������ł��B���͂�����A�`�[�Y�v���t�F�b�V���i������(C.P.A)��Ấu�A���v�X�̃`�[�Y����v�̍Â��ŐH�ׂ邱�Ƃ��ł��܂����B�{���{���Ƃ����g�D�ł����A�����Ƃ肵���H���ŁA�Ɠ��̎_�������Ƃ������܂���B�Ȃ��Ȃ��M�d�ɏ�ɂ��l�i�̍��������Ȃ̂ŁA���ɂ͏o���Ȃ��Ǝv���܂����A���̃`�[�Y���g���Đ��N���[���ƍ��킹�ă\�[�X�����ƁA�ƂĂ��������������ł��B���Ѓ\�[�X�ɂ��ĐH�ׂĂ݂����B(2004.11.11)
|
|
|

|
�`�[�Y�̊w�Z�ŏo���J�X�e���}�[�j���B���̃`�[�Y�ƌĂ�܂����A���͍����3��ځB2��ڂ̓`�[�Y�P�Ƃł͂Ȃ����]�b�g����������ǂ��B���{�ɂ��܂��ƁA�Â����@�ł͏o�����J�[�h��قɓ���Ĕ��y������Ƃ����������H���ރ`�[�Y�ł��B�O��͌����������ăS�c�S�c���Ă��āA�����f�ʂ̓{���{�������g�D�ŁA��u�`�F�_�����O�������悤�ȑg�D�Ɍ����A�T���[����J���^���Ɍ����Ȃ��͂Ȃ��B�H�ׂĂ݂�Ɩ��͌��I�łǂ̃`�[�Y�Ƃ��Ⴂ�܂��ˁB�Ɠ��̎_��������܂��B�g�D���Ƃ��t�H�[�N�Ŏh���ĐH�ׂ�ɂ͕s�����B��͂�\�[�X�Ȃǂ̗����p�Ȃ̂������ł��B(2008.7.20)
|
|
|

|
100��1680�~�̃J�X�e���}�[�j���B����̂̓{���{�����Ă��Ȃ��āA������X�b�p�b�Ƃ��������ŁA�Ȃ�ƂȂ��N���[���`�[�Y�̂悤�Ɍ����Ȃ����Ȃ��B���̃`�[�Y�ƌ����A���Y�ʂ����Ȃ��̂ł����A�ŋ߂͋U�����o����Ă��邻���Ȃ̂ŁA�M���̂ł���`�[�Y���X�Ŕ����Ƃ����Ǝv���܂��B�H�ׂĂ݂�Ƃ��Ȃ�_���ς��B�{�������H�����炵�Ă��_���ς��͏��m�̏�Ƃ��Ă��A���Ȃ�_���ς��B�O��̊����͂����n�����Ă�ȂƂ��������B(2009.5.30)
|
|
|
|

|
�J�`���J���@�b���E�V���[�m�E�A�t�~�J�[�g(DOP)�@
�������AM.G.38%�@100������700�~(�ʐ^��1/4�J�b�g�Ȃ̂�2800�~���炢�H)�����M
�C�^���A�E�o�W���J�[�^�B�A�����[�[�B�A�v�[���A�B�A�J���p�[�j���B
�R�ł�����ꂽ�Ђ傤����^�̌`����ۓI�ȃp�X�^�t�B���[�^���@�ł����Ă����`�[�Y�B�A�t�~�J�[�g�Ƃ������̈Ӗ��ŁA���������Ȃ����̂́u�J�`���J���@�b���E�V���[�m�E�r�A���R�v�ƌĂ�邻���ł��B(2005.10.1)
|
|
|

|
100������872�~
�����Ŕ������肵�Ȃ��`�[�Y�Ȃ̂ŁA2�N�Ԃ�ɐH�ׂ��B�����̍��肪�����̂ŁA�ǂ����Ă��u���܂݃`�[�Y�v�I��ۂ������Ȃ��Ă��܂��B�O��ɋ߂������̓{�T�{�T���Ă��āA�ߐH���������Ȃ��悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��B�p�X�^�t�B���[�^�ō���Ă���̂ŁA�Ƃ��������B�n�����ĐH�ׂ�Ƃǂ�Ȗ��ɂȂ�̂��낤���B(2007.10.6)
|
|
|

|
�t�F���~�G�w��100������1050�~�B���̒��ł͉��x�H�ׂĂ�����(�A�t�~�J�[�g)�̃`�[�Y�́u���܂݃`�[�Y�v�̈悩��E���Ȃ��ȁB�r�[���ɂ͍����Ǝv�������C���ɂ͍��킹�ɂ������B���܂݃`�[�Y�ɂ��Ă͍������B�����̓����C�N���Ă����C���[�W���ז�����B(2008.5.30)
|
|

|
�J�`���J���@���@1��(900�O����)��8000�~��
�������A���{�E���R��(�g�c�q��)
�g�c�q����J�`���J���@���͔��������ƗL�������ǁA�������Ă���2�����قǑ҂ȂǁA�Ȃ��Ȃ���ɂ��邱�Ƃ�����`�[�Y�Ȃ̂ł��B����Ȃɑ҂��Ă܂ł��`�[�Y��H�ׂ����Ǝv��Ȃ������̂ŁA���܂ł̓`�����X���Ȃ����������ł��B�~���N�̊Â݂��_�C���N�g�Ɋ����A�ƂĂ��~���L�[�Ȗ��킢�ł��B�ςȎ_���L���S���Ȃ��A�ƂĂ����������ł��B�����A������ˁ[�B�ʐ^�͔������炢�ɃJ�b�g���Ă��邯��ǁA100�O����900�~���炢�Ȃ̂ŁA1��(900��)��������8000�~�قǂ����B���ɉ����ς��Ȃ��Ȃ�ȁ[�B(2010.9.4)
|
|
|
|

|
�N�U���@Cousin
�������A
���M����^�C�v M.G.32%�@�t�����X�E�T���H���n��
���߂ĕ������O�̃`�[�Y���B�N�U���B�J�Y���Łu���Ƃ��v�̈Ӗ����Ƃ������Ƃ����ǁA�͂����ĉ��̂��Ƃ��̂���Ŗ��O�������̂��낤���H�O��̓����W���̃r�X�P�b�g�B�{�[�t�H�[����A�{���_���X�̂悤�ɑ��ʂ������Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���̂ӂ��̂��Ƃ��ł͂Ȃ����낤�B�����������肵�Ă��ăi�b�e�B�ȕ�������B�Ȃ��Ȃ����������B(2007.5.12)
|
|
|
|

|
�O���i�E�p�_�[�m�@�@���M����^�C�v�@
�������A
M.G.32%�@�C�^���A�k���p�_�[�m����
�p�_�[�m����̍L���͈͂ō���Ă���u�O���i�v�́u�������́v�Ƃ����Ӗ��B�E�������~���N�������邪�A�O���^�~���_�\�[�_���`�[�Y���ɑ�����̂ŁA�|�������������邽�ߖ��͔Z���B�����悤�ȃ^�C�v�̃`�[�Y�Ƀp���~�W���[�m�E���W���[�m�����邪�A������͕����������邪�A�����ŗ����ɂ��g���₷���B�C�^���A�ł́u�L�b�`���E�n�Y�o���h�v�ƌĂ�e���܂�Ă���B�������������łȂ��Ă��̂܂ܐH�ׂĂ��A�\�����������`�[�Y���Ǝv���܂��B(2006.11.4)
|
|
|

|
����ł��悭�����̂ɁA���L�����Ă��Ȃ��������Ƃ������B���܂�1���H�ׂĂȂ����ƂɂȂ��Ă��E�E�E�B�͂͂��A����Ȃ��������ȓ��L�ł��B���i�͂��肨�낵�ăp�X�^�ɂ������肵�ĐH�ׂ�̂���ŁA���ꂾ�����{���{���H�ׂȂ��̂ł����A�H�ׂĂ������͂Ȃ��ȁE�E�E�Ƃ�����ۂł��B����́A�ӂ����^�C�v�ƁA�����X���C�X����2��ނŖ��̈Ⴂ�������Ă݂܂����B�����ƕ\�ʐς������Đ�S�̂ŏ��ʂ̎|�݂������邱�ƂɂȂ�̂ŁA�|�݂͊Â݂Ɋ����₷���B�t�ɍӂ��ƃA�~�m�_�̉���̈ꕔ�Ŋ����邱�ƂɂȂ�̂ŁA�|�݂͋ꖡ�Ɋ����邱�Ƃ�����悤���B�Ȃ�ƂȂ�����͔���B�p�r�ɉ����Đ�����l���Ă����K�v������܂��ˁB(2007.12.1)
|
|
|

|
�t�F���~�G�ōw���A100��536�~�B�`�[�Y�������Ȃ����Ƃ͌����Ă����̒l�i�B���������Ŕ��������Ȃ����`�[�Y���Ȃ��Ȃ�܂��ˁB���͕��i�A�O���i�E�p�_�[�m�𗿗��p�ɔ����Ă���̂ŁA�������薡�키���Ƃ͏��Ȃ��̂ł����A���܂ɂ������Ă�������H�ׂ�ƁA�����Ȃ��ł���ˁB�X���C�T�[�ō���āA�����Ղ�ƃX�[�v�ɓ����̂��D���ł��B(2008.5.23)
|
|
|

|
�t�F���~�G�ōw�������u�`�[�Y���낢��H�ה�׃Z�b�g�v�̒��ɓ����Ă��A�O���[�i�E�p�_�[�m�B�u���C���h�œ��Ă�̂��y���݂ɂ��Ă��̂ɁA�O��ňꔭ�Ŕ������Ⴄ��B������ƊȒP�����ăc�}���i�C�ȁB���̃u���b�V���O���ďo�����O��A���̂܂ܐH�ׂ�ɂ͍d�����Ă��肨�낷���Ƃ��o���܂��A�̂ĂȂ��ł��������ˁB�O����l�i�̂����ł��B�H�ׂ�ɂ͍d�����Ă��A�A�~�m�_�͂����Ղ�܂܂�Ă��܂��̂ŃN���[���V�`���[��X�[�v�����Ƃ��ɁA�|�C�b�ƕ��荞��ł��������B�|�݂��o�ăX�[�v�����������Ȃ�܂���`��(2008.8.24)
|
|
|
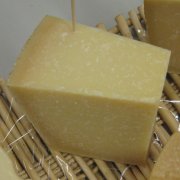
|
�O���i�E�p�_�[�m24�����n���B�p�_�[�m�����тō���Ă���B�ʏ��1�N���x�̏n�����Ԃł����A�n���m�����ʂɏn�������Ďd�グ���O���i�E�p�_�[�m�̍����i�ł����āB������́u�N�����F���Ёv�̂��́B24�����ɂ��Ă͐F�͏����������ȁB�A�~�m�_�͏����߂̌�������R����B�W�����W�����Ƃ����H���B����ł݂�Ə_�炩�߂ŁA�����_����������B���̎_���͂������Ȃ��̂��H(2009.12.5)
|
|
|

|
�g�����e�B�[�m�E�A���g�A�f�B�W�F�B�ł����Ă���O���i�E�p�_�[�m24�����B�L��ō���Ă���O���i�E�p�_�[�m�ł����A�g�����e�B�[�m�E�A���g�A�f�B�W�F�B�̎R�x�n�тŕ��q�����̃~���N���g���������͓̂��ʂɁu�g�����e�B���E�O���i�v�ƌĂ���ʈ�������Ă���B�������p���~�W���[�m�E���W���[�m�̂悤�ɗ[���̃~���N�܂ŐÒu���ĒE�����鐻�@���Ƃ��Ă��邱�Ƃ������������B����̂͂ǂ̂悤�Ȑ��@���s���B24�����n���Ȃ̂ɁA�f�ʂ̐F�͂Ȃ��������B�ł�����̓p�b�N���ꂽ���ŏ��ꂽ���̂��Ǝv����B���f�ʂ͔����Ȃ��ʏ��24�������炢�̐F���B�H�ׂĂ݂�Ɛ����������̂��_�炩���A�゠����
����������������B���ꂿ������̂��������ȁB���͕��ʁB(2009.12.5)
|
|
|
|

|
�O�����C�G�[��
Gruyeye�@(AOC)�@ �@
100������600�`800�~�� �@
100������600�`800�~��
�������A
M.G.45�`49%�@���M����@�X�C�X�E�t���u�[���n��
�O�����C�G�[���́A�X�C�X���\����R�̃`�[�Y�ł̊Â݂���������Ƃ��Ă��č���������[���B�R�̃`�[�Y�������A����̓A���p�[�W���Ȃ̂ʼnĂ̍��n�̖q��Ő������ꂽ���ƈӖ����܂��B�Ȃ̂ŕ��ʂ̃O�����C�G�[�����F���Z���A�~���N�̖����Ïk���Ă��ăi�b�e�B�[�ɕ�������B�R�̃`�[�Y������W�߂��`�[�Y�v���t�F�b�V���i������(C.P.A)��Ấu�A���v�X�̃`�[�Y����v��29��ނ������������`�[�Y�̒��Ŏ��̈�ԍD�݂̃`�[�Y�ł����B(2004.11.11)
|
|
|

|
100������500�~��W�����R�������t�����X���ł͢�R���e�v������Ă���B�����悤�ȃ^�C�v�Ȃ̂ɁA�X�C�X�̃`�[�Y�̓t�����X�̃`�[�Y�ɔ�ׂĂ��育��B�X�C�X�S�A�o��3�`4�����߂�B�₳�����N���[���F�œK�x�Ȓe�́A�����Čy���A�~�m�_��������B�`�[�Y�t�H���f���̍ޗ��Ƃ��Ă����łȂ����̂܂ܐH�ׂĂ����������`�[�Y���B���ɒ��H�ɖ�ƈꏏ�Ƀp���ɋ���ŐH�ׂ�����������ˁB(2006.2.4)
|
|
|

|
�����D���ȃ`�[�Y�̂����̂ЂƂ��O�����C�G�[���A�ł�����͑̒����C�}�C�`�������̂��A�����̂悤�ɂ��̃`�[�Y�Ɋ�����i�b�e�B�ȕ������Ȃ��A�����_��������p�T�p�T���Ă���悤�Ɋ����܂����B(2007.4.7)
|
|
|

|
�X�C�X��2�Ԗڂɐ��Y�ʂ������O�����C�G�[���B2007�N3���Ƀt�����V���E�R���e�n���̃O�����C�G�[�����`�n�b�ɔF�肳��A�����Gruyere�̒Ԃ���ꏏ�Ȃ̂ŁA�Ȃ���₱�������ƂɂȂ�܂����ˁB�����Gruyere�Ə����Ă�������A�X�C�X���t�����X���m�F���Ȃ��Ƃ����Ȃ��ˁB����̃O�����C�G�[���̓X�C�X���A�G�~�[�Ђ̏n��6�����ȏ�̂��́B�D�������������A�Ȃ�����Ȃ����ȁE�E�E�C�������B�����A�G�e�B���@���ɐH�ׂĂ��܂����̂ŁA�����킩��Ȃ��Ȃ��Ă����\����B�H�ׂ鏇�����ĂƂĂ���B(2008.3.1)
|
|
|

|
�t�F���~�G�ōw����100��483�~�B�������肵���R���e�Ƃ������������B�i�b�e�B�ȕ����Ō������Ȃ��A���ł��H�ׂ���`�[�Y�Ƃ�����ہB���l�i��100����500�~��邨�育�뉿�i�Ȃ̂��������Ƃ���B�`�n�b�ɂ�3�̃^�C�v�����邻���ł��B
Gruyere�@Switerland
�Œ�5�����n��
Gruyere�@Switerland�@Reserve
10�����`16�����n��
Gruyere�@Switerland d'Alpage�@5�`10���ɃA���p�[�W���@5�`10�����n���B(2008.6.6)
|
|
|

|
�t�F���~�G�ōw�����u�`�[�Y���낢��H�ה�׃Z�b�g�v�̃O�����C�G�[���B�u���C���h�Ō����u�ԁA�u�\�炪�₯�ɐԂ��Ȃ��v�Ƃ�����ۂ������̂ŁA�܂����O�����C�G�[���Ƃ͎v�킸�A�u�A�{���_���X�v�Ɠ���ŊԈႦ���B����̓X�C�X�̃O�����C�G�[����6�����n���B�Е��̂悤�ȍ���������āA�Ȃ��Ȃ��̔����B(2008.8.24)
|
|
|

|
�O�����C�G�[��(AOC)
�X�C�X�̃u���u�[���B�ō���Ă��邲�����ʂ̃O�����C�G�[���B�n���̃`�[�Y������ŁuGruyère�v�Ƃ������O�̃`�[�Y�́A������O�����C�G�[���^�C�v�Ƃ����Ӗ��ŕt����ꂽ���̂ł��邱�Ƃ������A�uLe
Gruyère �v�Ɗ����t�ŏ����ꂽ���̂�AOC�̃O�����C�G�[���Ƃ����Ӗ��炵���B�Ȃ�قǂˁBY�q�搶���y�Y�̃R���́A�O��̂Ȃ������h���X��Ԃł����A�uLe
Gruyère
�v�ł��B���n�ł͊O�炪�Ȃ��O�����C�G�[�������������Ă��������ł��B(2013.6.1)
|
|
|

|
�O�����C�G�[���E�_���p�[�W��(AOC)
�X�C�X�̃u���u�[���B�ō���Ă��āA�ĂɃA���v�X�ō��n���q�ō���Ă�����́B�S�̂�1.5���قǂ����_���p�[�W���͍���Ă��Ȃ��B�l�i���{���b�ƍ����Ȃ�B(2013.6.1)
|
|
|

|
�P�[�j�q�X�E���[�g���B�q�E�P�[�[�@Koning
Ludwing käse
�������A���M���� �@M.G50��
�h�C�c�E�o�C�G�����n��
�搶���h�C�c���甃���Ă��Ă��ꂽ�`�[�Y�B�`�[�Y�����菑���ŏ������������B�M�����Ŕ��ǂ�����A�ƂɋA���Ă��炢�낢���PC�Œ��ׂ����ʁAKoning�͉��l�ALudwing�͖��O(�x�[�g�[�x���Ɠ���)�ł͂Ȃ����Ƃ������ƁB����āu���[�g���B�q���̃`�[�Y�v�B�H�ׂĂ݂�ƃ}�C���h�ȎR�̃`�[�Y�̖��B���ʂɔ��������ł��B�H���̓��b�`���A�܂��Ⴂ�n���Ȃ̂Ŕ�܂ŐH�ׂ��܂��B(2011.11.19)
|
|
|
|
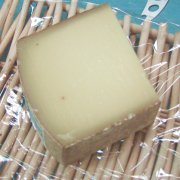
|
�R���e�@Comte
(AOC)�@ �@ �@
�������A���M�����@M.G.45%�@�t�����V���E�R���e�n��
�t�����X�Ő��Y�ʂ̃g�b�v�B�ߗׂ̔_�Ƃ��~���N���������_��Ɏ������ꊇ���Y����Ă���B
�R���͗̃J�E�x���V�[���t���̃R���e�E�G�N�X�g���A�v�e�B�b�g�Ђɂ��15�����n�����́B
�O��͍d���ĐH�ׂ��Ȃ��B���g�̓A�C�{���[�`�^�}�S�F�B
���H�̓X�e�B�b�N��(�_��)�ɃJ�b�g����Ă����̂ŁA�����������̂����i�b�c�̍���A�~�m�_�̃V�����V���������������킦�ā����B�������ł͂Ȃ��A���ꂩ��͂����낤�B(2005.1.29)
|
|
|

|
�R���e�͂`�n�b�ɉ��������������łȂ��A���̊Ӓ�m�ɂ���āA�`�[�Y�̖��A�H���ɂ���ă����N��������邻���ŁA20�_���_�̕]����15�_�ȏ�l�������`�[�Y�ɂ����A�̃x���}�[�N��\�邱�Ƃ�������A�u�R���e�E�G�N�X�g���v�ƌĂ�܂��B����̎��H���x�����x���B12�_�`15�_�̃`�[�Y�ɂ͒��F�̃��x�����\���A12�_�����̃`�[�Y�́AAOC�̔F�߂�R���e�Ƃ͖���ꂸ�A�O�����C�G�[���`�[�Y�ƌĂԂ����ł��B������āA�X�C�X�̃O�����C�G�[���Ɏ��炶��Ȃ����H�Ǝv���̂����ǁA�ǂ��Ȃ̂��H
���Ă��̃R���e�A�i�b�c�̍���A�ꖡ���Ȃ��A�A�~�m�_�̃W�����V���������H�������Ă���ς���������B���Ȃ݂ɓ��{�ɗA������Ă�����̂͗��x�����w�ǂƂ̂��Ƃł��B(2006.11.4)
|
|
|

|
�G�����F�E�����X�n�����R���e�B�ӂ��ɔ��������B(2006.11.4)
|
|
|

|
�̃x���}�[�N�������������N���̕i�����Ӗ�����A15�`13�_�̒��F���x���B�R���e���́A�t�����X�l��1�ԐH�ׂĂ���`�[�Y�����A���̒��ł��l�i����y�ŁA�������Z�����Ȃ��Ƃ����Ӗ��ŁA�����I��1�ԑ����H�ׂ��Ă���`�[�Y�ł��낤�B���܂ŗ̃��x���̂��̂����H�ׂ����Ƃ��Ȃ��������A����͐搶���ۂ��ƍw�����ꂽ�Ƃ������ƂŁA�������ɂ����\�ȗʂ��v���[���g���Ă����������B��24�����n���́����̂Ɣ�ׂ�ƁA�A�~�m�_�̑�����A�R�N�Ƃ����Ӗ��ł͏��ĂȂ����A�T���h�C�b�`�ɂ����肷��ɂ͂�����̕��������܂��ˁB���{�ł����F�̃��x���N���X�̂��̂�������y�Ɏ�ɓ���Ƃ����ł��ˁB(2007.5.12)
|
|
|

|
24�����n���̗��x���̃R���e�B�F���Z���A�~���N�̎|�����Ïk���ꂽ�悤�ȔZ�����B�A�~�m�_���������C���ƈꏏ�ɐH�ׂ�Ɣ��������B���܂݂Ƃ��ĐH�ׂ��ґ�`�[�Y�ł��ȁB(2007.5.12)
|
|
|

|
�t�����X�E�R���e�n���̃u�U���\���Ƃ����X�Ŕ������A�t�F���~�G����12�����n���R���e�B���x���ˁB�`�[�Y�V���b�v�ɂ�6�����̂����������甃���Ă݂�悩�������ȁB���F�����߂Ȉ�ۂŁA�ނ�����Ɛ������Ïk���Ă���悤�Ȋ���������A�����������҂����̂����ǁA�H�ׂĂ݂�Ƃ������ĕ��ʂɔ��������R���e�ł����B�R���e�͂������Ă��A�n�Y���̂Ȃ��`�[�Y�ł��ȁB���������̂͐�ΊO�������Ȃ����ɏd�����B(2007.12.17)
|
|
|

|
�t�F���~�G�Ђōw�����R���e
�h
�����^�[�j���@16�����n���B�O��͐[���������ɂȂ��Ă��āA�����f�ʂɂ̓A�~�m�_�̌����������Ă��܂��B�O��ɋ߂��Ƃ���̓A�C�{���[�ƌ��������������Č����܂��B�H�ׂĂ���Ƃ��Ȃ肵�����肵�����B������������A�I�̂悤�ȕ���������܂��B���I�ɂ͔����������ǁA���������Ⴂ�R���e�̕����D���ł��B(2008.4.12)
|
|
|

|
�t�F���~�G�ōw�����u�`�[�Y���낢��H�ה�׃Z�b�g�v�̒��ɓ����Ă܂����B�������ڂ������ăR���e�Ɣ����B���ʂ̃J�[�u�ł킩�����Ⴄ�ˁB�ڂ����́u�R���e�E�h�E�����^�[�j���@12�{(2007�N6������)�v�B4���ɐH�ׂ��������R���e�̃����^�[�j���͗ΐF�����Ă�������ǁA������Y��ȃA�C�{���[�F�B�i�b�c�̕������ۗ���12�����̏n���ł����A����قǃA�~�m�_�̌����͊����Ȃ��B(2008.8.24)
|
|
|

|
MOF�G�����F�E�����X�n�����R���e�B�n����18�����ȏ�Ƃ̂��ƁB�f�ʂ̐F�͂��Ȃ艩�F���Ē��܂��������ł����A�A�~�m�_�̌����͂킸���ɂ��邩�ȁH�Ƃ������x�B�ʏ�18�����ȏゾ�Ƃ��������������o�Ă���̂ł����A�ǂ����Ăł��傤�B�����W���̊O��͌����S�c�S�c���Ă���B�H�ׂĂ݂�ƁA�A�~�m�_�̎|�݂��y���ނƂ������́A�R���e�̖����Ïk�����Ƃ��������B���N�̖��Ƀt�����V���E�R���e�n���̃u�U���\���ŐH�ׂ�12�����̃R���e�Ɏ��Ă��邩�ȁB(2008.11.1)
|
|
|
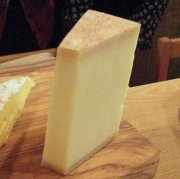
|
�`�[�Y��̂���`���Ń{�W�����[�k�[�{�[�����킹��`�[�Y�Ƃ��ăt�F���~�G�ōw���B�����^�[�j��8�{�A100��683�~�B7�����`9�����n���̂��́B�����Ƃ����قǂ̏n���ł͂Ȃ�����ǁA�Ⴗ�����R���e�̖����悭�o�Ă���悤�ȋC�����܂����B�{�W�����[�Ƃ��킹�Ă��Ȃ��Ȃ��̑����ł������A���}�X�^�[�h�Ƃ��킹�Ă��������������B�킸���ɃA�~�m�_�̃W���������ɂ�����܂����B���낻��A�~�m�_���o�n�߂�n���Ȃ̂ł��傤���B(2008.11.23)
|
|

|
�R���e�@8�����n���B���{�ł͂Ȃ�ł�����ł������n�����D�܂��X���ɂ���܂����A�R���e�̓o���~�W���[�m�E���b�W���[�m�̂悤�ɒ����n���ɂ����悤�ɒE�������~���N�������Ă��܂���A�`�[�Y�̓������炷��Ɠ����b���_�����₷���̂ŁA�����n�������Ⴍ���ĐH�ׂ�ق��������Ă���`�[�Y���Ǝ��͎v���܂��B���̏n����8�����ł����ց[�[���i�b�c�̕���������A�\�����������ł��B�i2011.9.3�j
|
|

|
�傫�ȃJ�b�g�̃R���e�B����̓`�[�Y���Ԃ�Nao����W�����ɗ����Č��n�Ŕ����Ă��Ă��ꂽ���́B3�������炢�̏n���B���������Ⴂ�n���̃R���e�͓��{�ł͂Ȃ��Ȃ���ɓ���܂���B�����Ă�����Ȃ�����ł��傤�B�������͂��߂Ƃ��鑽���̓��{�l�̓A�~�m�_���łł�����A�����n�����Ɩ������ɗL�肪������X���ɂ���܂����A�ł��Ⴂ�R���e�ɂ͎Ⴂ�Ȃ�̔�������������܂��B�Ⴂ�R���e�̔��������ɂ����ڂ�����������`���Ă��������Ǝv���܂����B�i2011.11.19�j
|
|
|

|
�t�����V���E�R���e�n���ł����Ă���R���e�́A�t�����X�ōł����Y�ʂ�����AOP�`�[�Y�B���̃R���e�͏��X�n�����߁B�m�A�[�b�g�̍��肪�S�n�悭�A�A�~�m�_�̌���������|�݂��\���A�Ō�ɂق�ꂳ���c��B����ł��ĖO���Ȃ��B����̃R���e�̂悤�ɁA���{�ɓ����Ă��Ă�����̂͏n�������߂̂��̂��������A�t�����X�ŕ��i�p�ɐH�ׂ��Ă���悤�ȎႢ�n���̃R���e���A�������Ȃ��ĂƂĂ��H�ׂ₷�����������ł��B���������Ӗ��ł��A�n�Y�������Ȃ��`�[�Y�ł��ˁB�i2012.08.04�j
|
|
|

|
�R���e�@12����
�R���e�Ȃ�ł͂̍��肪�₩�ŁA�k���ł��邾���Ŗ������`�B�F�����F���璃�F�ɂȂ肩���Ă���A�A�~�m�_�̌����̔����|�c�|�c������������B�H�ׂĂ݂�Ǝ|�݂������B������������B����Ŗ{����12�����H�Z���Z�ق�ƁH���̌�A24������H�ׂĂ����ς肵�Ă��̂ŁA����12������24�����͎��͋t�Ȃ�Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B(2013.6.1)
|
|
|

|
�R���e�@24����
�A�~�m�_�̌����͊m���ɂ���܂������͏������B�H�ׂĂ݂�Ɗm���ɃW�����b�Ƃ��܂����A����͋����͂���܂���B12�����ƐH�ה�ׂ܂������A�F��12�����̂ق����Z���F�����Ă��邵�A����������̕����������肵�Ă��܂��B�����12�����̕������肪�₩�Ŏ��͍D���ł��B�Ƃ������A���Ⴂ����Ȃ����ƁA�����v���Ă��ł����ǂˁB(2013.6.1)
|
|
|

|
�u�R���e�E2012�N9���̖�1�N�n�����́v
�N�₩�ȉ����߂̃N���[���F�B����������ނ����肵�Ă���B�����͉��₩�Ŏ_�������������A�|���Ǝ�X�������킢�������荇���������B�ŋ߃R���e�͒����n���^�C�v���A���ꂭ�炢�̃^�C�v���D�݁B�n��������Ή��ł����肪�����鎞���͉߂��A�x����Ȃ���u��X�������킢�������ȁv�ƍŋ߂͓��Ɋ����Ă��܂��B���ɃR���e�͂��������Ă��܂��B���������_�����ɃN���A�[�������������R���e�ł����B(2013.11.10)
|
|
|

|
�u�R���e�E2011�N9���̖�2�N�n�����́v�n��
�傫�ȃA�~�m�_�̌������f�ʂɏo�Ă��܂��B�A�~�m�_�̎|������Ɋ����A�|���̉�̂悤�ȃR���e�ł��B���������ł��B
�������������n�������R���e�������ƗL����Ă��܂������A���낻�뎄��������Ă����̂ł��傤���A�����������₩�Ȏ�߂̃R���e���D�݂ɂȂ��ĎQ��܂����B(2013.11.10)
|
|
|

|
�R���e
������̓p���̃`�[�Y������A�}���[���A���k�E�J���^���̂��̂ŁA���\�n�����Ă���R���e�ł��B�O��̊����Ƃ��A���F�̐[���F�ɂȂ��Ă���Ƃ��납����A�����n����ԂŔ������������ȂƊ��҂����Ă��܂��܂��B�l�I�ɂ̓R���e�͂��܂蒷���n��������̂ɂ͌����Ȃ��`�[�Y���Ǝv�����A���ɂ͋ꖡ���o����A�_���L�������肷��̂����Ȃ��Ɗ����Ă��܂����A���̃J���^������̂̓z���g�ɔ������������ł��B(2014.11.23) |
|
 |
�u��2��`�[�Y���y���މ�v�ł��o�������R���e�n���Ⴂ2��ށB�p���̗L���`�[�Y������u�J���^���v�Ŕ����Ă��Ă�������B�ʐ^��̂͏n���̎Ⴂ4�`8�����̂��̂ƃI�[�_�[�����̂ł����A�A�~�m�_�̓�����Ƃ����A�ǂ����Ă�1�N�ȏ�n�����Ă���Ǝv����B���̂�15�����ȏ�ŃI�[�_�[�������̂ł����A�F�A�A�~�m�_�̗ʂ��炵�Ă�2�N�͏n�����Ă���Ǝv����B�{���͏n���������Ȃ��Ⴂ���̂ƁA�����n���������̍��������Ă��炢�����ăI�[�_�[�����̂����ǁA�J���^���ɂ͎Ⴂ���̂����������̂��Ȃ��B�c�O�B
���R�Ȃ���A�ǂ���̃R���e���|�������Ղ�ŃR���e�̔����������悭�o�Ă���B��҂͋����|���̗��ɋ�݂����������߁A���̍D�݂͑O�҂ł����B�i2017.11.18�j
|
|
|
 |
�K
�������@���{�E�k�C�����@�����킹�`�[�Y�H�[
2016�N�W���p���`�[�Y�A���[�h����܁B�ȑO���肪�Ƃ��q��Ƃ����킹�`�[�Y�H�[��K�˂Ė{�Ԃ���`�[�Y�̂��b���f���܂����B�X�g���X�̂Ȃ����S���q�Ő��Y����Ă���A�͂̂���~���N�ŁA�����ȕ����^�ʖڂɍ��`�[�Y�����������Ȃ��킯������܂���B����́u�K�v�A�n�����Ԃ������A�A�~�m�_�̌������o�Ă��܂��B�N���[���F���A�Z�����F�ɂȂ��Ă��āA�͋����|���������܂��B�i2018.3.21�j
|
|
|
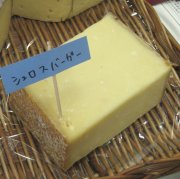
|
�V�����b�X�o�[�K�[�@Schlossberger
�������A�@M.G50���@�X�C�X
�V�����b�X�x���O�Ƃ������邪���Y�n�̋߂��ɂ���Ƃ������Ƃł��̖����t����ꂽ�����ł��B�h�C�c�ꌗ�̃X�C�X�̎R�ԕ��ō��n���q�������̃~���N�������Ă���`���I�ȃ`�[�Y�Ȃ̂������B������͏n��14�����̂��́B�u���C���h�Ō�����O�����C�G�[���ƊԈႦ�����B���̓A�b�y���c�F���[�̂悤�Ȋ����B�A�~�m�_�������Ղ�ł����A�ł����i�b�c�̂悤�ȍ���╗��������A�����ꂢ�B���`��A�ܑ̖��������B(2009.9.5)
|
|
|
|

|
�V���g�R�@100��630�~
�������@���M����^�C�v�@���{�E�k�C���\��(�����w�ɐV���_��)
�\���̋����w�ɂ̒����n���^�C�v�̃`�[�Y�ł��B�����w�ɂł͍Œ�11�����̏n������̔�����Ă���悤�ł����A����̂͏n������18�����ł��B�f�ʂ�����召�̃A�~�m�_�̌����������܂��B�F�̓N���[���F�ƌ������͉��F�ɋ߂��Z���F�����Ă��܂��B����͉Ă̐���H�ׂ����č���Ă��邩��ł��B�t�����X�̃`�[�Y�Ō����Ȃ�u�G�e�v�Ƃ������Ƃł��傤�B�|�݂������Z���A�������肵�������Ŕ��������ł��B���{�̃`�[�Y�̐擪�𑖂葱���Ă����{�����̌���̂ЂƂł��B���Ђ��������������B(2014.1.13)
|
|
|
|

|
�X�C�X�A���v�x���r���@
100������735�~�@
�������A
M.G.�s���@�@�X�C�X
�`�F�X�R����Ŏ�舵���Ă���G�~�[�Ђ̃I���W�i���`�[�Y�B�O�����C�G�[���̂悤�ȃn�[�h�^�C�v�̃`�[�Y�̊O��̕\�ʂɁA�o�W���A�I���K�m�A�Z�[�W�Ȃ�8��ނ̃n�[�u���܂Ԃ������̂ł��B������������ł��B�O�炲�ƐH�ׂ܂������A�n�[�u�̍��肪�i�b�c�̂悤�ȃ`�[�Y�̕����ƂƂĂ��悭�����܂��B���̂܂ܐH�ׂĂ������������A���Ⴊ�����Ȃǂ̖�̏�Ȃǂɏ悹�ďĂ��ĐH�ׂĂ��n�[�u�̍�����������������������ł��B(2011.8.31)
|

|
|
|
|

|
�X�g�����F�b�L�I�E�A���E�g���R���[�g�E�}�b�N�����@Stravecchio
al Torcolato Maculan�@
�������A
M.G.34%�@���M����^�C�v�@�C�^���A�E���F�l�g�B
�搶�̃C�^���A�E���F�l�g�B�̂��y�Y�`�[�Y�B�Y�n�̓��F�l�g�B�̃g���R���[�g�B�A�Y�B�A�[�S�̏n���^�C�v�ł���_�b���[���H��n���̃f�U�[�g���C���E�g���R���[�g�ɒЂ������́B���ł͖k�C�^���A�S�ʂɍL�܂������@�����A���C���╒���̍i�肩���ȂǂŒЂ�����ŏn��������^�C�v�̃`�[�Y���u�E�u���A�R�v�Ƃ����B�g�����ς炢�h�Ƃ����Ӗ�(���n�ł̓������b�RMorlacco�Ƃ����������`�[�Y������Ƃ����B�o������琥��H�ׂĂ݂���)�B���Ă��̐��������A�n���S�[�_�̂悤�Ȑ[���F�B���������X�Ђ��̂悤�Ȏ|�݂����̒������ς��ɍL����B���{���Ȃǂƍ��킹�Ă݂����������B�����v�`�v�`�Ɗۂ������������邪�A��������̗��n�B�C�^���A�k���͂��̃^�C�v�̃A�~�m�_�������Ȃ��B(2008.9.6)
|
|
|
|

|
�X�v�����c
Sprinz�@(AOC)
100������600�~�@
�������A
M.G.45�`49%�@���M����^�C�v�@�X�C�X�E�����X�C�X
18�����ȏ�n���̍d���`�[�Y�B���j���Â����[�}���ォ�瑶�݂��Ă����炵���B��p�̃J���i�ō���ĐH�ׂ�B���̃`�[�Y���L�������ĂăX�v�����c�����܂ŐH�ׂ����Ƃ������������Ƃɋ������B�H�ׂĂ��Ǝv���Ă����B
��������ĕ\�ʐς��L�����邱�ƂŁA���ʂŎ|�݂ł���A�~�m�_����������B���܂݃`�[�Y���B(2007.3.1)
|
|
|

|
�t�F���~�G�ōw���A100��725�~�B�x�����B�̃u���G���c�����炱�̖������������ł��B���[���b�p�̒��d���`�[�Y�̒��ōŌÂ̂��̂̂ЂƂ��Ƃ��B�O��H�ׂ��X�v�����c�ɔ�ׂ�ƐF���W���B�ʐ^�Ō����ƍ������Z�����A�O��ɋ߂������Ȃ̂��낤��(�O��͎���Ă����̂ŕs��)�B�����A�~�m�_�����������Ɍ�����B�A�~�m�_�̓W�����W�����Ƃ����H�����B��p�̃J���i�ō�����H�ׂ�Ɛ�ɓ�����ʐς��傫�����炩�A�|�݂��K�c���Ɗ�����B������������̈ȊO�ɁA�_��ɐ������̂����H�������A���������ق��������������ȁB(2008.6.6)
|
|
|

|
�`�[�Y��Ђɋ߂�F�l����A�ܖ������܂�1�������̃X�v�����c��2�s�ōw���B�s�ꉿ�i��100��700�~���炢������14,000�~�����B�j�i�̒l�i�ŏ����Ă�����ă��b�L�[��
���̎ʐ^��300�����炢���B�e�������̂ł��B�O�����d��������������ł��Ĕ����X���C�X���ĐH�ׂȂ��Ƃ炢�B�����̂�����͂܂��_�炩�߂ŃR���e�Ƃ����ꂭ�炢�d���Ȃ̂ŁA�X�e�B�b�N��ɂ��ĐH�ׂ��܂��B�A�~�m�_���W�����W�������Ƃ��ĊÂ݂Ǝ|�݂������`�[�Y�ł��B�T���_�Ɋ��߂̂悤�ɐU��|�����肵�ĐH�ׂ�̂��ǂ��B��p�̃J���i�Ȃ������đ��v�I�����X���C�X���鎞�͖�̔���s�[���[�ŁA�蕪���鎞�͂�������Ƃ������n�̕�A���͒��ؕ�Ő��Ă��܂���B(2011.12.29)
|

|
|
|

|
�X�v���b�T�E�f�b���E�W���f�B�J���G(�c�n�o)�@SPRESSA
DELLE GIUDICARIE DOP�@100����1450�~
�������A���M����@M.G29�`39���@�C�^���A(�g�����e�B�[�m�E�A���g�E�A�f�B�W�F�B�j
2003�N��31�Ԗڂ�DOP�ƂȂ������̃`�[�Y�́A�R�x�X�L�[�Œm����g�����e�B�[�m�����A�A�_���b�����u�����^���R�����ɂ���W���f�B�J���G�k�J�ő����Ă���B�o�^�[��������c��̒E�����������Ă���B�Ȃ���9��10���`6��30���܂Ő����ł���A7���`9��9���܂ł̐^�Ă͍���Ȃ��B�H�ׂĂ݂�ƁA���b�������Ȃ�����Ǐn�����������炩�|��������A��������⋭�߂̖��킢�B�`�[�Y�S�̂��������Ă��ăX�J�X�J�Ȉ���B���ꂪ�{���̖��Ȃ̂��H(2007.7.7)
|
|
|
|

|
�Z�^���i�C
�������AM.G.�H�@���{�E�k�C���v���S���Ȃ����E����ǂ��`�[�Y�q��
���{�̃`�[�Y��ꐢ��̂ЂƂ�A20��̍��ɒP�g�f���}�[�N��5�N�قǏC�s����}�C�X�^�[�̎��i�����ߓ��T���̍��Z�^���i�C�B�f���}�[�N�̃`�[�Y�ӂƂ��č���Ă��܂��B����̃Z�^���i�C�̊O��̓��b�N�X�ŕ����ďn�������������h���X�^�C�v�B�O�����C�G�[���̓��_�ۂ��g���āA�U�`�W����ԏn���������`�[�Y�B�u�Z�^���i�C�v�Ƃ͂��̂���ǂ��`�[�Y�H�[�̂��鐣�I�̃A�C�k��ł̒n���ł��B�}�C���h�Ȗ��킢�łƂĂ��H�ׂ₷���`�[�Y�ł��B(2010.9.4)
|
|
|
|

|
�u�^�J���̃^�J���v�@
�������@�k�C���E�r���R�E�`�[�Y�H�[�^�J��
�k�C���E�`�[�Y�H�[�^�J���ō���Ă��鋍�����̃n�[�h�^�C�v�̃`�[�Y�ł����挎�s��ꂽ�u��9�� ALL JAPAN �i�`�������`�[�Y�R���e�X�g�v�Ŕ_�ѐ��Y��b�܂��l����������B�r���R�ł��Z���q����^�c�����ꂽ�����ŁA�킳��̐ē����O(�Ȃ�݂j����Ɖ��l���`�[�Y������Ă��܂��B�A�~�m�_�̌������o�āA�|�����������芴������B(2013.11.10)
|
|
|
|

|
�g�[�}�E�X�p�C�X�@Toma
Alle erbe Aromatice�@100����880�~
�����@M.G.�s���@�C�^���A�E���@�b���E�_�I�X�^�B
�㊯�R�uEATALY�v�ōw���̃`�[�Y���`�[�Y��ɂāB�������肵���f�p�ȍ��Ƃ�����ۂ̃S�c�S�c�Ƃ������߂̊O��(�g���n�̊O��)�ɂ������E�ӏ��Ȃǂ�����B���]��Ƃ��[���łȂ������̂��ȁH�f�ʂ͂��Ȃ艩�F���Z���ڂŁA���J�j�J���z�[���������ς��ŁA�����N�~���E��̒܁E�u���b�N�y�b�p�[���������r�[���̂��܂݂ɂ��Ȃ肻���ȃX�p�C�X���������`�[�Y�B�X�p�C�X�̂Ȃ�������H�ׂ�ƁA��╗���Ɍ�����B���܂݃`�[�Y�Ƃ��Ă͏[��������������ǂˁB100��880�~�͂�����ƍ������ȁB(2008.11.9)
|
|
|
|

|
�g�[�}�E�s�G�����e�[�[�@Toma
Piemontese (DOP)�@250����2.81���[���A��470�~
�S���܂��͕����E�����������@�����M����
M.G.20�`40%�@�C�^���A�E�s�G�����e�B
�C�^���A�̃A�I�X�^�ɗ��s���A�������̂Ŕ����Ă݂܂����B���{�ł͂قƂ�nj������܂���B���R�ȕ\��Ŕ����ۂ��A�Ƃ���ǂ�����J�r�Ȃ�����܂��B�����f�ʂ̓��J�j�J���z�[������R�ŁA�c�ɍ��Ƃ������͋C�ł��B���{�ɂ��Ǝ��R�̓��A�̒����n���ɂʼn����ŐȂ���A60���ԏn��������Ƃ���܂����A�E�H�b�V�����Ă���悤�ȕ\��ɂ͌����܂���B���Ă���͓��A�A�n���ɂ̂ǂ����Ȃ낤�BM.G.��DOP�K��ł͕�������܂����A�����H�ׂ�����͂�������ƒW���Ȃ̂Ŗ��炩�ɒ�߂ł��ˁB�D�������킢�������s�G�����e��Bra�̃e�[�l���ɂ��������Ă܂����A������̕����������������B(2008.7.6)
|
|
|
|

|
�o�X�^���h�E�f���E�����e�O���b�p�@Bastard
del Monte Grappa
�������A
M.G.�s���@�C�^���A�E���F�l�g�B
�搶�̃C�^���A�E���F�l�g�B�̂��y�Y�`�[�Y�B�o�b�T�[�m�E�f���E�O���b�p�̖k���ɂ���O���b�p�R���Y�n�B��ł��������ď����������𑝂₵���邱�̂�����̌ŗL�̋��u�u�����[�iBurlina�v�̃~���N�ō���܂��B������y���������Ă��Ȃ��̂��낤�A���J�j�J���z�[���������ς��B�C�^���A�ŐH�ׂ��g�[�}�E�s�G�����e�[�[�ɂ��ʂ���悤�ȏ_�炩���ނ����肵���g�D�B�����͒��悭�A�}���l�[�Y���Ă����悤�ȕ�������������B�f�p�Ŕ���������(2008.9.6)
|
|
|
|
|

|
���C���̐_�l�̖��O�̃o�b�J�X�B�|�݂������ǂ�����Ƃ��Ă���̂Ŗ��O�̒ʂ�ɁA��������Ƃ����ԃ��C���ɂ悭�����܂��B�C���t�H���[�V�����Ƃ��āA�u���E���X�C�X�̃~���N�ō���A�Ă̍��n�ŕ��q���č��ꂽ8�����ȏ�̏n���Ƃ̂��ƁB������8�����O�ƂȂ�Ɠ~�ł�������ۂ�8�����ł͂Ȃ��A12�������炢�B�܂��N�̉Ăɍ��ꂽ���̂Ɛ����ł��܂��B�F���|�݂�12�����͌o���Ă��邭�炢�̐[���ǂ�����Ƃ��Ă��āA�z���g�ɔ��������ł��B���{�̈���^�C�v�̃g�b�v�N���X�ƌ����Ă����ł��傤�B(2010.9.4)
|
|
|
|

|
�p���~�W���[�m�E���W���[�m(DOP)�@100������620�~�@ 
�������A���M����v�C�v�@
M.G.40%�@�C�^���A�E�T���f�B�[�j���B
�G�~���A�E���}�[�j���B�̂�������ꂽ�n��ł������Y����Ă��Ȃ��`�[�Y�B�p�����U���ƌ����ƃ`�[�Y�̂��ƂقƂ�ǒm��Ȃ��������̓N���t�g�Ђ�z�����Ă�������ǁA�������Ƃ͕ʕ��B�p���~�W���[�m�E���W���[�m������N���t�g�ЂɁu�p�����U���v�Ƃ����\�L�̍����~�߂��AEU�̍ٔ����ɐ\�����Ă����Ă��邻���ł��B�E�����ō����̂Œᎉ�b�ŁA�����n�������̂ŃA�~�m�_�̌������o�āA���ނƃW�����W�����Ƃ��������B�p���~�W���[�m�E���W���[�m�͍ӂ��ă��C���ƈꏏ�ɐH�ׂ�̂���Ԕ��������B�p�X�^�̏�ɂ�������A�X���C�X����Ȃ�A�u�䏊�̃n�Y�o���h�v�̈��̂������O���i
�p�_�[�m�ŏ\�����ˁB(2006.1.7)
|
|
|

|
�p���~�W���[�m�E���W���[�m�c�n�o30�����B����Έ�ōw���B100����500�~���炢�Ɗi���Ȃ̂łǂ��Ȃ̂��ƕs��������܂������A���̒l�i�ŃA�~�m�_�������Ԃ�Ɗ������Ă��������ł����B�ӂ���30�������̂Ȃ�č���Ďg���ܑ͖̖̂����Ǝv���Ă��܂�����ǁA����Ȃ�ӂ�Ɏg���Ă��������B(2007.6.10)
|
|
|
 �@ �@
|
����̂́A�t�F���~�G�Ђōw���̃p���~�W���[�m�E���W���[�m18�����n���B18�����ȏ�n��������Ɋ�]�҂݂̂��錟���ɍ��i�������̂��G�N�X�g���ƌ����܂��B�p���~�W���[�m�E���W���[�m�����̃p���t���b�g������ƁA�G�N�X�g���ƍ��i�������̂́A�`�[�Y�{�̂ɂ�EXTRA�̍���A�J�b�g�������̂̓p�b�P�[�W�ɂ��E�̃}�[�N�����邱�ƂɂȂ��Ă��邻���ł��B�Ƃ������Ƃ�18�����ȏソ���Ă������p�b�P�[�W�ɏ��W���Ȃ����̂̓G�N�X�g���Ɩ����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����̃p�b�P�[�W�ɂ̓G�N�X�g���}�[�N�����Ă��Ȃ��B�܂�18�����͏n�����Ă��邯��ǂ��A�F��͎Ă��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB(2007.12.1)
|
 
|
|
|

|
�p���~�W���[�m�E���W���[�m24�����n���A�t�F���~�G�ōw���A100����672�~�B���̉ĂɃp���}�ɗ����悤�ƍl���Ă��āA�Ȃ�p���~�W���[�m�E���W���[�m�̃`�[�Y�H�ꌩ�w�������Ǝv���Ă���̂Ŏ��̒��ł͏{�̃`�[�Y�ł��B�傫���������������ꖂ�ƁA���̒��Ɏ|�݂��W�����ƍL����A�W�����W�����Ƃ����A�~�m�_�̐�G����ґ�Ȗ��킢�ł��B�����X���C�X����Ɛ�S�̂Ŏ|�݂���������̂ŁA���̂悤�ɐH�ׂ�l�������ł����A���̓K���K����ꖂ��ĐH�ׂ�̂��D���ł��B(2008.5.23)
|
|
|

|
�p���~�W���[�m�E���W���[�m�E�I�[�K�j�b�N�B�R�x�n�тɂ���u���E���B�b���Ёv�̂��́B���K�͂Ȕ_�Ƃ̂���1���ɐ����ł���̂�6�����B2003�N�̎R�̃`�[�Y�̃I�����s�b�N�ŋ��܂���܂��Ă��邻���ł��B�C���t�H���[�V�����������n�����Ԃ͕���܂��A�A�~�m�_�̂��傫���o�Ă���̂ŁA24�����͂䂤�Ɍo���Ă���Ǝv���܂��B�������������߂Ȃ̂��A��_�炩�߁B���͂��̂��炢�̍d���Ƃ������H���͍D���ł��ˁB���͓��ɃI�[�K�j�b�N������ǂ��Ⴄ���͎��ɂ͕���Ȃ������B(2009.12.5)
|
|
|

|
�p���~�W���[�m�E���W���[�m�E���@�b�P�E���b�Z�B�G�~���A�E���}�[�j���B�̒n��`���̋��u���b�W���[�i��v�B�ꎞ��900���܂Ō��������̂�ی삷�邽�߂ɒa�������u�ԋ�(���@�b�P�E���b�Z)����v���F�肵�����b�W���[�i��100���ō���Ă��܂��B�u�p���~�W���[�m�E���W���[�m�̃��[���X���C�X�v�ƌĂ��قǂ̋M�d�i�Ȃ̂������ł��B���݃��@�b�P�E���b�Z�̃p���~�W���[�m�E���W���[�m�͂킸��4���݂̂ō���Ă��邾���Ȃ̂��Ƃ��B����̂���͏n�����Ԃ͕s���B�A�~�m�_���傫���o�Ă���̂ŁA24�����`30�������炢�o���Ă������Ȋ����B�ʏ�̃`�[�Y�ɔ�ׂāA���F���Z���A�����Z���Ƃ����G�ꍞ�݂����ǁA�n�����Ԃ������̕��ƐH�ה�ׂĂ��Ȃ��̂ŁA�悭�킩��Ȃ��B�������������������Ȃ����͕ʂƂ��āA�`���͎���Ă������Ƃ��������ɂ͎^���I(2009.12.5)
|
|
|

|
�p���~�W���[�m�E���W���[�m��5�N�n���B60�����n�������E�E�E�������ˁB�����n���ӂƂ��Ă���u�{�i�[�e�B�Ёv�̂��́B�a��肩�炱������āA�����3�����������Ȃ������ł��B�����3�����������Ȃ��āA�X�Ƀ`�[�Y�����������̂�60�����ゾ�Ƃ������Ƃ��l����ƁA�Ȃ��Ȃ������Ƃ��đ�ς������Ȃ��Ƒz���ł���B100����1600�~�B��������4�{�����邪�A������d���Ȃ��낤�B�F���Z�����F���ۂ��Ȃ��ĂăA�~�m�_�̌��������Ȃ�傫���̂ŁA�S�[�_�̒����n���Ȃǂɂ��肪���Ȗ��X�Ђ����C���[�W���Ă������A������ƈ�����B�|���͂������肠�邪�ӊO�ɂ�������B����Ȃɂ����Ȃ��B����������̂��v�������_�炩���B���̍D�݂ł͂����܂ŏn�������Ȃ��Ă������̂��ȂƂ��������B(2009.12.5)
|
|
|

|
�s�A�[���F�@PIAVE
MEZZANO �iDOP�j�@
100g=\767
�������AM.G.31�`38%�@�@�C�^���A�E���F�l�g�B
�����2010�N5����DOP�ɔF�肳�ꂽ�ς�����s�A�[���F�E���b�c�@�[�m�B�܂����{�ɂ��ڂ��Ă��Ȃ��V�����`�[�Y�ł������܂��I�C�^���A��DOP��������̂͋v���Ԃ�̃j���[�X�ł������܂��ˁB���F�l�g�B�x�b���[�m�Ő��Y����܂��B���̓y�n���k�ɗ����s�A�[���F�삪���̖��̗R���ł��B�R�̃`�[�Y�炵���f�p�ŗD���������ŁA�����ł��H�ׂ�ꂻ���ł��B�i2011.5.7�j
|
|
|

|
�s�A�[���F�B
�C�^���A�E���F�l�g�B�̃h���~�e�R��n��̃`�[�Y�ŁA2010�N��DOP���擾�������́B�n���i�K�ɂ���Ă������o�[�W����������悤�ł��B���x���ɁuMezzano�v�Ə�����Ă���Ƃ��납��APiave
Mezzano�i61�`180���n���j���Ƃ킩��܂��B�Ⴍ�ėD���߁A�~���N�̊Ö����ق̂芴���܂��B(2015.1.25) |
|
|
|

|
�r�b�g�E�G�N�X�g���x�b�L�I(DOP)�@Bitto
�d�������� Vecchio
1�s��58.5���[��(��1���~)�@
�������A�����M����^�C�v�@M.G.45%�@�C�^���A�E�����o���f�B�A�B
�C�^���A���s���Ƀ`�[�Y�V���b�v�Ŕ������r�b�g�̃G�N�X�g���x�b�L�I�A�����340������܂��B����ł����`�[�Y�̒��ł��j�i�ɍ����A�A�Y�B�A�[�S�X�g���x�b�L�I�̖�{�̉��i�B���₭�R�����w�����āu������ăr�b�g�̒����n���^�C�v��ˁH�ƂȂ�̂͏�����߂̃��[���oReserva�ˁv�ƌ������r�[�A�X�̐l�̊�F������肠���������ƑE�߂Ă����B�����̕i���ۂ������ȁB�������艽�N���̂������Y�ꂽ�̂��ꐶ�̕s�o�ł��邪�A���̓X�ł̓X�g���x�b�L�I�����G�N�X�g���x�b�L�I�̕��������������A�F�����Ă��A�~�m�_�̌����̑傫�����炵�Ă��A4�N�ȏ�͌o���Ă�Ǝv���B���{�ł̓t�F���~�G��24�����n���̃r�b�g��100��1890�~�Ŕ̔����Ă邯�ǁA���n�ł��������������鉿�i�Ȃ�ł��ˁB����Ȃɂ���Ǝv��Ȃ������B�p�C�i�b�v���̂悤�ȍ��肪���Ď|�݂������A�{���{���ƕ���邭�炢�����Ȃ��Ă��܂��B���т肿�т�ꖂ�Ȃ�����{���ƍ��킹�ĐH�ׂĂ݂悤�Ǝv���܂��B(2008.9.6)
|
|
|
|

|
P.D.S
�@�@�@
�������@���M����^�C�v�@���R���^��s�E�f�R���b�e�E�o���r�[�m
���`��A�ǂ��Ȃ�ł��傤�B�{��ǂ�œƊw�ł����܂ō��ꂽ�̂͂������Ǝv���B���c�O�Ȃ��ƂɁA�����v���`�[�Y�̔��������̑傫�ȃ|�C���g�ł���u�~���N�̊Â݁v�u�n���̎|�݁v�����̃`�[�Y�ɂ͏o�Ă��Ȃ��B���͋ꖡ�ɕq���ȕ����Ǝv�����A����ɂ��Ă��ꂢ�B�Ō�܂Ō��ɋꖡ���c��̂��B�T��ނ̃`�[�Y�����H�������A�S���ɋ��ʂ��Ċ����邱�́u�ꖡ�v�A���R�͉��Ȃ낤�B�h�����z�ł��߂�Ȃ����B(2013.10.6)
|
|
|
|

|
�t�H���c�@�@��160����830�~
�������@���M����^�C�v�@���Ɍ��O�c�s�E�����q��`�[�Y�H�[
�C�^���A��Łu�����v�̈Ӗ��̃t�H���c�@�A�n�����Ԃ�15�����ȏ�A��������ƃA�~�m�_�̎|����������d�オ��ɂȂ��Ă��܂��B�p���~�W���[�m�E���b�W���[�m��O���[�i�E�p�_�[�m�ɋ߂��������ȁB(2013.10.6)
|
|
|
|
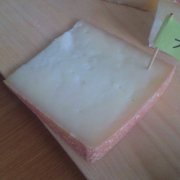
|
�t�H���^��
�@�@
�������@���M����^�C�v�@���R���^��s�E�f�R���b�e�E�o���r�[�m
�{��ǂݓƊw�ō���Ă���Ƃ����B�����ڂȂ��Ȃ��ǂ����������A�������H�ׂĂ݂�Ƣ�ꂢ�v�B�~���N�̊Â݂�������ꂸ�A�ォ��ォ��ꖡ�����銴���BY�q�搶�H���A�u�z�G�[�̔����������̂�v�Ƃ̂��ƁB�߂����B
�l�b�g�V���b�v�ł́u�X�C�X�̃��N���b�g�A�t�����X�̃A�{���_���X�ƌZ��`�[�Y�v�Ƒ肵�Ĕ����Ă���B���������āu�Z��v�Ƃ��Ă�̂��H�킩���B�h�����z�ł��߂�Ȃ����B(2013.10.6)
|
|
|
|

|
�t�H���e�B�[�i(DOP)�@Fontina�@100������1000�~�@
�������A
�����M����^�C�v�@M.G.45%�@���@�b���E�_�I�X�^�B
�e�͂�����A���`���`�Ƃ��Ă���B���@���ꏏ�ł����@�b���E�_�I�X�^��12�̌k�J�ȊO�ō��ꂽ���͍̂���Ă��A�t�H���e�B�[�i�Ƃ͖���ꂸ�A�t�H���^���ƌĂԂ����ł��B6/15�`9/29�̊Ԃ�100���Ԃɐ����̂��͓̂��ɔ����������āB
���āA���̃`�[�Y�A�t�F���G�~�ōw���B�O��̂Ƃ���Ƀt�H���e�B�[�i�̌k�J�̃}�[�N���ΐF�ł���B����͍��̂悤�ȒЕ��L������A�H�ׂĂ݂�ƁA�͂��݂��r�߂����̂悤�ȊÂ݂ƌ��Ɏc��ꖡ������B�i�b�c�̕���������B�M���ėn�����Ă݂�ƁA�����Z���œc�ɂ��ۂ����������_�A���N���b�g�Ɏ��Ă�C�����܂����B(2008.2.16)
|
|
|

|
�t�F���~�G�ōw����100����1050�~�B�̂̓t�����X�̃T���H���n���ȂǂƓ����T���H�C�A�����������̂ŁA�`�[�Y�������Ă���̂ŁA�A�{���_���X��N���b�g�Ɠ����悤�ɁA�O����E�H�b�V�����ă����W�����ł��Ă���B���������O�炪�������ȁA�Ƃ�����ۂł��B�ЂƂ����H�ׂāA����ς�Е����Ċ����������B���J�j�J���z�[�������\����܂��ˁB���̉ĂɃ��@�b���E�_�I�X�^�ɍs�����肾����A�ނ����ł������Ȃ̂�H�ׂĂ��悤�Ǝv���B�����̃t�H���h�D�[�^(�����E�����E�o�^�[�ō����C�^���A�Ń`�[�Y�t�H���f��)�͓~�̗��������ǐH�ׂ���Ƃ����ȁB(2008.5.23)
|
|
|

|
�t�F���~�G�ōw�����u�`�[�Y���낢��H�ה�׃Z�b�g�v�̒��ɓ����Ă܂����B������O��Ƀu���[�̃X�^���v�������Ă��邩��A�����t�H���e�B�[�i���Ɛl�ڂł킩���Ă��܂��B��������N���b�g�̂悤�ȒЕ����ۂ��������v���v�����邵�ˁB�ނ��ނ������g�D�ɂ��̍���A�a�ݕt���ɂȂ肻���B�܂������c�肪����̂ŁA���@�b���E�_�I�X�^�ŐH�ׂ��L���x�c�̃X�[�v������āA��ɗn�����ĐH�ׂ悧�`���Ɓ�(2008.8.24)
|
|
|

|
�㊯�R�uEATALY�v
100��1,080�~�B���@�b���E�_�I�X�^�ŐH�ׂ��{��̃`�[�Y�̔Z�������܂��o���Ă���̂ŁA�Ȃ��������������������Ƃ������A�����������Ƃ������A���E�ۓ��̋������ア���Ȃ��Ƃ�����ۂł����B�����ƃ��b�`���Ƃ��ĂĒЕ��L�������t�H���e�B�[�i���D���ȂȁA�Ǝ����̍D�݂��Ĕ����I(2008.11.9)
|
|
|
|

|
�v�����H���[�l�@���@���p�_�[�i�@Provolone�@100������578�~�@
�������A�����M�^�C�v�@M.G.44%�@�C�^���A�E�����o���f�B�A�B�Ȃǃ|�[�͗���A
�傫�ȕ�����80�L���������^�̃`�[�Y�B�m�i�V�^�A�T���h�o�b�N�^�A�T���~�^�Ƃ��낢�날�邪�A����̓T���~�^�B�u�����v���Ӗ�����u�v���[���H�[���v�Ƃ������t���炱�́u�v�����H���[�l�v�Ƃ������������Ƃ��B�p�X�^�t�B���[�^�ō����B�������DOP�������Ă��Ȃ����A�C�^���A�암�����Ƃ��Ƃ��̃`�[�Y�̔��ˁBDOP������͖̂k���v�����H���[�l
���@���p�_�[�i�B�@�ۂ��ăp�X�^�t�B���[�^�ō���Ă�˂��Ċ����B���̓}�C���h�B�n�����ĐH�ׂ�Ƃ����Ɣ����������낤�B(2007.10.6)
|
|
|

|
�t�F���~�G�ōw���A100��725�~�B�����ƃp�X�^�t�B���[�^�ō���Ă��邩�A�@�ۂ�Ă݂܂��ƁA3��ڂ̕����ŗ܂����B�u���C���h�Ńp�X�^�t�B���[�^�̊m�F����Ƃ��́A������������łȂ��A�S������Ă݂邱�Ƃ��d�v�ˁB���Ď��H�B���̂܂ܐH�ׂ�ƌ��t�͓K�łȂ���������Ȃ����ǁA�v���Z�X�`�[�Y�̂悤�Ȗ��Ɏ��Ă��邩�ȁH�o�Q�b�g�̏�ɏ悹�ďĂ������̂��A���H���܂������A�Ă��Ǝ|���ł��ȁA���̃`�[�Y�I�Ă��p�Ƃ��ĐH�ׂ����������ł��B(2008.5.30)
|
|
|
|

|
�y�R���[�m�E�T���h�E�t���X�R(DOP)Pecorino
Sardo �@100������630�~�@ �@100������630�~�@
�r�����A�����M����^�C�v�@M.G.40%�@�C�^���A�E�T���f�B�[�j���B
�y�R���[�m�E�T���h�́A�u�h���`�F�i�t���X�R�j�v�Ɓu�}�g�D�[���v��2�^�C�v������A����́u�h���`�F�i�t���X�R�j�v��20�`60�����̒Z���n���ł��B�����Ƃ肵���H���ŐH�ׂ�ƊÂ݂�����A�����_����������B
(2005.11.5)
|
|
|

|
�y�R���[�m�E�T���h�E�t���X�R(DOP)100����840�~��2�N�O��茴�����A���[�����Œl�オ�肵�Ă��܂��B�R���e�Ȃǂ̂悤�ɂ͉��M�����A�����M(40�����ʁH)����ƂȂ邻�����B���J�j�J���z�[���炵��������������B�~���L�[�̂悤�ȍ��肪����A�H�ׂĂ݂�ƃ~���N�̊Â݂�������B�~���N�������l�b�g���r�B
(2007.11.10)
|
|
|
|

|
�y�R���[�m�E�V�`���A�[�m�@(DOP)Pecorino
Siciliano
�r�����A���M����^�C�v�@M.G.40%�@�C�^���A�E�V�`���A�B
�y�R���[�m�E�V�`���A�[�m�́A���̖��̒ʂ�V�`���A���ō���Ă���B����ʂ����A�G�߂ɂ���Ė��킢�̈Ⴄ�`�[�Y������Ă���B�傫����4�`15�s�A�n����4�����`18�����Ƃc�n�o�̋��e�͈͂��L���B����͍̂��Ӟ�����(�c�n�o)�Ȃ̂ŁA�����ɂ́u�y�R���[�m�E�V�`���A�[�m�E�y�p�[�m�v�Ƃł��Ă炢���̂��낤���B���h�q����Ȃ�Ă��̂�����炵������ǁA����͂c�n�o���ǂ������s���B
����͐��k���V�`���A�y�Y�ɔ����Ă��Ă��ꂽ���́B���Ӟ��̃z�[����������������B�����k���ł݂�ƁA�z���C�g�E�X�e�B���g���E�������s�[���̃`�[�Y�̍���Ɏ��Ă���Ǝv�����B���k�n�̎_���ƁA���Ӟ��̍���ƁA�r�̃~���N�̂ɂ���������B�H�ׂĂ݂�Ɖ�����������ŁA���Ȃ�Z�����B�D�������킢�łȂ��쐫�����ӂ��Ƃ��낪�A�C�^���A�̓���Ċ��������܂����B(2008.3.1)
|
|
|
|

|
�y�R���[�m�E�g�X�J�[�m�E�X�^�W�I�i�[�g(DOP)�@Pecorino
Toscano�@100������700�~�@
�r�����A
�����M�����^�C�v�@M.G.40�`45%�@�C�^���A�E�g�X�J�[�i�B
�g�X�J�[�i�ŌÂ��������Ă����r�̃`�[�Y�B�E�����Ȃ��r�̃~���N������̂ŗD������������ƃR�N�������B�̂́u�J�`���v�ƌĂ�Ă��������Ɂu�y�R���[�m�E�g�X�J�[�i�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B�u�X�^�W�I�i�[�g�v�́u���Ԃ��o���āv�̈ӂ�4�����ȏ�̏n���̂��̂������܂��B
(2005.11.5)
|
|
|

|
�����4�����n���̃X�^�W�I�i�[�g�ł�DOP�ł��B�t�F���~�G�ōw���ƕ������̂ŁA�����炭�C���E�t�H���e�[�g�Ђ̂��̂��Ǝv���B�y�R���[�m�E�g�X�J�[�m�̓X�^�W�I�i�[�g�ȊO�ɁA20���̏n���́u�t���X�R�v�ƁA6�����n���Ŏ��͂ɃI���[�u�I�C����h�����u�I�[���E�A���e�B�R�v�A1�N�n���́u�E�i���m�v�����邻���ł��B�r�����̃`�[�Y������ǂ��A�����l�b�g�͋��̂��̂��g���Ă���Ƃ����B����́A���̒n���̃y�R���[�m�����A�������ꂽ����������̂��Ƃ��B(2007.11.10)
|
|
|

|
�܂��܂������4�����n���̃X�^�W�I�i�[�g�ł��ADOP�ł��B�C�^���A�̗r�͖쐫�����邯��ǁA��r�I����͗D�����^�C�v�ł��B(2008.3.1)
|
|
|

|
�t�F���~�G�ōw���@100����1082�~�@4�����n���B�O��ɋ߂����������F�����悭�A�������͏��������B�����͋��߂Ŏ|�݂��K�c���Ƃ���B�Ȃ����̂��c�ɂ��ۂ��Ƃ������A�������Ɍ����Ă܂��B(2008.5.30)
|
|
|
|

|
�y�R���[�m�E�g�X�J�[�m�E�t���X�R(DOP)�@Pecorino
Toscano�@100������819�~�@
�r�����A�����M�����^�C�v�@
M.G.40�`45%�@�C�^���A�E�g�X�J�[�i�B
�������Ƀy�R���[�m�E�g�X�J�[�m�E�X�^�W�I�i�[�g���H�ׂ��̂Ŕ�ׂĂ݂�ƁA�e�͂������ă~���N�̊Â�����ƂŔ��������B�t���X�R�͔M�������Ă��������������ł��B�{��ł͐��̋ƍ��킹�ĐH�ׂ�Ɩ{�œǂ��Ƃ�����܂����A���̋��Ĕ���������ł��傤���B�����{��ŐH�ׂĂ݂������̂ł��B
(2007.11.10)
|
|
|

|
�t�F���~�G�ōw����100��977�~�B�F���ŏ_�炩���A�e�͂�����B�~���N�̊Â݂ƍT���߂ȉ����ŁA�C�^���A�̃y�R���[�m�̃C���[�W�ƈ���ėD���������B���Ȃ݂��t���X�R���n������Ă��X�^�W�I�i�[�g�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂����[�ł��B(2008.5.30)
|
|
|

|
�t�F���~�G�ōw�����u�`�[�Y���낢��H�ה�׃Z�b�g�v�̃t���X�R�B������Ȃ����u���C���h�Ō����������y�R���[�m�E�g�X�J�[�m�E�t���X�R�Ɣ����Ă��܂����B���̃`�[�Y�̌�������\�͂����Ȃ荂���Ȃ��Ă����̂������܂��B���������Ƃł��B�_�炩���āA���ނƌ��̉��ɊÂ��������܂��B���܂ł̓~���N�̊Â����Ǝv���Ă������ǁA������ƈႤ�悤�Ɋ������B���̎��g�̊Â��ɋ��ʂ���悤�ȊÂ��ƌ����������ȁB�q�c�W���Ċ����B(2008.8.24)
|
|
|
|

|
�y�R���[�m�E���}�[�m(DOP)�@Pecorino
Romano �@100������460�~�@ �@100������460�~�@
�r�����A���M�����^�C�v
M.G.50%�@�C�^���A�E�T���f�B�[�j���B�A���b�c�B�I�B
���[�}����ɂ͍���Ă����Ƃ����C�^���A�������ŌẪ`�[�Y�ƌ����Ă���B���X���[�}�ō���Ă����̂Ń��}�[�m�Ɩ����t���Ă��邪�A���݂̐��Y�̒��S�̓T���f�[�j���Ɉڂ��Ă��܂��܂����B�E�������r�̃~���N��������B�����������̂ŁA�������肵�ė�����p�X�^�ɂ����ĐH�ׂ�̂���ʓI�B�H�ׂĂ݂�ƁA�z���g�ɉ��C�������B������Ƃ��������B
(2005.11.5)
|
|
|

|
����ĐH�ׂ�`�[�Y���ƍĔF���B���{���Ȃ�����������Ƃ̈ӌ����o�܂������A���̂܂܃{���{���H�ׂ�ɂ͉�������������C�����܂��B�H�ׂ���͂̂ǂ������Đ����������ł܂������́B�J���p�b�`���ȂǂɃ`�[�Y������ĐH�ׂ闿���̏ꍇ�A�������̃`�[�Y�A���Ƃ��p���~�W���[�m�E���b�W���[�m�Ȃǂ����A���̃y�R���[�m�E���}�[�m������������A�����������r���̕����F�������̂ŁA�ԂƔ��̃R���g���X�g���Y��ł����炵���B�u�J���{�i�[���v��u�A�}�g���`���[�i�v���A���̃`�[�Y��p����̂��{��̃��V�s�Ƃ̂��ƁB
(2007.11.10)
|
|
|

|
�t�F���~�G�w����100��767�~�B�������쓤���H���Ċ����H�|���|�������g�D�ŁA�Ȃ�Ƃ�����ς����Ƃ�B�܂�Ń^���R��ꖂ�B(2008.5.30)
|
|
|
|

|
�x���N�P�[�[�@Bergkase
�������A���M����
M.G.�s���@�h�C�c�E�o�C�G�����B�@�A���S�C�n��
�h�C�c�A���v�X�̎R�̃`�[�Y�B�u�x���N�v�Ƃ͎R�A�u�P�[�[�v�Ƃ̓`�[�Y�̈Ӗ��B���̂܂�܂ł��ˁB
�ȑO�A�搶���H�ׂ��̂̓~���N�̊Â݂������ς��ŁA�ƂĂ������������̂������Ƃ������ƂŁA����Љ�Ă����������̂ł����A����́E�E�E���ƃn�Y����������������܂���B�܂����A�`�[�Y�A�C�ƌĂ��K�X(�v���s�I���_�ɂ��)�ɂ�錊�ł͂Ȃ��A�������ɏo���Ă��܂��M�U�M�U�������J�j�J���z�[���̂悤���B���J�j�J���z�[���ɂ̓z�G�[�����܂�₷���A�z�G�[�����܂�ƎG�ۂ��������A�ꖡ�Ȃǂ̎G���̌��Ȃ̂��B���ۃJ�b�g���Ă݂�ƁA�Ă̒�z�G�[���o�Ă����B�H�ׂĂ݂�ƃ~���N�̊Â݂������������ɋꖡ������܂����B(2008.3.1)
|
|
|
|

|
�{�[�t�H�[��(AOC)�@ �@100��������900�~ �@100��������900�~
�������A���M�����^�C�v�@M.G.48%
�t�����X�E�T���H���n��(���[�k�E�A���v)
�A���v�X�R�[�ō����A�傫�ȎR�̃`�[�Y�B�n�����Ԃ�1�N�`1�N���B�A�{���_���X�Ɠ��l�ɑ��ʂ��ԗ֏�ɔ����Ă���̂������B�O��̕����Ɣ�߂��̐F�̕ς���������͂��Ȃ芣�����ĂĔ��������Ƃ͌����Ȃ��������ǁA�����̕����̓A�C�{���[�ʼn����������傤�ǂ悭�A�A�~�m�_�̌������݂�ꖡ���Z���A�������C�ɓ������B�u�v�����X�v�ƌĂ�Ă���̂��[���B(2004.11.6)
|
|
|

|
�T���H���̒���������ō����B�r�X�P�b�g��̊O��͌��߁B���Ă݂�ƔZ���A�C�{���[�F�B����ɂ��A�~�m�_�̌������݂���B�����k���ł݂�ƁA�Ȃ����c�i�ʂ̃j�I�C�B���H���Ă݂Ă��c�i�ʖ��B�Ȃ�łȂ�ł��傤�E�E�E�B�㖡�ɏ����u���v�̂悤�Ȏ_��������B����̂̓c�i�̖��������Ȃ������̂ŁA���܂�ǂ�����܂���ł����B(2007.3.3)
|
|
|

|
�{�[�t�H�[����1��45�s������B12���b�g���̃~���N��1�s�̃`�[�Y���o���邩��A12���b�g���~45�s�ŏ��Ȃ��Ƃ�540���b�g���̃~���N���K�v�Ƃ������ƂɂȂ�B���̂��Ƃ�����A���݂͐��Y�͋������_��ł���Ă���̂��Ƃ��B�B���ƂłЂƂ��\�ʂɉ���U��A�G�Ђ̂悤�Ȃ��̂Ń����W�����A���]������Ȃǂ̐��b���J��Ԃ��Ȃ�������B����ɂ���ďo����r�X�P�b�g�\�炪�ł���̂��B�ߋ��ɐH�ׂ��{�[�t�H�[���͊O�炪�������̂������������A����͔̂��߂����B���͔Z���߂�����ǁA���ǂ��Ȃ����������B(2007.5.12)
|
|
|

|
����̂��u�{�[�t�H�[���E�_���p�[�W���v�B�u�G�e���đ���v�̒��ł��W��1,500m�ȏ�̖q���n�ŕ��q�����u�A���p�[�W���̃{�[�t�H�[���v�ł��B����̂��A�Z���ŃR�N������B�₩�������S�����Y�����Ƀv�����X�ł��B(2007.9.1)
|
|
|

|
����̂��u�{�[�t�H�[���E�_���p�[�W���v�B�t�F���~�G�Ђōw���̃p�J�[���Ђ̂��́B100����1260�~�B�{�[�t�H�[���̃A���p�[�W����1500���ȏ�ƌ��߂��Ă��邪�A���͍��܂Ō�����Ă����B���̎�����(�{�[�t�H�[�����^���[�k��ƃA�{���_���X��)���R��o��Ȃ���A�R����(�V����)�Ń`�[�Y������Ă�����̂��Ǝv���Ă����B���A�Ⴄ���āB���̎�����(�Ⴆ���p�J�[����)�͎R�̘[�Ɏc��A�A���p�W�X�g�i�������j�ƃt���}�W���G���i�`�[�Y�E�l�j���ق��ĔC����̂������Ȃ̂ł��B�ւ��`�m��Ȃ������ȁB���āA����Beaufort�A�O��������A�O��ɋ߂��Ƃ���́A���Ȃ�Z���F�ɂȂ��Ă��܂��B����ɂ̓A�~�m�_�����������܂��B�����炭���Ȃ蒷���n�����Ă���Ƒz���ł��܂��B���͔Z���Ȗ��킢�ŁA�������������肵�Ă���B(2008.4.12)
|
|
|

|
�����͏n���m(MOF)�N���X�`�����E�W���j�G���̎肪����`�[�Y�̌����B�N���X�`�����E�W���j�G���̎肪�����{�[�t�H�[���B�ʐ^�ł͔����ł����A�A�~�m�_�̌����������Ă��āA�H�ׂ�ƍׂ������W�����W�����Ǝ��ɂ�����̂ŁA������x�̏n���͌o�Ă��Ă��邱�Ƃ���������B����10��������12�������炢�̏n���Ɠ���ł���B���肪�p�C�i�b�v���̂悤�ȃg���s�J���ŁA���ɂ�������B�E�����Ă��Ȃ��̂œ����b�������߂ȃ`�[�Y�ł��邯��ǁA�_���L���S��������ꂸ�A���炵���p�C�i�b�v���L�Ȃ̂͗��g�b�v�n���m�̎d����(�{�l�����Ɏ�������Ă���̂ł͂Ȃ��A�w�����Ă邾���Ƃ����b�������)�B(2008.10.4)
�����B�N���X�`�����E�W���j�G���̃`�[�Y�́u���E�`�[�Y����(��)�v����̎戵�B
|
|
|

|
�`�[�Y�̎�����ł����b�ɂȂ����搶�̃t�����X�y�Y�̃{�[�t�H�[���B���ƂƂ��̉ẴA���p�[�W���B�p���̃t���}�[�W�����[�u�A���I�X�v�̂��́B���������������̂��A���������������Ă��Ă܂����B�S�̓I�ɉ��F�����Z���A�A���p�[�W�����̂��ȁE�E�E�Ɗ��������܂��B�ẲԂ����H�ׂ����̃~���N�ō�����؋��ł��B�H�ׂĂ݂�ƃ{�[�t�H�[���Ɠ��̖F���ȕ��������������܂��B�o�m���Ȃǂ̋���ȃ`�[�Y��H�ׂ��ゾ�������炩����܂��A���҂��������t���[�c�̕����͊������܂���ł����B(2009.3.5)
|
|
|

|
MOF���[�����E�f���{�����̏n���̃{�[�t�H�[���E�_���p�[�W���B�O��͏����A�����j�A�L�����������A���Α��̊O��̓A�����j�A�L���Ȃ������̂ŁA���ɂȂ��Ă��������A�����j�A�L���Ă������̂Ɛ��������B�����悤�ɉ�]�����Ă��Ȃ��̂��ȁB�킸���ɃA�~�m�_�̌������������镔�������邵�A�O��̌���������̂ŁA�P�N�����炢�̏n���ł��傤���B�i�̂��镗���ŏ[�����������̂����ǁA���҂��傫�������������A��������قǂ܂ł͎����Ă��Ȃ������B�p�C�i�b�v���̂悤�ȃt���[�c�L�����҂��Ă��܂����A�Ȃ��Ȃ��o��Ȃ����̂ł��ˁB(2009.3.7)
|
|
|

|
����̓{�[�t�H�[���E�G�e(AOP)�B�{�[�t�H�[���̓T���H���n�����\�����^�̎R�`�[�Y�B�{�[�t�H�[���E�G�e�̓A���v�X�̎R�ɋ��������ĎR�̑���Ԃ�H�ׂ����Ăɍ��ꂽ�`�[�Y�Ȃ̂�����ǁA���q�E����E�����̂����ꂩ���A�W����1500���ɖ����Ȃ����̂������B���Ȃ݂�1500���ȏ�ŕ��q�E����E�������������̂́u�A���p�[�W���v�ƌĂя��i���l�����߂Ă��܂��B���āA����͉č��̃{�[�t�H�[���B�č��̂��͈̂�ʓI�ɔZ���F�����Ă����ۂ�����܂����A����͐F�������ł��ˁB�H�ׂĂ݂�ƁA�˂�����Ɛ�������������t���������肢���o���Ƃ͂����܂���B���������v���Z�X�`�[�Y�̂悤�B(2012.08.04)
|
|
|

|
����̓{�[�t�H�[���E�A���p�[�W��(AOP)�B�A���v�X�̎R��1500���ȏ�ŕ��q�E����E�����������u�A���p�[�W���v�A�{�[�t�H�[���̉��l�ƌ����Ă������ł��傤�B�����F�����Ă��Č��邩��ɂ����������B�H�ׂĂ݂�ƁA�{�����[�������i�i�ɈႢ�܂��B�|�݂���������Ƃ��邪�A�Ō�Ƀt���[�c�̂悤�Ȏ_��������܂��B�ƂĂ����������B(2012.08.04)
|
|
|

|
����͕��ʂ̃{�[�t�H�[��(AOP)�B���k����̉��l����̂��y�Y���{�[�t�H�[���B���l������ꂽ�����Ń`�[�Y�̏ڂ����f���͂킩��Ȃ��Ƃ̂��ƁB�ł͐������Ă݂܂��傤�B�܂��A�`�[�Y�̕\�ʂ�����Ƌ��߂ɐ^��p�b�N����Ă����`�Ղ�����̂ŁA�`�[�Y���X�Ńo�L���[�����Ă�������̂ł͂Ȃ��A�X�[�p�[�ȂǂŔ����Ă���^��p�b�N�̂��̂̉\���������B�H�ׂĂ݂�ƁA���X���ꂽ���肪����A�n���͎Ⴍ�_�炩���B�˂��˂����Ă��ăz�N�z�N�Ƃ��������������Ȃ��B�ō��̏o���̃{�[�t�H�[���̃A���p�[�W���ƐH�ה�ׂ��Ă��܂��Ƃ����߂����^�C�~���O�ŁA�c�O�Ȉ�ۂƂȂ��Ă��܂��܂����B(2012.08.04)
|
|
|

|
�{�[�t�H�[���@�L���ȏn���m�̂��̂łȂ��Ă����������{�[�t�H�[���ł����A����͓��ɃN���X�`�����E�W���j�G���̏n���ł�����ˁ[�B100�O������1800�~�B�Ђ��`�A�����B���������Ă݂�ƁA�m���ɂ��ꂼ�{�[�t�H�[���Ƃ����i�b�c�̍���ɉ����āA�p�C�i�b�v���̂悤�ȍ��肪������ꂽ�B���ɂ����{�[�t�H�[���B�N���X�`�����E�W���j�G���̏n���`�[�Y�͍���A�u���[�E�h�E���[�����炵���������A�ƂĂ��C�ɂȂ��Ă��܂����B(2013.3.30)
|
|
|

|
�{�[�t�H�[��(�O�U�r�G�E�_���B�b�g�n��)
�`�F�X�R�Ŏ�舵���A���łɃJ�b�g���ꂽ�^��p�b�N�̂��̂����Ȃ��A�O�����������Ȃ����̂����Ȃ������Ƃ̂��ƁB�p�b�N�̐Ղ��`�[�Y�ɕt���Ă����̂ŏ���L��S�z���܂������A�S����肠��܂���ł����B���ʂɔ��������{�[�t�H�[���ł��A�悩�����B���̃O�U�r�G�E�_���B�b�g���Ƃ����n���m�ɂ��ăC���t�H���[�V�������Ȃ��āA�ǂ�Ȑl���Ȃ̂�������܂���B�O�U�r�G�ƌ����ƃg�D�[���[�Y�̃`�[�Y���X�uXavier
�O�U�r�G�v���v���o�����A�ǂ����W�Ȃ��݂����B��ށB(2013.11.10)
|
|
|
|

|
���i�~�E�G�N�X�g���@��160����830�~
�������@���M����^�C�v�@���Ɍ��O�c�s�E�����q��`�[�Y�H�[
�����q��`�[�Y�H�[�̃`�[�Y�̏Љ�ł́A�u���i�~(3�����n��)���X��6�����ȏ�Q�����č�����v�Ƃ��邪�A�{�����낤���H���m�ɑ������킯�ł͂Ȃ����A���i�~�̍��������悻7�����قǂȂ̂ɑ��āA�n���������Ƃ������i�~�E�G�N�X�g���́A����ȏ゠��10�������炢���肻�����B�n�������ăT�C�Y���A�b�v����Ƃ͍l�����Ȃ��B�����炭�Ⴄ�^�ō��ꂽ���̂ł��낤�B�Ƃ���ƁA���i�~�Ɠ����J�[�h���Ⴄ�^�ł���A�X�ɒ����n���������Ƃ����������������̂ł͂Ȃ����H���͑S�̓I�ɕ��������ƂȂ����B(2013.10.6)
|
|
|
|

|
�����^�[�Y�B�I(DOP)�@Montasio
100g��810�~
�������A���M����^�C�v�@M.G.40%�@�t���E���E���F�l�c�B�A�E�W�����A�B����F�l�g�B
13���I�̔��Ƀ��b�W�I�C���@�̏C���m�����ɂ���č���Ă������̂��A�����^�[�Y�B�I�B�₪�ĕW��2753���̃����^�[�Y�B�I�R�ɏZ�ސl�����ɓ`���A1773�N�ɏB�s�E�[�f�B�l�s�����i�����߂Ĉ��̐��Y�ʂ��m�ۂł���悤�ɂȂ��������ł��B���āA���̃`�[�Y�̓t�F���~�G�ōw����12�����n�����̂ł��B�n�����ăA�~�m�_�̌������o�Ă��܂��B�ł�����͎|�ݐ����̃A�~�m�_�Ƃ͈Ⴄ�ȁB�ۂ��ăv�`�v�`�͂�����u��������n�v�B�n�`�~�c�̂悤�ȊÂ݂���B�����������������C�ɂȂ�B(2008.2.16)
|
|
|

|
�㊯�R�uEATALY�v�ōw���̃`�[�Y���`�[�Y��ɂāB100����980�~�B�������^�[�Y�B�I��H�ׂ��̂���2��ڂ������́H�Ƃ��������B���������`�A����܂艏���Ȃ������Ȃ��B�ʐ^�ɂ͎ʂ��Ă��Ȃ��̂����ǁA�\��͔����ۂ��Y��B���ʂɂ͢MONTASIO�v�ƃy�R���[�m�E���}�[�m�̂悤�Ɏ߂ɕ����������Ă��܂��B�O��H�ׂ����̂̓X�^�W�I�i�[�g12�����n���������̂ŁA�A�~�m�_����������n���������A����̂͂܂����`�b�Ƃ��Ă��ď_�炩���B���������߂ŗD�����������B���̃`�[�Y�̓X�^�W�I�i�[�g��肱�ꂭ�炢�̂ق������������C������B(2008.11.9)
|
|
|
|

|
�����e�E���F���l�[�[(DOP)�@Monte
Veronese
�������A�����M����^�C�v�@M.G.44%�@�C�^���A�E���F�l�g�B
�搶�̃C�^���A�E���F�l�g�B�̂��y�Y�`�[�Y�B���F���[�i�̃��b�V�[��R���Y�n�B�A�W�A�[�S�ɂ�������ȃ`�[�Y�ƌĂ�邯��ǁA�A�W�A�[�S�ƈ���ĂȂ��Ȃ����{�ɓ����Ă��Ȃ����������́B���n�ł͏n���̎Ⴂ�v���b�T�[�g�Ən���^�C�v�̃_�b���[���H�Ƃ���A�_�b���[���H�̒��ł����b�c�@�[�m�ƌĂ��6�������炢�̂��̂ƁA����ނ������Ă����Ƃ����܂��B�����6�����̃_�b���[���H�E���b�c�@�[�m�B�ꏏ�ɐH�ׂ����̂�4�N�Ƃ��̒����n���������������Ⴂ���������B�܂��������c���Ă��ă\�t�g�Ȃ̂ɁA�������肵�������Ɖ��������悭�����ĂĔ����B(2008.9.6)
|
|
|

|
�R�̃`�[�Y �@�u���E�����x���@
100����600�~
�������A���M����^�C�v�@���{�E�k�C���W�ÌS���W�Ò��E�O�F�q��
�}�C�y�[�X�_��ŗL���ȎO�F���o�c�����O�F�q��̃`�[�Y�H�[�ō����10�L��������傫�Ȉ���^�C�v�̃`�[�Y�ł��B���q�P�O�O%�i������^���Ȃ��j�ň�Ă�Ƃ����̂́A�ƂĂ���ςɂ��Ƃł��B�������G���ƈႢ�A�h�{���_�̖q����H�ׂ�������ł����`�[�Y�́A�����L���Ȗ��̔Z���`�[�Y�ɂȂ�ł��傤�B����̃u���E�����x����6�����n���B���Ȃ݂ɃO���[�����x����16�����ȏ�̏n���ł��B�đ����R�H�ׂĂ���̂ł��傤�B���F���Z���B�{�[�t�H�[����A�{���_���X�̃A���p�[�W�����v�킹��A�ƂĂ����̔Z�����������`�[�Y�ł��B���������`�[�Y�����{�ō���Ă���̂͂ƂĂ�������(2009.6.6)
|
|
|

|
���E�����^�j���[�h La
Montagnado
100����880�~�@
�������A���E�ۓ��@�C�^���A�E���@�b���E�_�I�X�^�B
�㊯�R�uEATALY�v�ōw���̃`�[�Y�B�O��̐F�����Ȃ�Z�������ۂ���ɁA�����ӂ����悤�ɔ������R�̃J�r�̂悤�Ȃ��̂����Ă���B�f�ʂ���̓N���[���F���物�F�̒��Ԃ�����̔Z���ڂ̐F�ŁA��������Ƃ������J�j�J���z�[�����ڗ��B�����ڂ͐����ꂽ�G���K���g�ȃ`�[�Y�̐����Ȉ�ۂł��B�����k���ƁA�\�z�ɔ����ă}�b�V�����[���̂悤�ȂȂ�Ƃ��������肪����B�H�ׂĂ݂�ƁA���C���������肵�Ă��邪�~���N�̊Â݂Ƌ���������̂ŁA���傤�ǂ��������B��������Ƃ������킢�Ŕ��������B��������DOP�łȂ��̂ɔ��������`�[�Y�ɏo���ƁA���Ɋ������B(2008.11.9)
|
|
|

|
���[�T�� �@�@
100����500�~
�������A�Z�~�n�[�h�^�C�v�@���{�E�k�C��������E���c�t�@�[��
���[�T���Ƃ͖q���̖��O�B���a�R�S�����E�����P�O�����E�d����X�����������傫�߂̃Z�~�n�[�h�^�C�v�̃`�[�Y�B�n�����Ԃ�8�����ƒ����B�O���[�̊O��B���̓A�C�{���[�Ō����|�c�|�c�B�H�ׂĂ݂�Ɖ������������̓��{�̃`�[�Y�ɔ�ׂ�Ƃ�����Ƃ��Ă���B���͂��ꂭ�炢�������������ق��������B����8�������n�����ꂽ���ɂ́A�������肵�Ă��āA�R�N��|��������Ȃ���ہB(2006.9.2)
|
|
|
|

|
���E�t�F�h�D�[�@Le
Fedou�@
�r�����AM.G.50%�@�t�����X�E���G���O�n���@
���b�N�t�H�[���Ɠ����ꏊ�ő���ꂽ���������E�ۗr���̃g���ł��B�O��͔��������ӂ����悤�ȏ�ԁB�s���l�[�R���ō����r�̃I�b�\�E�C���e�B�D���̎��A���҂���������̂����A��`�`�����B�҂�҂�Ɛ���h���悤�Ȏh��������A���Ȃ�h���B�v�`�v�`�Ɗۂ��A�~�m�_�̌����A���̚g���ł́u��������̗��n�v�̐H������B(2008.3.1)
|
|
|
|

|
�����E�w�E�~���^���@
�������A���{�E�k�C���\��(�����w�ɐV���_��)
�����w�ɂō���钼�a80cm�A�d����35kg�̑�^�̃n�[�h�^�C�v�̃`�[�Y�ł��B�����ڂ̃A�~�m�_�̌����ƐH�ׂ������ł́A����̂�1�N���9�`10�������炢�̏n���ł��傤���B���������w�ɂ̃V���g�R�̕����đ���H�ׂ����Ă��邩�畗�������������L��������܂����A����͂���ɔ�ׂ�Ƃ��������������肵�Ă���Ƃ������A�����H�ׂĂ��O���̂��Ȃ�����g�p�̃`�[�Y���ȂƂ�����ۂł��B���Ă鎞�ɂ͂��ꂭ�炢�����傤�ǂ����B(2014.2.2)
|
|
|