
山岳救助活動における注意義務
Duty of Care in Rescue Work about Mountain Accident
溝手 康史
| 2009年に積丹岳で起きた山岳遭難事故に関する裁判の判決(一審、二審)の検討を通して、山岳遭難に対する警察の救助活動の法的性格、救助活動に従事する警察官が負う注意義務の内容、警察が行う救助活動と民間人が行う救助活動の法的な違いなどを明らかにする。 さらに、この事故に対する社会の反応と裁判の過程を通して、山岳遭難や山岳救助をめぐる日本の法文化のあり方を検討する。具体的には、山岳遭難に対する「自己責任」論の問題性、日本で「責任」という言葉があいまいに使用される傾向があること、危険の引受法理などの責任を限定する考え方が安易に使用される傾向があること、山岳救助体制のあり方などについて検討する。 キーワード 注意義務(duty of care)、山岳事故(mountain accident)、救助活動(rescue work)、 責任(liability)、法の支配(rule of law) 溝手康史(広島県)Yasufumi Mizote 弁護士、広島山岳会、日本山岳文化学会遭難分科会 Lawyer, Hiroshima Alpain Club |
| はじめに 2009年に北海道の積丹岳(標高1255メートル)で遭難したスノーボーダーが、救助活動中に死亡する事故が起きた。この事故について、救助活動に従事した警察官に過失があったとして、損害賠償請求訴訟が起こされた。山岳救助活動従事者の注意義務が争点になる裁判としては、日本で初めてである。 2012年11月19日に札幌地方裁判所は、警察官の過失を認定し、警察(北海道)に対し1200万円の損害賠償を命じた1)。これに対する控訴審も、警察官の過失を認め、北海道に対し1800万円の支払を命じる判決を下した2)。 この事故について、危険な登山をした遭難者に対する「自己責任」の非難や、判決が山岳遭難の救助活動を萎縮させるなどの批判がなされた。 街中での救急事故や急病、海難事故、災害などでは、事故や疾患に対する「自己責任」の非難は少ない。事故や疾患の原因に関係なく、無償で救急業務を行うことが国や自治体の責務とされ、それに従事する公務員は職務上の注意義務を負う。しかし、山岳遭難については、従来、その救助活動が国や自治体の責務なのかどうか、山岳救助活動従事者の注意義務の内容があいまいだった。 本稿では、積丹岳事故の判決の検討を通して、警察の山岳救助活動の法的性格、救助活動に従事する警察官の注意義務、公的な山岳救助体制のあり方、公的な救助活動とボランティアでの救助活動の違い、山岳遭難事故における自己責任の意味などについて検討する。 積丹岳事故の概要 2009年1月31日に、スノーボーダーが積丹岳に登り、山頂付近で悪天候のために下山ルートを見失い、ビバークした。翌日、警察の救助隊が遭難者を発見したが、救助活動中に警察官が雪庇を踏み抜いて、警察官と遭難者が滑落した。 その後、警察官は、遭難者をストレッチャーに固定して斜面から引き上げ作業を行ったが、その途中で他の警察官と交替するために、ストレッチャーをハイマツに結びつけてその場を離れた。その間にストレッチャーとハイマツの結束が抜け落ちてストレッチャーが落下し、遭難者が死亡した。 この事故について、遭難者の遺族が警察(北海道)を相手に損害賠償請求訴訟を起こした。国家賠償法の規定により、公務員に過失がある場合には、公務員個人は原則として損害賠償責任を負わず、代わりに国や自治体が損害賠償責任を負う。警察の救助隊員は北海道の職員であるため、裁判の被告は北海道である。 1審判決(札幌地裁平成24年11月19日判決)の内容 裁判所は、遭難者の救助を任務とする警察の山岳救助隊に、一般的な救助義務はないが、山岳救助隊員として職務を行う警察官が遭難者を発見した場合に適切に救助する職務上の義務があるとした。そして、警察官は進行方向について細心の注意を払う必要があり、警察官が雪庇を踏み抜き、遭難者を滑落させた点に過失があるとした。裁判所は、事故に関する遭難者の過失を8割とし、過失相殺して北海道に1200万円の損害賠償を命じた。 裁判所は、その後の遭難者の引き上げ作業中に、遭難者を乗せたストレッチャーが落下した点の過失の有無について判断していない。民事訴訟は損害賠償請求権の有無を判断する手続であり、損害賠償請求権を根拠づける過失をひとつ認定すれば、それ以外の過失について判断する必要がない。複数の過失が問題になる場合に、過失をひとつ認定しても、複数の過失を認定しても、損害賠償責任の発生という結論は同じなので、無駄な作業をしない。 これは、民事裁判が真相の究明を直接の目的とせず(刑事裁判も同じである)、権利義務関係の存否を判断して紛争を解決する技術的な手続であることに基づく。そのため、裁判所は、ストレッチャーの落下が警察官の過失になるかどうかについて判断しなかった。 控訴審判決(札幌高裁平成27年3月26日判決)の内容 控訴審で、警察は、警察の山岳遭難救助活動の性格に関して、救助活動は法的な権限に基づく活動ではなく、民間救助隊の活動と同じ性格のものであり、救助活動がうまくいかなくても責任が生じないと主張したが、裁判所は、山岳遭難救助活動は、警察法2条1項の「個人の生命、身体及び財産の保護」に含まれ、警察の責務であるとした。また、山岳遭難救助活動は、警察官職務執行法3条1項2号の「適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者」に含まれ、二次遭難の恐れ等により救助が不可能ないし極めて困難だったとは認められないとし、警察官に遭難者を救助すべき職務上の注意義務(救助義務)があったとした。そのうえで、裁判所は、警察官がストレッチャーとハイマツを結束する際に、ストレッチャーがハイマツから抜け落ちないようにする注意義務があったとして、警察官の過失を認定した。 一審判決は、警察官が雪庇を踏み抜いて遭難者が落下した点に過失を認定したが、控訴審判決はその点について判断をしていない。この点も、裁判では、どれかひとつの過失を認定すれば足りるという民事訴訟の原則によるものである。 裁判所は、遭難者の責任割合を7割に変更し、過失相殺をして北海道に1800万円の損害賠償を命じた。 判決の意義 (1)警察の山岳救助活動の法的性格 山岳救助活動が警察の責務かどうかに関して、一審判決は、警察の救助隊規定は努力規定に過ぎず、警察の救助隊に山岳遭難者の一般的な救助義務はないとした。 控訴審で、控訴人(北海道)は、警察の山岳救助活動は、民間協力者が不足したことから警察が協力を求められて実施していたもので、警察の山岳救助活動は民間人の活動と同じ「任意活動」、「事務管理」であると主張したが、裁判所は、警察の山岳救助活動は警察の責務であると判断した。 従来、警察が行う山岳救助活動は、その法的性格があいまいだった。警察の主張は、警察が行う山岳救助活動は、法的義務がなく、民間人が行うボランティア活動としての救助活動と同じだというものである。ボランティア活動であっても、事務管理に基づく注意義務があるが(民法687条)、それは重いものではない。警察が、積丹岳の事故に関する責任を否定する根拠として、民間人の救助活動との同質性、「任意活動」、「事務管理」を主張したことは、山岳救助活動に対する警察の認識を率直に述べたものだろう。 警察官がボランティア的に行う行為であっても、それが職務行為である限り、給与や公務災害の対象となり、職務上の注意義務が生じる。一審判決は、警察の救助隊規定は努力規定に過ぎないとしたが、救助活動が職務であることから、職務上の注意義務を認定した。これに対し、控訴審判決は、警察の山岳救助活動が警察の責務であるとし、山岳救助隊員の注意義務を認定した。 現在、山岳以外での救助活動は消防機関が担い、海難救助は海上保安庁が担っている。しかし、山岳救助については、従来、警察が担いながらも、ボランティア的な認識と実態があったようである。それが、山岳救助体制における自治体間の格差をもたらしている。 控訴審判決は、山岳救助活動が警察の責務だと述べ、国や自治体が正面から公的な山岳救助体制を構築すべきことを問題提起している。 (2)警察官が負う注意義務の内容 積丹岳事故の一審判決は、進路を誤って雪庇を踏み抜いた点に注意義務違反を認定し、控訴審判決は、警察官がストレッチャーから離れた間にストレッチャーの結束が抜け落ちてストレッチャーが落下した点に注意義務違反を認定した。ミスの程度としては、後者の方が大きいだろう。 法的な注意義務の認定は、論理的に導き出されるものというよりも、ある種の法的な価値判断である。この事故が、50年前に起きたとすれば、警察官にこのような注意義務を課す判決は出ない。富山県警察山岳警備隊が発足したのが1965年、長野県警山岳遭難救助隊が発足したのが1966年であり、それ以前の時期に、山岳救助活動における警察官の注意義務を想像するのは無理である。 警察の救助隊に職務上の注意義務のあることは明らかであるが、その具体的な内容をどのように考えるかは、山岳救助に対する社会のあり方に左右される。登山に対する否定的な文化のもとでは、救助隊の注意義務が軽視されやすい。国民の安全性に対する期待と要求が年々高まっており、公的山岳救助活動に対する国民の期待も高い。裁判所の法解釈は、このような時代と社会の変化や国民の期待に応じて変わる。 (3)過失相殺 一審判決は、遭難者の責任割合を8割として過失相殺をし、控訴審判決は、遭難者の責任割合を7割に変更した。一審判決でも控訴審判決でも、遭難者の責任割合認定の前提となった事情はほとんど同じである。被害者側の責任割合の認定は、裁判所によるある種の法的な価値判断である。山岳遭難者に対する非難の強い社会では、10割の過失相殺(損害賠償責任の否定)もありうる。控訴審判決が認定した7割という被害者側の責任割合は、決して軽いものではない(交通事故で、7対3の過失割合を想起すればわかりやすい)。 (4)判決の射程範囲 この判決は、山岳救助活動に従事する警察官に一定の注意義務を課したものであり、山岳救助活動に従事しない一般の警察官には当てはまらない。また、民間の救助組織や山仲間の救助活動にこの判決が当てはまらないことも、当然のことである。 民間の救助組織や山仲間の救助活動の場合には、事務管理に基づく注意義務(民法687条)が生じるが、これは、警察官などの公務員が負う職務上の注意義務よりも軽い。現実には、山岳救助活動に関して、事務管理に基づく注意義務違反が問題となる場面はほとんどないだろう。また、後述の緊急事務管理の規定により、損害賠償責任が生じることはほとんどないだろう。警察官が、勤務時間外にたまたま遭難救助を手伝った場合には、民間人のボランティア活動と同じ注意義務を負う(給与の対象にもならない)。 ボランティアで行う救助活動について、救助活動従事者の責任を厳しく問うことに対して世論が違和感を感じる点は、日本も欧米も同じである。アメリカでは、後述のよきサマリア人法により、救助活動従事者の責任が軽減され、日本でも、緊急事態では重大な過失がある場合にのみ損害賠償責任が生じる(緊急事務管理、民法698条)。 このような緊急時の注意義務の軽減は、ボランティア活動についてであって、警察官のような職務行為については当てはまらない。その代わり、警察官個人は、原則として損害賠償責任を負わない扱いがなされている(国家賠償法)。 山岳救助活動をめぐる法文化 積丹岳の事故に関する裁判の経過や事故に対する世論と登山者の反応に、以下のような日本の法文化の傾向が表れている。 (1)「自己責任」の濫用 山岳事故が起きる度に、「自己責任である」という非難がなされる。積丹岳事故について、「遭難は自己責任であり、警察の責任を問うべきではない」という世論があった。 自己責任は、自分で決定したことについて自分で責任を負うというものであり、これは、当たり前のことである。一般に、当たり前のことは、あえて言う必要がないため、欧米では、自己責任という言葉が使用されることが少ない。しかし、日本では自己責任という言葉が多用され、事故や事件の関係者を非難する用語として使用されることが多い。 責任という言葉は、本来、他人に責任を問えるかどうかを問題にする場面で意味を持ち、「自己責任=他人に責任を問えない」場合には、「責任が生じない」と表現すれば足りるのであって、自己責任という言葉を使用する必要はない。 他方で、自分で決定していないことについては、自己責任が成り立たないが、日本では、自分で決定したかどうかに関係なく、自己責任という言葉が使用されることが多い。たとえば、競争の落伍者に対する自己責任の使用法がある。 (2)山岳遭難に対する非難 自動車の自損事故では、事故者が非難されることは少ない。海水浴中に溺れても、非難はされないだろう。しかし、山岳遭難者は、世論から非難されることが多い。 山岳遭難を非難するのは、「普通の者がしないような危険な行為を行う」からだろう。捜索、救助活動に税金がかかる点は、自動車事故や海難救助でも同じである(山岳遭難事故件数よりも、自動車事故件数の方がはるかに多い)。山岳遭難事故がもたらす「社会の迷惑」は、通常、その中味があいまいである。自動車の自損事故で道路が通行止めになれば、「社会の迷惑」の程度は山岳遭難よりもはるかに大きい。 さらに、登山が、自動車の運行などに較べて経済的な効用が少ないという点、登山が社会的少数者の行動であるという点、登山に「遊び」のイメージがある点などが、山岳遭難に対する非難をもたらすように思われる。そこには、「皆が、一生懸命に残業代未払で休暇をとれずに働いているのに、社会的生産に寄与することなく道楽をするのは許せない」といった感覚があるのではなかろうか。日本では、文化としての「遊び」が受け入れられにくい。 「普通の者がしないこと」をすることに対する反感や非難は、冒険的行動に対する否定的な文化をもたらす。新しいことに挑戦することが社会の発展をもたらすが、そこには、失敗というリスクがある。誰もしないことをすることに対する否定的な文化は、失敗を恐れる文化、ミスに対する厳しい非難の文化をもたらす。登山行為には、未知の自然との関わりを通して、人間の創造的精神や冒険的精神を養うという性格がある。 (3)責任回避 日本では、責任を負うことを恐れる人が多い。「自己責任」という言葉を非難のために使用することは、責任を負うことを恐れることと関係がある。 「責任」という日本語は非常に多義的である。そのため、「責任」という言葉が恣意的に使用されやすい。日本では、「責任=損害賠償責任」というイメージを持つ人が多く、それが責任を負うことを嫌う傾向をもたらす。しかし、損害賠償責任は、責任が現実化した場合に初めて問題になるのであって、現実化しない責任(日本語には、適切な言葉がない)という意味では、ほとんどの者が何らかの責任を負っている。 たとえば、「登山パーティーのリーダーはメンバーの安全を守る責任がある」と言う時、リーダーが損害賠償責任を負うことを述べているわけではない。「警察官に山岳遭難救助の責任がある」という時も同様である。警察官はさまざまな責任を負っているが、警察官が注意義務違反を犯さない限り、警察は損害賠償責任を負わない(警察官個人は、もともと国賠法により原則として損害賠償責任を負わない)。 人間は、誕生した瞬間から、社会の一員として社会のルールとしての法律の拘束を受け、さまざまな責任を負う。日本では、小さな子供が負う責任は、親が代位して責任を負い、アメリカでは5歳の子供でも損害賠償責任を負う3)。日米で法文化が異なるものの、小さな子供でも社会のルールに従うべきことは共通している。 ボランティア活動であっても、事務管理に基づく注意義務(民法687条)が生じ、責任がある。しかし、日本では、「ボランティア活動でも責任がある」と言うと、拒否感を示す人が多い。 公務員の場合には、職務上の注意義務と責任がある。民間企業の従業員であっても、職務上の注意義務と責任がある。登山者も、登山道で他人にぶつかって怪我を負わせてはならないなどの注意義務と責任を負っている。 このように注意義務や責任を負うことは当たり前のことであり、当たり前のことは、あえて言う必要がない。日常生活のうえで人間の生存に酸素が必要なことをあえて言う必要がないのと同じである。しかし、その点の自覚は必要である。 日本で、注意義務や責任を負うことに対し拒絶反応を示す人が多いのは、責任という言葉があいまいに使用され、非難や損害賠償のイメージと結びつきやすいからだろう。責任から目を背けることによって、責任を負わないと錯覚し、安心を得ようとする傾向がある。 人間は、地球上に1人だけが生存している場合を除き、複数の人間が存在すれば、そこに社会を形成する。社会的存在としての人間は、社会を平和に円滑に維持するために、社会のルールを定める必要がある。ルールは責任をもたらす。社会のルールのひとつに法律がある。社会の一員としての個人は、社会や他人に対し責任を負っている。 責任を負うことを回避するのではなく、責任を負っていることを自覚し、注意義務に違反して責任が現実化しないように行動することが必要である。どんなに大きな責任を負っても、注意義務違反をしなければ、何も問題はない。責任ある行動は、責任を自覚することから始まる。 一般に、公的な山岳救助隊員、山岳ガイド、医師、パイロット、自動車の運転者などが行う行為は危険を伴うため、課される注意義務が重い。これらの行為中に事故が起き、そこに行為者のミスがあれば、損害賠償責任が生じることが多い。損害賠償責任は、被害者の金銭的な補償や公平の観点から広く認められる傾向があり、工作物責任のような無過失責任(民法717条)や、自動車の運転のように免責事由が厳しく制限される場合がある(自動車損害賠償補償法)。これらについては、「悪いことをしたから責任を問われる」のではなく、損害賠償責任の範囲は法政策と裁判所の法的な価値判断で決まる。したがって、責任を負うことを危惧するのではなく、その現実化を回避する努力や工夫が重要である。同時に、損害賠償責任は、必ずしも「非難」と関係のないことを理解する必要がある。 (4)法の支配 積丹岳の事故などの山岳遭難に法律を持ち込むことを嫌う人が少なくない。登山は、法律から遮断された自由な領域だと考え、法律の介入を嫌う人がいる。しかし、前記の通り、法律は社会のルールとして国民自らが設けたものであり、それが登山にも適用されることは当然である。社会(特に、政治権力)が法によって規律されることを、法の支配(Rule of Law)という。もし、このような社会のルールがなければ、政治的、社会的強者が社会を支配しやすい。 関係者がすべて聖人君子であれば紛争は生じないが、人間はそれほど賢明ではなく、しばしば感情や経済的利益から互いに争う4)。「人間は感情や利害から争いやすい」という人間に関する歴史認識が法の根底にある。 法律の介入が登山の自由を損なうと考える人がいるが、もともと登山行為自体が憲法によって保障された自由に基づいている。法がなければ、登山は簡単に恣意的に制限されかねない(たとえば、戦争時の登山者の非国民扱い、社会的生産を損なう休暇取得の制限、江戸時代の移動の自由の制限など)。現在、自由に登山ができるのは、現在の憲法のもとで国民がある程度の自由を享受できることが「当たり前」になっていることの結果である。 (5)危険性の承認 積丹岳の事故の遭難者が、自ら危険なことを行ったという理由から、救助者に対して損害賠償請求をすることを非難する人が少なくない。「危険を認識しながら、あえて危険な場面に臨んだ者は、危険を作出した者に賠償を求めることはできない」という考え方は、危険の引受(Assumption of Risk)と呼ばれる。アメリカでは、一部の州で、厳格な要件を課したうえで、限定的に危険の引受法理が採用されているが、日本では危険の引受法理は採用されていない。 イメージ的には、積丹岳の事故と危険の引受法理が関係ありそうに見えるが、危険の引受法理は、「危険を認識していた者」と「危険を作出した者」の関係に関するものである。積丹岳の事故については、遭難者は、登山の危険は承認しているが、救助の失敗は承認していないので、危険の引受法理は当てはまらない。 (6)よきサマリア人法 積丹岳事故に関して、よきサマリア人法を持ち出す人がいるので、これについて付言する。 よきサマリア人法(Good Samaritan Act)は、緊急状態にある人に対し、義務がないにもかかわらず自発的に救命行為をする場合に、故意や重過失がない限り民事責任を免責する法律である。アメリカではすべての州によきサマリア人法があるが、日本にはない。日本では、前記の緊急事務管理(民法698条)で対応することになる。 よきサマリア人法は、ボランティア行為(無償という意味ではなく、義務を伴わない自発的行為という意味)に適用され、警察官のように職務上の注意義務がある場合は問題にならない。そもそも、公務員は国家賠償法により原則として民事責任を免責されている。また、よきサマリア人法は、警察のような組織の免責には当てはまらない。 よきサマリア人法が扱うのは民事責任である。アメリカなどでは、緊急状態にある人に対する民間人の刑事責任が問われることがないので、刑事免責は議論の対象になっていない。しかし、日本では、緊急状態にある人に対する救命行為時のミスについて、刑事責任を問われる可能性があるという問題がある。 (7)公的山岳救助体制の確立 現状では、山岳救助体制の自治体間の格差が大きい。街中での事故や海難事故などの救助活動が国や自治体の責務とされていることと対比すれば、山岳救助活動についても、国や自治体の責務として位置づけるべきである。 スポーツ基本法24条は、ハイキングその他の野外活動に関し、必要な施策の構築に努力することを国や自治体に義務づけている。「必要な施策」の中に、山岳救助活動も含まれる。 積丹岳事故控訴審判決は、裁判の性質上、山岳救助活動が警察の責務であること以上のことを述べていないが、公的な山岳救助活動は自治体警察だけの課題ではない。現在、消防、警察、民間組織など山岳救助活動が分立しており、効率や費用効果の点で無駄がある。 山岳救助活動は専門性を必要とし、警察や消防が日常的業務を行いながら片手間にできる仕事ではない。民間人の場合には、時間的、経済的にボランティア活動に限界があり、救助活動中の事故の公的な補償がないなどの問題がある。消防、警察の関係者と民間人(消防団員のように非常勤の公務員として扱うべきである)で構成される公的な山岳救助組織が必要だろう。 結論 積丹岳事故の一審、二審(控訴審)判決のいずれも、山岳遭難救助活動に従事する警察官に対し、救助に関する職務上の注意義務を認めた。二審判決は、警察の山岳救助活動が警察の責務であるとしている。 この事故の遭難者に対し、世論から「自己責任」の非難がなされたが、自己責任は、自分が選択したことについて責任を負うことを意味する。救助の失敗は遭難者が選択したことではないので、救助の失敗について、遭難者の自己責任は当てはまらない。また、警察の職務上のミスに関して、遭難者がその危険を引き受けたという考え方も当てはまらない。 日本語の「責任」という言葉は、多義的であいまいさを多く含んでいる。その結果、責任を負うことが多くの不安をもたらし、責任を負うことを恐れる人が多い。しかし、誰もが社会の中でさまざまな注意義務と責任を負って生きている。たとえ、注意義務を負ったとしても、事故が起きなければ何も問題はない。注意義務や責任を負うことを回避するのではなく、注意義務と責任を自覚したうえで、事故を回避することが大切である。 遭難事故の回避は、第一次的には登山者が行うべきことだが、不幸にして遭難が生じた場合には、公的な救助組織によって適切に救助できる体制を構築することが登山の発展のために必要である。 [注] 1)札幌地方裁判所平成24年11月19日判決、判例時報2172号77頁 2)札幌高等裁判所平成27年3月26日判決 3)「アメリカ不法行為法」、樋口範雄、弘文堂、23頁。日本では、「子供の行った行為は、親が責任を負う」という法文化とそれに対応した法律(民法714条)があるが、アメリカでは、子供は親から自立した存在として扱われる。最近は、日本でも、最高裁平成27年4月9日判決に見られるように、親の代位責任の範囲を限定する兆しが見られる。 4)ホッブズは、「リヴァイアサン」で人間の人間に対する戦争状態を指摘している(「世界の名著23 ホッブズ」、ホッブズ、中央公論社、156頁)。 [参考文献] 「レスキュー最前線」、長野県警察山岳救助隊、山と渓谷社、2011 「山靴を履いたお巡りさん」、岐阜県警察山岳救助隊、山と渓谷社、1992 「ザイルをかついだたお巡りさん」、長野県警察山岳救助隊、山と渓谷社、1995 「ピッケルを持ったお巡りさん」、富山県警察山岳救助隊、山と渓谷社、1985 「山岳救助隊日誌」、金邦夫、角川学芸出版、2007 「山岳警備隊 出動せよ!」、富山県警察山岳救助隊、東京新聞出版局、1996 「翼を持ったお巡りさん」、谷口凱夫編、山と渓谷社、2005 「アルプス交番勤務を命ず」、谷口凱夫、山と渓谷社、1998 「アルプス交番勤務からのメッセージ」 谷口凱編、山と渓谷社、2014 「山の軍曹 カールを駆ける」、木下寿男、山と渓谷社、2002 「遭難者を救助せよ」、細井勝、PHP研究所、2007 「スポーツ事故と自己責任による加害者の減責」、山田二郎、日本スポーツ法学会年報第2号、1995 「スポーツ事故と「危険引受の法理」」、及川伸、日本スポーツ法学会年報第2号、1995 「スポーツにおける違法性阻却」、日本スポーツ法学会年報第6号、1999 「野球観戦中の負傷事故と球場管理者の賠償責任ーアメリカ法における限定義務の法理をめぐって」、磯山海、日本スポーツ法学会年報第21号、2015 「新版・救急活動と法律問題・上巻」、丸山富夫、東京法令出版、2009 「医療と法を考える」、樋口範雄、有斐閣、2007 「続・医療と法を考える」、樋口範雄、有斐閣、2008 「アメリカ不法行為法」、樋口範雄、弘文堂、2009 「ボランティア社会の誕生」、中山淳雄、三重大学出版会、2007 「LEGAL LIABILITY in Recreation and Sports」,Brece B Hronek,Sagmore Publishing、2002 「登山の法律学」、溝手康史、東京新聞出版局、2007 「積丹岳での遭難における警察への損害賠償命令判決を考える」、溝手康史、岳人、東京新聞、2013年3月号、162頁 「山岳事故の法的責任」、溝手康史、ブイツーソリューション、2015 「世界の名著23 ホッブズ」、ホッブズ、中央公論社、1979 「自由論」、J・S・ミル、岩波文庫、1971 「ホモ・ルーデンス」、ホイジンガ、中公文庫、1973 「私事と自己決定」、山田卓生、日本評論社、1987 (日本山岳文化学会論集第13号、2016) |
![]() 「登山の法律学」、溝手康史、東京新聞出版局、2007年、定価1700円、電子書籍あり
「登山の法律学」、溝手康史、東京新聞出版局、2007年、定価1700円、電子書籍あり

![]() 「山岳事故の責任 登山の指針と紛争予防のために」、溝手康史、2015
「山岳事故の責任 登山の指針と紛争予防のために」、溝手康史、2015
発行所 ブイツーソリューション
発売元 星雲社
ページ数90頁
定価 1100円+税
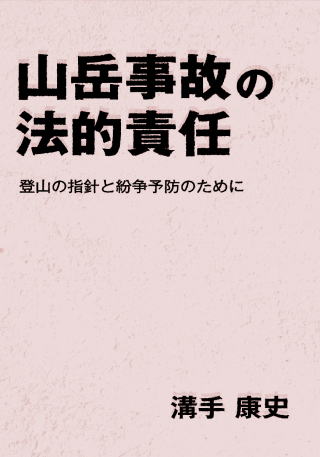
![]() 「真の自己実現をめざして 仕事や成果にとらわれない自己実現の道」、2014
「真の自己実現をめざして 仕事や成果にとらわれない自己実現の道」、2014
発行所 ブイツーソリューション
発売元 星雲社
ページ数226頁
定価 700円+税

![]() 「登山者ための法律入門 山の法的トラブルを回避する 加害者・被害者にならないために」、溝手康史、2018
「登山者ための法律入門 山の法的トラブルを回避する 加害者・被害者にならないために」、溝手康史、2018
山と渓谷社
230頁
972円
