�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| �@�@�@�@�u�o���H�v�̊T�O�Ɠo�R���[�g�̊Ǘ� �@�@�@�@�@�@�@�@Concept of �eTouhanro' and management of mountain route �a��N�j Yasufumi Mizote �L�[���[�h�F�o�R���A�o�R���[�g�A�o���H�A�ӔC�A�R�x���� Key word �Fmountain trail�Aclimbing route�A�souhanro�Aliability�Amountain accident �@�o�R���[�g�ɂ��āA�����ēo�邱�Ƃ��ł��郋�[�g�Ƃ悶�o�郋�[�g����ʂ��A�O�҂�o�R���A��҂�o���H�ƌĂԕK�v������B�����o�R���ƒ������Ȃǂ��ݒu���ꂽ���[�g�ł͗v�������\�͂��قȂ�A�������ʂ��邽�߂ɓo���H�̊T�O���K�v�ł���B�o�R���Ɠo���H�ł́A�����Ɋւ���l�������قȂ�B�o�R���ł́A�����q�́A�����s�ׂ̕⏕�I�Ȑݔ��ł��邪�A�o���H�ł͍����q�͓o�邽�߂̎�i�ł���B�o�R���[�g�̌`�Ԃ���ʂ���A�Ǘ��ӔC�͂���ɉ��������̂ɂȂ�A�ӔC�͈̔͂�����ł���B�o�R���[�g�̌`�Ԃ�O���[�h�́A���[�g�̗��O�ƃ��[�g��̍��A��q�Ȃǂ̐l�H���̗ʂƐݒu���@�ɂ���ĕς��B��������肷��̂̓��[�g�̊Ǘ��҂ł���A�Ǘ��҂����m�ł��邱�Ƃ��K�v�ł���B �a��N�j�i�L�����jYasufumi Mizote�@ �ٌ�m�A�L���R�x��A���{�R�x�����w���ȉ� Lawyer, Hiroshima Alpain Club ���̏��݁@ �@���{�̓o�R���̂قƂ�ǂ́A�����ēo�邱�Ƃ��ł��邪�A�o�R���ɂ�����ɍ����q�Ȃǂ��ݒu����Ă��邱�Ƃ�����B�����q���g��Ȃ��Ă��o�邱�Ƃ��ł���ꍇ������A�������g��Ȃ���A�N���C�~���O�̋Z�p���K�v�ɂȂ�ꍇ������B�O�҂̏ꍇ�́A�����q�Ȃǂ͂����܂ŕ����s�ׂ̕⏕�I�ݔ��ł��邪�A��҂́A�����q�͓o�R�̎�i�Ƃ��Ă̐ݔ��ɂȂ��Ă���B�O�҂́A�u�����q�������Ă��M�p����ȁv���\�����A��҂́A�����q��M�p�ł��Ȃ���A�N���C�~���O���[�g�ɂȂ�B���x�̕ʎR�����A�����x�̒��㒼���A����c���H�A�k�x���{���R���A���C�R�A�ΒȊx�A�ˉB�̋a�̌˓n��A���`�R�̏c���H�Ȃǂ̍����q�́A��҂̗�ł���B �@�����s�ׂ͂����ς瑫�̋ؗ͂��g�����A�����q�Ȃǂ�o��s�ׂ́A���̋ؗ͂����łȂ��r�̋ؗ͂�o�����X���K�v�ɂȂ�B�o�R���Ƃ������t�Ɋ܂܂��u���v�́A�l�����p����ꍇ�ɂ́A�u�����v���Ƃ�z�肵�Ă���B�����q�Ȃǂ������ݒu���ꂽ���[�g�ɁA�����\�͂�O��Ƃ����o�R���Ƃ������t���g�p���邱�Ƃ́A�o�R�҂Ɂu�����ēo�邱�Ƃ��ł���v�Ƃ��������^���鋰�ꂪ����B�悶�o��\�͂��v������郋�[�g�ł́A�����\�����邱�Ƃ��K�v�ł���B �@�o�R���Ƃ������t�̕��Q�������Ƃ��T�^�I�Ɍ����̂́A���`�R�̏c���H�ł���B�����ɂ́A�����̒��������ݒu����Ă���A���N�̂悤�ɏd��Ȏ��̂��N���Ă���B���̏c���H�ł́A���������������邽�߁A�u�����g���ăo�����X�悭����o�~����\�́v���v�������B����́A�����\�͂Ƃ͈قȂ�\�͂ł���B���̂��߁A�c���o�����L�x���Ƃ��������ł́A���̏c���H�͊댯�ł���B�����ɋ߂����ɒ�����������̂ŁA��ɑ��đ������܂��g�����ƂȂ��r�͂ɗ���o�R�҂́A�����ɘr�͂��g���ʂ����Ă��܂����ꂪ����B�K�C�h�u�b�N���ɁA�u��o��̌o����K�v�Ƃ���㋉�̏c���H�v�ƋL�q����Ă��邪�A���𗘗p�������A�N���C�}�[�ł͂Ȃ��A���Ɋ��ꂽ�o�R�҂̂��߂̃��[�g�ł���B �@���`�R�̏c���H�Ŏ��̂��������邽�߁A����P�����ׂ����Ƃ����咣���Ȃ���Ă���P�j�B����P������A�N���C�~���O���[�g�ɂȂ邪�A���`�R�ł́A���N�A���𗘗p�����o�R���s���Ă���A���ꂪ�����̓o�R�����ɂȂ��Ă���B������A�ȒP�ɔp�~���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���́A���`�R�̃��[�g�ɂ���̂ł͂Ȃ��A���[�g�ɂӂ��킵���Ȃ��o�R�҂��o��_�ɂ���B���`�R�̏c���H�ɕs�����Ȏ҂��c������A���̂��N���₷���A���[�g�ɂӂ��킵���҂��c������A����قǓ�����[�g�ł͂Ȃ��B���`�R�̏c���H���A�����ēo��c���H�̉����ōl���邱�Ƃɖ�肪����B �@���̓_�́A���`�R�����̖��ł͂Ȃ��A���x�̕ʎR�����⑄��c���H�ł����l�̖�肪����B���x�̕ʎR�����⑄��c���H�́A���̒��������`�R�قǒ����Ȃ��Ƃ��������̂��Ƃł����āA���x�̈Ⴂ�ł���B���x�̕ʎR�����⑄��c���H�ł����̂��N���₷�����A�����q��P�����ׂ����Ƃ����咣�͂Ȃ���Ă��Ȃ��B�����x�̒��㒼���ł�������肪���邪�A���̃��[�g�́A��q�̐��𑝂₵�A���ł́A�����ς��q��o�~���郋�[�g�ɂȂ��Ă���B ���{�̎R�̂قƂ�ǂ́A�R���܂ŕ����ēo�邱�Ƃ��ł���B�������A�ꕔ�̎R�́A�����ēo�邱�Ƃ��ł����A�o�R���[�g�ɍ����q��ݒu���āA�N�ł��o�邱�Ƃ��ł���悤�ɐ�������Ă����B���{�ł́A�o�R���̐����́A�N�ł��o�邱�Ƃ��ł���悤�ɐ������邱�Ƃ��Ӗ������B�������A�N���C�~���O�̑ΏۂƂȂ�悤�Ȋ��ɍ����q��ݒu���Ă��A���Ƃ��Ɗ댯���̂���ꏊ�Ȃ̂ŁA���S�Ɉ��S�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���`�R�̏c���H�̂悤�ɁA�����̍��Ő������Ă��A���̂��N����B�����x�̎R�������̂悤�ɁA���Ő������邾���ł͊댯�Ȃ̂ŁA�����̒�q��ݒu����������炷�B�������A����ł��A��q����]������댯��������B�N���C�~���O�̑ΏۂƂȂ�悤�Ȋ��ɍ����q��ݒu�����ꍇ�A����͕������ł͂Ȃ��B������u�o���H�v�ƌĂсA���̐��i�A�����m�ɂ��A�Ǘ��̂�������l����K�v������B �@�o�R�҂̚n�D�Ɣ\�͂͑��l�ł���A����ɍ��킹�đ��l�Ȍ`�Ԃ̓o�R���[�g���K�v�ł���B�������A�o�R���[�g��N�ł��o�邱�Ƃ��ł���悤�ɐ������邱�Ƃ́A�o�R���[�g���\�Ȍ���o��₷�����邱�Ƃ��Ӗ����A���p�҂̑����o�R���́A�N�X�A���[�g���₳�����Ȃ�X���������炵�Ă���B���Ƃ��ƁA�����q���Ȃ��Ă��o�邱�Ƃ��ł�����ł��A�o��₷�����邽�߂ɍ����q���ݒu�����X��������B �@�����o�R���ł́A�����q�͕����s�ׂ̕⏕���ł���A�ǂ����Ă��K�v�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�o�R���̍����q���ŏ����̂��̂ɂ��邱�ƂŁA�o�R���̑��l�����ێ��ł���B�o���H�ł́A�����q���Ȃ���A�N���C�~���O���[�g�ɂȂ邪�A�����q�Ȃǂ̗ʂƐݒu���@�ɂ��A�o���H�̓�Փx���ς��B�����x�̒��㒼�������`�R�̏c���H���o���H�ł��邪�A�����x�́A�����̒�q�̐ݒu�ɂ��A�N�ł��o�邱�Ƃ��ł��郋�[�g�ɂȂ��Ă���B���`�R�́A��q�ł͂Ȃ��A�����������邽�߂ɁA�댯���̂��郋�[�g�ɂȂ��Ă���B�����x�̒��㒼���̒�q��P�����A�ŏ����̍��ɂ���A���[�g�̓�Փx�������B���`�R�ł́A�������ׂĒ�q�ɕς���A���[�g�̊댯�������邪�A�����ɒ�q�̓o�~�ɏI�n����܂�Ȃ����[�g�ɂȂ邾�낤�B���̂悤�ɁA�o���H�́A�����̎d���ɂ���āA���[�g�̐��i�ƃO���[�h���傫���ς��B �@�o���H���܂߂ēo�R���̊Ǘ��҂m�ɂ��A���̃��[�g�͂����ɂ���ׂ����Ƃ����u���O�v�Ɋ�Â��āA�o�R���[�g���Ǘ�����K�v������B �u�o�R���v�Ƃ������{��̓��� �@�o�R���Ƃ������{��́A�u�o�R�v�Ɓu���v���������������̂����A���{��́u�o�R�v�́A���Ƃ��ƁA�n�C�L���O����N���C�~���O�܂Ŋ܂ލL�͂ȈӖ������B�o�R�ɑ�������p��́Amountain climbing�A�܂��́Amountaineering�ł��邪�Aclimbing�ɂ́Ahiking��walking�ƈ���āA�悶�o��Ƃ����Ӗ�������Bclimbing���u�N���C�~���O�v�Ƃ������{��ɖA����́A��o���A�C�X�N���C�~���O���Ӗ����Aclimbing�Ɓu�N���C�~���O�v�͓����Ӗ��ł͂Ȃ��B���l�ɁAhiking�Ɓu�n�C�L���O�v���Ӗ����قȂ�B �@���̂悤�ȍL�͂ȈӖ������u�o�R�v�Ɓu���v�������������Ƃ���ɁA�o�R���Ƃ������{��̓���Ȑ��i������B�N���C�~���O���[�g�͓o�R���ɂ͊܂܂�Ȃ����Aclimbing�A���Ȃ킿�A�u�悶�o��v�s�ׂ��v������郋�[�g�́A�o�R���Ɋ܂܂��B�������A�o�R���́A�u���v�ł���ȏ�A�����s�ׂ�����ꏊ�̃C���[�W�������A���Ƃ��ƃN���C�~���O���[�g�ł���悤�Ȋ��ɍ����q��ݒu�����ꏊ���A�u�����ēo�邱�Ƃ��ł���v�Ƃ����C���[�W�������₷���B ���[���b�p�A���v�X�ł́A��R�������̂ŁAhiking�i�����s�ׁj��climbing�i�悶�o��s�ׁj����ʂ���̂́A���R�Ȃ��Ƃł���B�����ł́A�R�����߂����s�ׂ̂قƂ�ǂ�climbing�ł��邪�A���{�ł́A�قƂ�ǂ̎R�������ĎR���ɍs����̂ŁAhiking��walking�̑ΏۂɂȂ�B �@���[���b�p�A���v�X�ł́A�n�C�L���O���ȊO�ɁA�N���C�~���O���[�g�ł͂Ȃ��o���I�ȃ��[�g������A�h�C�c��ł́AKlettersteig�i�N���b�^�[�V���^�C�N�j�A�C�^���A��ł�Via Ferrata�i���B�A�E�t�F���[�^�j�ƌĂ�A�t�����X�ł́AVia Ferrata�̕����ʂ��₷���Ƃ����Q�j�B����́A���������ɒ�q��C���[���ݒu����A�o�R�҂̓n�[�l�X�����āA���C���[�ɃJ���r�i���|���Ȃ���o��X�^�C���̃��[�g�ł���A�N���C�~���O���[�g�Ƃ͕ʂ̌`�Ԃ̃��[�g�ł���B����́A�u�o���H�v�Ƙa��A�{�e�ł����o���H�Ɏ��Ă���B�������A���[���b�p�A���v�X�̓o���H�ł́A���C���[�ɃJ���r�i�������Ď��Ȋm�ۂ��Ȃ���o��X�^�C�����̗p����A���{�̓o���H�̍�����Œ͂�œo��X�^�C���Ƃ͈قȂ�B�܂��A���[���b�p�A���v�X�̓o���H�́A�������[�g�Ƃ͂܂������ʂ̃��[�g�ƍl�����Ă���R�j�B���{�̓o���H�́A���{���L�̌`�Ԃł���A�ΊO�I�ɂ́Atouhanro�ƕ\������ق��Ȃ��B �@���[���b�p�A���v�X��j���[�W�����h�ł́A�o�R���[�g�̌`�Ԃ���ʂ��A���ꂼ��̃��X�N��o�R�҂ɔF��������H�v���Ȃ���Ă���S�j�B���{�ł��A���{�̎R�x�n�`�ɉ����ēo�R���[�g�̌`�Ԃ���ʂ��A����ɉ��������X�N�̕\���ƊǗ����K�v�ł���B�{���A�N���C�~���O�̑ΏۂƂȂ����N�ł��o���悤�ɐl�H���Ő����������[�g�́A�������Ƃ͌`�Ԃ��قȂ�̂ŁA������A�o���H�ƌĂсA�������Ƌ�ʂ���K�v������B �@�]���A���{�ł́A�o�R���[�g���N���C�~���O���[�g�Ɠo�R���ɕ����A�N���C�~���O�̑ΏۂłȂ���A���ׂēo�R���ɕ��ނ���Ă����B�o�R��o�R���Ƃ������{��̓��e����I�ł��邽�߁A�u�o�R�͎��ȐӔC�ł���v�ƌ����A�V�����ł̊ό���n�C�L���O�����ׂĕ����̊Ǘ��ӔC�������Ȃ��悤�ȃC���[�W�������炵�₷���B�o�R���́A�������[�g�̃C���[�W������A�o�R���͒N�ł��o�邱�Ƃ��ł���Ƃ����C���[�W���A���`�R�̏c���H�ɑ����̏c���o�R���D�҂��䂫����B���`�R�̏c���H�♛�x�̕ʎR�����̍���͕������ł͂Ȃ��A�������A�u�o�R���v�A�u�c���H�v�ƌĂԂ��Ƃ͌����^����B �@�����̍��́A�o�R���[�g�ɍ����q���قƂ�ǂȂ��A���`�R�̏c���H�♛�x�̕ʎR�����̍���̂悤�ȃ��[�g�͓o�R�s�\�ƍl���邩�A�N���C�~���O�̑Ώۂ������B�������A���̌�A���̂悤�ȓo�R���[�g�ɑ����̍����q���ݒu����A�N�ł��o�邱�Ƃ��ł��郋�[�g�ɂȂ�A���̂悤�ȃ��[�g�̐������o�R�̑�O���̑傫�ȗ͂ɂȂ����B�������A����͎��̂̑����̑傫�ȗv���ɂ��Ȃ����B �@�ʏ�̏c���H�́A�̗͂�������ΒN�ł��������Ƃ��ł��邪�A���`�R�̏c���H�♛�x�̕ʎR�����Ȃǂ́A�̗͂������Ă����炩�ɕs�����Ȑl������B���`�R�̏c���H�ō��̓r���Řr�͂��s���A�������𗣂��Ēė�����P�[�X�����̗�ł���B�����̃��[�g�ł́A�N���C�~���O�̋Z�p�͕s�v�����A��Ɋ���Ă��邱�Ƃ�o�����X�悭�����q��o�~�ł���\�͂��K�v�ł���B���̓o���H�ł��A���l�ł���B�����s�ׂƂ悶�o��s�ׂ���ʂ��A����ɉ����ēo�R���[�g����ʂ��邱�Ƃ��A���[�g�ɂӂ��킵���o�R�҂�I�ʂ��邽�߂ɕK�v�ł���B �@�܂��A���`�R�̏c���H�♛�x�̕ʎR�����̍���ł́A�����q��M�p���Ȃ��Ƃ���A�N���C�}�[�łȂ���Γo�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̂悤�ȃ��[�g��o���ʓo�R�҂ɑ��A�u�����q�������Ă��M�p����ȁv�ƌ����̂̓i���Z���X�ł���B���̂悤�ȃ��[�g�ł́A�����q���M�p�ł��Ȃ��͂����Ă͂Ȃ炸�A���̂悤�ɍ����q���Ǘ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�o���H�ɂ����鍽���q�̊Ǘ��́A�����o�R���̍����q�̊Ǘ��Ƃ͈قȂ鈵�����K�v�ł���B �o�R���[�g�̌`�ԂƐ��� �@�o�R���[�g�Ɋւ��āA�N������������̂��A�ǂ̒��x�܂Ő������ׂ����A�����ɔ����Ǘ��ӔC�͈̔͂Ȃǂ̖�肪����B�����ɂ��ẮA�o�R���[�g�̌`�Ԃɂ���ĈقȂ�B �@�o�R���[�g�́A�����o�R���A�悶�o��o���H�A�N���C�~���O���[�g�Ȃǂɋ�ʂł���B �i�P�j�������߂̓o�R���́A�@�V�����A�A��������Ă���o�R���A�B��������Ă��Ȃ��o�R���A�C���R��Ԃɋ߂����ɋ�ʂł���B�o�R���̕��ނ́A�̗́A�Z�p�A�댯���ȂǂɊ�Â����ނ���ʓI�ł��邪�A��L�̕��ނ́A�����̊Ǘ��ӔC���ӎ��������ނł���B�@ �@�u�o�R������������Ă���v�Ƃ́A����I�ɓo�R��������ꂳ��A�W���A���A��q�Ȃǂ��_������Ă��邱�Ƃ��Ӗ����A����x��댯���Ƃ͊W���Ȃ��B�o�R��������ꂳ��A�W���A���A��q�Ȃǂ��_������Ă��Ă��A�̗́A�Z�p��K�v�Ƃ��A�]���̊댯���̂��郋�[�g������B�Ȃ��炩�Ȓ�R�́A������������Ă��Ȃ��Ă��A���Ƃ��ƍ���x���Ⴍ�A�]���A�����̊댯�����Ⴂ�B�W������������Ă��Ȃ���A���������₷�����A���Ƃ������������Ă��R�[���߂��R�ł́A����̃��X�N���Ⴂ�B �@���{�ł́A�o�R���[�g��ɊǗ�����Ă��邩�ǂ����s���̍��A��q�A���[�v�Ȃǂ����܂�ɂ������B��R�ɐݒu���ꂽ���[�v�̂قƂ�ǂ́A�Ǘ����Ȃ���Ă��Ȃ��B�_���E�Ǘ�����Ă��Ȃ��l�H����M�p���邱�Ƃ͊댯�ł���A��L�̇A�ƇB�̋�ʂ́A�u�o�R���[�g�ɂ���l�H����_���E�Ǘ�����K�v������v�Ƃ������_�Ɋ�Â����ނł���B�A�́A�o�R���̐ݔ��̊Ǘ��ӔC�����ɂȂ邪�A�B�͖��ɂȂ�Ȃ��B �@�V���� �@�����̊ό��q��n�C�J�[�����p��������ł���A�댯���̂قƂ�ǂȂ������ł���B�������k���̕����A�㍂�n�t�߂̕����A���R�̎����t�߂̕����A�k�����x�ؒ�t�߂̕����Ȃǂ����̗�ł���B�V�����ŁA�]���A���A���Ȃǂ̎��̂��N����A�Ǘ��ӔC�������₷���̂ŁA����ɑΉ����������A�Ǘ����K�v�ł���B �A�������ꂽ�o�R�� �@�P�N�ɂP����x�A�o�R��������ꂳ��A�W���A���A��q�Ȃǂ��_���A��������Ă���o�R���ł���B�o�R�҂́A�o�R���ɂ���W���A���A��q�A�K�i�A��Ȃǂ�M�����邱�Ƃ��ł���B�����ēo�邱�Ƃ��ł��郋�[�g�ł���A�����q�͂����܂ŕ⏕�I�Ȃ��̂ł���B�@�ƈقȂ�A���A���A�]���Ȃǂ̎R�x�ŗL�̊댯��������A����ɂ��Ă͊Ǘ��ӔC�͐����Ȃ��B �B��������Ă��Ȃ��o�R�� �@����I�ɓo�R��������ꂳ�ꂸ�A�W���A���A��q�Ȃǂ��_������Ă��Ȃ��o�R���ł���B�o�R���ɐݒu���ꂽ�W���A���A��q�Ȃǂ͓_������Ă��Ȃ��̂ŁA�M�p�ł��Ȃ��B�o�R�҂́A�����q��M�p�����ɓo��K�v������B�{���A�o�R���ɐM�p�ł��Ȃ������q��ݒu���ׂ��ł͂Ȃ����A�o�R���ɒN���ݒu�������킩��Ȃ������q����������A����炪����I�ɓ_������Ă��邩�ǂ������s���ȏꍇ������B�o�R���̊Ǘ��҂́A�o�R���̕W���A���A��q�Ȃǂɂ��āA�u�����s�ǁv�A�u�M�p�ł��Ȃ��v�|�̊댯���̕\�������A�o�R�҂́A���������ȐӔC�ŗ��p����K�v������B �C���R��Ԃɋ߂��� �o�R���ɐl�H�I�Ȑݔ����قƂ�ǂȂ����R��Ԃɋ߂����ł���B�����܂œo�R�҂��������Ƃ̂ł��郋�[�g�ł���A�悶�o��s�ׂ��v������郋�[�g�͎��R��Ԃɋ߂��o���H�ɕ��ނ����B���x�̒����Y��k��O�̑��t�߂̓�������ɊY������B�R�x�̊Ǘ��҂́A���R��Ԃɋ߂����Ƃ��ĊǗ�����K�v������B �i�Q�j�o���H�ɂ��Ă��A�������ꂽ�o���H�A��������Ă��Ȃ��o���H�A���R��Ԃɋ߂��o���H�ɕ����邱�Ƃ��ł���B �@���x�̕ʎR�����▭�`�R�̏c���H�́A�������ꂽ�o���H�ł���A�Ǘ��҂�����I�ɍ����q��_�����邱�Ƃ��K�v�ł���B�����́A�����q���_������Ă���O��œo�R�҂ɗ��p����Ă���B�����A�����̍����q���A����I�ɓ_������Ă��Ȃ��Ƃ���A���Ɋ댯�ł���B�����o�R���ł́A�����q�͕⏕�I�Ȃ��̂Ȃ̂ŁA�M�p�ł��Ȃ������q���g��Ȃ����Ƃ��\�����A�o���H�ł́A�����q���g�p���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�N���C�}�[�łȂ���Γo�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �@�o���H�́A�l�H���ɂ���ĊǗ�����A���̗ʂƐݒu�̎d���ɂ���āA��Փx���ς��B�����x�̒��㒼���́A�o���H�Ƃ��ẮA�N�ł��o�邱�Ƃ̂ł��郋�[�g�ɂȂ��Ă��邪�A����́A���̂悤�ɐ������Ă��邩��ł���B���̃��[�g�̒�q��P�����āA���ׂč��ɂ���A���x�̕ʎR�����ɋ߂����x���̓o���H�ɂȂ�B���`�R�̍������ׂĒ�q�ɕς���A��q��o�~���郋�[�g�ɂȂ�B�o���H���ǂ̂悤�ȃ��[�g�Ƃ��Ĉێ����邩�́A���[�g�̊Ǘ��҂����肷��i�������A���{�ł́A���[�g�̊Ǘ��҂������܂��ł���j�B �@�o���H�ɐݒu���ꂽ�����q�́A�K���A�Ǘ��҂����N�_�����Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���B��������Ă��Ȃ��o���H�ɍ����q���ݒu����Ă��邱�Ƃ͊댯�ł���A�P�����邩�A�N���C�~���O���[�g�ɂ��ׂ��ł���B �@�o�R����o���H�ɐݒu���鍽���q�́A�K�v�ŏ����ł��邱�Ƃ��]�܂����B�Ȃ��Ȃ�A�o�R���ɐݒu���ꂽ�����q�̗ʂ�������A�_���A�����ɗv����J�́A��p�������邩��ł���B�_���A��������Ă��Ȃ������q�͎��̂̌����ɂȂ鋰�ꂪ����B �@�����x�̖k�������A�O��k�����A���x�����Y�����Ȃǂ́A���R��Ԃɋ߂��o���H�i�������A�ꕔ�ɃN���C�~���O�����A�������~����������j�̗�ł���B�������A���̂悤�ȃ��[�g�Ƃ��ĊǗ�����Ȃ���A���[�g�̏�Ԃ��ێ��ł��Ȃ��B �i�R�j���{�ł́A��L�̇@�A�A�A�B�̋�ʂ����m�łȂ��A�����o�R���Ɠo���H�̋�ʂ�����Ă��Ȃ��B���[���b�p�A���v�X��hiking��climbing����ʂ��邱�Ƃ́A�Ǘ��ӔC�̋�ʂɑΉ����Ă���Ǝv����B�܂��Ahiking��climbing�̋�ʂ́A�K�C�h�̈��S�m�ۋ`���̓��e���K�肷��B �@���{�œo�R���[�g�̌`�Ԃ̋�ʂ����m�łȂ����Ƃ́A�Ǘ��ӔC�̋�ʂƏ��݂̂����܂������Ӗ�����B�o�R���[�g�ɐݒu���ꂽ�����q�Ȃǂ��Ǘ��҂��ӔC�������ē_���A�������Ă��邩�ǂ����́A�l���Ɋւ����ɏd�v�Ȃ��Ƃ����A���{�ł́A�u�N�����_�����Ă���̂��낤�v�Ƃ������R�Ƃ����M���̂��Ƃɗ��p����Ă���B�o���H�ł́A�����q�͓o�R�̎�i�ƂȂ��Ă���A�����o�R���ł��A�����q���^�����ƂȂ��A�S�̏d��������o�R�҂������B�l�C�̂���o�R���̍����q�͒N�����_�����Ă��邱�Ƃ��������i�n���̎R�x��A�{�����e�B�A�A�R�����A�����̂Ȃǁj�A�Ǘ��҂����m�łȂ���A����I�ɓ_�����Ȃ����ۏ��Ȃ��B���R�����ȊO�̎R�ł͎��R�����@�̋K�����Ȃ��̂ŁA���A��q�A���[�v�A�W���A�e�[�v�Ȃǂ�N�ł��ݒu�ł��A����炪���u����₷���B�o�R���ɐݒu���ꂽ���A��q�A��q�A��Ȃǂ̊Ǘ��ӔC�̏��݂������܂��ł���A�����^�o�R�̈����҂̈��S�m�ۋ`���͈̔͂Ɛݔ��̈��S�m�ۋ`���͈̔͂��������₷���i���Ƃ��A�o�R���̘V����������q�̕��̂��N����ƁA��q�̊Ǘ��ӔC�ƃc�A�[�o�R�̃��[�_�[�̈��S�m�ۋ`���̊W�����ɂȂ�j�B �o�R���[�g�̊Ǘ� �@�i�P�j�ȏ�̂悤�ȓo�R���[�g�i�o�R���A�o���H�j�̊Ǘ������邽�߂ɂ́A�Ǘ��҂����m�ł��邱�Ƃ��K�v�ł���B���{�ł́A���R�����@�Ɋ�Â��������ƂƂ��Đݒu���ꂽ������ό��q�����̗V�����A�ѓ��Ȃǂ͊Ǘ��҂����m�ł��邪�A����ȊO�̓o�R���[�g�̊Ǘ��҂������܂��Ȃ��Ƃ������B�{���A�o�R���[�g�̂���y�n�̏��L�҂�Ǘ��҂��o�R���[���Ǘ����ׂ��ł��邪�A���̂悤�ɂȂ��Ă��Ȃ��B �@���̌����Ƃ��āA�N���J�݂������킩��Ȃ��o�R�����������ƁA���̂��N�����ꍇ�̖@�I�ȊǗ��ӔC�i�c�����ӔC�A���Ɣ����@�Q���A�H�앨�ӔC�A���@�V�P�V���j�̕s�������邱�ƂT�j�A�o�R���̊Ǘ��̔�p���S�̖��Ȃǂ�����B�����̖��͖��ڂɊW���Ă���B���{�ł́A�o�R���̊Ǘ����������l�H���ɂ����S���Ƃ����C���[�W�������A����́A�����̍ی��̂Ȃ������ɂȂ���₷���B�o�R���̍ی��̂Ȃ������́A�ی��̂Ȃ��Ǘ��ӔC�������炵�A�o�R���̊Ǘ����������X���������炷�B�o�R����N�ł����S�ɗ��p�ł���悤�ɐ������邱�Ƃ��A�u�o�R���̊Ǘ��v���ƍl����A���{���̓o�R�������ׂėV�����ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A����Ȕ�p��������A�Ǘ��ӔC���ی����Ȃ��B�������A�o�R���̌`�Ԃ�o�R���Ɠo���H�̋�ʂ�����A�Ǘ��ӔC�͂���ɉ��������̂ɂȂ�A�ӔC�͈̔͂����肳���B �@�V�����͒���I�ɓ_������K�v������A���◎�ɂ��āA�V�����̊Ǘ��҂ɊǗ��ӔC���F�肳��₷���B�]���̊댯���̂���ꏊ�ɂ́A�]���h�~�p�̍��ݒu���邩�A�댯���̕\�����K�v�ł���B�������A������̏��Ȃǂ̕����ŗL�̊댯���ɂ��Ă͊Ǘ��ӔC�͐����Ȃ��U�j�B �@�������ꂽ�o�R���E�o���H�́A�P�N�ɂP����x�̓_��������K�v������A����ŗ\���ł��Ȃ����R�ɋN�����闎���q�̕��ɂ��ĊǗ��ӔC�͐����Ȃ��B�V�����͕p�ɂɓ_�����ׂ��ł��邪�A�������ꂽ�o�R���E�o���H�ł́A�����܂ł̊Ǘ��͗v������Ȃ��B�����������̕����ܑ̍����ăn�C�J�[���]���������̂ɂ��āA�����̉c�����ӔC���F�肳�ꂽ�P�[�X�����邪�A����́A�����̊ό��q��n�C�J�[�����p��������ł̎��̂ł���A�P�N�ɂP����x�_�����Ă���Ζh�����Ƃ��ł����V�j�B�h�C�c�ł��A�n�C�L���O�R�[�X�ɂ����̕��̂Ɋւ��ĐӔC��肪�c�_����Ă���W�j�B �@�o�R���ɐݒu���ꂽ���Ɋւ��ĊǗ��ӔC��F�߂��ٔ��Ⴊ���邪�X�j�A���̃P�[�X���A���̊Ǘ��҂����m�ł���A�P�N�ɂP����x�_�����Ă���Ζh�����Ƃ��ł����P�[�X�ł���B���łȋ��́A�u���������Ă��M�p����ȁv�����藧�����A�ݒu�҂����m�Ȃ̂ŁA���ׂ�����ΊǗ��ӔC�������₷���B�������A�N���ݒu�������킩��Ȃ��Â��؋��ɂ��ẮA���̊Ǘ��҂��s���ł���A�Ǘ��ӔC�������ɂ����B �����̕����ł̗��؎��̂ɂ��āA���Q�����ӔC���ے肳�ꂽ�i�����n�ى�Îᏼ�x�����������Q�P�N�R���Q�R�������j�B�����̕����͐������ꂽ�o�R���ł���A�������ꂽ�o�R���ł́A���◎�ɂ��ẮA�����Ƃ��āA�o�R���̊Ǘ��҂ɊǗ��ӔC�͐����Ȃ��B �@��������Ă��Ȃ��o�R���E�o���H�ł́A�Ǘ��ӔC�͂قƂ�ǐ����Ȃ����A���̑���ɁA�ݔ����_���A��������Ă��Ȃ��|�̊댯�\�����K�v�ł���B�ݔ����_���A��������Ă��Ȃ����[�g�́A���̂悤�ȓo�R���Ƃ��ēo�R�҂ɋ��p����A���̂悤�ȓo�R���Ƃ��ĊǗ�����A���̂̑��Q�����ӔC�͐����Ȃ��B �i�Q�j���[�g��̍����q�Ȃǂ��_���A��������Ă��邱�Ƃ́A����炪�A�P�N�ɂP����x�̓_�����Ă���Ƃ����ۏ��Ӗ����A����ȏ�̃��[�g�̈��S�����Ӗ����Ȃ��B�R�x�n�`�������炷�댯����l�H���ň��S�����邱�ƂɁA���Ƃ��ƌ��E������B �@�o�R���́A���Ƃ��ƕ����ēo�邱�Ƃ��ł��郋�[�g�ł���i�����ēo�邱�Ƃ��ł��Ȃ����[�g�́A�o���H�ł���j�A�����q�Ȃǂ��Ȃ��Ă��ʍs�\�ł���B�o�R���ɍ����q��ݒu����A�o�R��������₷���Ȃ邪�A�����ēo�邱�Ƃ��ł���ӏ��ɍ��A��q�A�K�i�A��Ȃǂ�ݒu����A���ꂾ����p��������A�{�݂̊Ǘ��ӔC��������B�o�R���̍����q�Ȃǂ́A���̃��[�g�̗��O�ɏƂ炵�ĕK�v�ŏ����ł��邱�Ƃ��K�v�ł���B �@����ɑ��A�o���H�́A���Ƃ��Ƃƍ����q���Ȃ���A�N���C�}�[�ȊO�̓o�R�҂͓o�邱�Ƃ̂ł��Ȃ����[�g�ł���A�����q���K�v�ł���B�����ŁA��ʓo�R�҂̂��߂ɍ����q���ݒu����邪�A�����q�̗ʂ����[�g�̓�Փx�����肷��Ƃ������i������A���̐ݒu���@�����[�g�̏d�v�ȊǗ����e�ɂȂ�B�u���̃��[�g�͂����ɂ���ׂ����v�Ƃ������O���Ȃ���A�u�o��₷�������悢�v�Ƃ����p�^�[�i���Y���ƁA���p�҂𑝂₻���Ƃ����o�ϓI�ȓ��@���x�z���₷���B���̐ݔ����A���̓o�R���[�g�́u���O�v�ɏƂ炵�A�ŏ����̂��̂��ǂ����Ƃ����_���d�v�ł���B �i�R�j���{�ł́A�o�R���[�g�̌`�Ԃ̋�ʂ��Ȃ���Ă��Ȃ����߂ɁA�����Ɋւ��鎖�̂��ٔ��ɂȂ�ƁA����������ɂ��ĊǗ��ӔC�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����s���������₷���B �@�����ɂ́A�o�R���̑������A���炩�̌`�œ_���A��C����Ă��邪�i���ꂪ�Ȃ���A�o�R���͐��N�ŏ��ł��邾�낤�j�A�Ǘ��ҕs���̓o�R���������B�o�R�҂����S���āA���A���A��q�Ȃǂ��g�p�ł��邽�߂ɂ́A�o�R���[�g�̊Ǘ��҂��ӔC�������Ă������Ǘ����邱�Ƃ��K�v�ł���B �@�o�R���[�g�̊Ǘ��҂������܂��ŁA�o�R���[�g�̗��O���Ȃ���A���[�g�̌`�Ԃ�O���[�h���Ȃ�䂫�܂����ŕς���Ă����B���āA�u���{�̃}�b�^�[�z�����v�ƌĂꂽ�����x�́A���݂ł́A��q��o�~���郋�[�g�ɂȂ��Ă���A�N�ł��o�邱�Ƃ��ł���B����A���̃��[�g�ɁA�]���h�~�l�b�g��ݒu�����\�����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B �@���R�����ł͐l�H���̐ݒu�ɍ��⌧�̋��i���ʕی�n��A���ʒn��A���R�����@�Q�O���R���P���A�Q�P���R���P���j�A�͂��o�i���ʒn��A���R�����@�R�R���P���P���j���K�v�����A���R�����@�́A�u�D�ꂽ���R�̕��i�n�̕ی�v�A�u���p�̑��i�v�A�u�����̕ی��A�x�{�y�ы����v�A�u�����̑��l���̊m�ہv�Ȃǂ�ړI�Ƃ���@���ł���i���R�����@�P���j�A���ی�̎��_�����łȂ��A���p�̑��i�̎��_���������@���ł���B���R�ی�@�ɂ́A�u�o�R���[�g�͂ǂ�����ׂ����v�Ƃ������_�Ɋ�Â��Ǘ��͊܂܂�Ă��Ȃ��B�o�R���[�g�̊Ǘ��́A�o�R���[�g�̏��L���E�Ǘ����Ɋ�Â��čs���K�v������i���R�����ȊO�̎R�ł́A���R�����@�̋K�����Ȃ��j�B �@���Ƃ��A�k�������ł́A�L�����v�n�̐ݒu�́A���A�̖�蓙��������̂ŁA���Ȃ͊ȒP�ɋ��ł��Ȃ����A�����q�̐ݒu�́A�i�ς���ւ̉e�����������A�ނ���A���R�����@�ɂ����u���p�̑��i�v�Ɏ�����ʂ�����B�����x�̒��㒼���̑�ʂ̒�q�̐ݒu�������Ă���̂ɁA�k�������ɂ��Ď��R�����@�Ɋ�Â��č����q�̐ݒu�����ł��Ȃ����R���Ȃ����낤�B�������A�k�������ɍ����q��ݒu����A���j�I�Ɍ`�����ꂽ���[�g�̌`�Ԃ��ς��̂ŔF�߂�ׂ��ł͂Ȃ��B���l�ɁA�O��k���������ƒ�q�̃��[�g�ɕς���ׂ��ł͂Ȃ��B�����x�ɂ��Ă��A�u���{�̃}�b�^�[�z�����v�̖��ɂӂ��킵�����[�g���ێ�����K�v������P�O�j�B �i�S�j���{�̓o�R���[�g�́A�u���̃��[�g�͂ǂ�����ׂ����v�Ƃ������O�Ɋ�Â��Ǘ����Ȃ���Ă��Ȃ��B������o�R���[�g��N�ł��o���悤�ɂ���u��O���v���������犽�}����A������o�ϓI�ȗv�������i����B����炪�o�R���[�g��l�H���ʼnߏ�ɐ�������X���������炷���A���̂悤�ȎR�x�̐����͊��̔j��ł���A�����ɁA���R�Ƃ̊ւ�肪�{���ł���o�R�̖��͂����킹��B �@�u�o�R�Ƃ͉����v�A�u�o�R���[�g�͂ǂ�����ׂ����v�Ƃ����t�B���\�t�B�[���d�v�ł���B�o�R���[�g���A�u�֗����ǂ����v�A�u���������v�Ƃ����_�����ōl����A�o�R�����V���������₷���B�k��������O��k�����́A���[�g���Ǘ����ꂸ�A���܂��ܓo�R���J���̊S�̑ΏۊO���������ʂƂ��āA����̃��[�g���c�����̂ł���A�����A�����ɁA�c�Ə���������A�N�ł��o���悤�ɍ����q���ݒu����A���x�̕ʎR�����̂悤�ȃ��[�g�ɂȂ������낤�B����A���p�̑��i�ƈ��S���̖��ڂŁA�k�������ɔ����Ƃ������́u���h�ȏh�������v��ݒu���A�����q�Ő��������\�����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B������o�R���[�g�́A���O�Ɋ�Â��ĊǗ�����Ȃ���A���[�g�̉��ς�ێ����A�֗�����o�ϓI�ȗ��v�ɍ��E����₷���B�o���H�̊T�O�́A�o�R���[�g�̌`�Ԃ̂�����ƊǗ��̂�������l���邤���ŏd�v�ȈӖ��������Ă���B �@�o�R���[�g�̗��O�Ɋ�Â��Ǘ��́A�o�R���̊Ǘ��҂��s�����ƂɂȂ邪�A���L�n�ɂ���o�R���ł́A���A���A�����̂Ȃǂ��o�R���[�g�̊Ǘ��҂ɂȂ�͂��ł���11�j�B �i�T�j�o�R����o���H�̌`�Ԃ̋�ʂƊǗ��́A�o�R�҂��A�o�R����o���H�̌`�Ԃ̋�ʂɉ����Ă����̊댯���̒��x�𗝉����A�s���ł��邱�Ƃ��K�v�ł���B�o�R���[�g�̌`�Ԃ̋�ʂ́A�o�R�҂̔\�͍�������邱�Ƃ��O��ł���i���̓_�̔ے肪�V�������ł���j�B �@�ǂ�Ȃɓo�R���[�g�����Ă��A���̃��x���Ɍ��������o�R�҂��o��̂łȂ���A���̂��N����B�����q�̎��ɁA�K�i�A�萠��A��A�]���E���Ζh�~�l�b�g�Ȃǂ��K�v�ɂȂ�B�댯���̒��x�ɉ����čs���ł���o�R�҂̎��������Ȃ���A�ی��̂Ȃ������Ɣ�p��������A�ی��̂Ȃ��Ǘ��ӔC��������B�؍��ł́A�o�R���̓O�ꂵ�����S���ɂ���Ď��̂�h�~���悤�Ƃ��邪�A����ł́A�o�R�҂̎����I�ȃ��X�N���\�͂��炽�Ȃ�12�j�B �@�ݔ����Ǘ�����Ă��Ȃ��o�R����o���H�Ŋ댯�\�������Ă��A������C�ɂƂ߂邱�ƂȂ��s������o�R�҂�������A�댯�\���͖��Ӗ��ł���B�A�����J�̍ٔ����́A�{�݂̊댯�\���̗L�����d�����邪�A���{�̍ٔ����́A�댯�\�����d�������A���̂̉��[�u�̗L�����d������X��������13�j�B���̈Ⴂ�́A�댯�\���ɑ��鍑���̈ӎ��̈Ⴂ���琶������̂��낤�B �@�o�R�҂̎������́A����Ɍ��������Љ�I�ȓo�R���ɂ���ė{����B�o�R���[�g�̌`�Ԃ���ʂ��A�e�`�Ԃ̃��X�N�̒��x�m�ɂ��邱�Ƃ́A���̓_�ɖ𗧂ƍl������B �܂Ƃ� �i�P�j�o�R���́A�����ēo�邱�Ƃ��ł��郋�[�g�ł���A�����ēo�邱�Ƃ��ł��Ȃ����[�g�͓o���H�ƌĂԂׂ��ł���B���҂͂��ꂼ��v�������\�͂��قȂ�A���[�g�ɂӂ��킵���o�R�҂��o�邱�Ƃ��A���̖̂h�~�ɂȂ���B �i�Q�j�o�R���́A�V�����A�ݔ����Ǘ����ꂽ�o�R���A�ݔ����Ǘ�����Ă��Ȃ��o�R���A���R��Ԃɋ߂����ɋ�ʂł���B�o���H���A���l�̋�ʂ��\�ł���B���[�g�̌`�Ԃɉ����āA�u���̃��[�g�͂ǂ�����ׂ����v�Ƃ������O�Ɋ�Â��āA���[�g�̐�����Ǘ�������K�v������B���ׂẴ��[�g��l�H���Ő�������K�v�͂Ȃ��B �i�R�j�o�R���[�g�̊Ǘ��ӔC�i�c�����ӔC�A�H�앨�ӔC�j�́A�o�R���[�g�̌`�Ԃ�����e�ɉ��������̂ɂȂ�B�V�����ł͊Ǘ��ӔC���d���B�ݔ����Ǘ����ꂽ�o�R���E�o���H�ł́A�P�N�ɂP����x�̐l�H���̓_�����K�v�ł���A���̌��x�ŊǗ��ӔC��������B�ݔ����Ǘ����Ă��Ȃ��o�R���E�o���H�ł́A�Ǘ��ӔC�͂قƂ�ǐ����Ȃ��B �i�S�j�o�R���[�g�̏�̍��A��q�Ȃǂ̐l�H���̗ʂƐݒu���@�ɂ���āA�o�R���[�g�̃O���[�h���ς��B���̃��[�g�̌`�Ԃ�O���[�h�́A�u���̃��[�g�͂ǂ�����ׂ����v�Ƃ������O�ɂ���Č��肳���B������s���̂́A�o�R���[�g�̊Ǘ��҂ł���B�o�R���[�g��l�H���ʼnߏ�Ɉ��S�����邱�Ƃ́A���j��A�o�R�̎��E�s�ׂł���B�o�R���[�g�̊Ǘ��҂m�ɂ��A�o�R�̗��O�Ɠo�R�҂̑��l�Țn�D�Ɋ�Â������l�Ȍ`�Ԃ̓o�R���[�g���K�v�ł���B �i�T�j���̂悤�ȓo�R���[�g�̊Ǘ��́A�o�R���[�g�̌`�ԂƊ댯���̒��x�ɉ����ēo�R�҂������I�ɍs���ł��邱�Ƃ��O��ɂȂ�B [���A����] 1�j�œc�^��A�H���c���F���`�R �������o�R�֎~���H�A�R�ƌk�J�A902���A2010�A162�� 2�j���[���b�p�A���v�X�ł́A�o�R���[�g�́A�n�C�L���O���A���S�����ꂽ�o�H�A�o���H�Ȃǂɕ��ނ���Ă���B�n�C�L���O���́A�X�C�X�ł́A�N�ł��s���铹�A�R�Ɋ��ꂽ�n�C�J�[�̓��A�R�̊댯�����i�Ղ�����Ǔo����X�͂���j�ɋ敪����Ă���i�����x�m�q�F���[���b�p�A���v�X�o�R�E�n�C�L���O�A�{�̐�ЁA2009�A�Q�Q�Łj�B�����ł����n�C�L���O���͓��{�̓o�R���ɑ�������B�o���H�́A�N���C�~���O�̑ΏۂƂȂ��ǂɃ��C���[�A��q�A���̊K�i�Ȃǂ�ݒu�����C���[�W�ł���B 3�j�t�����X�ł́A�����ǂ�Via Ferrata�i���B�A�E�t�F���[�^�j��ݒu���悤�Ƃ������]�[�g�J����Ђ̌v�悪�c�_�̑ΏۂɂȂ�A�n���̎R�x�K�C�h�����̔��ɂ��A���~���ꂽ�P�[�X������i�ѓc�N��F��肩����R�A�x�͑�o�ŎЁA2011�A183�Łj�B�����ł́AVia Ferrata�̐ݒu�́A�A���s�j�Y���ƊW�̂Ȃ����W���[�J�����Ƃ�������������悤�ł���B���{�ł́A�o�R���̍��̓P�����߂���c�_�ɂȂ邱�Ƃ����邪�A�o�R���ɍ��A��q�A���[�v����ݒu���邩�ǂ��������I�ȋc�_�̑ΏۂɂȂ邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B 4)�j���[�W�[�����h�ł́A�g���C�����T�i�K�ɋ敪����A���[�g�̃O���[�h����ւ��ꏊ�ɂ͂����\������Ŕ��ݒu����Ă���i���z�^�E��������F�R�̃��X�N�ƌ����������߂ɁA�����V���A2015�A159�Łj�B�o�R���[�g�̌`�Ԃ���ʂ��A�o�R�҂����[�g�̃��X�N��F�����₷�����邱�Ƃ��d�v�ł���B 5�j�u���̉c�����v�́u�ݒu�E�Ǘ������r�v������A���⎩���̂ɑ��Q�����ӔC��������i�c�����ӔC�A���Ɣ����@�Q���j�B�u���̉c�����v�Ƃ́A���̖ړI�Ɏg�p�����o�R���A���A��A��q�A���A�K�i�Ȃǂ������B�u�ݒu�E�Ǘ������r�v�Ƃ́u�ʏ�\�z�����댯�ɑ��A�ʏ������ׂ����S���������Ă���v��Ԃ������B�܂��A�u�y�n�̍H�앨�v�́u�ݒu�E�ۑ������r�v������A���Q�����ӔC��������i�H�앨�ӔC�A���@�V�P�V���j�B�u�ݒu�E�ۑ������r�v�͍��Ɣ����@�Q���́u�ݒu�E�Ǘ������r�v�Ɠ����Ӗ��ł���B���̏ꍇ�A�H�앨�̐�L�ҁi�Ǘ��ҁj�����Q�����ӔC���A��L�҂����Ӌ`����s���������Ƃ��ؖ������ꍇ�ɂ́A�H�앨�̏��L�҂����Q�����ӔC���B���́u�͐A�E�x�������r�v������ꍇ�ɂ����l�̐ӔC��������B�o�R���t�߂̎����|��Ď��̂��N�����ꍇ�Ȃǂ��A���̗�ł���B 6�j�V���n�ٔ��������R�N�V���P�W���i�����P�S�O�Q���P�O�O�ŁA����^�C���Y�V�V�Q���P�O�O�Łj�A�����n�ٕ����P�W�N�S���V�������i�����P�X�R�P���W�R�Łj�A�������ٕ����P�X�N�P���P�V�������i����^�C���Y�P�Q�S�U���P�Q�Q�Łj�A�ō��ٕ����Q�P�N�Q���T�������A�X�n�ٕ����P�X�N�T���P�W�������Ȃǂ́A�V�����̊Ǘ��ӔC��F�肵���B�A�����J�̂��鍑�������ł́A�����W���[����������������ď�Q�����������Ă����Ƃ���A�n�C�J�[��������̏��̂��߂ɃX���b�v�������̂Ɋւ��āA���͎��R�̕����̈ꕔ�ł���Ƃ��āA�Ǘ��ӔC��ے肵���ٔ��Ⴊ����iBetty van Smissen�i1990�j�FLeagal Liability and Lisk Management for Public and Private Entities,Anderson Publishing,��20.31�j�B���{�ł́A�ٔ���͂Ȃ����A���l�ɍl���邱�Ƃ��ł���B 7�j�����n�ُ��a�T�R�N�X���P�W�������i�����X�O�R���Q�W�ŁA����^�C���Y�R�V�V���A�P�O�R�Łj 8�j�I�[�X�g���A�Ńn�C�L���O�R�[�X�ɂ�����ċN�������S���̂ɂ��ĕ����Ǘ��҂̌Y���ӔC������A���߂ɂȂ����P�[�X������A�h�C�c�ł��c�_������Ă���i�s�b�g�A�V���[�x���g�F�� ���Ǝ��̕���_�A�R�Ɵ�J�ЁA�P�W�Łj�B 9�j�_�˒n�ُ��a�T�W�N�P�Q���Q�O�������i�����P�P�O�T���P�O�V�ŁA����^�C���Y�T�P�R���P�X�V�Łj�A��㍂�ُ��a�U�O�N�S���Q�U�������i�����P�P�U�U���U�V�Łj�A�ō��ٕ������N�P�O���Q�U�������i�����P�R�R�U���X�X�ŁA����^�C���Y�V�P�V���X�U�Łj 10�j�}�b�^�[�z�����̃m�[�}�����[�g�i�w�������Łj�́A�Œ胍�[�v���ݒu����Ă���̂́A�S�̂̒��̂P�T�O���[�g���������ł���i�N���g�E���E�o�[�F�}�b�^�[�z�����őO���A�����V���o�ŋǁA2015�A�S�X�Łj�A����ȊO�́A���[�v�ɂ��m�ۂ��K�v�ȃ��[�g�ɂȂ��Ă���B�}�b�^�[�z�����ł����A��q�A���[�v��߂��炵�A�c�Ə����𑝂₹�A�N�ł��o�邱�Ƃ̂ł���R�ɂ��邱�Ƃ��\���낤���A�}�b�^�[�z�����́A�u�o�R�҂����ɊJ����Ă���v�i�����Q�P�U�Łj�B�����ł����o�R�҂́Ahiker�ł͂Ȃ��Amountain climber�̈Ӗ����낤�B�}�b�^�[�z�����̃m�[�}�����[�g�ł́A���O�Ɋ�Â��Ǘ����Ȃ���A���[�g�̃��x�����ێ�����Ă���B 11�j�h�C�c�A�I�[�X�g���A�ł́A�R�x�n�т̓o�R���̊Ǘ��ӔC�́A�����̏ꍇ�A�R�x�c�̂ɂ���i�s�b�g�A�V���[�x���g�F�� ���Ǝ��̕���_�A�R�Ɵ�J�ЁA2004�A�P�W�Łj�B����́A�R�x�̏��L�҂ł��鍑�����R�x�c�̂ɊǗ����ϑ����Ă�����̂Ǝv����B���{�ł��A���⎩���̂��������o���āA�R�x�c�̂ɊǗ����ϑ����邱�Ƃ͉\�ł���B 12)�؍��̓o�R���́A�Ε~�A�K�i�A�S���̊���~�߂��~���߂��A�o�R���ȊO�͗�������֎~�ɂȂ��Ă���B���ׂĂ̓o�R�����W����}�[�L���O���������A�؍��ł́A�o�R���̌`�Ԃ̋�ʂ��Ȃ��悤�ł���i���V�`���F��ؖ������������Ǘ����c�����������ԒT�K���C�@�Ƃ̌𗬎��ƂɎQ�����āA�����o�R���C���A�o�R���CVOL.31�A2016�A157�Łj�B 13�j�A�����J�ł́A���p�҂̑����ŁA�Ǘ��҂��A�u�V�j�֎~�v�A�u��э��֎~�v�̕\�������Ă������A�킩��₷���ꏊ�ɁA�u���ʉ��Ɋ₪����A��э��݂��댯�ł���v���Ƃ�\�������Ă��Ȃ������Ƃ������R����A�ٔ������Ǘ��҂ɑ��Q�����𖽂����P�[�X������iRONALD A.KAISER�i1986�j: LIABILITY LAW IN RECREATION,PARKS,& SPORTS,Prentice-HaLL,p.113�j�B���{�ł́A�z�e�������I�Ɏg�p���Ă����C������̋߂��Ɋ댯�ȏꏊ�����邽�߁A�z�e�����V�j�֎~��\������Ŕ�ݒu���Ă������A�q���ŔɋC�Â����M���������̂ɂ��āA�ٔ����́A�z�e���ɁA�q���댯���ʼnj���Ȃ��悤�ɂ��ׂ����Ӌ`�����������Ƃ��āA�z�e���̊Ǘ��ӔC��F�߂��i���n�ُ��a�U�P�N�T���X�������A����^�C���Y�U�Q�O���P�P�T�Łj�B�͐�~�ɂ�����t�߂���R�̎q������ɓ]�����ēM���������̂ł́A���ɁA�u���ԂȂ��̂ŁA���̏�ł����Ȃ��悤�Ɂv�Ƃ����Ŕ��ݒu����Ă������A�ٔ����́A�Ǘ��҂���ݒu���Ȃ������_�ɊǗ��ӔC��F�߂��i�_�˒n�ٓ��x�����a�U�Q�N�Q���P�Q�������A����^�C���Y�U�T�R���P�S�Q�Łj�B�܂��A��P�q�k�����Ύ��̂ŁA�����ɗ��Γ��̊댯������Ƃ̊Ŕ�ݒu���A���p�҂Ƀw�����b�g�𒅗p�����Ă������A�ٔ����͂�����l�������A�����̂̕����̊Ǘ��ӔC��F�肵���i�X�n�ٕ����P�X�N�T���P�W�������j�B �i���{�R�x�����w��_�W��P�S���A2016�����j |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
![]() �u�o�R�̖@���w�v�A�a��N�j�A�����V���o�ŋǁA�Q�O�O�V�N�A�艿1700�~�A�d�q���Ђ���
�u�o�R�̖@���w�v�A�a��N�j�A�����V���o�ŋǁA�Q�O�O�V�N�A�艿1700�~�A�d�q���Ђ���
�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@
![]() �@�u�R�x���̂̐ӔC�@�o�R�̎w�j�ƕ����\�h�̂��߂Ɂv�A�a��N�j�A�Q�O�P�T
�@�u�R�x���̂̐ӔC�@�o�R�̎w�j�ƕ����\�h�̂��߂Ɂv�A�a��N�j�A�Q�O�P�T
�@�@�@�@�@�@�@�@���s���@�u�C�c�[�\�����[�V�����@
�@�@�@�@�@�@�@�@�������@���_��
�@�@�@�@�@�@�@�@�y�[�W���X�O��
�@�@�@�@�@�@�@�@�艿�@�P�P�O�O�~�{��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@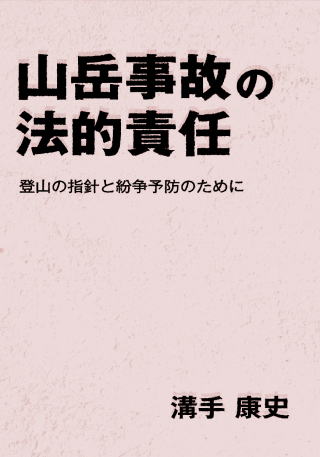
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@
![]() �@�u�^�̎��Ȏ������߂����ā@�d����ʂɂƂ���Ȃ����Ȏ����̓��v�A�Q�O�P�S
�@�u�^�̎��Ȏ������߂����ā@�d����ʂɂƂ���Ȃ����Ȏ����̓��v�A�Q�O�P�S
�@�@�@�@�@�@�@�@���s���@�u�C�c�[�\�����[�V�����@
�@�@�@�@�@�@�@�@�������@���_��
�@�@�@�@�@�@�@�@�y�[�W���Q�Q�U��
�@�@�@�@�@�@�@�@�艿�@�V�O�O�~�{��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
![]() �u�o�R�҂��߂̖@������ �R�̖@�I�g���u����������� ���Q�ҁE��Q�҂ɂȂ�Ȃ����߂Ɂv�A�a��N�j�A�Q�O�P�W
�u�o�R�҂��߂̖@������ �R�̖@�I�g���u����������� ���Q�ҁE��Q�҂ɂȂ�Ȃ����߂Ɂv�A�a��N�j�A�Q�O�P�W
�@�@�@�@�@�@�@�R�ƌk�J��
�@�@�@�@�@�@�@�Q�R�O��
�@�@�@�@�@�@�X�V�Q�~�@
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@