
| ツアー登山におけるパーティの形態と安全性 (抄録) ツアー登山における危険性は、その登山形態が大きく関係している。登山パーティーの機能として、集団による力の統合、安全性の機能、判断の多様性、娯楽性、引率性などがあるが、ツアー登山におけるパーティーは、集団による力の統合、安全性の機能、判断の多様性の機能が弱い。ツアー登山という形態は、人間のミスが事故に結びつきやすいという問題があり、それを回避するためにはツアー登山の対象を限定する必要がある。 日本の山がすべて山頂まで歩いて登ることができるということと、登山の商品化がツアー登山という日本特有の登山形態を生み出した。ツアー登山は旅行の延長的な性格があり、それが可能なためには、危険性が低いこと、体力や経験をそれほど必要とせず誰でも参加できること、緊急時の対処が可能であることなどが前提になる。 登山の引率者には、法律上、客の安全を守る注意義務が課され、条件の悪い時でも客の安全を守ることができるかどうかが、ツアー登山の範囲を規定する。登山において引率者が客の安全を守ることができる範囲は限られる。岩稜の縦走、転落の危険性のあるコース、エスケープルートのない縦走、悪天候時の避難の困難な登山などは、多数の客を引率するツアー登山の対象ではなく、客との間の強い信頼関係に基づく少人数のガイド登山の形態がふさわしい。 ツアー登山を規制する方法として、引率者等の刑事責任等、業界の自主規制、行政指導、法律や条例による規制などがある。 1、はじめに 2009年7月16日に大雪山でのツアー登山中に8名が死亡する事故が起きたが、それ以外にも、ツアー登山中の事故として、八ヶ岳静岡文体協遭難事故1)、羊蹄山ツアー登山事故2)、2002年のトムラウシ・ツアー登山事故3)などがある。 ここでいうツアー登山はツアー業者などが多くの客を引率する登山形態をさしており、 かつては30人の客を1人が引率するようなツアー登山もあったが、ツアー登山運行ガイドラインでは、引率者2~3人に対し、参加者15~25人を目安としている4)。それでも多くの客を引率することに変わりはなく、このように多数の客を引率する登山形態が登山の安全性にどのような影響を及ぼすのかが問題である。ツアー登山の形態はパーティーの形態と対象とする山域が大きく関係するので、この2点をとりあげ、ツアー登山の範囲を検討したい。 2、登山パーティーの形態と機能 (1)登山パーティーの機能 一般に、登山パーティーの形態はさまざまであるが、登山パーティーを編成する時、必ずそれがどのような機能を果たすのかを考える。この点は意識的な場合もあれば無意識的な場合もある。そこでそもそも登山パーティーは、どのような機能を持つのかを検討する必要がある。 登山パーティーの機能として、以下の点が考えられる。 ①集団による力の統合 これは、パーティーを編成することで「力を合わせることができる」ということである。「力を合わせる」ことは物理的な面だけではなく、精神的な面もあり、パーティーを編成することで登山行動が安定し強化される。 縦走登山ではパーティーを編成することで荷物の分担や精神的安心感が得られる。岩登りではパーティーを編成することで、ロープによる確保が可能になり、より困難な登攀が可能になる。冬山登山ではパーティーを編成することでラッセルが容易になるなど行動が強化される。 この機能を発揮するためには、登山パーティーは組織的に統率され、互いに強い信頼関係のもとに助け合うことが必要になる。 ②安全性の機能 もともと登山が対象とする自然環境に一定の危険性があり、これに人間の行動や判断が加わることで登山の危険性が生じる。自然に関与する人間の側の主体的な条件が、登山の危険性の程度を大きく左右する。登山者の主体的な条件には限界と個人差があり、パーティーを編成することで互いに補うことができる。初心者の不十分さを経験者が補うことは登山パーティーの機能の重要な点であり、参加メンバーが相互に補完することによって安全性が高まる。 ③判断の多様性 どんなスポ-ツでも人間の判断が要求されるが、登山は危険性を有する自然の中で行われる点で、人間の判断が生死に直結しやすい。 人間の判断は、五感の作用に基づく認識と、知識、経験に基づく判断から成り立つが、両者は密接に関係している。どんなに登山者に知識、経験、技術があっても、人間の認識には限界があり、また、自然のメカニズムを完全に認識することは不可能なので、登山者はさまざまな判断上のミスを犯す。この点は、リーダーやガイドも同じである。1人の人間の判断よりも多数の人間の判断の方が判断ミスのリスクが減る。小学校の遠足登山は危険性の低い山が対象であり、小学生に判断力がないので、引率する教師にすべての判断が委ねられるが、危険性の高い登攀では、1人の判断に頼るよりもメンバー全員で相談して行動を決定した方が安全性が高まる(ただし、メンバーにそれなりの判断の能力があることが前提である)。 従来、日本では、登山パーティーでは、集団による力の統合という機能が重視され、これに、組織的な団体行動観が加わって、すべての判断をリーダーに委ねる傾向があった。しかし、このような方法が妥当するのは、リーダーの能力と他のメンバーの能力に相当の差がある場合や、リーダーが判断ミスを犯しても致命的事故に至らないような山域に限られる。もともと人間の判断に絶対的な正しさはないので、1人の人間の判断に頼ることは、それ自体が大きなリスクをもたらす。過去に、リーダーの判断ミスがパーティーを遭難に導いたケースは多数ある(新田次郎の「八甲田山死の彷徨」など)。 参加メンバーに一定の力量がある場合には、メンバーが協力することで登山パーティーは判断の多様性という機能を持つ。 ④娯楽性 職業としての登山や記録をめざす登山、競技としての登山を除き、登山は趣味として行われるので、登山パーティーは娯楽性の機能を持つ。娯楽性という点では、パーティーの人数や形態の制限はない。 ⑤引率性 学校登山、ガイド登山、ツアー登山などでは、パーティーを編成することで引率という機能を果たす。引率性という点では、パーティーの人数は多数の方がよい。 (2)登山パーティーの形態と機能の関係 登山パーティーを編成する時、以上のようなパーティーの機能が考慮される。 集団による力の統合という機能を発揮するためには、登山パーティーは組織的に統率され、リーダーの強いリーダーシップが求められる。この点を重視すれば、リーダーの権限を絶対視する軍隊のような登山パーティーになるが、判断の多様性という機能を果たすためには、参加メンバーが自立的に思考、判断、主張できることや、参加メンバーの多様性が必要である。また、軍隊のような登山パーティーでは楽しくない。 集団による力の統合のための強いリーダーシップは、判断の多様性と相容れない面がある。参加メンバーが各自の意見を述べることは迅速な決定や行動に反し、迅速な行動ができないことがパーティーに危険をもたらすことがある。しかし、迅速な行動ができてもそれが間違った判断に基づくものであれば遭難の危険が生じる。 非常に微妙な判断を求められる困難な登山では、リーダーだけの判断で重要な決定をすることは判断ミスのリスクが大きくなる。参加メンバーの多様な登山経験や知識に基づいて全員で協議して叡知を出し合うことで、優れたパーティーの判断が可能になる。 一般的には、登山の危険性や困難性が増すほど、1人の人間の判断に頼ることのリスクが増すので、判断の多様性を重視した登山パーティーになる。冬山の一般ルートでの登山では、集団による力の統合のためのリーダーの強いリーダーシップがラッセルなどにおいて有効である。困難なアルパインクライミングでは行動内容を全員で相談することが多くなる。いわゆる極地法によるヒマラヤ登山などでは、判断の多様性と同時に多数の隊員をまとめるリーダーシップが必要になる。ツアー登山やガイド登山は、この機能を必要としないレベルの登山が対象となる。 気の合った仲間同士で構成されるパーティーは娯楽性を、ツアー登山や学校登山、ガイド登山などは引率性という機能を持つ。 登山パーティーの機能は、登山の目的や山域、危険性の程度、参加者のレベルなどに応じて考えられ、それをもとにパーティーの形態を考えることになる。 (3)ツアー登山におけるパーティーの機能と形態 通常、事故は1つのミスから起きるのではなく、幾つものミスや不運な偶然が重なって起きる。1件の重大事故の背後に300件のインシデントがあるというハインリッヒの法則があるが、たとえ、リーダーのミスがあっても、通常、それがすぐに遭難につながるわけではない。例えば、仲間同士の登山ではリーダーがルートを間違えても、他のメンバーが間違いに気づいて是正することは多い。たとえ1人の人間のミスがあってもそれを是正し、事故を未然に防ぐことが、登山パーティーの役割である。 しかし、ツアー登山などの引率登山では集団による力の統合及び安全性という機能は相互的ではなく、引率者から参加者へという偏面的なものである。つまり、引率者が参加者を補助し、参加者の安全に配慮するが、参加者相互間では集団による力の統合及び安全性の機能は弱い。また、ツアー登山ではパーティーに判断の多様性という機能がなく、引率者は常に孤独な判断を求められる。 2009年の大雪山での遭難では、客の1人が動けなくなった時、他の客は1時間以上も何もせずガイドの指示を待っていた。このような緊急時に全員で協力して困難を解決することがパーティーの本来の機能であるが、ツアー登山ではこの点が機能しにくい。また、ツアー登山では途中で不安を感じても声になりにくく、仮に客が意見を述べても引率者は無視しうる。新田次郎の描く八甲田山登山のケースでは、軍隊であるがゆえに隊長の誤った指示に従うしかなく遭難に至った。仲間同士の登山でも、熟練者と多数の初心者というパーティー編成の場合には、ツアー登山に類似した問題が生じる。 引率者が引率できる範囲は、①引率者の能力、②気象条件、時期などを含む対象となる登山の内容、③参加者の力量と数によって規定される。①ないし③は相互に関連しており、引率者の能力が優れていれば、かなり危険な登山でも引率可能であるが、引率者の能力が高くても、④物理的、生物的な引率の限界がある。例えば、参加者が動けなくなれば、引率者が背負って搬出するか、救助を待つしかないこと、体重80キロの人を背負うのは容易ではないことなどがある。それでも、参加者がリスクを承認していれば、引率が可能なので、⑤参加者のリスクの承認が、引率者の引率可能な範囲を広げる面がある。 かくして、引率登山の範囲を規定する要素として、①引率者の能力、②気象条件、時期などを含む対象となる登山の内容、③参加者の力量と数、④物理的、生物的な引率の限界、⑤参加者のリスクの承認があげられる。④は当たり前のことだが、自覚しない登山者が案外多い。⑤はツアー登山では十分に自覚されない傾向があり、重視すべきでない。 このような引率の範囲を規定する要素が、引率する客の数や対象山域等を規定する。 引率性という点では多数の客を引率する方が効率がよいが、ツアー登山では集団による力の統合、安全性の機能、判断の多様性を期待できないので、登山の安全性を確保する手法を考える必要がある。引率者の数を増やしたとしても、集団による力の統合、安全性の機能、判断の多様性をそれほど期待できない。前記ガイド・レシオで規定する数が適正なものかどうかは、ケースバイケースである。危険性の高い登山では、引率者の数を増やしても、ツアー登山という形態では安全性の実現は難しい。引率者の数を増やすことよりも、ツアー登山の対象山域を限定することの方が安全性という点で効果がある。 3、ツアー登山の対象山域 (1)ツアー登山が生まれた要因 ツアー登山は日本特有の登山形態であり、これが日本に生まれた要因として以下の点がある。 第1に、日本の山はすべて山頂まで歩いて登ることができるという特殊性がツアー登山を生み出した。日本では旅行と登山の境界が曖昧であることが、登山を引率型のツアー(旅行)として行う日本特有のツアー登山を可能にした。欧米の山は、登山(mountain climbing)とハイキングやトレッキングの対象となる山域を区別しやすいが、日本では両者の境界が曖昧である。欧米では、mountain climbingを日本的なツアー登山の形態で行うことはないと考えられる。日本人ガイドが、ヨーロッパアルプスの岩山で固定ロープを使用して多数の客を登らせ、地元市民から強い非難を受けたケースがある5)。 第2に登山の商品化がツアー登山を生み出した。手軽に、安く、効率的に登山をしたいという消費者の需要とそれが営利の対象となったことが、ツアー登山という商品を生み出した。商業的登山は、登山内容にふさわしいパーティーの形態を考えるのではなく、営利、効率、採算などの観点からパーティーを編成する。営利に結びつく限り、ツアー登山はその対象範囲を際限なく拡大する。旅行の場合には、営利、効率、採算などの観点からパーティーを編成しても、危険性が少なければほとんど問題が生じないが、登山はそうではない。 日本の山の多くは、無雪期に天候さえよければ登頂することはそれほど困難ではないが、悪天候や参加者の体調不良などの何らかのアクシデントがあれば遭難の危険が生じるという二面性がある。ツアー登山におけるパーティーの形態は、悪条件下での安全性の機能に乏しいので、悪天候やアクシデントがあった場合を想定して、ツアー登山の対象山域を限定することが必要になる。 (2)大雪山でのツアー登山事故について 2009年7月16日の大雪山でのツアー登山事故については、これが少人数の仲間同士の登山パーティーであれば、体力のレベルが事前にわかっていること、迅速な行動が可能であること、人数分のテントの携行が可能であること、体調の悪い者は自主申告し、それを前提にその日の行動について全員で協議することが可能であり、事故を回避できた可能性が高い。大雪山の遭難時に別の6人パーティーが同じ条件下で行動したが遭難しなかったのは、パーティーの形態が大きく影響している6)。 事故のあったルートは、行程の長さ、避難の困難さ、悪天候時の強風や寒冷などの危険がある。15名も客がいれば体調不良者が出る可能性が高くなり、登降、危険個所の通過、渡渉、緊急時の避難などあらゆる行動に時間がかかる。現実に、このパーティーの歩行のペースは遅く、増水した沢の渡渉などで時間がかかり、低体温症による大量遭難につながった。このようなルートではパーティーが迅速に行動できることが必要であり、50代、60代の年齢の15名のツアー登山の対象にすべきでなかった。 (3)ツアー登山の前提 ツアー登山は、ツアー(tour、旅行)という言葉に表れているように、多数の者を引率する旅行の延長的な性格がある。初対面の多数の客を引率するパック旅行は日本特有の旅行形態だと言われているが、これが可能なのは、旅行の危険性が低いこと、参加者が体力や経験を必要としないこと、緊急時の対処が可能であること、誰でも参加可能であることなどの前提条件があるからである。そこでは、参加者は自分の足で歩き、引率者は道案内や旅程の管理などをすることが想定されている。パック旅行では危険性がほとんどないことが前提であり、危険性を伴う旅行や参加者の体力を必要とする旅行の場合には、引率される客の数や参加資格の制限が問題になる。 登山は旅行と違って危険性があり、体力や経験を必要とし、緊急時の避難が容易でない。また、登山は、参加者の1人が動けなくなれば全員がそれに巻き込まれるなど、1人に生じた危険が他のメンバーに波及するという性格がある。したがって、ツアー登山という形態が可能なのは、危険性が低いこと、体力や経験をそれほど必要としないこと、緊急時の対処が可能であることなどの前提条件がある場合に限られる。伝統的に危険性を伴う登山における引率は、客とガイドとの間の信頼関係を前提とする少人数のガイド登山の形態がとられたのは、このような理由からである。 初対面の多数の客を引率するツアー登山は、悪天候や参加者にアクシデントが生じた場合でも引率者が対処可能な山域やルートに限るべきであり、それ以外の登山は、ガイドが個々の客の力量を把握したうえで客との間の信頼関係を前提とする少人数のガイド登山の形態がふさわしい。 (4)ツアー登山とガイド登山 伝統的なガイド登山は以下の特徴を持つ。 ①ガイドが客の経験、技術、体力等を把握している。 ②客とガイドとの間に信頼関係がある。 ③ガイドは客の安全を守ることを任務とし、ガイドが引率できる客の数は責任を持って安全を守ることができる範囲に限られる。 ④ガイドに客の安全を確保できるだけの経験、技術がある。 これに対し、ツアー登山は初対面の多数の客を引率し、客が自分の足で歩けることが前提であり、引率者は道案内や旅程の管理を主な任務とする傾向がある。 ツアー登山は、広い意味でガイド登山に含まれ、初対面の多数の客を引率する旅行の形態をガイド登山に拡張したものである。もともと両者を明確に区別しにくいうえに、最近は、ツアー登山の拡大とともに、ガイド登山がツアー登山に接近する現象が見られ、山岳ガイドが多数の初対面の客を引率する場合にはツアー登山との違いはほとんどない。旅行会社が行うツアー登山では、交通機関や宿泊の手配をし、山岳ガイドもしくはツアーコンダクター7)が引率するが、旅行業者の資格のないガイドが主催するツアーでは、交通機関や宿泊の手配ができないという違いがあるに過ぎない8)。ガイド登山がツアー登山に接近することは、ガイド登山の質と安全性の低下を意味する。 法律的には、ツアー登山とガイド登山を区別することはできず、どちらの形態でも引率者に客の安全を守るべき注意義務がある9)。ガイドが1人の客を引率する場合も、初対面の多数の客を引率する場合も、ガイドに課される法律上の注意義務に違いはない。仮に、契約書で、引率者の義務を道案内と旅程の管理に限り、安全管理は参加者の自己責任とすることを規定しても無効である(消費者契約法8条、10条)。 山岳ガイドはいかなる事態が生じても客の安全を守ることを使命としており、それだからこそ、ヨーロッパの山岳ガイドは高い技術、経験、使命感を持ち、社会的に尊敬されている。山岳ガイドは、警察官や消防隊員などと同じく、人の命を守ることを使命とする職業であり、それにふさわしい待遇と社会的地位が与えられる必要がある。同時に、山岳ガイドにはそのような職務を遂行できるだけの技術と経験が必要であり、ガイドの養成方法が重要である。 山岳ガイドは、特別な訓練と豊富な経験、技術を有し、客の安全を守るべき立場にあるが、それでもガイドのできる範囲には限界がある。もともと登山は自分の足で歩くか、自分の手足で攀じるものであり、動けなくなった人間の安全を守ることは容易ではない。観光旅行の場合には、客が動けなくなったり、急病になれば、近くの通行人の援助や救急車を呼ぶことが可能であるが、登山はそうではない。1人のガイドが同時に何人もの客の補助や救助できないことが多く、登山は旅行に較べて、引率者が客の安全を守ることのできる範囲が限定される。 岩稜の縦走であるとか、転落の危険性のあるコース、エスケープルートのない縦走コース、悪天候時の避難の困難な山域などで、ガイドが客の安全を守ることは簡単なことではない。登山は自然の中で行われる行為であり、何が起きるかわからないのが自然の特性である。 ツアー登山において、引率者がミスを犯さなければ事故を防ぐことができるが、ほとんどの山岳事故は人間のミスによって生じる。ミスを起こさない努力は必要であるが、人間のミスが完全になくなることはない。また、自然はそのメカニズムが完全に解明されていないので、人間の予測を超える事態が必ず生じ、これが判断ミスにつながりやすい。人間がミスを犯す存在だということを前提に安全対策を考える必要がある。リーダーに絶対的な権限を認める登山観は、「リーダーはミスを犯してはならない」ことが前提である。しかし、それでも事故が起きるのが現実であり、事故が起きれば「リーダーに責任がある」という非難を繰り返すだけでは事故を防止できない。危険性を伴う登山では人間のミスがあったとしても、ミスが致命傷にならない方策を常に考えておくことが必要である10)。 ツアー登山の参加者に一定のレベルを要求し、装備の強化、引率者の数を増やすこと、業者の安全管理体制の強化などの安全対策が考えられるが、いずれも限界がある。自分の能力を超えるツアーに参加する人を排除することは事実上困難であり、客の数が多ければ、もっとも力の劣る客が全体の足を引っ張ることになり、それが二次的、三次的な危険を招く。引率者の数が多くても、2009年の大雪山の事故のように客が15人もいれば行動に時間がかかり危険を招く。この遭難ではサブガイドは4人用テントを使用することなくザックに入れたまま下山しており、装備を強化しても意味をなさなかっただろう11)。多くの遭難で、衣類をザックに入れたまま凍死するケースは多く、装備の強化よりも、不十分な装備を使いこなせるだけの経験、技術の方が重要である。小学校の遠足登山で遭難が少ないのは、参加者のレベル、装備、引率の数と質の点で優れているというよりも、対象山域を限定しているからである。逆に、危険な山域での学校登山では、過去に重大事故が起きている12)。 また、遭難を防ぐために山小屋や登山道の整備、避難路の設置などの意見があるが、これは山での転・滑落を防ぐために柵や鎖、梯子、コンクリートの階段を設ける発想と同じである。登山道を柵や鎖、梯子、コンクリートで固めて安全にすれば、もはや登山道ではない。 4、ツアー登山の範囲 ツアー登山の対象は、山域やルート、参加者のレベル、時期などに応じ、どんな状況でも引率者が客の安全を守ることができる範囲に限定される。ツアー登山では、参加者相互間の援助が期待できず、また、一般に1人の引率者が客の安全を守ることができる範囲が広くないために、ツアー登山の範囲が制限される。 登頂をめざさないトレッキング、低山のハイキング、歩行時間の短い日帰り登山、エスケープや救助の容易な山など危険性の低い登山はツアー登山の対象にできるが、岩稜、難路、悪路が含まれる登山、降雪の可能性のある時期の登山、登攀的要素のある登山などはツアー登山の対象にすべきでない。前記八ヶ岳静岡文体協遭難事故は残雪期のツアー登山中の事故であるが、残雪期でなくても、南八ヶ岳の岩稜の縦走はロープによる確保などを臨機応変に行う必要があり、無雪期でもツアー登山の対象とすべきではない。無雪期の赤岳往復なども転・滑落の危険があり、同時に多数の客の安全を確保することは難しい。難路や悪路が連続する場合、ガイドが常に客の動向を注視している必要があり、1人のガイドが同時に注視できる客の数は2~3人ではないかと思われる。 槍ヶ岳の山頂直下で客が転・滑落すれば、転・滑落の予見可能性は容易に認定できるので、引率者に注意義務違反が認定されやすい。仲間同士の登山の場合には、参加者の力量がわかっており、参加者相互間の援助が期待できるが、ツアー登山ではこれらが欠けるので、引率者が客をロープで確保するなどの方策をとるべき局面が増える。3級のグレードの岩場でガイドがロープを使用して客の安全を確保すべきことはわかりやすいが、3級の岩場を梯子や鎖で整備すれば、「鎖場の登降は客の自己責任ではないか」などの議論が生まれやすい。しかし、このような場所で転落すれれば危険なことに変わりがなく、ガイドが客の転・滑落を防止すべき注意義務は基本的に同じである。このような安全の確保のためには、少人数のガイド登山の形態をとる必要がある。 縦走登山では客の数が多ければ歩行のペースが遅くなり、予定していた山小屋に到着できなければビバークになる。縦走登山中に天候が悪くなった場合、ツアー参加者の数が多ければ迅速な退避行動がとれず、危険を招く。何日にも及ぶ縦走登山では、荷物が軽いこと、緊急時に山小屋への避難もしくは下山が容易であること、1日の行程が短いこと、気象条件が厳しくない山域であること、日程に余裕があるなどの条件を満たせばツアー登山が可能だろう。 以上のように、多数の者を引率するツアー登山の対象は比較的易しい登山に限られる。「自分の力で登ることができるのであれば、わざわざツアーに参加する必要がない」という意見があるが、自分の力で登れない山をツアー登山で登るのは危険である。 ツアー登山は、旅行の形態をガイド登山に拡張したものであり、特に、日本特有のパック旅行の形態を登山に拡張することは登山のリスクを高くする。危険性を伴う登山では、リスクを最小限にするために少人数のガイド登山の形態がふさわしい。 ツアー登山という形態を生み出すのは消費者の需要であり、ツアー登山の対象を限定するうえで重要なことは、社会的な合意である。危険性を伴う登山はツアー登山の対象にならないという社会的合意があれば、そのようなツアー登山は需要がなく、成り立たない。ヨーロッパでは日本的なツアー登山は存在せず、ツアー登山の規制は問題にならないだろう。しかし、危険性を伴う登山をツアー業者にまかせて、手軽に、安く、効率的に行いたいという消費者の需要が強ければ、ツアー登山の範囲は際限なく拡大する。その場合でも、消費者が自分の能力の範囲でツアーを選択すれば問題は少ないが、消費者が常に賢明な選択をするとは限らない。自分の力で登ることに不安を感じる人がツアー登山に参加することは潜在的に大きな危険性を含んでいる。したがって、登山者の安全を守るためにはツアー登山の規制が必要になる。 ツアー登山を規制する方法として、ツアー登山運行ガイドラインなどの業界の自主規制や法律・条例による規制があるが、前者は法的拘束力がなく不十分である。危険性のある山域では後者の方法で営業的ツアー登山を制限することが必要である。なお、仲間同士の登山でも、多数の初心者を含む引率的な登山形態があるが、仲間同士の登山では基本的に自己責任が妥当するので、法的規制は問題にならない(2009年)。 [注記] 1)1978年4月29日に、静岡県社会人体育文化協会の職員1名が一般公募した30名の参加者を引率して、横岳付近の岩稜をトラバース中に参加者1名が滑落して死亡した。民事裁判で静岡県社会人体育文化協会及び引率した職員が損害賠償を命じられた(静岡地方裁判所昭和58年12月9日判決、判例時報1099号、p.21)。 2)1999年9月25日に、羊蹄山で旅行会社が募集したツアー登山に参加した14人の客のうち2名が凍死した。引率した添乗員は、刑事裁判(業務上過失致死罪)で、禁錮2年執行猶予3年の判決を受けた(札幌地方裁判所平成16年3月17日判決)。 3)2002年7月11日、トムラウシで、台風が接近中、ガイド1名、客7名というガイド登山が実施され、山頂付近で客の女性が死亡した(羽根多治:ドキュメント気象遭難、山と渓谷社、2003、p.94)。刑事裁判で引率したガイドは禁錮8月、執行猶予3年の判決を受けた(旭川地方裁判所平成16年10月5日判決)。 4)2004年に旅行業ツアー登山協議会がツアー登山運行ガイドラインを制定したが、業界内の指針であり、法的拘束力はない。2009年9月に、同年7月の大雪山の事故を受けて、一部改訂がなされた。 5)ツェルマットの登山センターのパンフレットには、登山に熟達した客の場合には、4000メートル峰に2人ないし例外的に3人のグループの引率が可能、山によっては3~5人の引率が可能と記載されているそうである(内田陽一:五十歳からの挑戦、東京新聞出版局、2005、p.139)。これらはすべて日帰り登山である。 6)2009年7月16日の大雪山での遭難時に、伊豆ハイキングクラブの6人パーティーが同じコースを歩き、1人が低体温症になったものの全員無事に下山した(しんぶん赤旗2009年9月14日)。このパーティーのリーダーの判断は遭難パーティーと大差ないが、仲間の援助・協力、6人という参加者数、参加者が事前にトレーニングをしていたこと、互いにメンバーの力量がわかっていることなどが遭難の有無を分けたと考えられる。 7)旅程管理業務を行う者のうち主任の者は、一定の研修を受けた実務経験者であることが義務づけられている(旅行業法12条の11)。これに基づいて旅行業団体が研修を実施しており、そこで得られる資格がツアーコンダクターの資格である。 8)旅行業法2条、3条。旅行業を営むには国土交通大臣の登録が必要である。 9)羊蹄山の事故の刑事事件に関する札幌地方裁判所平成16年3月17日判決は、「ツアー客を引率する添乗員としては、ツアー客が自集団に合流するのを待ち、その安全を図るべき業務上の注意義務がある」として、添乗員に禁固2年、執行猶予3年の刑の言い渡しをした。 10)ヒューマンエラーそのものを抑えることで事故を防止する手法はエラーレジスタンス、たとえヒューマンエラーが発生しても事故に結びつかないようにする手法はエラートレラントと呼ばれる(青山千彰:山岳遭難の構図、東京新聞出版局、2007、p.83)。クライミングにおける確保や冬山の滑落停止技術は登山者が滑落することを想定しており、滑落には人間のミスが伴うので、これらは後者の手法である。また、ビバーク用具や非常食を携行することも、予定通りの行動ができない場合に備えたもので後者の考え方に基づく。 11)岩城史枝:トムラウシ山遭難、東京新聞出版局、岳人748号、2009、p.154 12)1913年に木曽駒ヶ岳での高等小学校の学校登山で10名死亡した事故、1967年に西穂高岳での高校の学校登山で11名が死亡した事故がある。 |
![]() 「登山の法律学」、溝手康史、東京新聞出版局、2007年、定価1700円、電子書籍あり
「登山の法律学」、溝手康史、東京新聞出版局、2007年、定価1700円、電子書籍あり

![]() 「山岳事故の責任 登山の指針と紛争予防のために」、溝手康史、2015
「山岳事故の責任 登山の指針と紛争予防のために」、溝手康史、2015
発行所 ブイツーソリューション
発売元 星雲社
ページ数90頁
定価 1100円+税
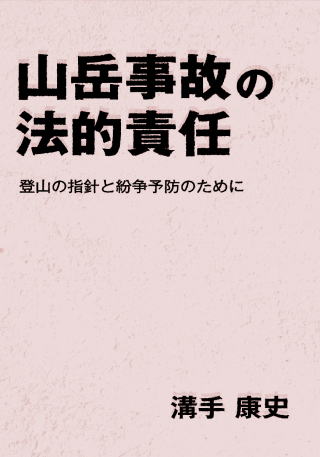
![]() 「真の自己実現をめざして 仕事や成果にとらわれない自己実現の道」、2014
「真の自己実現をめざして 仕事や成果にとらわれない自己実現の道」、2014
発行所 ブイツーソリューション
発売元 星雲社
ページ数226頁
定価 700円+税

![]() 「登山者ための法律入門 山の法的トラブルを回避する 加害者・被害者にならないために」、溝手康史、2018
「登山者ための法律入門 山の法的トラブルを回避する 加害者・被害者にならないために」、溝手康史、2018
山と渓谷社
230頁
972円
