Legal liability of mountain climbing and mountaineering
抄録
登山と危険を伴う旅行は、危険を伴う行為という点で共通し、事故が起きた場合の損害賠償責任に関して類似した問題が生じる。登山に関して引率者に参加者の安全を守る注意義務が生じるのは、教師と生徒、旅行会社と客、ガイドと客、講師と受講生などの特別の関係がある場合である。そのような特別の関係がなければ、原則として参加者の安全を守る注意義務は生じない。事故が予見可能な場合に引率者に注意義務が生じるが、予見可能性のレベルは引率関係の性格に左右される。国などが主催する登山では危険に対する厳しい予見義務が要求される。裁判所は、危険の引受を違法性阻却事由として扱うことはほとんどなく、危険の引受を注意義務を認定する際の事情として考慮している。裁判所は危険の引受を重視していないが、危険の承認は引率者の損害賠償責任を否定ないし軽減する重要な事由だと考えるべきである。
1、登山の範囲と特徴
日本語の登山の概念は相当に広い範囲まで含み、縦走、ハイキング、トレッキング、岩登り、沢登り、山スキー、山旅などを含み、旅行も山の中で歩く部分は登山に該当する。
登山は、①スポーツとしての性格と、②旅行としての性格を合わせ持ち、スポーツとしての登山には他のスポーツと同様の法理論が適用され、旅行という面では旅行業法等が適用される。
登山と一般のスポーツとの大きな違いは、登山が人工的な施設ではなく自然を対象とする行為であるために人工的な管理が困難な面があること、競技としてのクライミングなどを除くレジャーとしての登山には一義的に定まったルールがないということにある。前者は予見可能性や危険の承認の問題に関係し、後者はルールを基準にした違法性の判断ができないことを意味する。これらの点で、登山はレジャーとして行われるスキューバダイビング、パラグライダー、カヌー、ヨット、ラフティング、ダートトライアル(荒地等に設置したコースで車両を走行させるスポーツ)などの自然の中で行われる危険なスポーツと共通性がある。
また、登山と一般の旅行との大きな違いは、登山が危険を伴う行為だという点にあるが、辺境地域や治安の悪い地域での旅行は、危険を伴うという点で登山と共通性がある。
登山のようにルールのない危険な行為に関しては、どういう場合にそれが違法となるのか、あらかじめ危険が予想されていることを法的にどのように考えるべきかという点が問題になる。
2、法的責任と注意義務
(1)登山における法的責任の主なものとして刑事責任と民事責任がある。刑事責任として業務上過失致死傷罪、保護責任者遺棄罪などが問題となるが、もっとも問題になるのが登山の主催者や引率者、指導者(以下、引率者等という)の民事上の損害賠償責任である。
損害賠償責任の主なものとして債務不履行責任と不法行為責任があるが、前者は主に契約関係のある場合であり、後者は契約関係のあることを必要としない。山岳事故については債務不履行責任も不法行為責任も問題になるが、山岳事故に関して損害賠償責任を認めた判例はすべて不法行為を根拠にしている(注1)。
不法行為責任が成立するためには故意または過失が必要であるが、過失について裁判所は、結果の予見可能性が認められる場合に結果回避義務を課すという考え方をとっている
(注2)。
(2)損害賠償責任の前提となる注意義務として、安全配慮義務や安全を確保すべき義務(以下、安全配慮義務等という)がある。
安全配慮義務は、「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務」(最高裁昭和50年2月25日判決、判例時報767号11頁)とされ、「ある法律関係に基づいた特別な社会的接触の関係」の多くは契約関係がある場合であるが、契約関係がある場合に限られない(注3)。
安全配慮義務は債務不履行責任で問題となるが、不法行為責任では安全を確保すべき義務や安全に配慮すべき一般的な注意義務が問題となる。
債務不履行に基づく安全配慮義務と不法行為に基づく安全を確保すべき義務は微妙な関係に立つが、消滅時効期間を除きそれほど大きな違いがあるわけではない(注4)。
3、登山に関して安全配慮義務等が生じる場合
(1)学校登山
学校及び教師は、生徒の安全を守る一般的な義務、及び、契約に基づく安全配慮義務を負う(注5)。小中学生は自分の安全を自分で守るには心身の発達が未熟なので、学校主催の遠足、登山、ハイキング、社会見学、修学旅行等において、引率教師等の安全配慮義務等の内容は重いものになる。
高校生は小中学生に較べれば成人に近い面があり、学校のクラブ活動としての登山において、引率教師等は生徒に対する安全配慮義務等を負うが、小中学校ほど重いものではない(注6)。
大学生については、心身の発達の程度から成人に近い扱いがなされること、大学山岳部の活動は学生の自主的な活動の面が大きいことから、大学は山岳部の個々の具体的な行動に関して原則として安全配慮義務等を負わない。大学山岳部員が北アルプスで滑落した事故に関する名古屋高裁平成15年3月12日判決は、大学やリーダーの安全配慮義務等を否定した(弘前大学医学部山岳部事故)。
(2)ツアー登山、ガイド登山
旅行業者等が企画、手配して実施するツアー登山は旅行業法の適用を受ける。ツアー登山の多くは旅行契約に基づいて行われ、旅行契約の法的性質については争いがあるが(注7)、旅行契約の法的性格如何にかかわらず、ツアー登山の主催者や引率者は客に対する安全配慮義務等を負う。
ガイド登山には原則として旅行業法は適用されず、ガイド契約は旅行契約とは別の契約類型であるが、ガイドが客に対する安全配慮義務等を負う点では旅行契約と同じである。
羊蹄山事故に関する札幌地方裁判所平成16年3月17日判決は、刑事事件に関するものであるが、引率したツアーガイドは、客の安全を図るべき注意義務を怠ったと判断した(注8)。
この事故については、民事上も、事故当時の状況に照らせばツアーガイドの注意義務違反が認定できる(この事故の民事裁判は和解で終了した)。すなわち、事故当日は台風の通過直後で、暴風、大雨、洪水警報が出ていたこと、参加者が55歳~71歳だったこと、山頂付近が風速15メートル、視界が20~30メートルだったこと、遭難した客2名が途中から遅れて集団から離れたたことなどの事情があり、ツアーガイドが遭難を予見することが可能だった。そして、ツアーガイドはその後に遭難した2名の客が集団から離れないようにするか、遅れた2人が集団に到着するまで待つか、あるいは、山頂付近で2人の客を捜すべき結果回避義務を負っていたと考えられる。
カラコルムハイウェイ事故に関する東京地裁昭和63年12月27日判決(判例タイムズ739号190頁)は、パキスタンの山岳道路で起こったバス事故に関するものであるが、危険を伴う旅行という点で登山と共通性がある。この判決は、旅行業者に旅行者の安全を図るために危険を排除する措置をとる義務があることを認めたうえで、バスのタイヤがパンクした原因が不明だとして旅行業者の損害賠償責任を否定した。しかし、摩耗したタイヤで山岳道路を車が走行することが当たり前とされる地域の旅行では、このような事故の危険は参加者があらかじめ承認すべきであり、旅行業者に注意義務を課すことができない事案だった。
(3)講習会、研修会
講習会等として実施する登山では、主催者や講師に、講習契約に基づく安全配慮義務、 受講生の安全を確保すべき注意義務が生じ、講習内容が危険なほど、また、受講生が未熟なほどこの注意義務が重くなる。
大日岳雪庇崩落事故に関する富山地裁平成18年4月26日判決(判例時報1947号75頁)は、冬山での研修登山中の雪庇崩落事故について、引率した講師の注意義務違反を認定した。
(4)以上のように、引率者に安全配慮義務等が発生する場合は、教師と生徒、旅行会社と客、ガイドと客、講師と受講生のように引率者等と参加者の間に特別の関係がある場合(以下、引率登山という)である。そのような特別の関係が存在せず、仲間同士の登山、社会人山岳会、大学山岳部などの場合には、原則として参加者に対する安全配慮義務等は生じないと考えられる。
4、予見可能性について
注意義務を課す前提として事故の危険に対する予見可能性が必要であるが、引率登山では予見可能性の有無によって損害賠償責任が左右されることが多い。
前記の大日岳雪庇崩落事故は、雪庇の吹き溜まり部分が崩落したもので、講師や多くの登山家の経験からすれば予見が困難だった面があるが、裁判所は、国が主催した研修会であることを重視し、講師らが事前に雪庇の規模を調査する義務があったとして予見可能性を認めた(注9)。
サッカーの競技大会中の落雷事故に関する最高裁平成18年3月13日判決(判例時報1929号41頁、判例タイムズ1208号85頁)は、スポーツ指導者らの認識にとらわれることなく科学的知見等を重視して落雷の予見可能性を認めたが、学校行事や国の行事の場合には、引率者に厳しい予見義務を課して予見可能性を認める傾向がある(注10)。前記カラコルムハイウェイ事故に関する判決では厳しい予見義務が要求されておらず、予見義務や予見可能性のレベルは引率関係の性格に左右される。
5、危険の引受、危険の承認について
登山はもともと危険なものなので、登山中に生じる危険を絶対に予見できないわけではなく、また、ほとんどの山岳事故について事故後に子細に検討すれば、たいていどこかに人間の判断ミスを探し出すことができるので、引率者に過失を認定することはそれほど困難ではない(注11)。
しかし、引率登山で山岳事故が起きても、参加者があらかじめ危険を承認していたような事情があれば、損害賠償責任が発生しないとすることが公平である。アメリカ不法行為法には、事故の被害者が危険を引き受け、あるいは危険を承認していれば違法性が阻却され、損害賠償責任が生じないという危険の引受法理がある(注12)。
日本の裁判所は「危険の引受」や「危険の承認」を違法性阻却事由(民事訴訟法上の抗弁)として扱うことがほとんどなく、基本的にアメリカ型の危険引受法理は裁判所に受け入れられていない。東京地裁昭和45年2月27日判決(判例時報594号77頁、判例タイムズ244号139頁)はバレーボール競技中の事故について危険引受法理に基づいて違法性を否定したが、例外的な判例である。
しかし、以下のように、被害者が危険を承認していたことが注意義務の成否に影響を与えたと評価できる判例がある。
スキー場のゲレンデ以外の新雪のある斜面を滑降して雪崩事故に遭った事故(志賀高原スキーツアー事故)に関する長野地裁平成13年2月1日判決(判例時報1749号106頁)、は、被害者が登山経験や山岳地帯でのスキーの経験が豊富だったことから、リーダー的立場の者の損害賠償責任を否定した。被害者の経験が豊富なことが直ちに危険の承認のあったことを意味しないが、実態としては被害者はゲレンデ以外の新雪斜面での滑降に雪崩の危険があることを了解したうえでこのような行動をとったのであり、危険を承認していたという理由からリーダー的立場の者に注意義務を課すことができない事案だった。
前記のカラコルムハイウェイ事故に関する判決については、辺境の山岳地帯での旅行では参加者はこのようなバス事故の危険を承認すべきであり、この点が裁判所の判断に影響したものと考えられる。
ダートトライアル競技場において、初心者が練習運転中の事故によりベテランの同乗者を死亡させた事故に関して、千葉地裁平成10年9月25日判決(判例時報1673号119頁)は、ダートトライアルにおいては過去に転倒や衝突事故は珍しくないが、死亡事故がなかった等の理由から、運転者に被害者の死亡の予見可能性がないとして運転者の損害賠償責任を否定した。しかし、死亡事故は転倒事故や衝突事故の延長上にあるので、過去に死亡事故がなかったことから予見可能性がないという判旨には無理がある。判決がダートトライアルは「ある程度の危険を犯すことは当然に予定されていた」と述べているように、被害者が危険を承認していたことから加害者に注意義務を課すことができない事案だと考えるべきである(注13)。
大学合気道部の練習中に部員同士が衝突して脳挫傷等の傷害を受けた事故について、浦和地裁川越支部昭和55年12月12日判決(判例時報1019号111頁)は、危険をあらかじめ受忍することに同意していると解されるとして、不法行為責任を否定した。
裁判所は、危険の承認を違法性阻却事由ではなく、注意義務違反の有無を判断する際の諸事情のひとつと考えるものと思われるが、登山のように危険を伴う行為に関して危険の承認が違法性に影響を与える重要なファクターだと考えていないようである。この点は、恐らく、業者まかせのツアー登山では参加者が危険性を自覚しないことが多いこと、引率する側も引率される側も危険の承認を重視しないこと、自己決定や自己責任が重視されない日本の社会の実態が、裁判所の考え方に反映していると思われる。
登山は自然を対象とするので、引率者等が注意義務を尽くすかどうかにかかわらず、本質的に危険な行為である。危険な登山は、本来、危険を承認したうえで自己責任のもとに行われることが望ましく、危険の承認は引率者の損害賠償責任を否定ないし軽減する重要な事由だと考えるべきである。ただし、日本の引率登山の実情のもとでは、危険の承認の有無は厳格に判断される必要がある(消費者契約法8条は包括的な免責条項を無効としている)。
注1 辻次郎「登山事故の法的責任」、判例タイムズ997号38頁、1995年、判例タイムズ998号73頁、1996年
注2 潮見佳男「不法行為法」(信山社)153頁、2005年、内田貴「民法Ⅱ債権各論(第2版)」(東京大学出版会)320頁、2007年
注3 星野雅紀「安全配慮義務をめぐる諸問題」、現代裁判法体系27巻201頁、1998年
注4 内田貴「民法Ⅲ債権総論・担保物権(第3版)」(東京大学出版会)135頁、2007年
注5 齊藤隆「学校事故に関する国家賠償」、現代裁判法体系27巻119頁、1998年
注6 神戸地裁平成4年3月23日判決、判例タイムズ801号208頁、1993年
注7 佐々木正人「旅行の法律学(新版)」(日本評論社)10頁、2000年
注8 佐々木正人外「スポーツツアー事故における旅行業者の法的責任に関する一考察」、文教大学国際学部紀要16巻2号13頁、2006年
注9 北アルプズ大日岳遭難事故調査委員会「北アルプズ大日岳遭難事故調査報告書」、2001年、斎藤淳生編「北アルプス大日岳の事故と事件」(ナカニシヤ出版)、2007年
注10 奥野久雄、判例評論578号185頁、2007年
注11 湯浅道男「スポーツ事故訴訟における『判例』の機能」、日本スポーツ法学会年報第5号79頁、1998年
注12 及川伸「スポーツ事故と危険引受の法理」、日本スポーツ法学会年報第2号181頁、1995年、諏訪伸夫「スポーツ事故における危険引受の法理に関する考察」、日本スポーツ法学会年報第5号29頁、1998年、溝手康史「登山の法律学」(東京新聞出版局)284頁、2007年
注13 斉藤修、判例評論492号184頁、2000年
(日本旅行医学会学会誌第7号、2008、掲載)
![]() 「登山の法律学」、溝手康史、東京新聞出版局、2007年、定価1700円、電子書籍あり
「登山の法律学」、溝手康史、東京新聞出版局、2007年、定価1700円、電子書籍あり

![]() 「山岳事故の責任 登山の指針と紛争予防のために」、溝手康史、2015
「山岳事故の責任 登山の指針と紛争予防のために」、溝手康史、2015
発行所 ブイツーソリューション
発売元 星雲社
ページ数90頁
定価 1100円+税
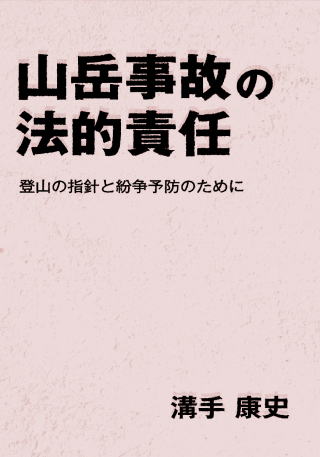
山と渓谷社
230頁
972円

