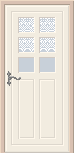

| 注文の多い料理店 その1 |
| 二人の若い紳士が、すっかりイギリスの兵隊のかたちをして、ぴかぴかする鉄砲をかついで、白熊のような犬を二疋つれて、だいぶ山奥の、木の葉のかさかさしたとこを、こんなことを云いながら、あるいておりました。 「ぜんたい、ここらの山は怪しからんね。鳥も獣も一疋も居やがらん。なんでも構わないから、早くタンタアーンと、やって見たいもんだなあ。」 「鹿の黄いろな横っ腹なんぞに、二三発お見舞もうしたら、ずいぶん痛快だろうねえ。 くるくるまわって、それからどたっと倒れるだろうねえ。」 それはだいぶの山奥でした。案内してきた専門の鉄砲打ちも、ちょっとまごついて、どこかへ行ってしまったくらいの山奥でした。 それに、あんまり山が物凄いので、その白熊のような犬が、二疋いっしょにめまいを起して、しばらく吠って、それから泡を吐いて死んでしまいました。 「じつにぼくは、二千四百円の損害だ。」と一人の紳士が、その犬の眼ぶたを、ちょっとかえしてみて言いました。 「ぼくは二千八百円の損害だ。」と、もひとりが、くやしそうに、あたまをまげて言いました。 はじめの紳士は、すこし顔いろを悪くして、じっと、もひとりの紳士の、顔つきを見ながら云いました。 「ぼくはもう戻ろうとおもう。」 「さあ、ぼくもちょうど寒くはなったし腹は空いてきたし戻ろうとおもう。」 「そいじゃ、これで切りあげよう。なあに戻りに、昨日の宿屋で、山鳥を拾円も買って帰ればいい。」 「兎もでていたねえ。そうすれば結局おんなじこった。では帰ろうじゃないか。」 ところがどうも困ったことは、どっちへ行けば戻れるのか、いっこう見当がつかなくなっていました。 風がどうと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はかさかさ、木はごとんごとんと鳴りました。 「どうも腹が空いた。さっきから横っ腹が痛くてたまらないんだ。」 「ぼくもそうだ。もうあんまりあるきたくないな。」 「あるきたくないよ。ああ困ったなあ、何かたべたいなあ。」 「喰べたいもんだなあ。」 二人の紳士は、ざわざわ鳴るすすきの中で、こんなことを云いました。 その時ふとうしろを見ますと、立派な一軒の西洋造りの家がありました。 そして玄関には、
という札がでていました。 |
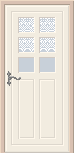

| 「君、ちょうどいい。ここはこれでなかなか開けてるんだ。入ろうじゃないか。」 「おや、こんなとこにおかしいね。しかしとにかく何か食事ができるんだろう」 「もちろんできるさ。看板にそう書いてあるじゃないか」 「はいろうじゃないか。ぼくはもう何か喰べたくて倒れそうなんだ。」 二人は玄関に立ちました。玄関は白い瀬戸の煉瓦で組んで、実に立派なもんです。 そして硝子の開き戸がたって、そこに金文字でこう書いてありました。
二人はそこで、ひどくよろこんで言いました。 「こいつはどうだ、やっぱり世の中はうまくできてるねえ、きょう一日なんぎしたけれど、こんどはこんないいこともある。このうちは料理店だけれどもただでご馳走するんだぜ。」 「どうもそうらしい。決してご遠慮はありませんというのはその意味だ。」 二人は戸を押して、なかへ入りました。そこはすぐ廊下になっていました。その硝子戸の裏側には、金文字でこうなっていました。
二人は大歓迎というので、もう大よろこびです。 「君、ぼくらは大歓迎にあたっているのだ。」 「ぼくらは両方兼ねてるから。」 ずんずん廊下を進んで行きますと、こんどは水いろのペンキ塗りの扉がありました。 「どうも変な家だ。どうしてこんなにたくさん戸があるのだろう。」 「これはロシア式だ。寒いとこや山の中はみんなこうさ。」 |