| 注文の多い料理店 その2 |
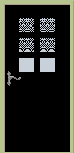
| 注文の多い料理店 その2 |
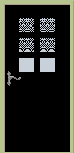
そして二人はその扉をあけようとしますと、上に黄いろな字でこう書いてありました。
「なかなかはやってるんだ。こんな山の中で。」 「それあそうだ。見たまえ、東京の大きな料理屋だって大通りにはすくないだろう。」 二人は云いながら、その扉をあけました。するとその裏側に、
「これはぜんたいどういうんだ。」ひとりの紳士は顔をしかめました。 「うん、これはきっと注文があまり多くて支度が手間取るけれどもごめん下さいと斯ういうことだ。」 「そうだろう。早くどこか室の中にはいりたいもんだな。」 「そしてテーブルに座りたいもんだな。」 |
![]()
![]()
| ところがどうもうるさいことは、また扉が一つありました。そしてそのわきに鏡がかかって、その下には長い柄のついたブラシが置いてあったのです。 扉には赤い字で、
と書いてありました。 「これはどうも尤もだ。僕もさっき玄関で、山のなかだとおもって見くびったんだよ」 「作法の厳しい家だ。きっとよほど偉い人たちが、たびたび来るんだ。」 そこで二人は、きれいに髪をけずって、靴の泥を落しました。 そしたら、どうです。ブラシを板の上に置くや否や、そいつがぼうっとかすんで無くなって、風がどうっと室の中に入ってきました。 二人はびっくりして、互によりそって、扉をがたんと開けて、次の室へはいって行きました。早く何か暖いものでもたべて、元気をつけて置かないと、もう途方もないことになってしまうと、二人とも思ったのでした。 扉の内側に、また変なことが書いてありました。
見るとすぐ横に黒い台がありました。 「なるほど、鉄砲を持ってものを食うという法はない。」 「いや、よほど偉いひとが始終来ているんだ。」 二人は鉄砲をはずし、帯皮を解いて、それを台の上に置きました。 また黒い扉がありました。
「どうだ、とるか。」 「仕方ない、とろう。たしかによっぽどえらいひとなんだ。奥に来ているのは。」 二人は帽子とオーバーコートを釘にかけ、靴をぬいでぺたぺたあるいて扉の中にはいりました。 |
![]()
扉の裏側には、
と書いてありました。扉のすぐ横には黒塗りの立派な金庫も、ちゃんと口を開けて置いてありました。鍵まで添えてあったのです。 「ははあ、何かの料理に電気をつかうと見えるね。金気のものはあぶない。ことに尖ったものはあぶないと斯う云うんだろう。」 「そうだろう。して見ると勘定は帰りにここで払うのだろか。」 「どうもそうらしい。」 「そうだ。きっと。」 二人はめがねをはずしたり、カフスボタンをとったり、みんな金庫の中に入れて、ぱちんと錠をかけました。 すこし行きますとまた扉があって、その前に硝子の壺が一つありました。扉には斯う書いてありました。
みるとたしかに壺のなかのものは牛乳のクリームでした。 「クリームをぬれというのはどういうんだ。」 「これはね、外がひじょうに寒いだろう。室のなかがあんまり暖いとひびがきれるから、その予防なんだ。どうも奥には、よほどえらいひとがきている。こんなとこで、案外ぼくらは、貴族とちかづきになるかも知れないよ。」 二人は壺のクリームを、顔に塗って手に塗ってそれから靴下をぬいで足に塗りました。それでもまだ残っていましたから、それは二人ともめいめいこっそり顔へ塗るふりをしながら喰べました。 それから大急ぎで扉をあけますと、その裏側には、
と書いてあって、ちいさなクリームの壺がここにも置いてありました。 |
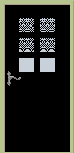

| 「そうそう、ぼくは耳には塗らなかった。あぶなく耳にひびを切らすとこだった。ここの主人はじつに用意周到だね。」 「ああ、細かいとこまでよく気がつくよ。ところでぼくは早く何か喰べたいんだが、どうも斯うどこまでも廊下じゃ仕方ないね。」 するとすぐその前に次の戸がありました。
そして戸の前には金ピカの香水の瓶が置いてありました。 二人はその香水を、頭へぱちゃぱちゃ振りかけました。 ところがその香水は、どうも酢のような匂がするのでした。 「この香水はへんに酢くさい。どうしたんだろう。」 「まちがえたんだ。下女が風邪でも引いてまちがえて入れたんだ。」 二人は扉をあけて中にはいりました。 扉の裏側には、大きな字で斯う書いてありました。
なるほど立派な青い瀬戸の塩壺は置いてありましたが、こんどというこんどは二人ともぎょっとしてお互にクリームをたくさん塗った顔を見合わせました。 「どうもおかしいぜ。」 「ぼくもおかしいとおもう。」 「沢山の注文というのは、向うがこっちへ注文してるんだよ。」 「だからさ、西洋料理店というのは、ぼくの考えるところでは、西洋料理を、来た人にたべさせるのではなくて、来た人を西洋料理にして、食べてやる家とこういうことなんだ。これは、その、つ、つ、つ、つまり、ぼ、ぼ、ぼくらが……。」 がたがたがたがた、ふるえだしてもうものが言えませんでした。 |