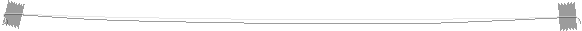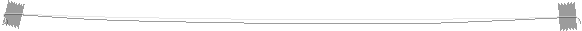車の達人になりた〜い
 車で事故らないように、私が普段気をつけている事や、トラブルの対処法を書いてみました。
みなさんが知っているような常識的な内容や、教習所で習う内容もありますが、初心者のために載せてあります。
書いてある内容を実行してみても、事故ることがあります。
あくまでも参考にして下さい。
車で事故らないように、私が普段気をつけている事や、トラブルの対処法を書いてみました。
みなさんが知っているような常識的な内容や、教習所で習う内容もありますが、初心者のために載せてあります。
書いてある内容を実行してみても、事故ることがあります。
あくまでも参考にして下さい。
駐車車両や乗降中バス等を避ける時の注意
上記のような場面で対向車がいなくなるのを待つ場合、避ける車の近くで待つとハンドルを回す量が多くなり
反対車線にはみ出る量も多くなってしまいます。
車1台分以上の車間を空けて待っていれば、あまりハンドルを回さなくても避けることが出来
あまりはみ出なくなります。
脇道や駐車場などから渋滞している道への合流について
駐車場などから混雑している道へ、なかなか出られない人が結構居ます。
車が途切れるのを待っていたり譲ってくれるのを待っていては日が暮れてしまうので自分から行動します。
まずはウインカーを点灯させます。(当たり前ですね)
渋滞で車が動かなくなっている時に、入れてもらう車(一番近い車)の運転手の目を見ます。
※ケンカを売っているわけではないので決して睨んではいけません
出来れば少し笑顔で運転手の目を見ると良いでしょう。
目が合ったら、そらされないうちに手を挙げたりお辞儀をします。
挨拶をしている車をブロックして入れさせない人はあまり居ないので入れてくれます。
車が動き出したらもう一度挨拶をして入りましょう。
逆にそういう場所で入ろうとしている車が居たら、入れてあげましょう。
アイドリング状態で長時間駐車時の注意
冷暖房のためにエンジンをかけたまま駐車することがあります。
エンジンをかけたまま駐車していると、排気管の繋ぎ目等から漏れた排気ガスが車内に進入する事があり
窓を閉め切っていたために一酸化炭素中毒で死亡する人がいます。
このような駐車をする時は、窓を少し開けておいたり時々換気することを忘れずに行いましょう。
ETC車線がある料金所での注意
ETCレーンがある料金所には「ETC専用」「ETC/一般」「一般」のいずれかの案内が出ています。
 ETC専用レーンなので一般車は通行出来ません。
ETC専用レーンなので一般車は通行出来ません。
 ETC車はETCシステムを使用して、一般車は通常の支払いで通行出来ます。
ETC車はETCシステムを使用して、一般車は通常の支払いで通行出来ます。
 ETC車・一般車共に通常の支払いで通行出来ます。
ETC車線でも、前車が通信異常や一般車のために停車する事があるので、追突しないように注意しましょう。
誤って専用車線に入ろうとした車が、急に車線変更してくる事があるので注意しましょう。
一般車が無人の専用車線に入ってしまった時は、インターホンで料金所の人に連絡して指示に従いましょう。
ETC車・一般車共に通常の支払いで通行出来ます。
ETC車線でも、前車が通信異常や一般車のために停車する事があるので、追突しないように注意しましょう。
誤って専用車線に入ろうとした車が、急に車線変更してくる事があるので注意しましょう。
一般車が無人の専用車線に入ってしまった時は、インターホンで料金所の人に連絡して指示に従いましょう。
高速道は暴走トラックが多い?
CBRさんからの投稿です。
ここをクリックしてください。
ギヤが入りにくい時の対応
ニュートラルから1速やバックギヤに入れる時、ガリガリと音がしてなかなか入らない場合
クラッチを踏み直すとスムーズに入りやすくなります。
停止するときのブレーキングについて
車を停止させる時に停止するまでブレーキを一定の強さで踏みつづけると、止まる瞬間にショックがあります。
(このようなブレーキングを「カックンブレーキ」と言う人もいます)
もし同乗者に車酔いになりやすい人がいると、止まる度に頭が前後に揺れるので酔ってしまいます。
停止する直前にブレーキを踏む力を弱めれば、スムーズに停止することができます。
混雑時の車線減少等による車線変更について
このような状態になったら、1台づつ交互に合流するのがマナーです。
合流される側の車線にいる車は、合流してくる車を1台入れてあげましょう。
入れてもらった車は後続車にお礼をすれば、後続車の運転手も悪い気はしないでしょう。
手をあげるもよし、ハザードランプを2〜3回点滅させるもよし、お礼の方法はいろいろありますが
暗い時に、車内で手をあげたりお辞儀をしても後続車には見えないので注意しましょう。
合流する車の車線変更は、なるべく車線が減少する直前の場所で行います。
手前で車線変更すると、合流される側の車線に入ろうとする車の方が多くなりその車線の流れが
悪くなってしまいます。
混雑時の車線変更について
混雑時、隣の車線のほうが流れがいいと、そちらの車線に移りたくなるものです。
遅い車線と速い車線で、速度差が結構ある時に、遅い速度のまま車線変更を行うと後方から来る速い車に
ブレーキを踏ませたり、最悪は衝突します。(下の合流地点の注意と一緒ですね)
車線変更をするときは、まず前の車との車間をあけて、その車間を使って加速します。
加速中に前の車がブレーキをかけることがあるので車間は長めに、前方をよく見て注意して加速してください。
そうすると速度差が少なくなるので、スムーズに車線変更が出来ます。
高速道路等の合流地点(IC・JCT等)の注意
インターやジャンクションで本線に合流するとき、加速車線でしっかり加速できていない車が結構多くいます。
本線に入る時点で、本線の車以上の速度に達していないと、その車にブレーキを踏ませたり、最悪は衝突します。
「加速車線」とは読んで字のごとく加速するための車線なので早い段階で本線の速度に達するようにしましょう。
加速できずに本線の車も入れてくれない状況になると、止まるという極めて危険な状態になってしまいます。
加速車線で止まると、後ろで加速している車に追突される可能性があります。
本線の車より速いぶんには、自分が速度調整して本線の車の後ろに入ればいいのです。
本線の車は、自分より遅い車(加速出来てない車)が流入してくるとわかったら、右の車線に移るようにしましょう。
もし右に移れないときはブロックしたりせず、入れてあげましょう。(運転が上手い人ばかりではありません)
駐車や右左折時のウインカー点灯時期について
ウインカーをつける時期は道交法で30m手前(3秒前)と決められているのはご存じだと思います...が!!
時々直前でつけて、後続車に迷惑をかけている車がいます。
たとえば右折専用車線が無い2車線以上ある道路で右折するする時、直前でウインカーを出すと
後ろの車は車線変更をすることが出来ないため、右折完了するまで後ろで待たなければなりません。
もし早めに出していれば後ろの車は左に移ることが出来、前の車を待つ必要など無いのです。
駐車するときも早めにハザードをつけることで、後続車はスムーズに右へ移ることが出来ます。
30mといわず、もっと早めのほうが良い場合もあるのです。(早すぎるのも問題ですけど...)
ウインカーやブレーキランプの確認
ウインカーのランプがどこか切れた状態で、切れた側(右or左)のウインカーを点灯させると点滅が早かったり
点滅しなくなります。(例外の車種もあります)
ウインカーの点滅が「いつもと違うな」と感じたら、切れていないか確認してみましょう。
ブレーキランプはブレーキを踏んでいるときしか点灯しないので、一人が踏んで、もう一人が確認します。
一人で確認したい(見てくれる人がいない)場合、コンビニ等にバックで駐車してガラスに映ったブレーキ
ランプを見て確認するか、信号待ちなどで停まっているときに、後ろの車がトラックや金属製バンパーのタクシー
だった時に、鉄板に映ったブレーキランプを見て確認するなどの方法があります。
有料道路の回数券について
均一料金の有料道路は、乗るときに料金を払います。
(首都高や阪神高速等の都市高速、外環や中央道の特定区間<高井戸−八王子>等のJHの高速)
このような道路は回数券が発売されていて、料金所では回数券を渡すだけで通過できます。
料金を払って、領収書を受け取るよりも早く通過できるだけでなく、金券ショップ等で購入すると
現金で支払うより15〜20%安く購入できるという利点もあります。
(金券ショップは電話帳タウンページの”商品券売買”で調べて下さい)
駐車時の方向について
小売店や公共の駐車場で前向き駐車を指定しているところが増えています。
これは近隣の住宅や草木に向けて、排気ガスをかけないようにするための気配りです。
指定のない場合でも出来るだけ、このようなことを考えながら駐車しましょう。
エアコン使用時のアイドルアップについて
エアコンを使用していると時々アイドリングの回転数が上がります。
AT車でDレンジになっている時に回転数が上がると、クリープ現象で前に進もうとする力が強くなります。
その時、ブレーキが甘いと前に進んでしまうので、注意して下さい。
雪道での4輪駆動車について
最近スキー場に向かう路上にて、RV車等の4駆の事故が急増しているそうです。
4駆の車はFF(前輪駆動)やFR・RR・MR(後輪駆動)にくらべ低摩擦路面(滑りやすい路面)で
滑りにくいのですが、滑りだすまでの限界が高い分、滑り始めると回復するのが難しくなります。
4駆をあまり過信すると、事故ってしまうので注意して下さい。
静電気対策
冬になると湿度が下がるのでドアを閉めようとしたときにバチッとくることが多くなります。
静電気は、髪の毛や衣服とシートの摩擦で帯電するので、ちょっと見かけは変ですがシートに座っている
状態から、ドアを手で持ちながら降りるとあまり痛い目にあわないですむようです。
ABS装着車運転時の注意
ABS(アンチロックブレーキシステム)はブレーキをかけている時にタイヤがロックすると
高速でポンピングブレーキをかける感じで、ロックしないようにします。
雪道などの滑りやすいところで、ABS無しで走るときはブレーキを強く踏むことが出来ません。
ABS付で走るときに、無しと同じような走り方をするとABSがききません。
熟練者でロック寸前のブレーキテクニックがあれば普通に踏んでもよいのですが、普通の人は
強めに踏んでABSをきかせる(ロックさせる)ほうが停止距離が短くなります。
ガガガッとかガリガリとか異音のようなものが聞こえますが、故障ではなくABSの動作音です。
バッテリーあがり
バッテリーがあがってしまった時はブースターケーブルを使い、他の車から電気をもらってエンジンをかけます。
このような時のためにケーブルは普段から用意しておきましょう。(なるべく太い物が良いでしょう)
一般的には赤と黒のケーブルで赤を+側、黒を−側につなぎます。
つなぐ時には順番があります。
故障車の+ → 救援車の+ → 救援車の− → 故障車のボディ(エンジンの金属部分やボンネットを止めてる金具)
最後は必ずボディに接続してください。(その接続時には火花がでます)
あがってしまったバッテリーからは可燃性のガスが発生する事があり、最後故障車の−に接続すると火花で
引火・爆発する恐れがあります。
つなぎ終わったらエンジンかけます。
しばらくたてば充電されるはずですが、すぐあがるようですとバッテリーか発電機の寿命です。
ケーブルを外す時は、接続した時の逆の順番で外します。
牽引
故障車を牽引する時、故障車のエンジンがかからないとハンドルのパワステやブレーキがきかないので
注意が必要です。(ハンドルが重い・ブレーキを強く踏まないときかない等)
停車する時にロープが緩むと発進する時にショックがあるので、止まる時には緩まないよう後ろの車が
先に止まるようにすると良いでしょう。
鍵の閉じ込み防止
市販品の、鍵のケースをマグネットで見えないところに貼っておくグッズを利用するのも良いでしょう。
私はウインカーレンズの中に入れてあります。(ネジ止めされているのではがれてなくなったりしない)
しかしドライバーが無いと出す事ができません。
最悪レンズを割れば出てきます。
ヘッドライト切れ
ガムテープ等がある時は、ヘッドライトの上部に貼ってハイビームにして走ります。
上向きの部分が隠されているので、対向車に迷惑がかかりません。
これは応急処置なので早めにヘッドライトバルブを交換しましょう。
対向のバイクについて
前から向かってくるバイクは車と違い車体が小さく、実際の速度よりも遅く感じられます。
行けると思って横切ると衝突してしまうことがあるので、かなり余裕をもって走りましょう。
ライトの点灯時期
薄暗くなっても、ライトを点灯しない人が多くいます。
自分が見えているからかもしれませんが、視力の悪い人に存在を気付いてもらえません。
早めに点灯しておけば、交差点等でミラーに映るので、別方向からくる車に気付いてもらえるので
衝突しないですむかもしれません。
自分ではよく見えていても、夕方・早朝・曇り・雨・霧等で少しでも暗いときはライトを点灯させましょう。
右折や右への横断時について
右方向に行くのに、しっかりと右に寄らないため、後ろに渋滞を作る人がいます。
余地が少ないところを無理に通り、こすって行く人もいるので、出来るだけ寄せるようにしましょう。
他にも情報があれば教えてください。
随時追加していきます。

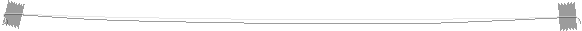
ぱんぴ〜のホームページに戻る
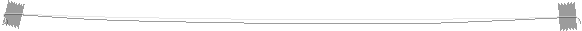


 ETC専用レーンなので一般車は通行出来ません。
ETC専用レーンなので一般車は通行出来ません。
 ETC車はETCシステムを使用して、一般車は通常の支払いで通行出来ます。
ETC車はETCシステムを使用して、一般車は通常の支払いで通行出来ます。
 ETC車・一般車共に通常の支払いで通行出来ます。
ETC車線でも、前車が通信異常や一般車のために停車する事があるので、追突しないように注意しましょう。
誤って専用車線に入ろうとした車が、急に車線変更してくる事があるので注意しましょう。
一般車が無人の専用車線に入ってしまった時は、インターホンで料金所の人に連絡して指示に従いましょう。
ETC車・一般車共に通常の支払いで通行出来ます。
ETC車線でも、前車が通信異常や一般車のために停車する事があるので、追突しないように注意しましょう。
誤って専用車線に入ろうとした車が、急に車線変更してくる事があるので注意しましょう。
一般車が無人の専用車線に入ってしまった時は、インターホンで料金所の人に連絡して指示に従いましょう。