1.ダイブテーブルに戻ろう
(ダイビング・コンピュータの潜水可能時間)
ダイビング器材メーカのTUSAは東京医科歯科大学高気圧治療部と共同し、ダイビングコンピュータの潜水可能時間を信用してダイビングを行うことの危険性について次のように説明しています。「全国の減圧症患者数は、年間1000人近くいると推定されており、決して他人事では済まされない問題なのです。しかも、減圧症にかかった人の多くが、ダイビング中はダイブコンピュータを使用し、無減圧潜水時間を守っていることが分かっています。無減圧潜水時間を守っているのに、減圧症になってしまうことがある。これは一体、なぜなのでしょうか?」
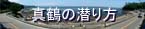
(1)検証されている安全な潜水時間はダイブテーブルまで
減圧理論については別章で説明しますが、ダイブテーブルを作成する際に使われている減圧理論式をそのままマルチレベルダイビングに適用してプログラミングしたものがダイビングコンピュータです。周囲の圧力の変化を基にしてリアルタイムに窒素吸収量や放出量を計算するというものです。これが本当にできれば良いのですが実際には出来ていないのが現実です。
ダイブテーブルを作成するための理論式を作るのには、歴史的に実際に人間が鋼鉄製の容器に入り、実験的に行われてきました。その実験は一定の圧力まで加圧し、時間を計り、大気圧に減圧してどのような症状が発生するかを調べるというものでした。ダイブテーブルは、この実験が行われたのと同じ前提である、潜水開始時刻、最大水深、潜水終了時刻の3点で管理をするということで安全性を確保できていたのでした。ダイブテーブルを作成する上では、便宜上、窒素の吸収の速度が異なる組織という大雑把な観点で理論をつくり、それを基にしてテーブルを作成し、運用上も実験を行った条件から逸脱しない範囲で使用することにより減圧症予防をしていました。ダイブテーブルを使用して潜水する上では便宜的に作った減圧モデルでも充分であったからなのです。
ところがダイビングコンピュータは、上記の実験結果が、マルチレベルダイビングにも当てはめてよいだろうという仮定をしてしまいました。充分な臨床を伴わずにダイビングコンピュータに適用されてしまったのです。ダイブテーブルを作成するために便宜上作られたモデルが、その運用の条件である潜水開始時刻、最大水深、潜水終了時刻の3点の管理を逸脱して使用され始めてしまったのです。もし現在のダイビングコンピュータに対して減圧理論を適用する際、ダイブテーブルと同様に三点の管理による残潜水時間の表示も追加していたとしたら、ダイビングコンピュータでの問題は起こりにくいものとなっていたはずです。浮上速度の超過のアラームや潜水可能時間の表示、細かい水深表示など、便利な機能により、更にダイビングが安全なものになった事と思います。実際には最大水深30mでも総潜水時間が25分を超えた際に、三点管理に基づいてプロフィールに関係なく減圧警告(Deco)を出すコンピュータは現在存在しません。
(2)本当の窒素量計算には「律速(りっそく」パラメータの考慮が必要
生理学者も自ら認めていますが、現在のダイビングの減圧理論を見ると、まだ不十分な状態です。実際の窒素の吸収や放出に基本的に必要なパラメータが考慮されていないからです。現在の減圧理論で考慮されていないのは「律速(りっそく)」というパラメータです。これは液体や固体の中に気体の分子が浸入していく様子を研究する「速度論」の立場では、基本的な考え方でこれを考慮しなくては始まらないパラメータです。これを考慮しないと、結果として誤った窒素濃度が算出されることとなります。しかしこれが現在のダイビングコンピュータの限界と言えますが、現在のダイビングコンピュータは各組織の律速段階は固定されていて一つです。それは瓶の首が太い瓶に水を出し入れするのか、口の広い瓶に水を出し入れするのかに例えられています。しかし本当の現象は、そうではなく、よく高速道路を例にとって説明されます。同じ一本の高速道路でも上りと下りで渋滞するところが異なったり、交通量によっても渋滞する場所が変わったりする現象です。この渋滞する箇所のことを律速段階と言います。同じ組織でもある濃度における律速段階、その際の圧力差による律速段階が異なる可能性があると考えるのが一般的なアプローチ方法です。マイクロバブルの形成による影響で窒素放出が遅れるという特殊なことを考えるよりも、むしろ律速段階を実験的に正確に調査しなければ真の減圧のモデリングはできません。日本ではecoカーの高性能電池の開発が盛んですが、この充放電を分析にも、この律速段階の調査から始まるなど、様々なものの開発の基礎研究の場面で調査されています。これらの先進的な材料メーカでは、この律速段階を実験的に確認しながら開発を行っていますが、それと比較し限定的な実験と簡易的な数学に頼るアプローチが現在の潜水医学の現状ということを考慮しておきましょう。(体内の窒素量の計算を、圧力と時間で計算するということは、充電式の電池で言うと、充電電圧と充電時間、放電電圧と放電時間で最終的なバッテリーの充電状態を計算するのと同じです。ちなみにそのような方式を取ると、電池が液漏れを起こしたり、破裂する危険性があります。)
(3)NAVYのダイブテーブルに対する誤解
一部のインストラクターや医学者は、ダイブテーブルが屈強なアメリカ海軍のダイバーによって作られ、一般の人が使用すべきでないというニュアンスで解説しています。例えばDAN-japanの会報「Alert
Diver Vol.43]には「あくまで米国海軍現役ダイバー用に考えられたテーブルであって、一般のレジャーダイバーを対象としたものではないということを忘れておられる方が非常に多いのでは(云々)」と述べられています。またこれまでNAVYのテーブルは長時間潜水や大深度潜水で不正確であると言う説明が繰り返し行われてきました。
しかしここで The US Navy Dive Tables 5% Failure Rate Myth を見てみましょう。ミシガン大学のLarry "Harris" Taylor, Ph.D. は、1990-1995のThe US Naval Safety Center report を調べ、実際の発症率は減圧潜水も含めて0.06%であったと述べ、信頼性が高いテーブルであると述べています。むしろ日本の潜水医学が誤ったデータを基にして述べ、世界に取り残されているという一つの例です。
また被験者が屈強なアメリカ海軍の軍人だったからということも実は無理があります。実は肉食が中心の米国人は体脂肪率が高く、日本人と比較して減圧症が発症しやすいという逆の実験結果が出ています。つまりアメリカ海軍のダイバーが被験者だったから日本人のレジャーダイバーが使用するのは危険というのは、指摘される観点から見ても全く逆で、まず正しいとは言えません。(実際には被験者は軍人も参加したということに過ぎません)。更に言うと負担の大きい軍務における作業潜水での減圧症発症率(5%)よりも、レジャーダイビングの方が発症率が高いとする根拠が実は明確ではありません。むしろ軍務潜水の方が発生率が非常に高く、これは日本でも実際のOBたちが述べていることです。こうした一部の医師の思い込みによる発言が、国際標準のU.S.NAVYのダイブテーブル離れをさせてしまい、結局、U.S.NAVYのテーブルで規定されていた高所移動についての基準もより不明確にしてしまっている事が問題で、実際に減圧症が国内だけで年間1000件も発生していることについて潜水医学者達の反省が全く見られません。減圧症予防に必要なのは、学問としてのダイビングではなく、実務としてのダイビングであり、高所移動まで含めて管理できる国際標準のU.S.NAVYのテーブルでないと私たちは実務が行えないのです。
潜水医学という学問によって、基準があいまいになってしまった結果、ダイブコンピュータを頼る方向にダイバーが「流されて」しまう結果になっている現状があります。ダイビングコンピュータの方が甘く計算され、長く潜れる計算結果を求めるダイバーの心の隙をついてしまい、ダイバーとの利害が一致してしまい、真の安全対策が取られない状況になっています。その為、それが一般化してしまい、ダイビングコンピュータを用いたのに減圧症が発生した場合は、個人の体質やその日の体調という説明が公的機関ですら見解を出す状態にまでなっています。しかし実際にはU.S.NAVYのダイブテーブルやその使用方法から逸脱していたか、使い方を誤解しているからだと考えます。
U.S.NAVYには潜水記録制度があり、減圧症が発生した場合のプロファイルも管理され、それがデータとして蓄積されています。ログは減圧症予防に再度フィードバックされるシステムがあります。これによりNAVYのダイビングマニュアルも第6版になってダイブテーブも更新され、従来言われてきた浅い水深における長時間潜水にも訂正が入っているほか、ダイブコンピュータでは計算できない高所移動のテーブルも準備されています。これまでは一部の生理学者が潜水医学と称して高所移動の危険性も含めて潜水の安全対策を語っていますが、U.S.NAVYのダイブテーブルを使用して高所移動のテーブルまで引き、守っていれば、ここまでの社会問題にもならなかったはずです。生理学者や潜水医学者の定性的な説明はもうこの程度にしていただき、実際のダイビングで減圧症にかからないようにする具体的な基準、U.S.NAVYのテーブルや、それを用いる際の注意事項などの基準にもう一度立ち返ってみましょう。
(4)メーカの対応にばらつき
ここでイタリアのダイビングメーカのMARESのホームページを見てみましょう。
「この計算は繰り返し潜水にも拡張され、ダイブテーブルが出来上がりました。これは今日でも使われています。しかしながら、こうしたテーブルはマイクロバブルの形成を考慮していません。一方で、新しいRGBM
Mares-Wienkeアルゴリズムではこれを考慮しているのです」
としています。つまりダイブテーブルの方がリスクが高いとしていますが、実際にはダイブテーブルよりもダイブコンピュータの方が、長い潜水時間でも安全と判断してしまいますので説明としては誤っていますし、もともとはテーブルを作成する為の理論にマイクロバブルを考慮しただけですので、テーブルを否定しながらもマイクロバブルを考慮しただけでマルチレベルダイビングに適用してもよいとする説明は矛盾したものがあります。そういう意味では国産のダイビングコンピュータのメーカ、TUSAのホームページはダイビングコンピュータで潜水時間を管理するのは既に限界であるとし、テーブルを使うよう薦めています。これは正しく説明していると言えます。どのメーカもダイビングコンピュータ自体の機能にあまり差はありませんが、このようなメーカの姿勢には消費者として賛同できるものがあります。