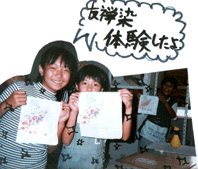自ら追究する子を育てる「総合的な学習の時間」の試行
ケナフを育てて紙を作ろう(5年生時)
ぼくの私の手づくり修学旅行(6年生時)
2カ年の実践を通して
|
はじめに
いよいよ新指導要領が完全実施となる。そうなると年間105時間,1週あたり3時間が「総合的な学習の時間」としてカリキュラムの中に設定される。これはたいへんな時間数である。社会科や理科と同じである。おまけに教科書もないときているから,無計画に行き当たりばったりで進めていくとゆゆしき事態になってしまう。そのあたりのことを私ちはじっくり考えてみる必要がある。
とかく新しいことに対しては様子を見て,という逃げ腰になりがちである。受動的な姿勢では,すべてが後手後手に回る。最終的に被害を被るのは子どもたちなのだ。この105時間を“子どもたちに与えられた,子どもたちのための時間”というように前向きにとらえ,教師集団は知恵を出し合って創造的な学習活動を構築していくべきであろう。
こういった点から,本学年(現在6年生)の子どもたちは,平成9年度(4年生時)から「総合的な学習の時間」の試行を重ねてきた。 |
《抜粋》 平成9年度 総合的な学習の時間活動計画
1 活動の目標
子どもたちの興味・関心に基づいた,教科の枠を越えた学習を組み立て,その
実践を通して学ぶ楽しさを味わい,自ら学ぼうとする意欲を育てる。
2 目指す子ども像
① やりたいことを持ち,意欲を持ってやり抜ける子
② 思いやりの心を持って,友だちと協力して活動に取り組める子
③ 今までの学習(体験)をもとに,自ら判断して行動できる子
3 テーマを設定するにあたって
(1)子どもたちの興味・関心に基づく。
(2)自らが設定した課題を,自らの興味・関心に基づき,ゆとりを持って課題解
決や探究活動に主体的,創造的に取り組めるよう配慮する。
(3)自然体験やボランティアなどの社会体験,観察・実験・調査・もの作りや生
産活動などの体験学解決を重視する。 |
以上のような基本的な考え方のもとに,全校体制で実践を重ねてきた。一昨年(4年時)の活動概略は以下の通りである。
《抜粋》 4年2組 原始の灯をともそう
1 活動内容
・ 文明の利器を使わないで,自分たちの力だけで工夫して火を作り出す。
・ 自分たちで生み出した秀,5年生からもらったお米を工夫して炊き,カレーライスを作って食べる。
2 ねらい
・ 自分たちで設定した課題を,自分たちの力だけで試行錯誤しながら解決していく活動を通して,追究することの楽しさを味わい,も
のの見方・考え方を育てる。
・ 生み出した火でご飯を炊き,カレーライスにして食べることにより,やり遂げた喜びを味わう。
・ グループで協力して追究活動を重ねていくことにより,思いやりの心をはじめ,好ましい人間関係を育てる。
3 活動計画 |
| 月 |
活動内容 |
教 師 の 留 意 点 |
4
|
テーマの決定 |
・ 各自のアイデアを生かし,個性が生きるよう配慮する。
・ 形状,材質,方法などを試行錯誤する中で,よりよい方法を追究しようとする態度を育てる。
|
10年度,子どもたちは5年生となった。4年生時の学年主任は引き続きこの子たちを受け持つことになった。担任3人で学年経営方針について話し合った際,2年間を見通した「総合的な学習の時間」を設定し,学年メイン活動とすることを確認し合った。“だれもが自分の力を発揮して追究し,やり遂げた充実感を味わう ことができる”そんな体験をさせてやりたいという教師の願いが込められている。こうして設定されたのが5年生での「ケナフを育てて紙を作ろう」そして6年生での「手づくり修学旅行」である。
11年度,6年生になった。学年主任を含め,2人の担任が引き続き受け持つことになった。計画通り今年度の学年メイン活動を「京都を知り,京都に学ぼう―ぼくの私の手づくり修学旅行―」として実践を開始した。
Ⅰ 研究のねらい
“自ら課題を見つけ,自ら学び考え,問題を解決する力などの「生きる力」を育てる”(指導要領解説:総則編)。この一文では「生きる力」を,例えば“問題を解決する力”としている。私たちはこれを「個性を生かして追究し,学ぶ楽しさを味わう」と解釈し,目標をこの1点に絞って取り組んだ。
― 研究のねらい ―
自ら課題を見つけ,個性を生かして追究し,学ぶ楽しさを味わえる子を育てる。
Ⅱ 研究の仮説
①「自ら課題を見つける」ために
そのために“豊富な問題を内包している題材”を取りあげる。子どもたちが今までに見たことも聞 いたこともないもの,経験したことのないものを用意するとよいだろう。
②「個性を生かして追究する」ために
そのために“どこからでも切り込んでいける間口の広い題材”を取りあげる。個性を生かすことに 有効に機能するだろう。子どもたちは好奇心のかたまりである。刺激的な出会いさせをれば,興味関 心も湧いてくるだろう。
③「学ぶ楽しさを味わう」ために
そのために“追究した結果を,実際にやってみる,試してみる(体験)ことができるような題材” を取りあげる。また,子どもたちが満足できるまとめ(アフターケア)をすることも大切なことであ る。
以上の仮説を満たす活動として,5年生での《ケナフ栽培と紙すき》6年生での《手づくり修学旅行》は最適であると考えた。また,実践において以下のことがらにも留意することとした。
▽ コンピュータを活用する ▽ 学級の枠を越えた集団で取り組む
▽ 個と集団の場を効果的に使い分ける ▽ 教師の十分な支援
|
Ⅲ 研究の見通し(2年間を見通して)
1 5年生での実践計画
ケナフの種まきから紙の有効活用までを連続した活動として設定した。紙すきは
ケナフを紹介して頂いた青年会議所(JC)との交流という点から合同で実施する
ことにした。
また,環境教育の一環として体験を重視すると同時に,発展活動として福祉施設
のお年寄りに手紙を書こうという活動も設定した。
2 6年生での実践計画
5年生時に育てた実践力をフルに発揮する場として,手づくり修学旅行を取りあ
げた。4月から総合的な学習を使って継続した実践ができるよう,旅行も秋季実施
に変更した。“京都を知り,京都に学ぼう―手づくり修学旅行―”をスローガンに
活動を設定した。
3 コンピュータの活用について
ケナフという未知の植物,そして行ったことのない京都,さまざまな情報が必要
である。ケナフの紙すきの方法は先行実践者がおらず,情報の多くをインターネッ
トに頼った。また,京都市バスや地下鉄の路線系統やダイヤなどもインターネット
の力を借りた。
この実践時にはコンピュータが導入されていなかったため,家庭でのコンピュー
タ活用を働きかけた。保護者にも協力していただくよう依頼し,自分でも使えるよ
うになろうと呼びかけた。その結果,資料の大半は子どもたちが調べてきた。
また,教師の支援として,ホームページを開設し実践の様子を多くの人たちに発
信した。世界に向けて自分たちの実践を送り出しているというということが子ども
たちの大きな励みとなった。コンピュータが2つの実践で大きな力となった。
Ⅳ 5年生での実践 ― ケナフを育てて紙を作ろう ―
1 ケナフとの出会い
平成9年度の3学期,JCの方にケナフを紹介して頂いた。今でこそマスコミで
紹介され知名度が高くなったが,この頃は職員の中にもこの植物を知っている者は
皆無であった。
子どもたちは美しい大きな花をつけたケナフの写真を見て,非常に大きな関心を
示した。さらに紙が作れるということから,育ててみたいという実践意欲が高まっ
た。追究の対象と極めて衝撃的な出会いができ,実践意欲が大きく盛り上がった。
2 実践の概要〈T男の取り組みから〉
T男は明るく快活な子であるが,根気強さにやや欠ける。栽培委員会に所属して
いるが,栽培活動に対しての興味・関心は薄い子である。学級の係活動でも,自分
の気に入った活動を除くと主体的な行動はあまり見られない。学習面では,根気よ
く追究するという姿勢があまり見られない子である。こんなT男に継続して根気よ
く追究すること,そして分かるおもしろさを体験させたいと考えた。
(1)種まき
5月16日,T男はプリンの入っていたカップに綿を敷いて,その上に種を2
粒置いた。ケナフという未知の植物への興味・関心が高まっていることが読みと
れる。「百科事典でケナフを調べたが,どこにもなかった」と,追究する意欲も
見せている。
T男のケナフ日記
JCの人が見せてくれた写真に写っていたケナフを初めて見たとき,ほんとうにびっくり
した。百科事典で調べたけど,のっていなかった。いったいどんな植物なんだろう。人間の
背より高くなるんだから,きっとジャングルになるだろう。それにケナフから紙が作れるな
んておどろきだ。ぼくも作って,自分だけのノートを作ろう。
(2)花壇への定植
驚くべき早さで発芽し,どんどん成長していった。そして6月20日,ビニルポ
ットの苗をケナフ花壇に定植した。
(3)開花までの世話
この年は台風が多く,3m以上も成長したケナフはそのたびに倒れてしまった。
T男は根方に土盛りをし,踏み固め,懸命に修復した。また,T男の発案で畝にそ
ってロープを張って,倒れないようにすることになった。たいへんな作業であった
が,T男は学級のみんなをリードして活躍した。今まで見られなかった姿である。
またこのころ,自分でインターネットが使えるようになり,いっそうたくさんの
資料も集めてくるようになった。インターネットの情報により,T男の目は環境問
題に広がっていった。これが後の「見つめ直そう,学区の環境」の学習へとつなが
っていく。
(4)開 花
ここまで2度の台風で打撃を受けたケナフであるが,子どもたちのがんばりで立
ち直りを見せの話によると9月中には花が咲くということだが,9月になっても一
向にその気配が見られない。やっと下旬になってつぼみが見られるようになった。
(5)取り入れ
花が散り,葉が落ち始めた11月初め,ケナフの取り入れをした。畑から抜いて
枝をはらい,茎を輪切りにする。茎の直径は3~4センチあり,のこぎりでなけれ
ば切れない。また,小さなとげがあるので,枝払いがたいへんである。
T男は方法をインターネットで既に知っており,みんなにそれを広た。活躍の場
が得られ,積極的に取り組んだ。
(6)パルプ作り
11月17日,パルプ作り。短冊状になったケナフの表皮を,さらにはさみで細
かく切り刻み(チップ作り),ミキサーにかけて砕く。それに苛性ソーダを混ぜ大
鍋で煮沸する。この日は青年会議所のメンバー5人の力を借りて実施した。また,
地元新聞「知立暮らしのニュース」の取材をうけた。
T男のグループは,市の福祉フェスティバルでケナフの紙すきを体験しており,
ここでもリーダーシップをとって活躍した。また「なべが足りないかもしれない」
と次の活動を気づかう余裕も見せていた。
 |
 |
 |
ケナフの花
|
パルプ作り
プライバシー保護のため,画像処理してあります |
ケナフの取り入れ
プライバシー保護のため,画像処理してあります |
(7)紙すき
12月5日,紙すき。牛乳パックパルプを混ぜた紙すき用のパルプを作り,い
よいよ紙すき開始。この日もJCの方の応援を得て実施した。どの子も,自分た
ちが育ててきたケナフを使っての紙作りということで,意欲的に取り組めた。最
終的には,一人あたりA4判4枚と葉書サイズ6枚程度を完成させることができ
た。
T男の表情には,自分の追究活動や栽培活動に十分満足している様子が表れて
いた。はじめ「自分だけのノートを作りたい」と言っていたのが「環境保護のチ
ラシを作って配りたい」と変化していることにも注目したい。
(8)一人暮らしのお年寄りに手紙を書こう
できあがった葉書の活用法を話し合う中で,市内の一人暮らしのお年寄りに手
紙を書こうという意見が出された。早速市福祉協議会へ出向いて相談した結果,
老人福祉施設ヴィラトピア知立を紹介していただき,お年寄りに手紙を書くこと
になった。そして3月18日,子どもたちと一緒に手紙を届けた。
3 本実践の価値
〇 ケナフは二酸化炭素を大量に吸収し,酸素を大量に排出する。また森林資源に
かわって紙の原料になることなどから,環境に優しい植物と言われている。この
ことをインターネットで調べてきたT男の発言から,作文学習「見つめ直そう学
区の環境」という実践へつながり,T男だけでなく子どもたち全体が環境問題へ
と学習が発展していった。
〇 JCの方,新聞取材に訪れた地元紙の方,また手紙を届けたヴィラトピア知立
の方々など,地域の方との交流を通して,子どもたちのものの見方・考え方が広
がると同時に,自分達の実践を広めることができた。このことはやり遂げた充実
感を味わうのに一役かった。
〇 資料を手に入れにくいケナフであったが,子どもたちはインターネットなどを
駆使し,私たちが驚くほどの資料を集めてきた。調べれば分かるという喜び,学
びの快感を身をもって味わうことができた。このことは次年度の実践に大きく貢
献した。
Ⅴ 6年生での実践(今年度の実践) “京都を知り,京都に学ぼう”
― ぼくの私の手づくり修学旅行 ―
1 ねらい達成のために
この実践では見学地の選択,使用交通機関の決定,実際に行動する道順など,す
べてを子どもたちが計画する。また時差をつけて出発するグループ活動の形態をと
る。これは5年生時から考えていた。それを考慮に入れ,まず山の学習で伊那の田
園地帯をめぐるグループオリエンテーリングを実施した。ついで6年生になった5
月,交通機関を使いこなす練習として,名古屋市の地下鉄を使ったグループ活動を
実施した。
このような修学旅行に向けた活動を柱として“学年経営計画〈本HPに掲載して
あります〉”と“修学旅行推進計画〈本HPに掲載してあります〉”を立てた。ま
た,6年生での総合学習を「京都を知り,京都に学ぼう―ぼくの私の手づくり修学
旅行―」とし,修学旅行に向けての活動として位置づけた。
また,この実践では保護者の協力が必須である。5年生末に概要については連絡
済みであるが,4月に改めて詳細を報告し,合わせてアンケートを実施して意見を
聞いた。そして事前に説明会を開き,直接疑問点や問題点について話し合う機会を
持った。
児童に対しては,各学級2名ずつの代表で構成される“修学旅行推進委員会”を
設け,すべての計画を子どもたち中心で行うように位置づけた。教師は子どもたち
の主体性を尊重し,支援する立場をとることとした。
2 T男のこと
T男はケナフの活動を通して調べることの楽しさを味わった。もともと社会科の
好きなT男は,今回の実践に対し「ぼくたちが修学旅行を作っていいの,ほんとに
?」と,早くから意欲を燃やしていた。後日談であるが,実際に自分の案を実証す
るため京都へも出かけている。
3 実践の概要
(1)京都を知ろう
目的地を決めるには,まず全体の姿を知らなければならない。そこで京都の歴
史・伝統・産業・風俗などを調べ,自分の興味・関心の対象を絞り込んだ。
この活動では子どもたちの意識を京都へ向け,問題意識を持たせ,自己の課題
を決定するという点からも重要な活動である。子どもたちはさまざまな角度から
京都を調べはじめた。明治維新,平安遷都,足利幕府,豊臣秀吉そして清水焼や
西陣織,友禅染,祇園祭や大文字焼きなど,さまざまなテーマを挙げた。
最終的には6月19日の推進委員会で,世界文化遺産と伝統工芸という2つの
大テーマが設定された。
(2)目的地を決めよう
言い換えればこれが自己課題決定の場面になる。自分の興味・関心から行って
みたい場所を決め,さらに追究する。そしてその場所への行き方も決めるのであ
る。ここからは学級解体して,同じ興味・関心の子同士が集まってグループを編
成した。
自分の追究テーマから目的地を選定し,それを友だちと調整しながら目的地を
決めていった。明治維新→二条城,足利幕府→金閣寺・銀閣寺,平安文化→清水
寺,伝統工芸→友禅文化会館といったように追究テーマと目的地を組み合わせて
いった。T男は伝統工芸体験コースを選んだ。最終的に決まった目的地は次の通
りである。
決定したコース
① 世界文化遺産コース
京都駅→清水寺→金閣寺→竜安寺→宿舎
② 世界文化遺産コース
京都駅→金閣寺→銀閣寺→二条城→宿舎
③ 伝統工芸体験コース
京都駅→京都友禅文化会館→古代友禅苑→宿舎
(3)目的地調べ
自分の目的地が決まったら,次はその目的地についてさらに追究を重ねていく。
同じコースを選んだ子たちが集まり,話し合いを重ねる。T男は友禅染について,
さらに追究を重ねた。「なぜそんなに値段が高いのか」という点に関心が向いたよ
うである。
(4)名古屋グループ活動 6月11日実施
本番と同じく学級を解体した男女混成のグループで実施した。京都を想定し,実
際に地下鉄を使い,交通機関の利用や,目的地を探しながら歩くという練習をした。
金山駅から名古屋城,名古屋港をめぐるコースで実施。
(5)グループ編制
各コースそれぞれ男女混成7~8人のグループを編制する。当日はこのメンバー
だけで行動する。編制の仕方については子どもたちに任せた。T男のグループは男
子3人女子4人の7人グループである。
(6)コースづくり
今回の実践での最も重要なポイントがコースづくりである。5時に宿舎にもどっ
てくるまではグループだけでの行動である。そのためにはどういう順番で回ればよ
いか,交通機関は何を使うかなど,大人でも難しい行程表づくりに取り組む。実践
にあたって次のことを子どもたちに示した。
コース作りの約束 ① 午後5時までに宿舎に帰ってくる。
② 回る順番は自分たちで決める。
③ 使える交通機関は市バスと地下鉄(1日乗車券を使う)
④ 時刻も調べる。
この約束にしたがって,子どもたちは懸命に調べ始めた。主な調べるポイントは
以下のとおりである。
調べるポイント ① コース作り《京都駅を出発してから,まずどこへ行くか。次にどこへ行くか。》
② 交通機関の選択《そこへ行くには何系統のバス,地下鉄に乗ればよいか。》
③ 交通機関のダイヤ《そのバス,地下鉄は何時何分発で何時何分着か。》
④ 利用するバス停《目的地の最寄りバス停(地下鉄駅)はどこか。》
⑤ バス停から目的地へ《バス停(地下鉄駅)から目的地までどう行けばよいか。》
以上のように,京都駅で解散してからは,宿舎へ着くまですべてが子どもたちに任
されている。そのための支援として,教師は次のことを準備し,子どもたちを支援し
た。
教師の準備 ① 京都市内の地下鉄と市バスの系統図を各グループに1部ずつ配布。
② 京都市内の地下鉄と市バスの時刻表を各学級に1冊ずつ配布。
③ 京都市街地地図を各学級1冊ずつ配布。
④ 市販の観光ガイドブックを各学級2冊(2種類を各1冊)ずつ配布。
⑤ 希望する子にはインターネットからの資料を提供する。
T男は自分の得意な分野でもあり,ここぞとばかり大活躍した。彼にとって,ここ
は主役となれる場である。インターネットで手に入れた市バスの系統図や時刻表を駆
使して京都友禅文化会館と古代友禅苑を回るコースを見つけだそうとがんばった。こ
の活動でのT男の活動をまとめると以下のようになる。
T男の追究の様子(T男の準備記録から作成)
① 友禅文化会館への行き方
まず,最寄りのバス停を探した。旅の情報誌から「中の橋五条」であることを見つける。雑誌の付録の系
統図では位置を見つけられなかった。早速インターネットで位置を確認する。
② バス路線を探す
京都駅から直接行ける75系統を見つけるが,1時間に1本しかなく,6グループで使うには無理である
ことを知る。五条からなら73と80系統が1時間に3本出ていることを見つける。地下鉄で五条まで行き,
そこからバスを使うことに決める。所要時間12分。
③ バス停から友禅文化会館まで
ここは徒歩である。道のりを市街地地図を見て調べた。3本目の交差点を右へ,その交差点名は「花屋町
通り」など,安心して歩けるように調べた。
④ 中の橋五条から古代友禅苑へ
古代友禅苑の最寄りバス停は「大宮松原」であることを情報誌から知る。京都市バスのホームページから
32系統が最も便利であることを知る。1時間に3本,所要時間10分であることを突き止める。たいへん
な喜びようであった。
⑤ 大宮松原から古代友禅苑へ
ここでも市街地地図で丹念に調べた。徒歩5分で簡単にいけることを見つける。
※ 古代友禅苑から宿舎へは全員いっしょに行動することになっているので,コース調べはここまで。
《教師のコメント》これがだめなら次は,と何度も何度も資料を変えて追究していた。もう少しでおわりとい
うところで振り出しにもどったこともしばしば。大人なら嫌になるほど,ねばり強い追究を
重ねた。
 T男のみならず,ほとんどの子どもたちが資料をとっかえ
T男のみならず,ほとんどの子どもたちが資料をとっかえ
ひっかえ,友だちと交換しながらこの難問に挑んだ。一つで
きたらまた次の問題が出てくる。大人ならとっくに嫌になる
ほどの時間と手間をかけた。
そのためコースができあがったときには,歓声をあげてや
り遂げた喜びをかみしめていた。
(7)教師の支援
子どもたちが一生懸命取り組んでいるのを黙ってみている
わけには行かない。教師側は以下のことがらについて準備し
た。
① 3つのコースの下見
子どもたちの設定したコースは机上の計画である。教師
コース作り情報交換板
が現地へ出向いて,コース通りに行動した。その結果,
これなら大丈夫だという自信を持つことができた。下見は
3回実施した。また,この結果から当日の立ち番教師の位置や移動の仕方に
ついても決定した。
また,子どもたちだけでは難しいと思われる箇所については,下見結果か
ら「グループ行動の手引き」を作成し,子どもたちへ配布した。
② 救急病院の調査
子どもたちが行動中に病気やけがをすることは十分考えられる。その場合
に備え,最寄りの救急医療機関の所在地を調べ,万一に備えた。
③ 交番の所在地調査と警備の依頼
安全に活動できるように各見学地の最寄り交番を調べ,警備を依頼した。
④ 同行の旅行業者と宿舎への依頼
いっそうの安全確保ため,添乗員には職員同様の体制に入っていただい
た。
また,宿舎の方には宿舎を本部とすること,地理に詳しいことから緊急の
場合駆けつけていただくことの2点を依頼し,快諾を得た。
⑤ 手荷物の発送
新幹線で京都駅到着後グループ活動に入る。洗面具や着替えなどの入った
旅行バッグは不要である。旅行バッグは前日に宅配便で宿舎に送ることにし
た。
⑥ 保健衛生に関する依頼
宿舎や食事をとる場所などの保健衛生について,府衛生部に依頼した。
⑦ 児童と職員への緊急時の対応について
児童,職員双方に緊急時の対応の仕方について万全を期した。
(8)しおりづくり
ここまで調べてきたことをグループごとでまとめ,個人別にしおりを作った。
グループごとに目的が異なるため,個性あるしおりができあがった。T男のしお
りは,友禅染の歴史,現在の様子,完成までの工程,そして友禅文化会館と古代
友禅苑への経路がしっかりとまとめられていた。
(9)修学旅行当日の子どもたちの動き
T男のグループは10時15分京都駅発である。まず地下鉄で五条まで行き,
そこから市バスに乗り換えて中の橋五条へ。ついで徒歩で友禅文化会館へ行く。
T男が見つけたコースである。五条で市バスに乗り換える点が難しいが,地上へ
あがったらT男がすぐにバス停を見つけた。そして73系統のバスが通ることを
確認し,難なく乗車することができた。また,文化会館への道のりも,追究の結
果を生かして予定時刻前に到着することができた。ここでは染め体験はせず,友
禅染の概要について映画や見学で理解を深める。
昼食を取り,次の目的地の古代友禅苑へ向かった。古代友禅苑では,染め体験
をした。7枚の型紙を驚きの目で見ていたが,どの子もみんな楽しそうに友禅染
を体験した。
世界文化遺産コースの方は,バスに乗り間違えるなど,いろいろハプニングが
あったようだ。しかし本部に連絡が入ることもなく,自力で解決し,全員予定時
刻までに宿舎へもどってくることができた。
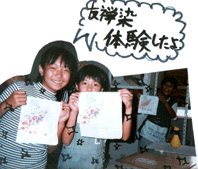 |
 |
| 友禅染を体験(プライバシー保護のため画像処理してあります) |
バス停を見つけて一安心(プライバシー保護のため画像処理してあります) |
(10)旅行を終えて
終了後は,以下の活動に取り組み,やりっ放しにならないよう配慮した。これ
らの活動の中心は表現活動である。自分たちの感動や発見を全校の友だち,そし
て保護者,職員に伝えるために取り組んだ。
できあがった作品は授業参観に合わせて展示したり,他学年の子も見ることが
できる場所へ展示するなど配慮した。特に5年生の子たちが来年のことを考えて
か,盛んに見に来ていたのが印象的であった。
旅行後の活動 1 写真コンクール
グループごとで制作。4つ切り画用紙に写真を貼り,コメントをつける。
2 パンフレットづくり
各自で制作。入場券や写真を貼り,コメントをつける。8つ切り画用紙を使用。
3 修学旅行報告会
授業参観で実施。グループごとに旅行の報告をする。
4 紀行文の執筆
各自で取り組む。文集としてまとめる。
4 本実践の価値
〇 漠然としたとらえであったものが,調べれば調べるほど疑問が湧いてくる。例えば,
T男のように,単なる染め物でしかなかった友禅染が「なるほど,だから値段が高いん
だ」という意識に変容してくる。
一歩進んでは立ち止まり,発見とともに新たな疑問が生まれてくる,という繰り返し
こそ子どもの知的好奇心を揺さぶるものである。
〇 コースや時刻調べは,調べた結果をはっきりとした行動,言い換えれば体験に移すこ
とができる。そういった意味から子どもの追究意欲をいやが上にも盛り上げた。
また実際の体験の場でも緊張感が伴い,グループみんなで全力を尽くしたという姿勢
が目立った。
〇 「先生,今日総合の時間ないの」という声がよく聞かれた。学ぶ楽しさを味わうこと
のできた子たちの声である。調べて分かり,そしてまた分からなくなる。子どもたちに
とっては今までにない魅力ある学習であった。
T男の旅行後の作文
みんなどきどきだった。それはちゃんと行けるかどうかだ。
「ちゃんと行けるかなあ」
S君も心配していた。
「あれだけ調べたんだから,大丈夫だよ」
とぼくは言った。しかし京都駅を出たとたん,7人だけになって急に心細くなった。でも,行くし
かないと,気合いを入れた。 ~ 中 略 ~
五条のバス停もすぐ見つかったし,73系統のバスがここを通ることもすぐ分かった。
「ここに73と書いてあるよ」
とKさんが見つけた。すべて調べたとおりだ。自信がわいてきた。 ~ 中 略 ~
中の橋五条から友禅文化会館までの道も調べたとおりだった。花屋町通りの交差点もすぐ見つか
った。
友禅文化会館に着いた。Sくんが,
「あっ,S先生がいる」
と大声で言った。みんなS先生の顔を見たら,緊張していたせいか,急に力が抜けてしまった。
~ 中 略 ~
全部調べたとおりに行けたのでとてもうれしかった。まったく知らないことだったけど,調べた
らちゃんと分かった。
バスを乗り間違えグループのI子の作文
「あっ,バス来てる。早く乗ろう」
H君が言ったけど,そのバスは92系統。本当なら204か205に乗るはずだ。
「ちがうよ,92だよ,これ」
と私が言ったとたんドアが閉まった。でもまた開けてくれた。H君があまりに乗れ乗れと言うから,
つい乗ってしまった。
一つバス停に止まった。私たちは心配になって運転手さんに聞いてみた。
「すみません,このバス金閣寺道通りますか」
「金閣寺行くの?これじゃ行けないね。ここで降りて,204か205が来たら乗りなさい」
と言って教えてくださった。私たちは運転手さんのおかげで無事金閣寺に着くことができた。運転手
さん,本当にありがとうございました。
それからも何度か道を聞いたりしたけど,京都の人はとても親切に教えてくださった。京都の人っ
て,みんな親切な人ばかりだった。 ~ 後 略 ~
Ⅵ まとめと今後の課題
学ぶ楽しさを味わってもらおうと2年間取り組んできた。子どもたちにとって新鮮な出会い
の「ケナフ」と,興味湧く「手づくり修学旅行」を設定することで,ねらいの達成を図った。
K男をはじめ,ほとんどの子どもたちが今までになく意欲的に取り組んだ。実践を振り返り,
その要因を次のように考える。
成 功 の 要 因
① ケナフと修学旅行が子どもたちの興味・関心にマッチし,実践意欲が盛り上がったこと。
② ケナフも修学旅行も内包する問題が多様で,子どもたちの知的好奇心を満たしたこと。
③ 切り込む間口が広く,子どもたちそれぞれの個性に応じた追究に耐えられたこと。
④ インターネットをはじめ,多様な情報収集につとめたこと。
⑤ ケナフも修学旅行も,追究した結果を直接体験することができたこと。
⑥ 子どもたちが直接行動する場面に関わる決断の機会を与えたこと。
多くの成果を上げることができたが,今後も以下の点についてさらに実践を重ねたい。
今後の課題
① 学校の学習場面だけでなく,日常の生活場面でいっそう生きて働く力として身につくように
させたい。
② 生涯「学ぶことは楽しい」という意識を育て,生涯教育の基礎づくりとしたい。
③ インターネットをはじめ,情報の収集能力そして処理能力をさらに高めたい。
④ 共に学び,共に高めあうという意識をさらに高めたい。
⑤ 環境を大切にし,自分のできることから始めていこうとする気持ちを一層高めたい。





 T男のみならず,ほとんどの子どもたちが資料をとっかえ
T男のみならず,ほとんどの子どもたちが資料をとっかえ