レベル別曲リスト
● VIOLONCELLO REPERTOIRE SELECTED SYLLABUS(英語)
● 英国王立音楽検定(ABRSM)グレード別課題曲リスト(英語)
曲選びの参考になります
● VIOLONCELLO REPERTOIRE SELECTED SYLLABUS(英語)
● 英国王立音楽検定(ABRSM)グレード別課題曲リスト(英語)
曲選びの参考になります
ウェルナーは日本でもっとも有名なチェロ教則本かもしれません。賛否両論のある教則本。 この教則本を途中でギブアップして中断してしまう人は多いです。第3ポジションに入ったあたりで辞めてしまう かたが多いように思います。
ここで辞めてもなんとかなる。アマオケで弾けるところだけ弾いて、弾けない個所は弾き真似をして、 とりあえず楽しむことはできる。でもソロを楽しむにはちょっと難しいかも。
ウェルナー前半はわりとすっと進む事ができるけど、 後半は意外と難しく、まるでロッククライミングのようです。 非常に内容が濃くて、難しいテクニックがさらっと何の解説もなく出てくる。 一週間で一段しか進まないこともあります。 ここはチェロ人生最初にして最大の難所だったように思う。 練習曲の解説が少ないので、今練習しているものが何のための練習なのか、 しっかり目的意識をもって練習しないと、途中で意味が分からなくなって挫折してしまう。 独学はかなりの意志の強さが必要。 この教則本をきっちり最後までやれたなら、きっとチェロはかなり上達できると思います。
ドッツァウアー: 113の練習曲 第1巻
ドッツァウアー: 113の練習曲 第2巻
ドッツァウアー: 113の練習曲 第3巻
ウェルナー後半から平行してドッツアー1巻をやりました。ウェルナーがなかなか進まない時期に、 これがストレス解消&癒しとなりました。 二巻をやりおえれば、曲を自力である程度練習できるようになります。自分で指使いやボウイングを 考えることができるようになってきます。アマチュアオーケストラに入団したいのならば、 ドッツァー二巻までは終わらせたいところです。3巻は「なんなのこれ!」って感じです。 3巻をやると、オーケストラのチェロパートの楽譜がちょっと可愛く見えてきます。
Duport(デュポア デュポール)はアでもなくルでもなく、ノドの奥でうがいするみたいな感じの音。 このエチュード、とても綺麗な曲で、演奏会のアンコールで弾く方もいるよう。 非常に難しい。でも綺麗な曲だから報われます。 私は先生から「結局Duporとはお友達になれなかったね」と言われましたっけ(泣) いつかソナタやコンチェルトを弾けるようになりたいならば、ぜひここまでは進んで欲しいです。
Popper High school of cello playing
え~っと、難しいっていうか、弾きにくいっていうか、 なんでこんなに意地悪なことばかりするの!(怒)となるエチュード。 私・・・・嫌いでした(泣)
嫌いでしたが、再び練習を始めました。技術の維持のためにです。約10年ぶりに弾くと、 以前よりは余裕をもって弾くことができる自分がいて、ちょっと嬉しかったです。 この教則本はウォーミングアップとして弾いてるプロの方もいます。 ークラスで受講したジェレミ先生に、 特に6番、9番、13番を暗譜して、 ウォーミングアップとしていつも弾くように勧められましたが・・弾いてない(汗)
このエチュードを制覇すれば、ドボコンやエルガーはとりあえずは弾けるでしょう。 音楽的に弾けるかどうかは、また別・・・・
聞かれたのですが・・・実はやったことがない。すみません、分かりません。
これをやっている方が多いようです。私はやったことがありません。試しに本を購入して中身を見てみました。 ドッツアーやデュポールやその他のエチュードがセレクトされている?ドッツァーは元の楽譜と見比べると違っていたりする。 難易度が前から順番にだんだん難しくなる・・・・というわけではなく、簡単だったり、突然難しくなったり、 ちょっと使い辛いと感じたのですが、どうなんでしょう。 ドッツァー、デュポール、ポッパーとやった方が難易度もだんだんに上がって行って効率良いような気が・・・・。
共著:マーティン・スタンツェライト・竹内千寿
24 lessons 芸術的チェロ演奏のための実践的メソッド Vol.1
24 lessons 芸術的チェロ演奏のための実践的メソッド Vol.2
ウェルナーを途中で挫折してしまう大人(大学生以上)のアマチュアの方を多く見てきました。やはりウェルナーはつまらない・・・(--) そこで、練習の目的を明確にし、基礎もきちんとやりつつ、並行して曲(二重奏も楽しめる)も楽しめ、 スマホでお手本も見られるエチュードを作りました。(すみません宣伝ですね)
大人になってから趣味でチェロを始めた方などを対象としています。 先生についてレッスンを受けるのが一番ですが、 地方都市ではレッスンに通うのが困難な場合もありますので、 自習できるよう、全曲インターネットで視聴できるようになっています。
一巻12レッスンで構成されています。 1レッスンを2週間-1か月ほど練習することを想定。 半年から一年で一冊が終わるように構成されています。 (人によって進度の差はあります)。
二巻レッスン13~24では各レッスンで有名なチェロの小品を仕上げていきます。 曲を演奏するために必要な基礎テクニックを先に練習し、 そのあと曲を練習するという構成になっています。
チェロを独学で始められた方は、早く曲を弾きたくて、基礎の練習もそこそこに曲を練習してしまう。 基礎が無いので早い時期に行き詰ってしまいます。そこでこの教則本では基礎を練習しつつ、 それと並行して曲も楽しめるように工夫しました。
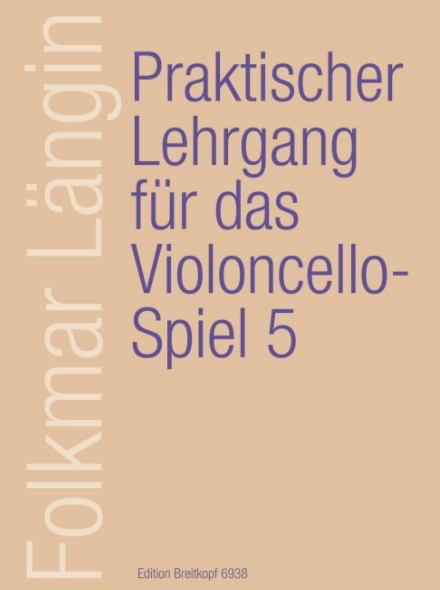
この教則本は全5巻で構成されています。 この本の5巻を使って親指を使う練習をしました。練習曲として有名曲の中の親指を使用する箇所を集めて使っています。 非常に楽しめます。私も将来、このコンチェルトが弾けるようになるかも?!とワクワクさせてくれるエチュードです。 アカデミアミュージックで 購入可能。
チェロで第九に参加してみたい方へ。 ベートーベンの第九のチェロパートはかなり難しいです。しかもページ数も多い! 難しい箇所の指使いや練習方法を解説しています。
Cello Scales & Arpeggios, ABRSM Grades 1-5
Cello Scales & Arpeggios, ABRSM Grades 6-8
初めて音階を練習する人は、この本がとっつきやすいと思います。 グレード1から8までのレベルに分けれていて、 難易度順に音階が並んでいますので、最初から順番に練習していくだけです。 グレード1は第1ポジションだけで弾ける1オクターブの音階、その次は拡張のある音階、 ポジション移動のある音階・・・と、だんだん難しくなっていきます。 2巻最後のグレード8は、英国の音楽大学の入試レベルです。
上級者向けかもしれません。初心者がいきなりこれを見ると卒倒するかも。 初級の方はこれをやる前に、前述の英国王立音楽検定 スケールとアルペジオ1巻&2巻をやった方が良いと感じます。 その後でこのレーブやデイリーエクセサイズをやれば、すんなりと入っていけると思います。 レッスンではやらなくなったけれど、 今もウォーミングアップとして音階やアルペジョの練習をしています。
左指の運動、ポジション移動の練習が沢山のっています。音階、右手のボーイング、左手の練習と、これ一冊で 一通りの練習ができます。オールインワンな基礎練習の教則本。
Sevcik for Cello - Opus.2 part1
Opus 2はpart1~6まであるようですが、私はpart1とpart4を練習しました。 7年近くレッスンで見てもらいました。
初級者の頃は右手の練習の重要性を理解する事が出来ませんでした。 練習もサボり気味でした。でも今になって焦っております。
右手の練習は庭のお手入れのようなものです。 庭は綺麗に整備しても、しばらくすると雑草がはえてきたり、 木の枝が伸び放題になって荒れてしまいます。 庭を美しく保つには定期的なお手入れが必要です。 右手も放っておくと、すぐに変な癖がついてしまいます。 ですから練習の初めに開放弦を練習して整えてやります。
チェロを始めて30年近くなった今も、 練習の初めには開放弦の練習をしています。
上級になってくると、右手が非常に重要になってきます。 速弾きなどは左手に注意が向きがちですが、 右手がどんくさくて速く弾けない事が多いです。
特にアマチュアは左手ばかり練習して、右手の練習はしないことが多い。 でも右手はとても重要。できれば先生について練習するのが良いと思います。 もし独学でやるならば、youtubeに参考になる動画が多数アップされています。 それらを参考にし、自分の演奏姿を撮影して、それを見ながら練習することをお勧めします。
チェロ ブートキャンプ1音階初級
チェロ ブートキャンプ2音階中級
チェロ ブートキャンプ3音階上級
チェロ ブートキャンプ4 弓のトレーニング 初級~中級
チェロ ブートキャンプ5 左手のテクニック 初級~中級
1巻~3巻は音階を練習するための教則本。4巻は弓のトレーニングです。
特に4巻は、初めて右手のボウイングを練習する初級者に最適です。この4巻をやってから上述の
Sevcik for Cello - Opus 2: School of Bowing Techniqueをやるとスムーズに練習できると思います。
いきなりセブシックは厳しいかも。
楽譜は読まずに、ダンスのように指の動きを丸覚えしようとする方もいますが、 楽譜が読めた方が断然楽で練習もはかどります。急がば回れです。ぜひ楽譜を読む練習をしてみてください。
子供時代から楽器をやっていた人が、なぜ楽譜が読めるのか?それは下記のようなワークブックを子供時代に 地道にやっているからです。大人の方も「子供向けだ」と馬鹿にせず、ぜひ取り組んでみてください。
チェロはヘ音記号です。ヘ音記号がぜんぜん読めない!という方は、 へおんきごうのワーク・ブック1 と へおんきごうのワーク・ブック2 をお薦めします。 amazonなどでは売っておらず、発見が遅れました(^^;;出版社のウェブサイトで販売されています。 こういったワークブックを子供のころに私もやりました。 子供向けだとバカにせず、やってみると良いと思います。手を動かすことで 記憶に定着します。全二巻
やさしく学べる子供の楽典 では 楽譜の決まりを学べます。楽譜の読み方を学べます。 子供向けだと馬鹿にせずやってみてください。
ハ音記号スタディ ~12のトレーニング~
チェロは上級になってくると、ヘ音記号の他に、テノール記号やト音記号も読まなければなりません。
この本はテノール記号の他にアルト記号やソプラノ記号の読み方を練習し、最終的には音程を
視覚的、相対的にとらえるようになるための訓練の本です。ト音記号とヘ音記号は
すらすら読めることが前提の本です。上級者に良いかも。
私も現在これを使用中。(ハ音記号とはアルト記号、テノール記号、ソプラノ記号の総称)
AURAL TRAINING IN PRACTICE Grade1-3
AURAL TRAINING IN PRACTICE Grade4-5
AURAL TRAINING IN PRACTICE Grade6-8
これは英国王立音楽検定の耳のトレーニングの本です。英語が読めるのでしたらお勧めします。 GRADES1-3(初級)、GRADES 4-5(中級)、 GRADES 6-8(上級)の三種類が出版されています。CD付き。 これは指導者用のテキストなのですが、自分で独学でやりたい人にも向いています。 教えるコツ、聞き取りのコツがいろいろと書いてあります。英国王立音楽検定の試験対策として、私はこれを使って自分で独学しました。 問題集としてSpecimen Aural Testsもグレード別に販売されています。
「私、全然リズム感も音感も無くて…」と心配そうな生徒さんには、この本の一巻を使用しています。 どれくらいの音感やリズム感を持っているのか確認できます。そして聞き取る練習に利用しています。 簡単なメロディーを聴きながら手拍子をする練習や、3拍子と4拍子を聴き分ける練習があります。 上級になると終止形の聴き分け、和声進行の聴き取り、転調の聞き取りなどの課題も出てきます。
日本でよく見かける本は、初級者のうちはハ長調ばかり。ところがこの本は最初からいろんな調性が出てきます。 相対音感を身につけさせる目的かなあ?と思いました。音の機能を聴きとらせる感じ(トニック、ドミナント、サブドミナントなど)。
たぶん日本でいちばん広まっているソルフェージュの本かな?私も子供のころ、これでソルフェージュの練習 を行いました。ソルフェージュができると、楽譜をみながら歌ったり、頭の中で音を鳴らすことができ、 楽器練習がはかどります。
リズムを読み取るのが苦手な方に最適かと
リズム練習とソルフェージュ1
リズム練習とソルフェージュ2
リズム練習とソルフェージュ3
アマオケなどで演奏を楽しみたい方は、さらに「リズム練習とソルフェージュ」 も練習するといいでしょう。 アマオケは膨大な量の楽譜をできるだけ早く譜読みする必要があります。初見力が必要です。 初見には「瞬時に音を読み取る」「瞬時にリズムを読み取る」の二つの能力が必要。 音を読み取る練習は、単語カードを使ってやると早く習得できました。単語カードの表に音符、裏にドとかレと音名を書いておく。 音符を見てパッと何の音か言えるように練習します。 リズムをパッと把握する練習はこの本を使いました。毎晩布団の中で手を叩いて、 リズムの練習を行い、初見力を鍛えました。3巻のリズム練習を3周やりました。
楽典は「やさしく学べる音楽理論」。和声は赤本を使いましたが、、、今は売られているのかどうか?。 楽典や和声の基礎知識があるだけで、音楽のとらえ方がより深くなると思います。 へ~~~!と目から鱗な体験ます。メロディーに簡単な伴奏も付けられるようになります。
赤本のあと、「新しい和声──理論と聴感覚の統合 」を使って勉強しました。これは現在芸大で使われている和声の本です。 赤本の和声の表記は日本独自のものらしいです。新しい和声は国際標準の表記です。かなり難しい。分厚い。独学は厳しいかも。
![]()
チェロ・レポート
社会人になってからチェロを習い始めて、いったいどこまで上達できるのか?
30年におよぶ体を張った 実験の記録!
Amazon,storesで販売中!
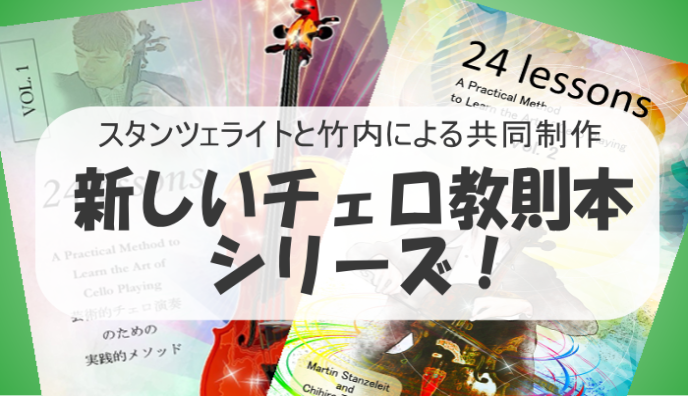
スタンツェライトとTakapiこと竹内の共同制作による教則本のショップです。