緋に燃ゆる彼方

|
群衆のただ中、ひるがえった髪の色彩に目を奪われた。 それは御庭番衆御頭、四乃森蒼紫が、河原に打ち上げられた私兵二人の死体を、何の感慨も抱かずに眺めていた最中の出来事だった。 同時に、向こうもこちらに気が付いた。風になびく、常よりもずっと濃い赤を刷く髪の間から、現れたきつい眼差しが蒼紫を睨め付ける。 明らかに警戒の色を宿した瞳が、ひどく懐かしい気がする。あの呪わしい無血開城より十年が過ぎ、残った部下たちの行く末以外にはたいして興味を持たずに生きてきた蒼紫にとって、これはひさかたぶりの衝撃だった。 一見するだけなら小柄で、女にも見まごうほどの優しい顔立ちをしている。なのに、その身体から一瞬立ち昇った、激しい闘気はいったいどうだ。気の弱い者なら晒されただけで、平静ではいられなくなるような、確固たる闘う意志。そして、炎のようなそれは一瞬の後には掻き消され、見返す視線の冷たさが、無言の圧力を感じさせる。 「……べし見」 隣に立つ部下に呼びかけた。 「お前の鼻を潰した剣客、確か赤毛で左頬に十字傷があるといったな」 「はい……え、あ」 その言葉でやっと奴の存在に気付いたべし見の、騒ぎ立てる様子の中には微かな脅えがある。残った四人の内では最も非力とはいえ、まがりなりにも江戸城本丸を警護した御庭番衆に属する者を、無意識な恐怖で縛るとは……。 ──胸に感嘆が沸き上がる。それまでただの興味でしかなかった相手への感情が、蒼紫の内で徐々に変質を遂げていく……これが始まりだった。 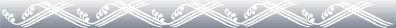
江戸城御庭番衆の創立は、八代将軍吉宗の御代まで溯る。 それまで、系列はあれどもバラバラに使われていた細作は、組織化され情報機関として、また将軍家の影の守護として位置づけられた。他の隠密と区別され、御庭番衆という身分を得たとも言える。 だが、細作は細作──影に生き、影に死すという立場までが変わった訳ではない。有事あれば真っ先に切り捨てられる運命……だからこそ、能力が、真の実力だけが重視される集団へと、変化していった事は想像に難くない。 四乃森蒼紫はそんな集団の頭領の息子として生まれ、その父を幕末の動乱期に亡くした。当時、蒼紫は数えで十四歳。やっと子供時代を脱するか否か、という齢だった。 実力だけが重視される御庭番衆において、御頭は世襲の地位ではない。にもかかわらず、蒼紫はわりとすんなりそれを手に入れた。周りに存在した幾人かの他候補も、彼が御庭番衆の頭領たる事を認めたのだ。彼の持つカリスマと実力に屈して。 ──しかし、もしかしたらそれは、真実ではなかったのかもしれない。 時代は討幕へと向かっていた。十四代将軍徳川家茂が病死した四カ月後、孝明天皇が崩御した。一貫して、佐幕寄りの意見をとり続けたこの天皇の死因については、砒素系の毒による中毒だったという根強い噂がある。 新たに即位した明治天皇は若干十五歳。そして将軍家を継いだ一橋慶喜は、幼少の頃より聡明のきこえも高かったが、それ故に計算高い人物でもあった。日本を外国勢力から守り、徳川家の権力や財産をでき得る限り確保する──そのために必要とあれば、自らの誇りも家臣の命もあっさり犠牲にできるような。 これを、情報機関でもある御庭番衆の幹部たちが、知らぬ訳はない。考えようによっては、面倒が降りかかるであろう御頭の地位を、要領の悪い子供に押し付けたともいえる。 無論、そんな人間ばかりではないのも理解っている。最後まで蒼紫の盾として、忠実に支えてくれた元御頭候補もいる。だが、情報獲得のために各地へ散っていた者たちには、鳥羽伏見の戦いを境にして帰城しない数が圧倒的に増え、無血開城となった時点で、城に残った人数は元の半数にも少し足りなかった。 それ故に、最後まで残った者たちの進退は蒼紫の責任となった。ある程度、身分を認められた数人以外の俸禄を打ち切られた時も、あらゆる手を打ち御庭番衆全員を養った。そしていつまでもこのままではいけないと、なんとか新たな職を見つけてやり、第二の人生を踏み出させた。 そうして数年がゆき過ぎ、殆どの部下を送り出した時になって、蒼紫は初めて気付いたのだ。胸の奥にぽっかりと口を開けた、虚無という名の暗闇に。 仕えるべき主君を失い、身分を失い、細作としての戒律を捨て、生まれて初めて得た自由──もう、誰の命令も受ける必要はなく、好きなようにやりたい事をやればいい。なのに、何をやっていいか判らない。やるべき事がみつからない。自分の望みさえもが見えてこない。 生きている気がしない。 何を見ても、聞いても、しても……ひたすらに空しく、時間だけが砂のようにさらさらと、合わせた手の隙間からこぼれていくばかりだった。 そんな蒼紫を、ギリギリの所で絶望から救ったのは、最後に残った四人の部下だった。 異形異相の者、一つの技しか持たぬ者、裏切りの経歴を持つ者──平和な暮らしに馴染めず、戦う事だけしかできず、なおかつ仕官が許されない四人のために、御庭番衆御頭であり続けなければならないという責任の重みが、蒼紫の消滅しかかった足元を固めてくれたのだ。 故に蒼紫は、自分一人だけをという仕官話を全部断った。この四人も一緒に雇ってもらえる──御庭番衆としての己らが求められているところへ行こうと決めた。 しかし、それはなかなか難儀な事でもあった。 明治になってから、社会は激しく移り変わっていっている。御庭番衆としては、尊王派がつくった明治政府にはいろいろ文句もないではないが、あえて倒してやるほどに幕府に未練も愛着もない。かといって政府のために働くのも、どうも釈然としない。 つまり政治がらみでなく、蒼紫を含めた五人をまとめて雇えるだけの、財力がある者を探すしかなかった。 自然、相手は商人、実業家──それもただの用心棒であきたらず、情報集団としての御庭番衆を欲しがるようなといえば、よほどひどい恨みを買っているか、裏の業界の危ない商品にでも手を出している人間だけに限られる。だが、そんな人間の屑どもに寄ってくる輩など、たいした能力を持つ訳でもなく、江戸城を守り切った御庭番衆の敵ではない。 そうして、より危険な闘争が待つ仕事への何度かのくら替えを繰り返し、御庭番衆はこんなところまで来たのだ。 「──緋村剣心……人斬り抜刀斎か。予想外の大物だったな」 般若からの報告を一通り聞き終えて、蒼紫はぼそりと呟いた。これまで闘った用心棒や刺客にも維新志士くずれの者はいなくもなかったが、皆たいした腕の持ち主ではなかった。志士といってもピンからキリまである。官軍が有利とみてからのにわか志士も多い。 だが、奴は違う。幕末の京都、壬生狼と恐れられた新撰組と、互角に渡り合った筋金入りの長州派志士。古流剣術の一派である飛天御剣流、その抜刀術を極めたとして、志士名にそれを留める伝説の人斬り……。 「伝説になるほどの働きをし、それでいて維新後官職につかなかった変わり種。今の身分は流浪人……見た目ほど気楽なものでもないようですが」 「有名税ってやつだろう」 この町の神谷道場の食客となって一カ月余り──剣客警官に始まって、ヤクザに菱卍愚連隊、比留間兄弟に相楽左之助、それに鵜堂刃衛……既に五指に余る相手と、騒ぎを起こしている。 「絡まれやすいわりには、本人の生活志向はいたって穏健のようです。掃除洗濯飯炊きと、まめまめしく家事をこなしてます。重い買い物は嫌いみたいですな」 「だが、そんな生活をしながらも腕は鈍っていないと?」 「はい」 般若の声が微かに笑みを刷く。 「ついこの間、奴と闘った浮浪人斬り鵜堂刃衛……あれもまた、二階堂平法を極めた達人。その刃衛、死因は自刃ですが、その前に右腕の肘を砕かれて筋を断ち切られてます。逆刃刀で叩き潰したんだとしたら、恐ろしい破壊力です。あのままでも、十分に人を殺せます」 「そうか……」 それまでまったく表情のなかった蒼紫の口元が、ほんの少し笑みの形に歪められた。 「……大物だ、十年ぶりの」 幕府の終焉と共に、存在の意義を失った御庭番衆。新たなる意義を見いだそうにも、恨むべき主君は既に力を失い、倒す甲斐さえないものに堕していた。 闘う事しか知らない四人のために。この胸に巣喰った暗闇を埋めるために。 欲しかったのは強大な敵だ。 無敵伝説を誇るあの男を、初めて倒すという栄光を手に入れる。だが、 「──観柳は臆病だ。伝説の人斬り抜刀斎の事を知ったら、どんな手を使っても直接の闘争は避けるだろう」 「しかし抜刀斎は、けっこう激情家です」 いくら闘いたくとも、それが許されない状況を思い描いて眉をしかめた蒼紫に、般若の飄々とした声が呼びかける。元の疑問と直接はつながらない台詞に、微かに首を傾げ振り向いた。 「たとえ穏便に済ませたい観柳が、高荷恵を脅迫して無理矢理戻らせたとしても、緋村がそれを黙って見過ごすとは思えません」 元々、新型阿片“蜘蛛の巣”の製造方法を唯一知るあの娘が、逃げ込んだ先に偶然緋村がいた事から話が始まったのだ。助けるだけの縁も理由もない通りすがりだった上に、明らかに法に触れる阿片絡みの事件だということも半ば承知して、奴は高荷恵を守った。初めの関わりは巻き込まれたにしても、その後の展開は人がよいという言葉で片付けていいものか、結構疑問を感じる。 だが、般若はあっさりそれを肯定した。 「かなり面倒見の良い男です。一度庇った相手は見捨てないでしょう」 「面倒が降りかかるだけなのにか」 「損得で動くような人物なら、こんなところにいません」 命懸けで時代を駆け抜けた維新志士も、今では政府の要職に就いて安穏としている者が多い。中でも薩摩、長州、土佐、三藩の出身者はそれらの席の大半を占め、文字通りこの日本を動かし権力の旨みを享受している。 緋村剣心は、官軍の勝利が確実となった鳥羽伏見の戦いを境に姿を消し、その後も再三の着任要請を拒否し続けている。己の剣一本で世直しをしようとしたあの頃のまま、市井の人々を守るための流浪人となって。 「いまだに……心は維新志士のまま、という訳だ」 呟きと共に漏らされた苦笑は、微妙な歪みを経て自嘲に変わった。緋村と、未だ確固たる“現在”を見いだせない己を、引き比べるように。 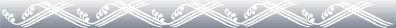
「観柳!!」 窓の下から飛んできた常になく鋭い緋村の声に、武田観柳は青ざめた。神谷道場を焼き打ちすると脅迫し、高荷恵を自分から戻って来させたのは、この男との直接の対決を避けるためだった。だが、彼女が戻ってまだ一刻も経たないというのに、既に私兵団のほとんどは昏倒し、問題の緋村はもう目の前にいる。 「……年貢の納め時だ。武田観柳」 平静な声が言葉を紡ぐ。 「恵殿を連れて、降りて来い」 見上げる瞳の色が琥珀色に澄み、感情が表れていないからこそ、ぞっとするほど恐ろしい。 しかし青ざめて硬直していた観柳は、その食いしばった口から呻くような声を漏らし始めた。徐々にそれは形を成し、いつしか哄笑へと変わっていく。状況にあまりに似合わぬ笑い声に、緋村たち三人が眉をひそめるのが見える。 追い詰められ、一本切れた人間独特のかん高い声で、観柳は叫んだ。 「……す、素晴らしい! 私兵団五十人余りを、息もつかぬ間に倒すとは。流石は伝説の人斬り、緋村抜刀斎!!」 満面に冷や汗を垂らしながら、芝居がかった様子で両手をぱぁんと高く打ち鳴らす。恐怖に強ばった口元を無理矢理吊り上げ、必死に笑顔を保ちながら、観柳は最も有効だと信じている解決案を声高に示した。 「見事です、その剣腕気に入りましたよ。御庭番衆に加え、あなたが私の下に入ってくれれば、まさに最強!! 私兵団五十人分の報酬を払いましょう。どうです。是非とも私の用心棒に!!」 ──大間抜けである。 緋村は損得を無視して野に下り、己の良心と倫理だけに従って、剣は振るうが人殺しをしないただの流浪人たろうとしている男だ。今はもう剣一本では世を変えられない事、そして激動の時代を先導する政治が、どんなに腐りやすいものかという事を百も承知の上で。 理想だけでは国は造れない。だが、それでもなお、幕末の理想のまま維新を生きようとしている。金銭など奴の眼中にはない。 「──降りて来るのか、来ないのか、どっちなんだ?」 発した声の温度が下がった分、小柄な体から発される怒りが倍増したようだった。一歩一歩ゆっくりと、こちらへ近づいてくる。 「で…では百人分!」 緋村の歩みは止まらない。 「に…二百!!」 「──わからん奴だな」 蒼紫は溜め息をついた。緋村に対する御庭番衆の調査結果は、焦った観柳の脳裏から飛んでしまったらしい。何のために事前調査をしたのだか。 「金で懐柔しようったって無駄だ。緋村抜刀斎は、損得で動く男ではないと言ったろう」 呆れたように呟いた蒼紫の言葉を聞くなり、観柳は引っ繰り返った声で絶叫した。 「わかった、私の負けだ。降参する! 高荷恵は手放そう!!」 流石に、意外そうな表情を浮かべた三人の歩みが止まる。そこへ畳み掛けるように言い募った。 「だが、一時間だけ時間をくれ! こちらの方でも何かと準備が要る。一時間後に必ず送り届ける。頼む、この場はおとなしく退いてくれ!!」 「いきなり何を言い出すかと思えば、そんなの信用できるか。このタコ!」 それまで、緋村の横で比較的静かにしていた相楽左之助が、眦を吊り上げて噛み付く。これまでの観柳のやり様から見れば、この疑惑はもっともな事である。大方、その一時間の間に高荷恵を拷問して、問題の新型阿片、蜘蛛の巣の製造法を聞き出せばいいとでも思っているのだろう。無論緋村らに、こんな戯言を容れる義理はない。しかし、 「剣心!」 いきなり背を向け門の方へと戻り始めた緋村に、周りのほうが驚いた。 「ちょっと待て。お人好しにも程があるぞ!! オイ!」 弥彦とかいう小僧が、食ってかかるのを無視して進んだ緋村は、玄関脇のガス燈のすぐ下でピタリと歩を止めた。それまで己に都合のいい事だけを考え、引き攣ったような笑みを浮かべていた観柳の顔に、疑問がよぎる。 いつのまにか、緋村の腰にある逆刃刀の鯉口が切られている。流れるように鞘走った。 逆刃が一閃した。 驚愕した一同の目前、台座の部分をすっぱり断切されたガス燈が、宙を飛ぶ。叩き切られた勢いのまま半分台座を付けた灯籠は、硬直した観柳の立つ窓のすぐ横に激突した。衝撃で窓ガラス一面に亀裂が走る。 緋村抜刀斎が吼えた。 「一時間以内にそこへ行く!! 心して待ってろ、観柳!!」 今度こそ観柳を竦み上がらせたその台詞に、蒼紫はクスリと笑みを漏らした。報告にあった通り、普段の呑気で穏健な姿からは想像もつかない。 「姑息な奸計は火に油……か。成程、確かに激情家だ」 激怒したまま自分のところまで来るとも思えないが、それならそれでいいかもしれない。怒りの後で冷静になった奴は、きっとより手強くなっている。それでこそ闘う甲斐があるというものだ。 そんな夢想を遮って、脅えきった観柳が振り返る。 「お…御頭、御庭番衆の配──」 「もう済ませた」 意味もなく広いこの屋敷だが、下から攻め上がる道は一本しかない。その道筋、玄関を入ってすぐのところに般若が、突き当たった階段に式尉が待ち構えている。さらにその先、この部屋の正面、展望室へと続く階段があるダンスホールで、蒼紫は奴を待つ。狭い空間での闘いは御庭番衆の十八番だが、あのホールくらいの広さがあるなら、大技も出せてなおよいだろう。 あの男とどう闘うか──脳裏にいろいろ作戦を浮かべて楽しんでいる蒼紫に向かって、青いのを通り越してどす黒い顔色の観柳が、ヒステリックに叫んだ。 「いいか、べし見やひょっとこの様な役立たずのクズは、もう真っ平だぞ! 高い給金に見合うだけの働きをせん奴は、この私が許さんからな!!」 居丈高に言い放たれたその台詞に、蒼紫の眉根が寄る。元々、派手な闘いを期待してここにいるだけの蒼紫達御庭番衆は、観柳など何とも思っていない。その職業倫理は、金を貰った分は守ってやるか、ぐらいの気分でしかないのだ。 それに向かって、すっかり主人のつもりで怒鳴りつけた観柳は、急に変わった蒼紫の形相にギョッとした。これまで、ほとんど表情を変えた事のない蒼紫の身体を、闘気にも似た憤怒が押し包んでいる。 「『この私が許さん』とは、どういう事だ?」 ずいっと一歩迫って低く呟く。 「勘違いするなよ。御庭番衆を束ねるのは、お前じゃない」 襟首をつかんで目の高さまで持ち上げ、引き攣る観柳をうっそりと恫喝した。 「……俺の御庭番衆だ。何人たりとも、卑下する事は許さん」 反駁できずに震えるだけの身体をドサリと床に落とし、平静に戻った声で続ける。 「説明の続きだ。連中の狙いは高荷恵──この女は、三階の展望室に幽閉しておく。お前は余計な口出しをせず、ここで金勘定でもしていろ」 ──どうせそれしかできないのだから。しばらくの間、迫り来る恐怖を味わうがよかろう。分相応に、高荷恵を諦めて逃げ出していれば、こんな事にはならなかった。有り得る未来として、こういう事態の可能性も報告してあったのだから。 (もっとも──こいつの欲深な頭では、そんな選択をする訳もなかったがな) 観柳は、抜刀斎として名高いあの男が、何の縁もない女を庇ってここまでするとは、かけらも思わなかったのだろう。全てを金で換算する、自分の基準で相手を測った。その報いがきただけだ。 蒼紫は長身を屈めると、意識をなくして床に横たわる高荷恵を抱き起こす。そのままそっと立ち上がり、女を抱いたまま観柳を残して部屋を出た。振り返る事など、思いつきもしなかった。 |
