|
狭い展望室の中、カラカラと軽い音をたてて、短刀は床を転がった。瞬時、不思議そうな表情を浮かべた高荷恵に、それを取るよう蒼紫は目線で促す。 「──お前の短刀だ。返しておく」 神谷道場を庇うためにおとなしくこの館に戻ったように見えた女は、反す刀で観柳に切りつけた。戻るくらいなら死んだ方がマシだと。もうこれ以上、罪を重ねて生きる気がしないと呟いて。 幾度となく、他人を巻き込んでも自分だけは、なんとか逃げ延びようとしていた女と、同一人物とは思えない。たった十日間を過ごした神谷道場での日々が、それほどまでに安らかなものだったのか。それともそれ故に、脅しをかけられた時の絶望が深かったというのか……。 全てを承知の上で、緋村に対するオトリとしての役割を、彼女に振ったのは蒼紫自身だ。時代に翻弄された“高荷”の娘──彼女の根底にある優しさが、世話になった人々の危機を見過ごせないだろう事を予測して。 だがそんな思いは一切気取らせず、蒼紫は表情を変えずに淡々と言葉を続けた。 「ヘタに希望は持たない方がいい、奴等はここまで辿り着けはしない。一時間後にお前を待つのは、観柳の拷問……苦痛の生か、安息の死か。せめて自分で望む方を選べ」 苦痛の生の後に来るのも、また死である事を考えると、ただ死に方を選ぶだけだ。しかし、それでも選べるだけましというものだと、蒼紫は思う。自分の意志の届かぬどこかで全てが決定され、事態がどうにもならなくなってからしか手が出せない──蒼紫のこれまでの人生はその連続だった。 だからこそ、もう真に求めるものしか見たくはない。そのためなら、全てのものを犠牲にできる。 そう、哀れな娘を見殺しにする事など造作もない。 呟いた心の内が、微かに痛んだが無視をする。ただ、訳が理解らないという顔をした女に、説明だけはしてやった。 「観柳が欲しがる阿片や金など、俺達にはどうでもいい事だ。御庭番衆が求めているのは“闘い”そのもの……阿片密売でキナ臭くなりそうな此処に闘いを求めて来たが、お前のおかげで至高の敵と巡り会えた。それはその礼だ」 今のうちにこの短刀で自害すれば、観柳の手に蜘蛛の巣の製造法を渡す事もない。つまり、これ以上犠牲者を出す事もなくなる。それは死んでいく彼女の、唯一の救いとなるだろう。 「……お前の幸薄い人生には、少し同情する。だが」 これ以上、どうする事もできない。また、どうしようとも思わない。戦に家族を失い、故郷をなくし、頼りとした人に裏切られ、欲深な人間にいいように利用されて、今また何もできずに死んでいくだけの、無力で哀れな女……。 「──それもどうでもいい事だ」 乾いた声音でそう呟き、蒼紫は扉を閉めた。その音は、自分で思っていたよりもずっと大きく、そして空虚に響いた。 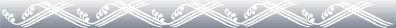
開け放しておいた正面の扉から、緋村剣心は現れた。脇に弥彦を連れている。相楽左之助の姿はない。 長い赤髪の間から覗く、落ち着いた茶の瞳がじっと蒼紫を見詰める。静かな声が問うた。 「……お互い顔は見知っているが、話すのは初めて──でご ざるな…」 「ああ…」 顔だとて、たった一度互いに見交わしただけだ。だがそれは、忘れようもない衝撃と印象を残してくれた。待ち望んだ相手、だ。 緋村はまっすぐに蒼紫を見詰め、先程観柳を怒鳴りつけたのとは別人のような、穏やかな声で語りかけてきた。 「般若にも言った台詞でござるが──拙者、不要の闘争は出来れば避けたいでござる。そこをどいて、観柳と恵殿の居場所を教えてはくれぬか」 「……そう言われて、般若は道をあけたか?」 刹那、ピクリと身体を震わせた相手に、蒼紫は微笑んだ。感情のこもらない平坦な声で続ける。 「──あけなかっただろう」 この場に達するまでの道筋に、置いた護りは二人。階段の方から聞こえる打撃音からすると、式尉はこの場にいない相楽、喧嘩屋斬左と戦っている。そして般若は、もう倒されている。般若は蒼紫を決して裏切らない。持ち場を死守しろとの命令を無視して、緋村たちを通す筈がないのだ。 己を倒すだけの能力がなければ、蒼紫がわざわざ闘う価値はない──そう言って般若本人が一番手を志願した。真に強い者と闘いたいという、蒼紫の希望に応じて。 バサリと上着を跳ね上げ、蒼紫は腰のものを指し示した。 「二人の居場所は、その逆刃刀で問え。俺は、これで答えてやろう」 ──動乱の幕末から、ずっと蒼紫と共にある小太刀。江戸城に忍び込んでくる敵の隠密を、数え切れないほどこれで倒した。何よりも信用のおける相棒だ。 小太刀を脇差と勘違いして、馬鹿にされたと騒ぐ小僧を下がらせて、緋村は苦笑しつつこちらへ向き直った。 「確かにあれが脇差なら、手こずらずに済むでござるけどな」「“小太刀”の特性を、知ってはいるようだな」 小太刀を、スラリと鞘から抜き出して水平に構える。 刀と脇差の中間の長さを持つ小太刀は、刀より短い分攻撃力に劣るが、軽量で小回りが利くだけ非常に防御力が高い。つまり盾として使用可能なのだ。 緋村の表情が険しくなる。微かな呟きが漏れた。 「……攻めに回るのは、かなりの不利か…」 「そうか」 ポツリと返した蒼紫の台詞に、緋村の瞳が眇められる。 「ならばこちらから攻めてやろう」 「な……?」 見開かれた瞳の茶が薄くなる。言葉と同時に床を踏み締め、蒼紫は一瞬のうちに緋村の眼前に迫った。右手の小太刀を振り下ろした先に、逆刃刀の刀身が繰り出されるのは予定のうちだ。ギンッと硬い音をたてて刀同士がぶつかった一瞬後、振り上げた右足が緋村の左頬に命中した。 そう、小太刀は決定的な武器ではない。小太刀を盾とし、拳や蹴りで攻撃する。狭い室内空間での闘いが多い、御庭番衆独特の戦闘方法だ。 衝撃で吹き飛ぶ奴を追いながら、呼吸を溜める。体勢を立て直されないうちに、更に激しい連続拳打を加えた。 反動でこちらも少し後方まで飛ばされる。軽く着地した蒼紫のすぐ後、緋村もまた足場を確保し攻撃を加えてきた。 素早い振り下ろしをことごとく小太刀で受け止め、最後の一撃を跳ね上げ向き直った。 緋村もまた、こちらを伺っている。小さな独白が、広いホールにこだました。 「──小太刀で鉄壁の防御をしき、般若と同じ拳法で攻撃する戦闘の型か……」 一見、たいしたダメージを受けていなさそうな緋村の肩が、微かに揺らぐ。それを見届けて、蒼紫は無造作に応えた。 「……一つ、間違えているな。般若に、拳法を教えたのはこの俺──」 肩の揺れが酷くなり、刹那驚いたように目を見開いた緋村が、ガクリと膝をつきそうになる。今頃になって、先程の連打が効いてきたのだ。当たっていないように見えたそれも、着実に食い込んでいた訳だ。 「師弟の拳では、速さも重さも全く違う。同じだと思ってい るとそうなる」 静かに事実を告げ、蒼紫は緋村を見詰めた。 「抜刀斎。お前に私怨はないが、最強の維新志士としてここで死んでもらうぞ……」 その言葉に、緋村の瞳が訝しげに細められる。 「……どうやら、お主たちは観柳のために闘っているのでは、ないようでござるな」 「あたり前だ。あんなカス、どうなろうと知った事ではない」 「では……江戸城御庭番衆として、維新で潰れた徳川幕府のためか?」 無感動に言い捨てた蒼紫に、緋村はもう一度問うた。しかしどこか不可解そうなそれは、緋村自身もその言葉を信じていない事を示している。蒼紫の瞳に、痛みに似た色が微かに浮かんで消えた。 徳川幕府──あの時までそれは、蒼紫にとって絶対的な権威を誇る主君だったのだ。 強ければいいという基準の、寄せ集めの色彩が濃くなった幕末の御庭番衆の中で、創立時から続く蒼紫の家系は、代々御頭を輩出してきた名門である。影役とはいえ、先祖代々伝わる職務に対する義務感と忠誠心は、余人に想像出来ないほど強いものであった。 だが、それらが一気に瓦解して、蒼紫は心の拠り所を失った。当然の常識として教え込まれてきた全てが、まったく意 味をなさなくなった。 ことさら平静に、感情を交えない言葉が綴られる。 「──お前も志士なら知っていよう。鳥羽伏見の戦いでの、徳川慶喜の振るまいくらいは……」 「ああ……」 当時、敵側であった緋村にも具合の悪そうな顔をさせてしまうほど、最後の将軍慶喜の所業は見苦しかった。 大政奉還の後、更に所領の全てを返上しろと迫る薩長に対し、会津に押し切られる形で京に進攻する事になった徳川軍に、同行するのを慶喜は拒んだ。それだけならまだしも、鳥羽伏見で味方の軍勢が必死に戦っている間、夜陰に紛れて本営である大阪城を抜け出し、軍艦で江戸に帰還してしまったのだ。万を越える兵を見捨てて。 江戸帰還の後も、帰城せずに上野寛永寺に閉じこもり、ただひたすらに恭順の意を示し続けた。それにより全権を任された勝海舟と、西郷隆盛の会談において江戸決戦は回避され、江戸城は無血開城を迎えた。 「そして御庭番衆は、闘う事なく幕末を終えた……」 ──いろいろな意見がある。 慶喜の行動にも、様々な理由があるのだろう。しかし、彼を信じて戦い続けた兵にとって、命を懸けて江戸城を守った御庭番衆にとって、それがいったい何の意味を持つというのか。理解っているのは、ただ一つ──遠いところで初めから負けが決められて、自らの存在意義である“闘い”をもさせてもらえずに、時代を終えざるをえなかった事。 全ての努力が、無になったという事だけなのだ。 「腑抜けの徳川など、どうでもいい。ただ──闘えなかった事だけが俺達の無念。歴史の流れに“もしも”はないが、あの時江戸決戦があれば……俺達が闘っていれば」 平静を保っていた声が、微かに揺れた。 「維新の勝利は幕府のものだった筈だ」 戦力的には、負ける筈のない戦いだった。いくら最新型の銃や砲があったとて、物量は幕府側が圧倒的に勝っていた。本来なら、海軍兵力も比べようのないものであり、なにより幕府には情報戦の最大の切り札である諜報部隊、御庭番衆がいた。 物量や情報で立ち勝っても、気持ちの上で負けてしまえば同じ事。全てを諦めたとき、戦いの勝敗を待たずに慶喜はもう負けていたのだ。 今でも時々夢を見る。 もしあの時、慶喜が諦めなかったら。あの鳥羽伏見の戦いの時、慶喜たちが逃げ出したりしなかったら。更に決戦が行われていれば、江戸の町を焼き払う予定だった。そしてその隙に、官軍中枢の志士どもを殺す事が出来ていたら。 「だが、今更そんなコトをやっても何の意味もない。今、意味があるのは幕末維新における真の“最強”……それは、御庭番衆だったという『証』だ」 『証』と言いながら、それさえもまた本来己のためではない。全てがどうでもいいという虚無感を、悟らせないように一息で言い切った蒼紫を、緋村の視線が鋭く射貫いた。 静かな声で緋村は言う。 「あの時代……維新志士か幕府侍かを問わず、多くの者が闘いに身を投じた」 表情を変えずにその言葉を聞いている蒼紫に、緋村は微かな苛立ちを見せた。むっとしたように、心持ち声が低くなる。 「敵対はした。だが、どちらが正しくどちらが間違っているではなく──ただ、この国の未来を憂い、人々の安息と幸福のために命を懸けた」 人々の安息と幸福のためと言うなら、幕府はなくなって正解だ。いまだ混乱のただ中ではあるが、封建的身分制度がなくなった事は最終的には多くの人々のためになるだろう。 頭ではそう理解るのだ。しかしそれもまた、幻のように実感出来ない。心が凍ってしまっているかのようだ。 「……平然と、町を焼き払うと言うお前にあるのは、血みどろでいて氷の様に冷たい闘争心だけ」 そう断じた緋村の言葉に、蒼紫はうっすらと微笑う。犠牲になる者たちを気遣えず、ただ緋村と闘いたいというこれは、やはり闘争心なのだろうか。今までの者たちとは格の違う、真に強い敵に対しての。 いや、何かが違う気がする。 刹那、心のうちで首を傾げた蒼紫に向かって、緋村の堅い声が響いた。 「維新志士としても、流浪人としても──お前を黙って見過ごす訳にいかぬ……!」 ──考え込んでいる暇はなさそうだった。 |

