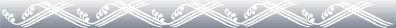
緋村達が去った後、蒼紫は一人立ち尽くしていた。あまりにたて続いた衝撃に、なにもかもがぼんやりと霞んで見える。 蒼紫は頭の隅で自問した。一体……何故、ここに立っているのか。すると、周りの様子が少しだけ目に入った。 機関砲にずたずたにされた御庭番衆四人の死体。それらの死に顔は一様に、安らかとは言い難い。蒼紫は、それぞれの瞼をそっと閉じてやった。 一歩、また一歩と足を踏み出すごとに、激痛が走り意識が明瞭になっていく。それと共に後悔の気持ちが沸き上がってきた。 部下たちは、蒼紫にとって守るべき相手だった。精神的には守られることも多々あったが、こんなふうに死なせるために、この十年連れ歩いてきた訳じゃない。己が死ぬ事についてたいした感慨を持たない、生きる意志の希薄な蒼紫を守るために、何故彼らが死ななければならないのか。 そこまでして守る何が、この身にあろうというのか。 理不尽な思いに苛まれる蒼紫の耳に、微かな警笛が届いた。警官隊が、この騒ぎに気が付いてやってきたのだ。 蒼紫はもう一度、並んだ死体を眺め考えた。彼らに守られた命だ。ここでむざむざと警察に捕まる訳にはいかない。脱出路から一人逃げるのは簡単だが、ここに彼らを残して行きたくはない。一遍に全員を運び出すのは無理だ。そして、もう時間がなかった。 部屋の片隅に落ちていた、血に塗れた愛用の小太刀を蒼紫は手に取る。息がないのを確認してから、それを般若の首にそっと当てた。 「……すまない…」 吐息のような呟きが、微かに震えた。 しかし、ためらっている暇はない。蒼紫は覚悟を決めると、今までの人生の半分以上を共にしてきた朋友の首に、小太刀の刃を振り下ろした。 真っ赤な血が辺り一面に飛び散り、更に蒼紫の心を絶望に染めた。 観柳の隠し通路を抜けると、そこは屋敷裏の林だった。目の前に高い外塀がそびえている。その向こうはもう外だ。 蒼紫は両手に下げた部下達の首をしっかり持ち直すと、足の傷を無視して跳躍した。塀に飛び乗って上を見上げれば、空が夜明けの光に白んできている。その中で、星々が最期の瞬きを見せている。 背後からバタバタと近づく足音に、蒼紫は屋敷の方を振り返った。かなりの人数の警官隊に交じって、緋村たちの姿もある。 捕まえろと叫びかけた警察署長を、一発どついて相楽が声を上げた。なにげない調子の中に微かな痛みを交ぜて。 「──おめーのせいじゃねぇよ。あの回転式機関砲はどうしようもねぇ。御庭番衆はおめーを生かすために死んだ。けど、決して恨んだりしちゃいねーよ」 いっそ、恨んでくれるような連中だったら、こんなにも辛くはないのだろう。もう、御庭番衆の守るべき徳川の江戸城はない。御庭番衆とて、御頭に従う理由など本当はない。なのに、自らの命に代えても蒼紫を守ろうとしてくれた。こんな不甲斐ない、情けない御頭を。 だからこそ、自分自身が許せない。守られた命を大切にしなくてはという義務感はあるが、同時になにもかもがどうでもいいような気もするのだ。 全てを失いたった一人になった蒼紫が、生きていたとて何になるのだろう。 すっかり虚無感に取りつかれ暗くなっている蒼紫に、緋村がふと声を掛けた。 「蒼紫」 大きな瞳に決意を浮かべ、硬い表情で緋村は言葉を綴る。 「お主が、もしどうしても自分を許せぬのなら、今一度拙者と闘え。闘って、拙者を倒して、“最強”の二文字を四人の墓前に添えてやれ」 ──死ぬな、というのか。たとえ、緋村を殺す事だけを生き甲斐にしても……とりあえず生きろと、狙われる羽目になるお前が言うのか。 仲間を失った痛み、自分のせいで助かる筈の相手を死なせてしまった悲しみ、それでも生きていなければいけない苦しみ──見返した緋村の瞳の中に、同じ苦悩があるのを蒼紫は見た。 最前線を駆け、伝説になるほど人を斬った抜刀斎も、それらに耐えて明治を生きているのか……。 人斬りも御庭番衆も、今の時代には無用の長物であるべきだ。だが、それでは生きていけない。新たなる自分を見いだし、それに順応しなければならない。 でも、もう少しの間だけ。 いつの日か、救いを見いだせるようになるまでの間だけ、必要とする支えを緋村に求めても、いいのだろうか。 人斬りとしての緋村は幕末の象徴だ。闘う事を禁じられた蒼紫と違って、まさしく混乱の血煙の中をくぐり抜けて来た。だが、それを押し殺し流浪人として生きる今、蒼紫に手を差し伸べようとする。見詰めたくも語りたくもないだろう、人斬りの技量を餌にしてまで。 緋村の背後に、緋色の焔が立ち昇る。江戸城を燃やすかもしれなかった幕末の炎……何かを変えていこうとする、意志の力。 ここまでされて、応えない訳にはいかないだろう。蒼紫は、真正面から緋村を見返し、淡々と言葉を綴った。 「……抜刀斎。俺がおまえを殺すまで、誰にも殺されるなよ」 約束したのだから。 おまえは、いつでも挑戦して来いと言った。自らを倒せと、その華を四人の墓前に添えてやれと。 だから、おまえは俺のものだ。 他の誰にも倒せない最強の維新志士──緋村剣心、抜刀斎。俺だけが、いつかお前を倒すのだから。 緋村の瞳に浮かんだ安心したような笑みを認めて、蒼紫は踵を返した。あわてて追いかけてくる警官隊を捲きながら、蒼紫の口元にも、初めて微笑みが浮かび上がってきていた。 |

