|
意識の回復は唐突だった。無様に床に寝そべった己を発見し、蒼紫は必死で身体を起こした。息が切れる。かといって、深く息を吸おうとすると、喉に激痛が走る。 ゼイゼイと荒い息をつく蒼紫の耳に、緋村の声が届いた。 「たいした回復力でござるな」 「──俺は、落ちていたのか……」 「まあ、十秒ほどでござるがな」 これまで酷く勘に触ったどこか気遣うような言葉が、たいして気にならない。完璧に負けたためか。それともあれが同情であって同情でないと、理解ったような気がするからか。 それでも敢えて聞いてみる。 「何故、とどめを刺さない?」 微かに頬を歪め、緋村は言った。 「今の拙者は流浪人、人斬りではござらん。だが、とどめを刺さずともどちらに軍配が上がったか、お前程の男ならわかるでござろう」 ……それは、確認するまでもない。もし、緋村が蒼紫を殺す気でいたら、蒼紫はとっくの昔に死んでいる。苦笑を含んだ般若の言葉が、頭の隅でこだました。 (……あのままでも、十分人を殺せます) つまりこれでもまだ、緋村は手加減しているのだ。最後には殺す気はなくなっていたとはいえ、こちらは全力で立ち向かった。負けを認めざるを得ない。 小さく溜め息をついた蒼紫に、緋村は平静な声で問うた。 「蒼紫、一つ答えろ。お前は影役とはいえ、御庭番衆御頭ほどの大役を務めた男。維新の折、仕官の話は一つや二つではなかったろう。なのに何故、このような用心棒まがいの真似をした? 自分の力量を生かす場が欲しかったのなら、他に選べる場はあったはず……」 「……仕官の話なら山程あったさ……」 素直にそんな言葉が出た。これは部下達には言えない。言ったら最後、奴らが萎縮してしまうのが理解っているから。 「だが、それは全て俺一人だけのこと──他の御庭番衆には、誰一人として仕官話はなかった……」 いい奴らなのだ。確かに見かけはごついし、御面相は凄まじい、また経歴もよくない。しかし、蒼紫の一番辛かった時期を、彼らは忠実に支えてくれた。彼らがいなければ、己の虚無感に食い潰されて、蒼紫は生きていなかっただろう。 「その部下達を見捨てて、御頭の俺が仕官など──何故できる?」 呟くようにそう漏らした蒼紫を、見詰める緋村の瞳に痛みにも似た色が過る。 「最後の将軍、徳川慶喜のような醜い裏切りは、俺は御免だ」 「徳川慶喜は──」 半ば駄々をこねるように言い放たれた蒼紫の台詞にも、緋村は誠実に対しようとする。だがあえて、それを遮るように言葉をついだ。 「わかっているさ。慶喜がした絶対恭順──あれは戦争をヘタに長引かせて、国力を低下させないための高度な政治判断だというのだろう」 理屈は理解る。あのまま幕末の内乱が続いていれば、混乱に乗じた諸外国によって国土は分断され、日本という国は消滅していたのかもしれない。慶喜は大きな視野を持ち、国を守るために敢えて、自らの全てを捨ててしまった──それもまた一つの見方である。 しかし、納得できるかどうかは別の問題だ。 裏切られ見捨てられた者の側から見れば、保身にみちたただ醜いだけの行動でしかない。だから……。 「だがそれでも、俺は御免だ」 吐き捨てるように繰り返される言葉に、返す言葉を失って黙り込んだ緋村へと視線を向ける。淡々とまるで他人事のように、蒼紫は言った。 「──とどめを刺せ」 緋村になら、殺されてやってもいい。胸の奥の虚無感を抱えたまま、生きていくより楽かもしれない。こんな情けない敵の事まで気遣ってしまう、人殺しを嫌がる優しい元人斬りのために、脅しのような言葉を続けた。 「でなくばこの先、俺は何度でもお前を狙うぞ」 「構わぬ。気の済むまで挑んでこい」 表情を凍らせ、それでも緋村は云う。 「だが他の者を巻き込む闘いは、決して許さぬでござるよ」 自分だけが狙われるのなら……それで蒼紫の気が済むならいいと言うのか? 今回、彼の負った怪我は半端なものではない。一歩間違えば、本当に死んでいたかもしれない重傷だ。その加害者に向かって──まったく、どこまで人が良いのやら……。 その時だった。 「──あれ程大口を叩いておきながら、敗北とは情けないですね! 四乃森蒼紫!!」 いきなり開け放たれた正面の扉の向こうに、観柳が立っていた。横には何やら白い布を被せた大きな荷物がある。 状況が理解っているのかいないのか、観柳はにいっと口元を歪めて偉そうに言い放った。 「あんまりあなた達がだらだら話し込んでいるから、待ち切れなくて出て来てしまいましたよ」 「観柳……」 呟く蒼紫の向かいで、緋村の気配が冷たく凍りついたようになる。低く言葉が綴られた。 「丁度いい。探す手間が省けたでござる」 「大した自信ですねェ。だが!」 下品な笑い声を上げながら、観柳は傍らの荷物から白布を勢いよく剥ぎ取る。その中から現れたのは……。 「これを目の当たりにしても、その自信保てますかねェ!!」 「なんだありゃ……」 「まさか……」 回転式機関砲──黒光りする鋼鉄の銃身。後の機関銃の原型になったという無骨なその姿は、通常の銃とは比べ物にならないくらい不吉に大きい。蒼紫も実物は初めて見るが、その恐るべき威力は重々承知している。 観柳が自慢げに哄笑した。 「そうです、回転式機関砲!! しかもこれはまだ、世界のどの軍にも紹介されていない、最新型の横流し品。幕末の時のものなどとは比べ物にならない高性能。じっくりと試しましょう!」 血走った観柳の目と真っすぐこちらへ向けられた銃口に、蒼紫の全身がそそけだった。 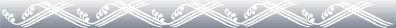
広い空間に、弾丸の発射される激音が際限なく響き渡る。嬲るように足元ばかりを狙ってくるため、とりあえず走り回っていれば当たりはしないが、それも観柳の気まぐれが続いている間だけだ。 機関砲の恐ろしい所は、精密な射撃の腕が要らない事だ。素人が適当に振り回しても、それなりに的に当たる。 「すごいでしょう!! なんと弾丸を一分間に二百発も発射するんですよ!!」 自慢そうに叫んだ観柳の目は、既に一本切れていってしまっている者独特の、鈍い血の色を刷いている。抜刀斎への恐怖と、蒼紫たち御庭番衆への一挙に沸き上がった不信感が、この小心者のまともな判断力を突き崩してしまったのか。 いくら何でもこんな銃声を立て続けたら、周りの住宅地へも音が漏れてしまう。漏れるどころか、響き渡っているかもしれない。それはつまり、警察への通報を意味し、程なく警官隊が踏み込んできたとておかしくない。 そんな状況で、蒼紫と緋村を殺したとて何の意味があるだろう。観柳は恐怖と興奮に血が上り、商売も何も全て忘れてしまっているとしか思えない。 大体何でこんな所に、こんな兵器があるのだ!? 「立ち止まったら当ててしまいますよォ!!」 「観柳! 貴様、どうしてそんな兵器を!」 引っ繰り返った声で、楽しそうに絶叫する観柳に、蒼紫は必死で叫び返した。 観柳の血相が変わった。 「“様”をつけんか、無礼者めェッ!!」 銃口がまともに、蒼紫の足を捕らえた。 瞬時、足が燃えるように熱くなり、動けなくなった。 「蒼紫!」 そのまま、受け身も取れずに床に崩折れた蒼紫に、緋村の必死の声が投げられる。だが、こちらに来る訳にはいかない。一カ所にまとまったら、標的になるだけだ。 「全く……ま、いいでしょう。一服ついでに、答えてあげま しょうか」 やっと上半身を起こした蒼紫に向かって、観柳は偉そうにほざいた。成り金なケースから葉巻を一本取り出し、気障臭く火を付ける。 「私はねェ、阿片の密売人なんてちっぽけな商人で終わるつもりなど、初めからないんですよ。私の究極の野望は、この世で最も儲かる商人になる事」 「まさか……」 ただの小心者だと思っていた。女を脅して阿片の密造をさせ、小金を稼いで満足するタイプの情けない男だと。まさか、そこまで本格的に悪辣だとは、不覚にも気が付かなかった。 「死の商人、つまり武器商人です」 口の端を吊り上げた観柳は、得意そうにこれからの計画を語る。新型阿片で資金を儲け、最新型回転式機関砲を目玉にその筋に殴り込む。これで押しも押されぬ大商人のできあがりだと。 本来、口外する筈のないそんな計画をばらしたからには、この場にいる人間全て、生かしてこの部屋から出す気はないという事だろう。 緋村の目が怒りに細められる。低く呟かれた疑問は、軽蔑に満ちていた。 「……貴様、そこまでして──他人の人生と命を喰い物にしてまで、金を手にしたいでござるか……」 「ま、馬の耳に念仏でしょうけどね」 己と正反対の倫理観に基づいて生きる緋村を、観柳は馬鹿にするように見やった。 「緋村抜刀斎、おまえがその超人的な強さを得るまでに、どのくらいの年月と代償を払ったか──それは決して並大抵のものでは、なかった筈でしょう? だが、しかし!」 指し示された回転式機関砲が、不気味な輝きを放つ。 「金があればそれ以上の力でさえ、容易く手に入れられる。一瞬にして! 何の代償も払わず!!」 狂気に取り憑かれた顔で、観柳は絶叫した。 「金! まさにこれこそ力の証。真の最強はこの私、死ね!!」 観柳の両手が、引き金に掛かる。まず、動けない蒼紫が狙われるだろう。今まで、たいして生きていたいとも思わなかったが、こんなアホにみっともなく殺されるのは業腹だ。蒼紫は怒りの余り、ギリギリと奥歯を噛み締めた。 と、その時。 「今だ! 抜刀斎、走れ!」 いきなり響き渡った般若の声に、緋村が反応した。撹乱するように走り抜ける緋村と、すれ違い様に式尉が飛び込んで来た。標的を絞れずにうろたえた観柳は、案の定安易な方向へ流れる。 「……ええい、まずは動けない蒼紫から!」 「そうはいかせねぇ!」 銃口が蒼紫を正面に捕らえた瞬間、式尉の身体が立ち塞がった。轟音をたてて発射された弾丸の全てが、式尉の広い背中に吸い込まれてゆく。 蒼紫は目を見開いて、文字通り身体を張って己を守った部下を見詰めていた。何故だ。いったい、何が起こった!? 「式…」 「……おっと…そんな顔すんなよ。あんたらしくもねェ……」 急速に血の気を失い、死相が現れてきたその顔で、式尉は微笑って見せた。 「……俺は結構満足してんだ。薬を使ってまで手にした自慢の筋肉が、弾丸にも勝る盾にだってなるって、証明でき…て……ね」 「式尉……」 目の前で、庇うように盾になったままこと切れた式尉を、蒼紫は呆然と見上げた。要領の悪い元薩摩藩隠密──あの時、江戸城に忍び込まず蒼紫と出会わなかったなら、こんな死に方はしなかっただろうか。 「ぬかせェ! そんな肉塊、二百連発で粉々に──」 口から泡を飛ばして叫んだ観柳の前に、今度はひょっとこが走り込んだ。ひょっとこの腹は油袋だ。下手に銃を使うと、撃った人間も火達磨になる。それを見越しての、無謀な突撃だった。 機関砲の弾丸が、無防備な頭に集中した。 「ひょっとこ!!」 叫んだ蒼紫の前で、致命傷を受けたひょっとこが前のめりに倒れていく。そして、その背に負われた樽の中から、べし見がいきなり飛び出した。捨て身の姿勢で、攻撃を仕掛ける。 「くらえ、毒殺螺旋──」 「うわああ……っ!!」 パニックに陥った観柳が、やけくそで巻散らかした弾の殆どが、べし見の小柄な体にめり込んでいく。弾丸の勢いに吹き飛ばされて、べし見は背中から床に落下した。 息も絶え絶えの小さな呟きが漏れた。 「お…御頭、やっぱりダメでした……すんません、最期の最…期まで……俺達役立た…ず…で……」 ──悪夢のようだった。 江戸城が陥ちたあの時、ある意味で蒼紫は死んだのだ。だが、部下達がいたから……御頭であったからこそ、ここまで生き延びてきた。蒼紫には、彼らを守り幸せにする責任がある。そう思うことで、蒼紫もまた守られてきた。 なのに、これはいったい何だ? 目の前で死んでいく彼らのために、何もすることができない。 呆然と動くことも忘れてしまったような蒼紫の耳に、悲鳴のような緋村の叫びが響いた。 「待て、般若!!」 同時に飛び込んできた般若が、蒼紫を庇うように回り込む。その隙に、緋村は床に落ちた逆刃刀へと駆け寄った。 獰猛な表情を浮かべた観柳が、向かってくる般若に照準を合わせる。そのまま轟音と共に全ての弾が、般若の全身に叩きつけられる。誰よりも身直にいた大切な友の身体から、吹き出した血が空間を赤く染めて流れるのを、蒼紫は黙って見ているしかなかった。 逆刃刀を拾い上げた緋村が、観柳に向き直る。その瞳は氷のように冷たいものと、怒りの炎を同時に宿していた。 不気味な哄笑を続けながら、観柳が叫ぶ。 「そこまでだ、抜刀斎!! 化け物面を囮にして斬り込もうとは非情の人斬りらしい手段だが、結局どいつもこいつもみーんな無駄死にって訳だ」 言いながら、またも引き金に手を掛けようとする観柳の様子に、蒼紫は焦って緋村を見詰めた。このままだと緋村まで、御庭番衆の二の舞いになってしまう。それだけは何としても阻止したかった。 力の入らない足を叱咤して、無理矢理立ち上がる。だが、そこまでだった。上げた視線の先に見えたのは、今にも引かれようとしている機関砲の引き金──。 「死ねェ!!」 叫びと共に、観柳の手に力が込められた。だが、 弾が出なかった。 「手元をよく見ろ」 緋村はぼそりと呟いた。 「一分間に二百発も発射するんだ。後先を考えずに撃ちまくれば直ぐさま──」 ……弾丸切れを起こすという訳だ。図らずも、四人が囮となり弾を無駄遣いさせた事が、緋村を、そして蒼紫を救った。 「無駄死になんかではない。御庭番衆四人の命が、貴様の回転式機関砲に勝ったんだ」 平静に続けられる言葉に、緋村の怒りが感じられる。言葉と共に観柳に歩み寄り、小柄な身体から怒気を発して、緋村抜刀斎が絶叫した。 「命乞いなら貴様の好きな、お金様に頼んでみろ!!」 振るわれた逆刃刀の打撃に、観柳はぼろ屑のように吹き飛んだ。 |

