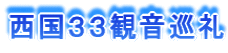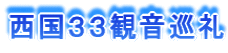第21番札所 穴太寺
その3
天台宗
<本尊 聖観世音菩薩>
開創 705年
宿を出て、バスで穴太口へ。ここから、鄙びた参道を歩いたお陰で、お年寄りと挨拶をしながら参ることが出来た。境内では、女性の方が3人ほどで清掃をしていた。写真を撮りながら、少し言葉を交わした。大きく、静かな、雰囲気の好いお寺だった。ゆっくりと、そして、朝一番の心を込めてお参りした。納経は、女性の方が書いてくれた。
伽藍の紅葉が映えて美しい
第22番札所 総持寺
高野山真言宗
<本尊 千手十一面観世音菩薩>
開創 886年
阪急の駅から町の中を歩いて数分、忽然と階段、、大きな門が現れる。入り口は狭そうなのに、中に入ると、意外に広い。しかも、街中にしては、静かな佇まいである。お経もゆったりと読誦できた。
堂宇はこじんまりとしていて、仁王門や、本堂とはアンバランスな感じを与える。
第23番札所 勝尾寺(弥勒寺)
高野山真言宗
<本尊 十一面千手観世音菩薩>
開創 727年
千里中央から満員バスに揺られること50分、大きな寺領を誇る門前に着く。横の土産物屋から入山料を払って境内に入る。現代風に造園を重ねているようだ。朱塗りが新しいお堂と、鎌倉時代の建物とが渾然一体をなしている。
門前で経を読むような気分で、読誦する。何となくなじめぬまま、寺を後にする羽目に。
左から、大師堂、閻魔堂、不動堂
左から、開山堂、荒神堂、二階堂
上中、鎮守堂、上、多宝塔
左薬師堂
第24番札所 中山寺
真言宗中山寺派総本山
<本尊 十一面観世音菩薩>
開創 604年
阪急中山駅を降りると、もうすぐに大きな山門が待っている。門に比べて、前に道幅が狭く、カメラの枠に収まりきれない程だ。参拝客の中には、赤ちゃんを抱いた人たちもいて、関西での、安産祈願のお寺として人気の高さを感じる。前庭も広く、ゆったりとしているので、それなりにお参りが出来る。広い割りに、お堂を巡ってお参りするという雰囲気が少ないのは何故だろうか。
↑大師堂と大師像↓
左から、開山堂、護摩堂、閻魔堂、薬師堂
第25番札所 清水寺
天台宗
<十一面千手観世音菩薩>
開創 627年
レンタカーで門前の大きな駐車場まで行けた。暖かな日差しを浴びて、朱塗りが映えていた。先着の夫婦が記念撮影中だった。最近まで、災害に遭うことが多かったお寺で、再建中の堂宇も多いようだ。既に再建されているお堂は立派なものが多い。
根本中堂
地蔵堂
薬師堂
おかげの井戸(こん浄水)
第26番札所 一乗寺
天台宗
<本尊 聖観世音菩薩>
開創 649年
朝、レンタカーで姫路を発った。一条寺はかなり田舎に入ったところにあった。未だ、少し空気がひんやりする中を、きれいに紅葉したかえでの傍から石段を登る。現在、本堂は改築中で、常行堂を仮本堂にしている。そのため、薄暗く、狭い所での読誦となった。古刹と言うイメージぴったりの山寺だった。
経堂
見事な三重塔
第27番札所 圓教寺
天台宗
<本尊 六臂如意輪観世音菩薩>
開創 966年
東京から新幹線で昼前に姫路に到着。すぐにバスで書写山へと向かう。ケーブルを降りゲートを通ると、既に山内という感じである。未だすぐには本堂に至らず、長い坂を登る。途中33観音像が点々と立っている。本堂、摩尼殿は舞台造りで、大変立派だ。広い伽藍には、映画で有名になった三殿や、いろいろな建造物があり、全てをゆっくりと見ていると、結構時間がかかった。
三元堂・大講堂、食堂、常行堂
左から、開山堂、金剛堂、寿量院
第28番札所 成相寺
高野山真言宗
<本尊 聖観世音菩薩>
開創 704年
宮津からバスでケーブル下まで。ケーブルを上がったところから山内バスで、山門を通り過ぎて階段下まで行く。ここにあるのが「撞かずの鐘」石段を登ると本堂だ。観光客もいるが邪魔にはならない。遠く、高いところまで来たものだという感慨あり。鄙びたお寺である。
巡礼堂
鉄湯船、撞かずの鐘、五重塔
第29番札所 松尾寺
真言宗醍醐派
<本尊 馬頭観世音菩薩>
開創 708年
東舞鶴から、隣の松尾寺まで電車で行き、そこから歩いた。暫くは平坦な田舎道を歩くが、舗装道路に出た途端上り坂が始まり終わることがなかった。お寺の石段の下に着くと、ホッとして暫くは立ち止まっていた。石段を登ると、手洗いがあり、更に少しだけ段があった。非常に印象的な本堂が正面にあり、ここで一人じっくり読経をした。朝の空気が爽やかで、山寺の情緒が染み込んでいた。本堂以外には、目立つお堂もなく、内陣にあった和尚の書いた文を1枚買い求めた。
第30番札所 宝厳寺(竹生島)
真言宗豊山派
<本尊 千手千眼観世音菩薩>
開創 724年
舞鶴を朝発って、松尾寺を経て、敦賀経由、長浜まで、長い道のりであった。更に、船で竹生島に渡った。寺と神社しかない神の島。そんな雰囲気はあまり感じないうちに石段を登って本堂へ。なんせ、秀頼の時代からのお寺であり、見所も多いのではと思っていたが、その割には狭い境内で、迎えの船が来るまでの時間が余った。
三重塔、宝物殿、本坊
雨宝堂、護摩堂、鐘楼