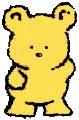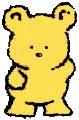家庭の窓 家庭の窓
|
昨年暮れの新聞報道で,中高生,視力1.0未満なお?割という見出しに目が止まりました。調査をした文部科学省はスマートフォンや書籍を読む際には目を30センチ以上離すことなどを呼びかけている,とあります。別の日の紙面には,豪16歳未満のSNS禁止という見出しが掲載されていました。SNSは暴力や自殺,違法薬物使用を誘発しかねない有害コンテンツに子どもがさらされたり,学校の集団いじめの温床になったっりする弊害が指摘されてきた,と理由が説明されています。
ネット社会に潜む心身の健康弊害への接触を避ける動きは,コロナ禍への対応であったソーシャルディスタンスを想起させます。一方で,弊害を除去する対応も必要があり,そのためには発信者の特定が必須となります。ネット社会という公開の場に参加するためには,どこの誰であるという最低限の情報の公開が資格になるはずです。情報は誰が発信しているかによって伝わるものです。人が見えない暗闇から聞こえてくる声は気味が悪いだけです。
SNSというネット空間との関わりが今の時代の定番になってしまっていますが,まだ世間が十分に試行錯誤の経験を重ねる期間を経ていないことから,その間合いの取り方が洗練される段階に到達していません。新しい技術はよりよいものに改良されていくプロセスを踏みます。技術として高度化が進んでも,過ぎては人の道具には相応しくありません。人の社会的な能力はゆっくりと成長することを弁えておくことが大事です。
物理的な機械については,有効に運用するためには,それなりの資格の獲得や訓練が課されています。間違った運用がもたらす危険や不都合を回避することは求められるからです。未熟なものが運転できないという制限などがあります。情報システムについてもそれが社会的機構であるために,それなりに運用の適正さが存在するはずです。問題が生じた面で,必要な対処を施していきながら,馴染ませていく社会的な了解を作っていくことになります。程の良い技術に根気よく育てていくことが今後の課題となります。
|
|
|