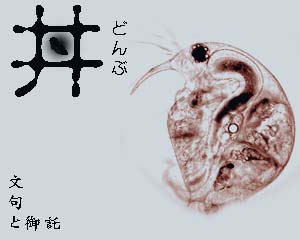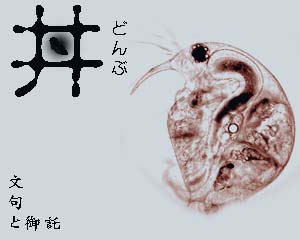|
■ 「弔問」について
|
2006年03月28日(火)
|
山崎の10年物をお湯で飲んでいたら興が乗ってきたので詩のほうも書きます。作品はこちらですよ。
うちのBBSで蟹ちゃんが書いていた「いいつくす」というのは、でも結局は詩にすべきエッセンス(=答え、になるのか?)を出し尽くすということなんだと思うのです。これに色々ついて文の「脈」ができるのが小説だし、あくまでもエッセンスをビビッドに抽出できるのが詩だと思うわけです。もちろん脈自体がエッセンスである場合もあります。伊藤比呂美さんの「河原荒草」なんかまさにそうよ。あれは、すごい。
さて、「弔問」。今回わかりやすい。喪失感。死んだり壊れたり無くしたりという喪失感はわかりやすい。で、この喪失感をいかにビビッドに見せるか、でこの書き方になる。
で、今回、ほぼノンフィクション。登場人物も、最初は色々な人物をいれましたが、やっぱり濁るのでやめました。全部実名、全部、本当に、亡くなってます。あ、嘘。<暴れ馬>だけはまだ現役ですが。
ナニを見せるか。むしろ、ナニが見えるか。それは、語り手の人間関係だし、登場する人物との相関関係でもある。72歳の鳶を「平ちゃん」と呼べ、おじさんの息子が63歳etc...で、淡々と逝ったものを列べて、最後に<ごォっそり>、<居>なくなる。つまり、リストの存在は<い>たのではなくて、<居>たのだというあたりもポイントなのです。本当は。
結局ネタはそういう居なくなったリストと喪失感で、それをどう見せるか、という話。実は「喪失感」も語り手の人物像を描く上での「ネタ」でしかないというのが、小生の本意なのですよ。やっぱり最終的には人間を書かないと、面白くないんだ。抽象はどうでもいい。
|
|