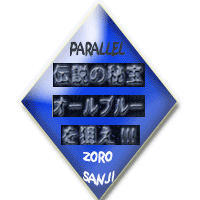
◆
111
◆
サンジはゆっくりと目を開けた。
すばらしく高くて美しい天井が見えた。
ゆうるりとした風がほほを撫で、
しずかな光が室内に差し込んでいた。
木の葉がさわさわと音をたて、
果物のあまずっぱい香りが流れてきた。
そこは、おだやかであたたかい空気に満ちていた。
ああ、オレは死んだんだな。
サンジはぼんやりと考えた。
最後にゾロに会えたと思ったのに、
ゾロは消えちまった。
あの無駄に固くて鍛えた筋肉が煙みてえになくなっちまった。
会えて、オレはうれしかったのに・・・。
サンジはゆっくりと目を閉じた。
目を閉じると、どこか遠くで鐘の音がしているのが聞こえた。
・・・鐘?
どうして・・・?
おれは、死んだはずなのに・・・。
身体を起こしたサンジは、
自分が見た事もないような、
豪華な金色の服を身にまとっていることに気づいた。
身体の奥には、もうすっかり慣れた痛みと疼きがおきた。
え・・・?
何・・・?
サンジはふらふらと立ち上がると、
楽園のように美しい園を歩いた。
建物は豪華で美しく、広大な庭は完璧な美と自然を作り出していた。
サンジは庭のすみに、見慣れた姿があることに気づいた。
白いヴェールをかぶったアルビダは、
悲しげな表情で立っていた。
「あの鐘は、サーの戴冠式の合図だよ。
ここは、クロコダイル国王の作られたばかりの城さ」
アルビダはわざと冷たく言った。
驚いているね。
信じられないって顔をしている。
そうさ、あんたは、クロコダイルを道連れに、あの世に行く気だったから。
ニコ・ロビンがこっそりあんたに渡した薬。
それが何だか知らないとでも思っているのかい。
死んで楽になろうと思ったのかい?
そんなことは許せない。
そんなことはだめだ。
だから、アタシはこっそりただの媚薬と取り替えてやった。
アタシはあんたの事なら、
もう何でも知っている。
あんたが、どんな思いで毒薬を使おうかと思ったことも分かる。
アタシがどれだけあんたが憎かったか、知らないくせに。
どれだけあんたを哀れに思ったことか、知らないくせに。
憎くて、憎くて。
でも、憎みきれない。
「アタシはあんたなんか、嫌いだから、もう面倒はみたくないんだよ。
サーが来る前に、ここから逃げることにしたよ」
サンジの顔は悲しげに歪んだ。
「だから、これは、捨てずに、あんたが渡すんだ。
いいね、必ず、あんたが直接渡すんだ。
そうしないと、許さないからね」
アルビダはそう言って、
紙袋に入ったものをサンジに手渡した。
それを受け取った瞬間、
サンジの目には涙があふれた。
「どうして・・・これを・・・?」
それは、誰にも知られないように、
こっそり作り続けていた編み物だった。
もう、渡す者もいないのに。
憎くて恥ずかしいものだったはずなのに。
アルビダはサンジを見ていられなくなって、
背を向けた。
その不格好で目の荒い、
目立つ緑色の腹巻。
あんたが、どれだけ苦心して作ったか、
アタシは知ってるよ。
本だけはサーに買ってもらったみたいだけれど、
白い毛糸だけ手に入れ、
それを自分が植えたミドリなもので染めて、
編み棒まで作って、
誰にも見つからないようにこっそり作った。
あんた、どんな顔をして作ってたか知ってるかい?
どれだけ、ゾロが好きなのか知ってるかい?
しあわせそうな顔をしていた。
あんなに文句を言っていた腹巻を、
あんたはせっせと作っていた。
作り終えたそれを、
あんたは捨てて、
毒薬を手にした。
勝てるわけない。
最初から、アタシがこのコに勝てるわけなんかない。
ゾロはこのコに夢中で、このコもゾロが大好き。
どんなに離れていたって、心は離れることはない。
このコは、ゾロを好きな心だけは、クロコダイルにひとかけらも与えなかった。
敵わない。
このコこそ、ゾロにふさわしい相手。
ゾロは生きているんだ。
アタシの事は分からなくても、
このコのことはきっと分かる。
いつかは、きっと分かる。
だから、このコは死んではだめだ。
絶対に、ゾロに会わなくては、だめだ。
ニコ・ロビンは、麦わらの一味がここに来ると言った。
もう、アタシには夢も希望もない。
でも、せめて何かしたいじゃないか。
哀れなこのコとゾロのために、
何かしてやりたいじゃないか。
このコがあんまりバカだから。
鐘の音が、少し大きくなった。
戴冠式の間じゅう、王の支配下にある何万という鐘はすべて鳴り続ける。
戴冠式とその後のパレードのための警備員は十万人を越えるという。
戴冠式の後、民衆の前で演説をし、それからパレードを終え、
二時間後には、クロコダイルはここにやってくる。
華美な式典や、晩餐会などはすべて排除して、
この場所で楽しむためにやってくる。
「王の部屋」であるここの警備は三重の城壁で囲まれており、
二百人近い精鋭がこの場を守っているという。
ただの私室のはずなのに。
麦わら盗賊団が、いかに有能であっても、
この難攻不落の城の中まで来れるわけがない。
でも、もしわずかでも可能性があるのだとしたら?
信じていいのだろうか?
アタシにもまだ未来があることを。