「バールストン・ギャンビット」なる言葉が、一般に浸透し始めたひとつのきっかけは、「十角館の殺人」(綾辻行人,1987)になるかと思います。
令和6年3月、この「十角館の殺人」が、Huluオリジナルドラマとして実写化されました。私もふつうのミステリ好きとして、全5話を(2日で)一気見してしまいました。
ドラマ内では、登場人物2人が声を揃えて「バールストン・ギャンビット!」と言うシーンもあり、「おー」と思った次第です。
日本国内でこの「バールストン・ギャンビット」というミステリ用語を、チェス用語の側面も含めて、最も丁寧に説明しているのはこのサイトだという自負がありますので、この機会にこのページを改訂することとしました。
オリジナルドラマを見て、このサイト(ページ)にたどり着いた方もいるかと思います。「ミステリ」と「チェス」双方から、この「バールストン・ギャンビット」とう言葉を、改めて解説してみたいと思います。
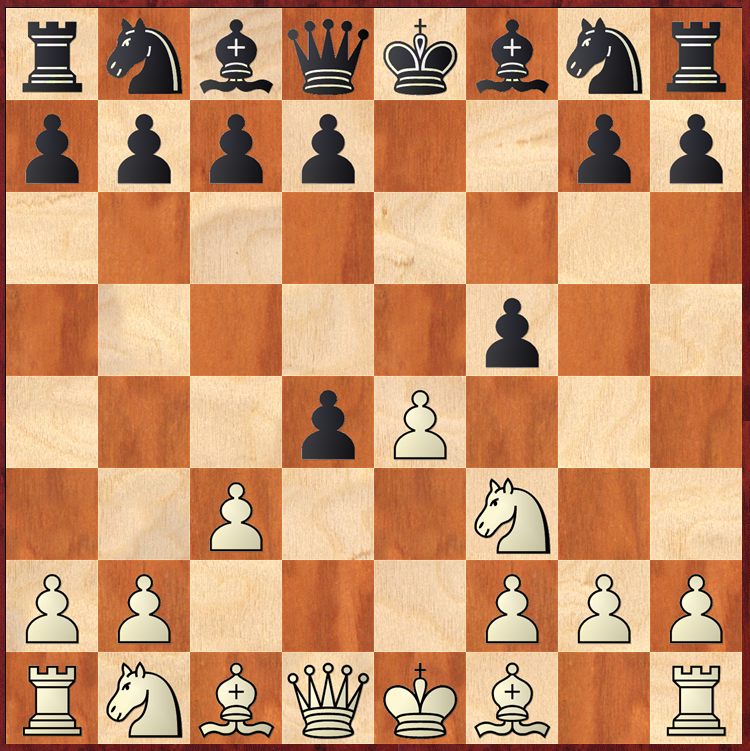 |
|
| 【図−1:これがバールストン・ギャンビットだ!】 |
バールストン・ギャンビット。
これは1.e4 e5 2.Nf3 f5から始まるラトビアン・ギャンビットにおいて、白から3.d4とした上で、3…exd4 4.c3?!とカウンターでギャンビットをかます・・・とかでは無く、つまりはチェス用語ではありません。
なんとこれ、「ミステリ」用語なのです。
上の局面図は冗談なので信じないようにお願いします。
この用語はフランシス M.ネヴィンズ Jr.の造語、初出は「エラリイ・クイーンの世界」(1980年)とのこと。この本は、日本では古本でしか出回っていない模様です。
出典となるべき「エラリー・クイーンの世界」は手元にないので、ネット上に転がっている情報を紹介しましょう。
ギャンビットを「先攻法」と訳すセンスも如何なものか(これは「エラリイ・クイーンの世界」を訳した秋津知子さんのセンスなのか)とも思うのですが、「ギャンビットは、チェスのさし始めの手」とか書いている人もいたりするわけです(上記の解説のほうがまだマシ)。
ともかく、日本のミステリファンは「バールストン・ギャンビットとは、真犯人が自らを死んでしまったかのように見せかけるトリックである」とまでは理解しても、なぜそこに「ギャンビット」というチェス用語が用いられているのかとまでは理解できてはいないkと改めてたい方がほとんどでしょう。
まずは「バールストン・ギャンビット」の解説です。
これ以降、ミステリ的には「ネタバレ」が続きますので、読みたくない人はここまででストップ。
ところで、これ以降の文章を書こうとして検索してたら、なんと現在ではシャーロック・ホームズの全作品(完訳)がネットで公開!いやぁ、驚きました。
さて、「バールストン」の出典は、シャーロック・ホームズシリーズの長編「恐怖の谷」です。事件の舞台となったのがイングランド南東部サセックス州の「バールストン館」。ここで館の主人であるダグラス氏が死体で発見されたのですが、実はこの死体は別人で、ダグラス氏は生きていた(殺したのはダグラス氏)、ということが元ネタとなります。
このように、「死体として発見された人が実は生きていた(その人間こそが犯人だった)。」というトリックを、「エラリイ・クイーンの世界」の著者であるフランシス M.ネヴィンズ Jr.は「バールストン・ギャンビット」と名付けたわけです。
そして、このトリックの名称をわざわざ「ギャンビット」と名付けたわけですから、ネヴィンズ Jr.は相応のチェス好きであったと類推できますし、その元々の意味を理解した上で、この「ギャンビット」という単語を使っているんだと考えて良いと思います。そうでなければ、普通に「バールストン・トリック」とでも呼べば良いだけですから。
次にチェス用語における『ギャンビット」の解説です。
ギャンビットとは、チェスの序盤戦術の一つであり、定跡の名称としても使われているものです。
キングズ・ギャンビット、エバンス・ギャンビット、そして私が愛用するラトビアン・ギャンビットなど、多くのギャンビット定跡があります。
そして、この「ギャンビット」という戦術・定跡の特徴は、
・チェスの序盤戦において
・ポーン(通常は1つ)と引き換えに
・主導権や駒の展開、盤面中央の制空権などの優位を得る
ことが挙げられます。
ということは、やはり「バールストン・ギャンビット」もチェスと同様に、物語の序盤において、何かと引き換えに何かを得ているからこそ「ギャンビット」という呼称が与えられているはずなのです。ということで、私は真剣に考えました。

そこで、私が出した結論はこれになります。
「ミステリ小説の序盤において、真犯人が自らの自由や地位・立場と引き換えに、自らの無罪証明あるいは殺人という目的の達成を得る」ということではないかと。この状況に鑑みて、フランシス M.ネヴィンズ Jr.さんは「ギャンビット」という単語を、このトリックに当てはめたのではないかと思うのです。
生き残った真犯人は、もう社会的には「自分自身が死んでいる」状態にあり、真っ当な人生は送れないわけで、目的を達成するにしても実際にはポーン1つどころでは無い大きな代償が伴うと言わざるを得ません。
ただ、そんな「バールストン・ギャンビット」を繰り出した真犯人も、物語の上ではやはり名探偵さんにそのトリックを暴かれ、結果的に「このギャンビットは成功しなかった」となるわけです。現代チェスの世界においても、トップレベルにおいては多くのギャンビット定跡が通用しなくなっていることと重ね合わせ、私は思わず涙してしまうわけです。
また、「バールストン・ギャンビット」というトリックそのものも、科学的捜査が発達した現代では、小説としてもなかなか使いにくい状況にもあるようです。
ちなみに、「エラリイ・クイーンの世界」では、クイーンが物語を作る上でよく使ったトリックが2つあり、1つがこの「バールストン・ギャンビット」、もう1つが「ダイイング・メッセージ」だそうです。思えば、「Xの悲劇」にはこの両方が用いられていました。
最後にこれだけは言っておきたい。「ミステリ小説で顔の無い(潰れた)死体が出てきたら、バールストン・ギャンビットだと思え」。
| TOP | INDEX | << PREV | NEXT >> |