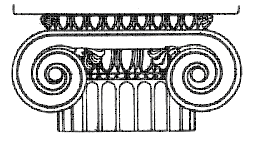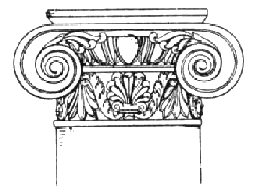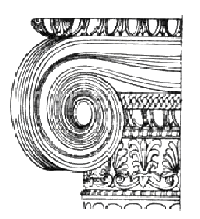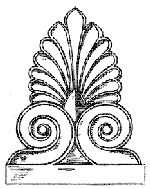|
The art of Austrian Violin Back |
オーストリア製・リメイク品はアート?? |
| 本器が仕上がった頃、第4回・卒業高校OB美術展があった。 今年は、なんとか油絵の小品二点を仕上げたのだか、本器も木工品としてタイムリーに出品させていただいた。 |
そこで、一般の人たちが「美術展なのに、何故ヴァイオリンを・・?」という疑問にお答えするつもりで、筆者の考えをA4・7ページに書いてプリントアウト、クリアーフォルダー二部に入れ、見ていただいた。 たいはんはHP本文と共通するもので、その内容は以下の通り。 |
|
 |
 |
|
| ◇ リフォームやリメイクでも芸術品なの? | ||
|
普通、修理や修復には、この業界の専門用語としてリペアー (repair)を使っています。
しかしながら、私は今回の作品のように『つくり直し』の場合には、あえて「リメイク(remake )」という言葉を用いいています。
その意味としては、ただ、元通りに修理や修復する、復旧するのではなく、ときにはまったく別のものにつくり替えてしまうこともあるからです。 本来、つくり替える必要がない、いいものでは絶対にそんなことはしません。 つくりそのものや、故障箇所がどうしようもないものを、少なくとも私のもてる力量の範囲で、少しでも無駄に破棄するようなことなく、 レッスン生程度の練習用になればと願ってやっているのです。 では、そんなものに芸術性があるのか? と誰もが思うでしょう。 もともと「芸術」とは、あるものを『私はこう捉える』とか『こう表現する』という自己表現であり、主張でもあると、私はつねづね認識しています。 ヴァイオリンは、標準的な大きさや形、その他もろもろの規制があり、また製作過程においても、仕上げでも、いろいろなハウツーがあります。 |
大きさでは、名手・パールマンのような、
どんな大男が使うヴァイオリンでも、ボディの標準的な大人用(4/4)のボディの長さは355mm前後に限られています。
また、五嶋みどりさんのような、小柄な女性が使うものでも、大きさは関してはまったく一緒です。
(ただし、製作者により、デザインやタイプにより、数ミリの差はあります。) 形は、だいたいがストラディバリウス型が主流になっていますが、その他、グァルネリウス型やヤコブ・スュタイナー型など、 有名なものでは過去の名工たちの作品に模して何種類かがあります。 そうした限られた中で、それぞれ製作者の個性・主張が入ります。 板の削り方やアーチング(カーブのとり方)、板そのものの厚さ、ネックやスクロール(渦巻き)彫刻の形、ニス仕上げの方法、あるいはニスそのものの色合いやぼかし方、 使う部品のデザインや仕上げの違い、材質の違いなどなど、そうしたことの中にまで、それぞれに好みや主張が入ります。 その違いだけでも、オールドっぽくなったり、モダンになったり、高級感があふれたり、普及品になったりと、 できあがったものの表情は全く違うものになります。 |
|
|
つぎの写真をよく見比べて見て下さい。左側が既存の表板を本体から剥がしたもの。 右が今回、私がつくり替えたもの。 このように、並べて比べるとよく分かりますね、既存のものには繊細さや美しさ、スマートさがありません。 とりわけ、エッジ(周辺部)の削りが悪く、ぎこちないし、C部の縁が均等に削れていないのも気になるところ。 緻密さに欠けているし、平面的で、とくにf字孔のカットもやや稚拙ささえも感じられます。 そのため輪郭もシャープではないし、パフングを含めたエッジの処理も劣悪です。 
自分でいうのも、少々気恥ずかしい気もしますが、新しい方の輪郭や外形の形が、ずっとシャープに見えませんか? それが、私がここで主張したい制作者としての「美意識」の違いであり、刃物の使い方や感性の違いといえるのでしょう。 ですから、上述したように、それぞれの工程にも、少しでもシャープなプロポーションにしたり、スマートな削りに、というように、 そのつくり手の美意識や、主義・主張をしっかりもっておこなたものであれば、 絵や彫刻同様、それはもう『芸術品』としての「作品」といえるものではないかと確信しているのです。 |
||
|
◇ リメイクやリペアーは新作より難しいもの また、新しくつくる場合なら、それぞれの部材や部品づくりにしても、図面通りに、標準的なつくりで工程を進めることができます。 万一、少し違ったとしても、それからつくるものを前のものに合うようにしながらやれば、なんとかできてしまうものです。しかし、リメイクやリペアーではそうはいきません。 既存のものに合わせ、しかも、ぴったりと合わせてつくらなければなりませんから、ずっと難易度が高くなります。 ◇ リペアーの練習・教材用として入手 わたしは、もう何年も前から、そうしたリペアーの練習用として、古い、どうしようもないものをネットオークションで落札し、使えるものにしてきました。 つまり、もともとの原型はジャンク品で、最悪の場合はゴミにしてもおかしくないというものです。 そうしたものだけに、思い切ったつくり替えができるのです。 ◇ 本器の、もともとの姿 (以下、写真はHP本文と同じもののため、ここでは省略) 表板にはあちこちに「割れ」があり、分厚く塗られていたニスにもひび割れができていました。 ネックのスクロール(渦巻き)の形にしても、私から見たらずいぶんと貧弱で、丸に、ふくよかさや豊かさがありません。 あとで、バラして外すときに分かったことですが、この作者は、ネックの全長と高さ、その両方を切り間違えていて、2カ所に接ぎ合わせがありました。 本体側の、裏板に接する面(ボタン部分)に一カ所、ボディに差し込んであるホゾ穴の末端に一カ所、4mmほどの厚さの切片が接いでありました。 また、裏板の厚さをチェックしてみたら、標準的な裏板の厚さは、周辺部で2.5mm、中央中心部では4.5mm程度です。それが、周辺部の薄いところでは1.8mmしかなく、 また、反対に周辺部でも厚目のところでは3.3mm以上のところもありました。 表板も、全体に薄すぎていて、それであちこち割れたのだろうの推測しています。薄ければよく振動すると勘違いしている人もいますが、そうではありません。 薄くするところとしっかりと残すところが必要で、それで丈夫でいい音の楽器になるのです。  裏板や側板の素材からすると、決して見劣りするような材料ではありませんが、 初心者がどこかの工房に習いに行ってつくったもの、そんな感じのつくりでした。 右の写真が製作者のラベルと、鉛筆で走り書きした数値は、筆者がチェックした裏板の板厚。 ◇ 表板とネックをつくり替える つくり替えるといっても、図面も型(テンプレート)もありませんから、比較的、安定している裏板から型紙をとり、それからテンプレートをおこし、 それを基準に表板をつくっていくしかありません。 まず、裏板にトレペをあてがい4Bの鉛筆で外形を写し取ります。 その紙を切り抜き、半分に折って(この場合は3mm厚)片面白ベニヤに転写、ミシンノコで正確に切り抜き、それが表板・製作用のテンプレートになります。 左側のものが、そのテンプレートを基準にして切り抜き、表面だけすでに削りあがった本器に使うための表板です。 なお、裏板の周辺部は「反り返り(チャンネル彫りともいう)」分が少なく、周辺だけにやや厚さに余裕があったので、ご覧のように少しだけ削り直してあります。 ◇ 表板に、ひとつの試み 本来なら削りあがった表板に、バス・バー(この写真では右の写真・中央より少し上に、横に走っているバー)を、あとから貼り付けるものです。 でも、昨年、修復を依頼された古いイタリア製のバーは、本体から削りだした一体化したものだったのです。 あとから削ったものを貼るのは簡単ですが、正しい位置に正しいサイズで削り出すのは、だいぶ面倒な作業になります。 しかし、貼った物より削りだした方が丈夫に決まっています。 なぜならこのバーは、ネーミング通り、低音域の振動を表板全体に響かせ、伝える役割と、駒から受ける弦の張力を表板全体に拡散させる働きがあるのです。 そのため、一体化したバーには、いい効果が期待できjす。 |
◇ ネックは、つくり手の腕の見せ所 ネックのスクロール(渦巻き)は、製作者の彫刻技術がいちばん問われる場所でもあります 固いカエデ材から、上下左右・裏表からよく見て、バランスのいい形になるよう少しずつ彫り進め、仕上げていきます。 右の、対比写真の状態では、まだまだ完成品ではありませんが、少なくとも既存のものより、かなりふくよかな丸みになっていることがお分かりいただける思います。 既存のものでは、外周の円が、上(この写真では下)にきて、急に巾が狭くなっていて、それが全体のバランスを崩し、なんとなく貧相に見えるのだと思います。  粘土細工なら、何度も修整して、後からつぎ足していけば形をととのえることができますが、木工では削りすぎはゆるされません。 木工の怖さは、うっかりした削りすぎで、このように、徐々に悪くしてしまうということがあるのです。 ましてや、この人はサイズを間違えてカットしているのですから、わたしならボツにして、工房のインテリアにしてしまうところでしょう。 でも、この人は、平気でそのまま使っていたのです。 ◇ 組み込み 部品ができれば、あとは組み立てるだけ、ここからは標準的な作業で工程が進みます。 筆者は新作の場合でも、ニカワづけする際、最低限の着色を施してから行っています。 それは、はみ出したニカワにはニスや着色剤がのらないため、色むらとして出やすいからです。そこで、耐水性のあるアルコール系のカラーニスで着色しているのです。 ◇ ニス仕上げの美 既存のニスは、ゴールド系の単色塗り、しかも、後日、ひび割れが出るほどの厚塗り。 わたしは着色後も、計14〜5回、薄く塗り重ねて重厚感を出していくタイプ。 油絵のマチエールと同じ考えです。しかも、できるだけ立体感が出るような工夫も、ここでは駆使しています。 絵画的な表現ではシェイディング(陰影描法)というのでしょうか、そんなテクも今回は応用しています。 しかも、もともとがある程度の古さなので、アンティークな感じも出したいのです。 右の写真が元の仕上げ、下が塗っている最中の写真です。中央部をやや明るく、周辺部を濃くして立体感を強調しています。 レッド・ブラウンのヨーロッパ製のオイルニスを塗っては研ぎ、研いでは塗りを繰り返しているところです。 さらに、エッジの先端部だけは、美人の鼻筋に色の明るいファンデーションを塗るがごとく、白っぽく浮き出させています。 ここではある程度塗ったあと、新たに塗ったニスを、溶剤をしみ込ませた布で、そっと拭き取るのです。それが、また全体の立体感を強調する効果を生みます。 指板やナット(指板の付け根・弦の出口の黒い黒檀製の小さな部品)、サドル(テールピース{弦緒止め}のワイヤーが載る黒檀の部品)も新しく削りました。 ◇ 完成 ペグ(弦巻き)、テールピース、スポアー(アゴ当て)には、わたしの好みで紫檀(ローズウッド)製を使いました。 駒は、ドイツ製の古い形のものを使い、弦はレッスン生に人気のオブリガードを張りました。 ここまでお読みいただいた方には、ヴァイオリンづくりにおける美意識の大切さがお分かりいただけたと思いますし、また、これもひとつの芸術品と考えて差し支えないことも、ご理いただけたと思います。 |
||||||
| *参考資料 ◇ ネックのスクロール(渦巻き)彫刻 | |||||||
| ヴァイオリンを含むヴァイオリン族の楽器(ヴィオラ、チェロ)の頭部には、ご覧のような渦巻き文様が彫られています。
この文様をさかのぼると、古代ギリシャのパルテノン神殿が造られた紀元前7、8世紀にもなります。 その、パルテノン神殿などの柱・エンタシスの柱頭部にこのイオニア式の文様が使われています。
ミロ島から発掘されたヴィーナスも、その顔の縦横の比率やボディのスリー・サイズにも、 古代ギリシャ時代からもっとも美しい比率とされてきた『黄金分割』が使われています。 ヴァイオリンのボディもヴィーナス同様、黄金比から形成されています。 そうした美の極致にあるものだけに、やはり制作には美意識を持ってあたりたいと、筆者は常々思っているのです。 いちばん最後の図も、パルテノン神殿・装飾瓦に使われている文様です。  これらのイオニア式文様も、日本の唐草文様同様、植物の生命力に由来するもので、 まさに『無限の生命』をあらわしているものだと思っています。 ヴァイオリンを最初にデザインした人は、こうした由緒あるたいへんおめでたい文様をネックに取り入れたりして、 多分、『音楽の無限性』をもあらわしたかったのではないか、と筆者は推測しています。 それだけに、この渦巻きも、できるだけ「美しい形」に彫ってやらなければならないです。 最後までお読みいただいき、感謝! 感謝です。 ◇ 油絵は、上の写真にある、この年の卒業高校OB美術展にヴァイオリンとともに出品した 『読書をする女』と、『婦人像』の人物画二点、いずれもF10号です。
|
|||||||
| Back | Page Top | repair_index | HOME |