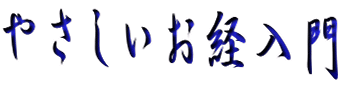
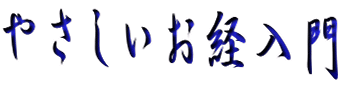
ばっくなんばぁあ~15
第 六 章
「いろいろなお経」
| *ジャータカ 今回より、初期経典の一つであります「ジャータカ」についてお話しいたします。 「ジャータカ」とは、直訳すると「生まれていた時のこと」という意味になります。訳を知っても意味がよくわからないと思います。漢訳された「ジャータカ」は、「本生経(ほんじょうきょう)、本生話、本生譚」と呼ばれています。まあ、簡単にいえば、「お釈迦様の前世の話」です。 このお経ができたのはお釈迦様が涅槃に入られたのち100年~紀元後500年ですから、約1000年間という長きにわたってまとめられたようです。 その内容は、 「お釈迦様は、約2500年前に生まれてきて、その生の時に仏陀になったのではなく、何度も生まれ変わって多くの善行を行い、徳を積んで仏陀になったのだ」 と説き明かしています。つまり、お釈迦様の前世の話をまとめたのが「ジャータカ」なのです。なので、「お釈迦様の前世話」と言われているのです。その内容を簡単にではありますが、みていきましょう。 (なお、後に紹介いたします物語は、「すずき出版 仏教説話大系」を参考にいたしました。) A、序 序文として分けているわけではないですが、ジャータカは初めにお釈迦様が仏陀になられた因縁話を説いています。これは、そのあとに続く話のいわば序文のようなものなのです。この因縁話がないと、続くお釈迦様の前世の話が始まらないからです。簡単にその内容を紹介しておきます。 お釈迦様は遠い遠い昔、お釈迦様がシッダールタとして生まれる91劫年前、スメーダという名でした。スメーダは、青年になってディーパンカラという仏陀のもとで修業を始めました。そして、ディーパンカラ仏陀から 「スメーダ、汝は遥か未来に釈迦如来という仏陀になるであろう。しかし、そこに至るまでには91劫という長い年月、五百数十度生まれ変わって菩薩行を行わねばならぬ」 という予言を受けるのです。スメーダは、その予言の通り550回生まれ変わり、善行をし、徳を積み続けた結果、今世においてシッダールタとして生まれた青年が、6年の苦行の末、深い瞑想をし釈迦如来という仏陀となったのだ、と説いています。 そして、次にジャータカは、その550回のお釈迦様の前世についてや、お釈迦様の前世において関わった人々について説くのです。もちろん、そこには「徳積みとは、善行とは、菩薩行とは」などという教えが含まれています。また、「愚かな者、欲張りな者、頑固な者」たちの哀れな行く末が説かれ、「愚か者にはなるな」という戒めが説かれています。 それは、物語・・・童話や寓話のような・・・になっています。主な話をいくつか紹介いたします。 B、本文 ①ジャータカ10 「王と仙人」 ヒマラヤに仙人がいた。その仙人は一人で修業に励んでいた。やがて仙人の名声は世間に広まり、多くの弟子ができた。 仙人は、雨季になると弟子を連れ、村々を托鉢しながら国王所有の園林に滞在することとなった。やがて雨季も開け、仙人はヒマラヤに帰るため国王にお礼に出向いた。すると国王は仙人に 「そのようなお年で、どうしてヒマラヤに戻られるのか。お弟子たちだけをヒマラヤに帰し、仙人はここに残られたらどうですか」 と言った。仙人は国王の言葉に甘え、弟子たちだけをヒマラヤへ帰すことにした。弟子の中で、かつてある国の王であった最年長の修行者に他の弟子を率いるよう頼んだ。 それからしばらくたったある日のこと、その最年長の修行者が仙人を訪ねてきた。その修行者は、仙人に挨拶を済ませ仙人の横に座った。ちょうどそこへ国王がやってきた。仙人は国王に挨拶をしたが、修行者は挨拶もせず、ただニコニコ王を眺め、 「わたしは何と平穏な暮らしをしていることか。ああ、よかった、よかった」 と言っているだけであった。 王は、修行者の様子に腹を立て、仙人に言った。 「なんだこの修行者は。国王である私を見て挨拶すらしない。私が仙人様の面倒をみていることも知らないのか。なにがよかった、よかった、だ」 すると仙人は 「私が国王様の世話になっていることは、あの者もよく知っております。ただ、彼は修行者になってからの暮らしが嬉しくてたまらないのです。あのように喜びを表すことによって、国王様にお礼を言っているのですよ。実は、出家する前は、あの者もある国の王でした。出家する前は、王の威光や武器などで自分の身を守っていました。しかし、今はなにも守る必要がない。守るものが何もないのですな。それが嬉しくてたまらないのですよ。」 と国王に言った。そして詩を歌ったのだ。 「他人を守ることもなく 自分を守ることもない 諸欲に惑うこともなく ただ安楽に身を任す 心安らぐその暮らし」 国王は、その話と歌を聴いて、なるほどと納得し、城へ帰っていったのだった・・・。 物語はこれだけです。これで、何が言いたいのか、よくわからないのではないでしょうか。簡単にいえば、「俗世のすべてを捨てて出家をすれば、こんなに安楽なことはない。修行はつらいものではない」ということが言いたいのでしょう。さらに「出家した者は、国王より上とか下という、枠にはとらわれない」ということもあるでしょう。 まあ、確かに、出家して修行者となり、世間から離れて、托鉢による生活をすれば、ある意味楽ではあるでしょう。家族を守る必要もなく、出世も気にすることなく、稼ぎの多寡を心配することもありませんから。 しかし、実践するのは大変難しいですね。昔のインド、という性質であればこそ、可能なことです。現代には、到底無理な話です。 が、近づくことは可能です。一切の煩わしさから離れ、修行者として生きる・・・ことは不可能ではありません。多くの欲望を捨てなければなりませんけどね。でも、たとえば、多額の借金を抱え、自己破産をし、一家離散してしまった・・・となれば、いっそのこと出家して修行者となり、おとなしく山中に住んだほうが安楽でしょう。自殺・・・なんてことを考えないで、出家したほうが徳が積めるっていうものです。悟りが得られるかもしれませんし。 現代に生きる我々は、多くのものを背負い過ぎなのでしょう。少しは荷物をお降ろせば、楽になるのですけどね。これは、そういうお話です。 ちなみに、元国王の修行者がお釈迦様の前世ですね。 ②ジャータカ16 子ジカの智慧 ある森林の中に一群れのシカが暮らしていた。その群れは、気品ある風貌で優れた知恵をもったシカ王に率いられていた。その王に従っている限り、他のシカたちは安心して暮らすことができた。 ある時、王の妹シカが子ジカを連れてきて言った。 「兄さん、この子は生まれつき利発で今年生まれた中でも際立っています。兄さんのような立派なシカに育てたいので、兄さんの智慧を授けてあげてください」 「ほう、澄んだ美しい目をしている。いいだろう。明日から毎朝私のもとへ来るがいい」 シカ王は子ジカにそう言ったのだった。 翌日から、子ジカは言われたとおりに王のもとにやって来て、いろいろなことを王から教わった。毎日毎日、子ジカは王のもとで教えられた。そうして次第に、その目は智慧の輝きが増していったのだった。 ある日のこと、その子ジカは仲間たちを森の中を散歩していた。すると 「ガチャッ」 と音がした。なんと、子ジカの前足が鉄の罠にはまってしまったのだった。もがけばもがくほど罠の歯が肉に食い込んだ。仲間のシカたちは、驚き恐れて逃げ去ってしまい、誰一人助けてはくれなかった。困った子ジカはもがくのを止め、冷静に考え始めた。 一方、逃げ帰った他のシカから話を聞いた母ジカは、王シカのもとへ急いだ。 「兄さん、あの子が罠にかかってしまいました。どうか助けてください。早くしないと、殺されてしまいます」 王シカは、落ち着いていった。 「あわてなくてもよい。落ち着きなさい。心配することはない。あの子なら自分で解決するであろう。元気に戻ってくるから夕食の支度でもして待ってなさい」 と妹シカをなだめて帰したのだった。 そのころ、罠にはまった子ジカは、できるだけ痛くない位置に体をずらし、ゆっくり横たわり、足を延ばして腹這いになった。そして、後ろ足で周りの土や草を掘り上げ、苦しさの余りのたうちまわったように見せかけた。さらに、大小便を漏らし、身体に唾液をかけ、舌をだらりとだし、死んだように見せかけたのだった。 やがて猟師がやってきた。 「おや、シカが罠にかかっている。ほう、ずいぶん暴れたな。今朝早くにかかったに違いない。よし、罠を外すか・・・」 猟師はそういって子ジカの罠を外した。そして、シカを縛るつる草を取りに行った。 子ジカは、猟師の姿が見えなくなると立ち上がって、さっさと帰っていったのだった・・・。 この聡明な子ジカがお釈迦様の前世ですね。 これは、どんな困難にあっても、慌てず騒がず、智慧を絞れば乗り切れるものだ、ということを教えています。 人は、困難に出会ったときや不測の事態におちいったとき、慌てます、焦ります、気が動転して何をしていいか分からなくなります。その結果、さらに状況を悪化させています。そういうものです。で、取り返しがつかなくなってしまうのです。 しかし、事が起きた時、慌てずに、騒がずに、焦らずに、気を落ちつけ、ゆっくり状況を見まわし、冷静に考えることをしたならばどうでしょうか?。事態を一層悪化させることにはならないのではないでしょうか。 どんな悪い状況に陥っても、冷静に心落ち着けることが、まず第一にするべきことなのです。ここでは、そのことを智慧ある子ジカの判断に譬えて説いてあるのです。 言うは簡単なんですが、なかなか冷静になれないのが人間です。しかし、日頃から冷静になることを心掛けておけば、いざという時役立つものです。慌てず、騒がず冷静に・・・・。この物語の子ジカのようになりましょう。 ③ジャータカ22 犬の教訓 昔、ある墓地に数百の野犬が住んでいた。その群れを率いているのは一匹の堂々たる白犬であった。 ある時、その国の王の愛馬の革の手綱が食べられてしまうという事件がおこった。家来たちが調べてみると、馬の周辺には犬の足跡が多数見つかった。家来たちは国王に報告した。 「犯人は、どうやら犬のようです。街にいる野良犬の仕業でしょう。」 「そうか、そういうことなら街中のすべての犬を殺してしまえ。わしの愛馬の綱を食った罰だ」 国王はそう命じたのだった。 街では犬狩りが始まった。それは容赦ないものであった。追い詰められた犬たちは、王である白犬に助けを求めた。王の白犬は尋ねた。 「手綱を食べたのはどの犬だ。」 「我々の仲間にはいませんでした。どう考えても我々は城内には入れません。となると、お城で飼われている国王の犬が犯人だと思います」 「そういうことか、わかった。もう何も恐れるな。すべて私に任せなさい」 白犬はそういうと、たった一匹で城へ乗り込んでいったのだった。 その白犬の余りにも堂々とした姿に、家来たちは誰一人捕まえようとする者はいなかった。白犬は、すばやく国王の前にでると、王に問うた。 「国王よ、なぜ我々を殺そうとなさるのか」 「わしの愛馬の手綱を食ったからだ。だから、すべての犬を殺せと命じた」 「すべての犬を殺すのですか。一匹残らず」 「う、うぅぅ、いや、王宮の犬だけは別だ」 「王よ、それはおかしい。あなたはご自分の愛馬や愛犬がかわいいばかりに、王としての道をお忘れになっている。一国の主たるもの、物事を判断するには、ちょうどつりあった天秤のようにどちらにも傾かない公平さがなければなりません」 白犬は、そういうと詩を歌った。 「血筋正しい王の犬 彼らは罰を受けないで 我ら野犬は殺される 血統毛並みそれだけで 彼らは罰を受けないで 弱い者のみ殺される どうしてこれが公平な 王の裁きといえようか」 これを聞いた国王はむっとしていった。 「では、お前は犯人を知っているのか」 「知っています。国王の愛犬です」 「何を証拠に!」 「それでは、その証拠を見せましょう。愛犬を連れてきてください。そして、バターと薬草をください」 白犬は、連れてこられた国王の愛犬にバターを混ぜた薬草を食べさせた。すると、国王の愛犬は、ゲロゲロと革を吐きだした。それは、国王の愛馬の手綱だった。 それをみた国王は、ひどく恥じ入り、白犬に頭を下げ、それよりのちは公平な政治を行ったという・・・。 これは今の世の中にも通じる話ですよね。世の中、弱い者が苦しむようにできています。特に昨今はひどいですね。政治改革と称して、弱い者が苦しむような改革を多数してきました。医療費の問題、障害者への給付金の問題、生活保障費や介護費用などなど。血統のいい自分たち(政治家や官僚)の甘い汁はカットしないで、庶民が頼りにしている部分だけをカットしてしまう。不公平を絵にかいたようなやり方ですよね。王宮の犬は大切にされ、野犬は狩られるのです。 こうした不公平な扱いは、国だけではありません。学校内や会社内、家庭内でもあることです。子供たちは比較され、出来が悪いからと差別され、愛想がないからと排除され、理不尽な理由からいじめられるのです。 会社内でも同じですよね。あの人のここがいや、あそこが気に入らない・・・・などと差別が繰り返されます。それを見極め、調整する役の上司も不公平の渦の中にいるのです。 国を仕切るもの、役人を仕切るもの、国民を仕切るもの、会社を仕切るもの、学校を仕切るもの、家庭を仕切るもの・・・・彼らは、すべてにおいて公平に判断しなければならないはずです。すべてに平等であるべきでしょう。「我が身かわいい」、「身内びいき」ではいけないのですよ。ところが、現実は王宮の犬は優遇されているのです。 さてはて、こんな世の中に一匹の白い犬は現れるのでしょうか?。それが期待できないのなら、多くの野犬が声を立てるしかありませんねぇ・・・。 物語中の白い犬は、もちろんお釈迦様の前世です。 ④ジャータカ33 「ウズラ捕りとウズラ」 昔、ある村の近くに大きな森があり、数千羽のウズラが住んでいた。そのウズラたちは朝早くからにぎやかに活動していた。 村には、ウズラ捕りの名人と言われている若者がいた。彼は、毎日たくさんのウズラをとり、街に出てそのウズラを売って生活をしていた。ある日のこと、その若者が街から帰ってくると、村の人が声を掛けてきた。 「今日もたくさん稼いできたのか。いいなぁ・・・。いったい、どうやってそんなにたくさんのウズラを取るんだい?」 若者は、自慢げに答えた。 「簡単さ。ウズラの鳴き真似をして、ウズラを呼び寄せるんだ。あとは、そうっと網を掛けるだけ。それだけだよ」 「ウズラの鳴き真似?。そんなことでウズラが集まってくるのかい?」 「ああ、集まってくるよ」 そういうと、得意げな様子で若者は家へと戻っていた。村人は、羨ましそうにその姿を見ているだけだった。 確かに、その若者はウズラの鳴き真似が得意だった。彼が鳴き真似をすれば多くのウズラが集まってきたのだ。しかし、数千羽いるウズラの中には、賢いウズラもいた。 「どうして毎朝あんなに多くの仲間が捕まっていくのか・・・。朝のあの鳴き声は、誘惑の罠だということに気がつかないからだ。愚かなことだ・・・。しかし、それをいくら注意しても無駄だ。あの声は巧妙で、仲間の声と聞き違えてしまうのも無理はない。では、捕まらないためにはどうすればいいのか・・・。そうだ、一羽一羽が勝手にもがいていてもだめだ。みんなが力を合わせねば・・・・」 賢いウズラは、森中のウズラを集めていった。 「いいかいみんな、毎朝やってくるウズラ捕りの網から逃げ出す方法を考えた。これは、一羽だけではできない方法だ。みんなの協力がいる。今からそれを教えるから、しっかり聞いてくれ」 賢いウズラは他のウズラに網から逃げる方法を教えた。 「まず、網が掛けられたらあわてちゃいけない。暴れると網に絡まってしまうからね。おとなしくするんだ。そして、ゆっくり網の目に頭を突っ込むんだよ。みんな、それぞれが網の目に頭を突っ込むんだ。それで、全員が網に頭を突っ込んだら、誰かの合図でイバラに向かって一斉に飛び立つんだ。イバラの森についたら、網をイバラに引っ掛けるんだよ。そして、そっと頭を抜いて逃げるんだ。網はイバラに絡まっているから大丈夫だ。みんなはイバラの下のほうを飛んで逃げればいいんだよ」 賢いウズラの提案にみんなは納得し、明日から早速この作戦で行こう、と決めたのだった。 翌朝のこと、いつものようにウズラ捕りが、鳴き真似をしてウズラを呼び寄せた。いくら注意しても、多くのウズラがその甘い鳴き声に簡単に誘惑されてしまった。そして、いつものように網に捕まったのだった。 しかし、そこからが違った。どのウズラも慌てず、ゆっくり網の目に頭を突っ込み、一斉にイバラに向かって飛び立ったのだった。作戦は成功した。網に捕らわれたウズラは一羽もいなかった。それは、翌日も、その翌日も続いた。 毎朝、ウズラを一羽もとらず帰ってくる若者を見て、その妻が若者をなじった。 「あなた、毎日毎日手ぶらで帰ってくるけど、本当に森にウズラを捕りに行ってるの?。さては、女のところへ遊びに行ってるんでしょ」 「バカなことを言うな。毎日、俺は森に行ってるさ。ウズラの奴が賢くなってな。逃げるようになったのだ」 若者は女房にウズラの様子を語った。 「それじゃあ、私たちは生活できないじゃないの。いったいどうするの?」 女房は、若者に愚痴った。 「大丈夫さ。これは根競べだ」 若者はそういうと、ニヤッと笑ったのだった。 ある日のこと、賢いウズラが木の枝から森の様子を眺めていると、喧嘩をしているウズラの姿が目にとまった。それは、些細なことから始まったケンカだった。そうして眺めてみると、あちこち喧嘩が起っていた。どれもこれも、ほんの小さなことが原因で大きな喧嘩になっていた。やれ頭を踏んだ、足が羽根に当たった、落とした餌を奪った、羽が当たった、くっつくな俺が留まる場所だ、うるさいピーピーわめくな・・・・などなど、あちこちで言い争いやつつき合いをしているのだった。 「あぁ、これではだめだな。あんな些細なことで罵りあっていては、今度網に捕らえられた時、喧嘩するに違いない。その場の状況も忘れて、些細なことで言い争いやつつき合いを始めるに違いない。きっと、再び多くのウズラがとらわれていくだろう。何度言っても愚かな者はその習性を直そうとはしない。この森のウズラたちは救われないな・・・・」 賢いウズラの予見通り、翌朝多くのウズラが捕らえられた。網にかかった時に、同じ網の目に頭を突っ込もうとして争いを始めた者や、羽が当たった、足を踏んだ、頭を蹴られたなどと言って争いを始めた者が多くいたからであった。彼らは、捕まっている状況も忘れ、今何をすべきかということを忘れ、争いを始めたからであった。 「やはりな・・・。彼らは私の忠告を忘れてしまった。それぞれが勝手なことばかり言いあって協力しようとしない。これでは、いずれ災難が自分にも降りかかる。この森にはもう住めないな・・・」 賢いウズラはそういうと、彼の意見が理解できる仲間のウズラとともにその森を去ってしまったのだった。 一方、若者は再び多くのウズラを捕まえることができるようになり、女房とともに喜びあっていたのだった・・・・。 この物語は「所詮、愚かな者は救われない。痛い目に遭うのだ」ということを教えています。もっと細かく言えば、いくつかの教えが含まれています。 1、「いくらいいことを学習してもそれぞれが勝手わがままなことを言って、協力しわねば破滅へ向かうのだ」ということ。 2、「他人の稼ぎを羨むな、羨むなら同じように努力せよ」ということ。 3、「一時の不運を嘆き、愚痴を言うな。時がたてば解決することもある。待つことも大事だ」ということです。 1についてはよくわかりますよね。愚かなウズラたちのことです。でも、これ人間にもあてはまるんですよ。たとえばエコ。地球温暖化の問題はみんな知っています。何をすべきか、何をしたらいいかもよくわかっています。でも個人個人が勝手なことを言って協力しようとはしていません。誰でもできることはたくさんあるのに、みんな自分勝手なことを言っていますよね。まあ、国をあげて勝手なことを言っている国もありますが・・・・。 もっと身近な学校や会社内でも似たようなことがあるんじゃないでしょうか?。こうしたらいいのに、とみんな分かっていることだけども、なかなか協力体制がとれない・・・・。個人の利益や都合が優先されてしまうんですね。あ、国会そのものがそうですね。あの中の議員さんは、まさにこの愚かなウズラですな。とすれば、賢い国民はこの国を去るしかない?のかも知れませんね。 2は、若者を羨んだ村人です。羨ましいと思うなら、若者を真似てウズラの鳴き真似をマスターすればよろしい。できないなら、他の方法を考えるか、他で稼げばよろしい。他人を羨む必要はないのです。 3は、若者の妻ですね。一時的に稼ぎが悪くなったからと言って、愚痴ったり責めたりする必要はないのです。まずは、「なぜそうなっているのか」を聞き、「今後の方針」を聞き、結果を待てばいいのですよ。結果がなかなか得られなければ「方針を変える」だけです。ちょっとしたことに一喜一憂しないで、落ち着くことが大事ですね。 とまあ、これだけの教えを含んではいるのですが、最も大事なことは「愚か者になるな」ということです。状況をよく考え、今何をすべきかを判断せよ、個人の感情や利害関係は後回しである、ということですね。それが賢者の選択です。国会という森のウズラさん、賢い選択をしてくださいね。 そうそう、当然、森を去った賢いウズラがお釈迦様の前世です。 ⑤ジャータカ37 「シャコの智慧」 昔、ヒマラヤの山中にニグローダの大木があった。その木の下にはシャコという名の小さな鳥と、猿と象が住んでいた。象は大きなものを運んだり、木をゆすって実を落としたりした。猿は木に登り、木の実を採ってきた。シャコも木から木へ飛び移り、木の実を落としたりして、生活をしてた。 初めは仲のよかった三匹だったのだが、そのうちにお互いに不平不満を持つようになった。たとえば、象はこう思った。 (俺は重いものを持ったり、生活に邪魔な倒木をどけたり、木に体当たりをして木の実を沢山落としたりしている。こんなに働いているのに、猿の奴はただ木から木へ飛び移っているだけだ。あれは遊んでいるに違いない。シャコは身体が小さいから仕方がないが、猿は許せん) 一方、猿は猿でこう考えていた。 (象の奴は楽でいい。あのでかい身体を木にぶつければいいんだから。力も強いから重いものを持っても平気だし。それに比べると俺は危険ばかりだ。木から木へ飛び移るとき、落ちるかもしれないからね。危なくって仕方がない。シャコのように羽があるわけじゃないからな。象の奴は、いつも危険な目にあっている俺に気遣いもしないで、バクバク大食いばかりしている。楽なことばかりしているくせに食うことだけは一人前だ。まったく、俺のほうが年長で働きものなのに、俺のほうが賢くて気がきくのに、尊敬すらしない。年長者や賢い者を敬うべきなのだ。そうだ、あの象の奴にガツンと言ってやろう。誰が一番偉いのかってことをな) ある日のこと、猿と象はお互いの鬱憤をぶつけあった。 「おい象、お前、誰にものを言っているんだ。象ってのは、年上の者を敬わない生き物なのか?」 「なんだと猿!、お前のほうが年下だろう。しかも、お前は愚かものだ。俺のほうが年長で賢いに決まっているだろ。俺を敬うのが筋ってものだろ」 こうして二匹は言い争いを始めたのだった。その内容は、やれどっちが働きものか、どっちが身が軽いか、どっちが力があるか・・・・そして、どちらが年長で賢くて尊敬されるに値するか・・・であった。 そんな争いをしていても埒が明かないのは当然だった。そこで、象が言った。 「だいたいな、俺はあのニグローダの大木がこんな小さなころから知っているんだ。確か、あのてっぺんの枝が俺が小さかった時、へその位置にあったよ。お前なんて、あの大木の小さなころなんて知らないだろ。だから、俺のほうが年長さ。」 「何言ってるんだ。俺なんて子ザルの時、あの木がすごく小さくて、木のてっぺんの芽を食べていたんだ。子ザルの時だぞ、だからすごく小さかったさ。そんな小さなニグローダの木を見たことないだろ」 「俺が小象のときだって、小さかったんだ。その時はこうして四つん這いになっていると、へそが地面につきそうだったんだ。そのへそに、あのニグローダのてっぺんが触ったんだぞ。だから、あのニグローダが芽が出てきたばかりのころのことなんだよ」 シャコは、この二匹の不毛な言い争いを木の枝から眺めていた。やがて、二匹の言い争いの矛先はシャコに向かった。 「おいシャコ、そんな上から眺めているが、お前はどうなんだ。まあ、どうせお前が一番若いのだろうけどな」 「そうさ、俺たちにはかなわないだろうな。あははは」 象と猿はシャコを笑ったのだった。シャコは、 「二人とも、このニグローダの木の小さい時を知っているんだね」 「ああ、そうさ。よく知っている。だから俺たちはお前よりも年長さ」 「ふ~ん。私がヒナだったころ、ここには大きなニグローダが立っていた」 「ほらみろ。お前がヒナのころには、この巨木はあったんだ。お前は一番若いな」 シャコは二匹がつぶやいているのを無視して話を続けた。 「でね、私が一人で飛び発てるようになったころ、その大きなニグローダは枯れてしまった。私は落ちていたニグローダの実を食べていた。で、そこで糞をしたら、その糞に種が混じっていたんだろうね。いつの間にか芽が出てそれがこんなにも大きな木になったんだよ。このニグローダは2代目なんだよ」 その話を聞いた象と猿は、驚いて顔を合わせた。その様子を見ていたシャコは大きな声で笑った。 「もっとも賢いのは私だったね」 と。自分たちの愚かさに気がついた猿と象は、黙ってそれぞれの仕事を始めた。その後は、言い争うことなく、シャコに従ったそうである。 似たような話がお坊さんを題材にした落語にあります。詳しい内容は忘れましたが、どの修行僧が一番度量が大きいかを争った・・・ところから始まったと思います。ある僧侶は須弥山・・・今のエベレストですね・・・に座ってまんじゅうを食べたといい、ある僧侶は地球に座ったといい、ある僧侶はその地球を飲み込んだといいました。そこで、その地球を飲み込んだ僧侶が一番度量が大きいかと思ったら、別の僧侶がこう言いました。 「だれじゃ、わしの腹の中で言い争いをしているのは」 どの僧侶もその僧侶の腹の中で言い争いをしていた・・・・というわけですね。ま、愚かなことだ、と戒めているわけです。 これと同じで、どっちが年上か、どっちが賢いか、などというのは言い争うことではありません。どっちが偉いのか、などということで言い争うのは愚の骨頂ですね。 しかし、こういう争いは日常によくあることですよね。くだらない言い争いがもとで殺人事件に発展した・・・なんてこともあるくらいです。あまりにも馬鹿げてますよね。 と、他人の愚かさはよく気がつくものです。しかし、自分のことはわかりません。あなたは大丈夫でしょうか?。くだらないことでいい争いなどしてませんか?。不毛な言い争いからは怨みしか生まれません。そんなくだらない言い争いには参加せず、高みの見物・・・・と参りましょうかねぇ。 くだらない言い争いに終止符を打った賢いシャコがお釈迦様の前世です。 ⑥ジャータカ96 「夜叉の誘惑」 昔、バーラーナシーの王には100人の子がいた。ある日のこと、その100人目の王子が、ある修行者のもとへ相談にやってきた。 「私は王子と言っても100番目です。このままでは父王から領土を分けてもらえることはありません。とても一国の王となることはできないのです。どうしたらよいのでしょう」 修行者は王子の相談にこう告げた。 「ここからはるか北西に行ったところにガンダーラ国があり、タッカシラーという都があります。そこへ行くことができれば、必ずや国王となれるでしょう」 その話を聞いた王子は、 「そうですか。では私はその国に参りましょう」 と勢い込んで答えた。しかし、修行者はなおも告げた。 「しかし、その国に行くのはとても危険です。というのは、途中に未だかつてだれ一人通り抜けたことがない森があるのです。その森を回避すれば、ガンダーラ国へ至る日数がかかりすぎ、好機を逃すでしょう。ガンダーラ国へ行って国王となるには、この森を通らねばなりません」 「いったいどんな森なのか、あなたはご存知なのですか」 「はい、その森には恐ろしい夜叉が住んでいます。その夜叉は女で、その森を通るものを誘惑し、食べてしまうのです。未だ、その女夜叉の誘惑に勝った者はいないのです。ですから、多くの者がその森を迂回していくのです。しかし、あなたが国王となるには、この森を通らねばなりません。そして女夜叉の誘惑に打ち勝たねばならないのです。」 「わかりました。そう教えていただいたからには、絶対に女夜叉の誘惑に打ち勝ち、国王となって見せましょう」 王子はそう決意すると、翌日にも旅立つことを宣言しました。そんな王子に修行者は、砂と糸を渡し、 「夜叉が襲ってきた時は、この砂を頭からかぶり、糸を身体に巻きつけるがいいでしょう」 と告げた。王子は砂と糸を喜んで受け取った。 翌日、王子が城を旅立とうとすると、今まで仕えてきた家来が5人、供をするといいだした。王子は、とても危険な森を通るのでついてこないように言ったのだが 「大丈夫です。どんな誘惑にも負けません」 というので、供になることを許したのだった。 王子たち一行は、誘惑の森にさしかかった。注意して進むよう、王子は忠告した。しかし・・・・。 一人、二人と女夜叉の誘惑に負け、家来たちは次々に夜叉に食べられてしまった。そして、ついに王子一人になってしまったのだった。 やがて、王子は無事、森を通過し終わった。しかし、女夜叉は自分の誘惑に打ち勝った王子が許せず、王子の後を追った。 ある村にさしかかった王子を追ってきた女夜叉は、あわれな美しい女に変身して、村人に泣いて頼んだ。 「どなたか、あの前を逃げるように行く若者を止めてください。あの者は私の夫です。私を捨てて逃げているのです」 村人は女に同情し、さっさと走り抜けようとする王子を呼びとめた。 「こんな美しい女房を捨てて、あなたはどこへ行くだね。あなたはそれでも人間か。人ならば、奥さんを待ってあげなさい」 王子は、そんな村人に走りながら叫んだ。 「村人の皆さん。その女は人ではありません。夜叉です。気をつけてください。家の中に入って扉を開けてはいけません。騙されてはいけません。夜叉に食われますよ!」 「あはは、まさか。あんな美しい人が夜叉なわけがないだろ。そんな言い訳はいいから、待ってあげなさい」 村人は誰一人、王子の話を信じなった。夜叉は 「ひどい人だわ・・・。あんなにも愛してくれたのに・・・」 と泣き崩れ、村人の同情を買ったのだった。しかし、王子は村人からなんと言われようとも、止まることなく村を走りぬけたのだった。村人のなかには、そんな王子のことは忘れ、自分の女房にならないかと声をかける者もいた。こうした者は、哀れにも夜叉の犠牲になったのであった。 次の村でも、その次の村でも同じようであった。そして、ついに王子はガンダーラ国の手前の村にいたった。しかし、そこで夜叉に追いつかれてしまった。 王子は、ある家に立てこもり、修行者から授かった砂をかぶって糸で身体を巻き、身を潜めていた。その家の周りを女夜叉は泣きながら廻っていた。 「この家に私の夫が逃げ込んでいます。私を見捨てようというのです。どなたか、私の夫を呼んできてください」 そこへたまたまガンダーラ国の王が通りかかった。 「あの美しく魅力的な女は何を泣き叫んでいるのじゃ。調べてこい」 国王に言われ家来が女夜叉の話を聞いてきた。 「この家にあの女の夫が立て籠もっているそうです。それで泣いているのだそうです」 家来の報告を受けた国王は、その女のために家に向かって叫んだ。 「わしはガンダーラ国の王じゃ。中の者、汝の女房が泣いているぞ。早く出てきてあげなさい。こんなに美しく魅力的な・・・・女性を泣かすとは、許されんことじゃ」 すると家の中から王子の声が響いてきた。 「その女は夜叉です。気をつけてください。食べられてしまいますよ。もう何人もその女夜叉の誘惑に負け、食われてしまいました。王様、その女の誘惑に負けてはなりません。逃げてください!」 「なんと、お前はこんな美しい女性を夜叉というのか・・・。なんという男じゃ」 「国王様、夫が言っていることは嘘です。私から逃げたいばかりにあんな嘘をついているのです」 女夜叉はそう言うと泣き崩れた。国王は、その女夜叉を抱きかかえ、 「どうじゃ、あんな男は忘れて、わしの第一王妃にならぬか。汝のように美しく魅力的な女性なら、宮中にいるわしの王妃たちも文句は言うまい。汝に勝てるような女はおらぬ。なあ、あんな男は捨てて、わしの王妃になれ」 国王の言葉は家の中にも聞こえた。 「国王様、いけません。その女を城中に入れてはいけません。そいつは夜叉です。そんな奴を城中に入れたら国が滅びます」 王子は必死に叫んだが、女夜叉の魅力のとりこになってしまった国王は 「何を言っておるのだろうか。こんなに美しく魅力的な女性が夜叉のわけがあろうか。ほら、お前のことを思って泣いているではないか。なんと哀れな・・・。もうよい、こんな薄情な男は捨てて、城へ来なさい」 といって、全く取り合わなかった。一方、夜叉は顔では泣いていたが (城中に入れるのか・・・。うん、それもいい。もうこんな男はどうでもいい。国王について城へ行くか・・・) と心の中で王妃になることを決めていた。そうして、まだ未練があるかのような態度をしながらも、内心では喜んで国王についていったのである。 数日後のこと、いつまでも門があかないことをいぶかしんだ街の人たちが、強引に城の門をあけると・・・・そこは地獄のようだった。あちこちに人の骨や肉が散らばっており、あたりは血の海だったのである。城の中には生きている者は一人もいなかった。 「し、城が・・・・これではこの国は滅んでしまう・・・・。国王が連れ帰ったあの女は、やっぱり夜叉だったのか・・・。旅の者の言うことを聞いておけば・・・・」 街の人々はあまりに凄惨な城の中を見て、途方に暮れたのだった。 その日、すぐに街の有力者が集まって、今後のことを話し合った。 「どうだろうか、あの旅の若者に国王になってもらったら・・・。あの若者は、初めからあの女を夜叉と見抜いていた。それにあんなに魅力的で美しい女性の誘惑にも負けなかった。聞くところによると、彼と一緒に旅をした5人の者は、あの女が夜叉と知っていたにもかかわらず、誘惑に負けたそうじゃないか。なるほど、あれほどの器量をしていたのなら、誰でも負けてしまう。国王があの女を城に連れて行かなかったら、われわれも危なかったくらいだ」 「確かに、わしもあの女に見惚れていた一人じゃからのう。いいじゃろう、あの若者を王として迎えよう」 話がまとまって、有力者たちは旅の若者に、タッカシラーの国王になってもらえるように頼みに行ったのであった。 若者は、実は自分はバーラーナシーの100番目の王子でることを皆に告げ、この国にやってきたいきさつを話したのであった。 「なるほど、その修行者はこの国が滅ぶことを分かっていたのか。それで王子を遣わせたのだな。王子ならば申し分はない。早速、国王になってもらい、タッカシラーを復活させてもらおう」 こうした街の有力者たちは、新たな王を迎えたのであり、バーラーナシーの100番目の王子は、修行者の言葉通り、国王になったのであった。 誘惑には誰しも弱いものです。生きていくうえで、人は様々な誘惑に出会います。その誘惑についつい負けてしまい、初志貫徹できないのが人生なんですねぇ・・・・しみじみ・・・・。 思えば、もっとあのとき勉強していれば、あんなTV番組に負けないで勉強していれば、友人の甘い誘いに乗らないで勉強していれば、異性への興味に負けないで勉強に励んでいたら・・・・もっとましな人生になっていたかも・・・。 と思ったことが誰しもあるのではないかと思います。人は甘い誘惑に弱いものなんですよ。 大人になってからも、様々な誘惑が取り巻いていますよね。酒・タバコ・異性・風俗・賭け事・金・遊び・・・そしてワイロなど。 「おいしい話がありますよ」 罠と分かっていてもついついはまってしまう心の弱さ・・・・。 「お兄さん、いい子がいますよ」 いけないと分かっていても、ついつい足が向いてしまう心の弱さ・・・・。 「大丈夫、ばれやしませんよ。このお金でなんとか、そこのところを・・・・」 金の魔力についつい負けてしまう根性の無さ・・・・。 世の中、いっぱいありますよね、負けてしまうこと。 「わかっちゃいるけどやめられない」 そういうことなんですよね。でも、誘惑に負けるということは、身を滅ぼすということでもあります。ほら、去年のあの官僚もそうですよね。業者の甘い誘惑に負けて、官僚から一気に罪人へと転落です。 そういう悪い誘惑に負けて罪を犯してしまい、奈落の底へまっしぐら・・・・という人が後を絶ちません。明日は我が身、皆さん甘い誘惑に負けない堅固な心を持ちましょう。 そして、 「それは悪い誘惑だよ、乗っちゃだめだよ」 という忠告には耳を傾けましょう。 さらに、外見には騙されないように注意しましょう。人は外見で判断してはいけません。美しい女性、イケメン男性・・・いくら外見が良くても、性格や性質が悪い場合もあります。人は外見だけでなく、内面もよくよく見ないといけませんよね。けっして、外見や外面、肩書、見てくれ、よさそうな話・・・には騙されないよう、注意してください。外箱がいくら立派でも中身がマガイもの・・・ということなど、いくらでもありますから。人も物も、偽装にはよ~く注意してくださいね。 ということをこの物語は教えているのです。もちろん、絶世の美女であり、超魅力的な女性の姿をした女夜叉に騙されずに初志貫徹した王子こそがお釈迦様の前世です。 ⑦ジャータカ115 「欲張りなめんどり」 バーラーナシーの都の近くに大きな森があった。その森で一羽の鳥が生まれた。その鳥はヒナの頃から聡明で、いつしか森の鳥の仲間から慕われ、鳥の王になっていた。 その森は、泉もあり食べ物に事欠かず、平和で豊かな森であった。しかし、平凡な日々は退屈な日々となり、鳥たちは王に別の場所に移ることを提案した。王も仕方がなく、旅に出ることを承諾した。 ヒマラヤの近くまでやってきた鳥たちは、町に近い森で休むことにした。森は豊かで川も近くにあり、食べ物に困ることはなかった。 鳥の群れの中に一羽の欲張りなめんどりがいた。めんどりは森にいるのがつまらなくなり、町のほうへ出かけて行った。ある広い通りに出ると、そこには道のいたるところに米や豆の穀物が落ちていた。その道を通る荷馬車が落としていった穀物だった。荷馬車はひっきりなしに通り、穀物はいつも落ちていた。 めんどりは、その穀物を見つけると、目を輝かせお腹いっぱいになるまで食べた。腹いっぱいになって休んでいためんどりは考えた。 (こんなにいい御馳走にありつける場所をみんなに教える必要はないな。自分だけの秘密にしよう・・・。あぁ、でも・・・他の鳥が見つけてしまうといけないから、先に『この場所は危険だから寄りつかないほうがいい』と言っておこう。そうすれば、誰にも盗られることはない・・・・) めんどりは群れのいる森へ帰っていった。 夕方、あちこち飛び回っていた鳥たちが森に戻ると、その日の出来事を報告しあった。初めて見る花や風景、おいしい食べ物などを紹介しあった。めんどりも町の話をした。 「たくさん穀物が落ちているけど、町には行かないほうがいい。荷馬車がしょっちゅう通っているから、いつ轢かれるかわからない。とても危険だわ。あそこへ行くのは命を落としに行くようなもの」 と、みんなに警告することを忘れなかった。その話を聞いた仲間は 「いいことを教えてくれた。私は明日、町に行こうと思っていたのだ。行かなくてよかった」 とめんどりを褒め称えたのだった。そして、よい警告を与えてくれたので「警告者」というあだ名をつけた。 めんどりは (しめしめ・・・。これであの場所は私のひとり占めだ・・・) とほくそ笑んでいたのだった。 翌日、めんどりは一羽で町に出掛けた。そして、ご馳走である穀物を一生懸命についばんでいた。 (まだ大丈夫。荷馬車は遠い。もう少し食べなきゃ・・・) そう思って穀物をついばんでいると・・・・・あっという間もなく荷馬車に轢かれてしまったのだった。 夕方のこと、めんどりがいないことに気付いた鳥の王は、みんなに手分けして探すように言った。すると、町の道路で轢かれて死んでいるめんどりを見つけたのだった。王はその姿を見ていった。 「めんどりは他の鳥に町へは行くなと警告した。食べ物を独り占めしたかったのだ。そして、荷馬車に轢かれて死んだ。しかし、めんどりが死んだのは荷馬車のせいではない。自分の欲によって殺されたのだ。欲張りは身を滅ぼすのだ」 皆はそれを聞いて、愚かなめんどりを哀れに思った。 よくある話ですよね。欲張り過ぎてバカを見る、というパターンです。他人事・・・と思ってはいませんか?。物語の世界だけだと、現実にはそんな人はいない・・・と。そんなことはありませんよ。形は変われど、似たような話はよく聞きますよね。日本だってあったじゃないですか。バブル時代が。まさにこのめんどりと同じでしょ。 まだ儲かる、まだ値が上がる、もっと儲けられる、もっともっと・・・・。こんなおいしい話、他人に教える必要はない、こっそり独り占めしよう・・・・。 バブルのころは、こんなことは当たり前だったですよね。で、結果は・・・みなさんご存知の通り。いつの時代も、どこにでも欲張りなめんどりはいるんですよ。 この話を読んで、 「バカだねぇ。人間はそんなことはしない。いや、私はそんなことはしない。くだらない話だね」 と思わないでください。似たようなことをやっている者はそこかしこにいるし、意外と自分もやっているものです。よ~っく注意しましょう。 言うまでもなく、鳥の王がお釈迦様の前世です。 ⑧ジャータカ157 「ライオンと山犬」 昔、ある山の洞窟にライオンが住んでいた。ある日のこと、湖の中にある島にシカが草を食べているのが目に入った。 「あの島へは行けるのか?。ふむ、それほど遠くはない。よし・・・」 ライオンは、助走をすると湖のふちを蹴り、島に向かって飛んだ。しかし、着地したところが悪かった。泥の中に身体が落ちてしまったのだ。 「なんと・・・。この島は泥の島だったのか」 シカは驚いて逃げていった。ライオンは慌てた。慌ててもがいたが、ますます泥の中に身体が落ちていった。 「軽率だった・・・。よく見てから飛ぶべきだった。どうやら、向こう側は泥ではないようだ。しかし、このままでは足は届かない。誰か助けは来ないか・・・・」 ライオンは百獣の王であるから、助けを呼ぼうと思ったが、王の権威がすたるのでやめた。仕方がないので、誰か助けが来るまで待つことにしたのだ。 一週間がたった。ライオンは飲まず食わずで泥の中にいた。そこへひょこりと山犬がやってきた。 「うわ、びっくりした」 山犬はライオンを見て身震いした。しかし、ライオンは動ける状態ではなかった。山犬が様子を見ていると 「山犬よ・・・・。逃げることはない・・・・。わしはこのように泥の中にはまって動けない。もう一週間になる。たのむ、助けてくれぬか」 ライオンが山犬に助けを求めてきたのだった。山犬は、それを聞き、じっと考えていたが 「助けたいのはやまやまだが、助けるのはやめる」 といった。 「なぜだ?。なぜ助けてくれない」 「助けるってことは、裏切りの種をまくってことだからだ」 「裏切りだと・・・・」 「そう。おれはいつも助けたいと思っている。そういう気持はいつも持っている。でも、これまで助けてあげたものに裏切られているんだ、何度も。おれは裏切られてばかりだ。あいつを助けなければ、あのとき助けてあげなければ、こんなにつらいめにあわなかったろう、悲しいめにはあわなかったろう・・・という後悔ばかりなんだ。今だって、助けた途端に食べられてしまうだろ。だから助けられない」 「世の中のやつらは信用できないというのか」 「だって、ひどい目にばかりあってきたから」 「百獣の王であるわしも信用できないのか」 「う~ん・・・。助ければ裏切られる・・・・。でも助けてあげたあとの、あの気持は格別だ。他を助けるすがすがしい気持ちと、裏切られる悔しい気持ち・・・・。どっちが重いんだろうか・・・」 山犬は迷った。そして 「あぁ、仕方がない、助けてあげるよ」 山犬はにっこり笑ってそう言った。 「頼む・・・。わしは決して裏切らない。一生、恩に着るよ」 「その言葉を信じるよ」 山犬はそう答えると、ライオンの周りを掘り、水を流し込んだ。ライオンの重い身体が浮かんだ。山犬はライオンの下に潜り込むと、担いで島の固い土地のほうへ運んだのだった。 「ありがとう、約束は必ず守る」 そういうと、ライオンと山犬は湖で泥を落とした。ライオンの姿は、やせ細ってはいたが百獣の王の貫禄があった。山犬はそれを見て身構えた。 「あわてるな。裏切ったりはしない」 「しかし、あなたは腹ぺこだ。一応、身構えておかないとね」 「わしは百獣の王だ。いくら腹がへっても裏切りなどという卑劣なことはしない。誇りがあるからな」 その時、水牛が近付いてきた。一瞬だった。ライオンは瞬く間に水牛を仕留めた。そして、山犬に言った。 「お礼だ。水牛の一番うまいところをやろう。先に食べるがいい」 山犬は遠慮したが、ライオンも譲らなかった。そこで、山犬はライオンの言葉に甘えることにした。こうして、ライオンと山犬は仲良くなったのだ。 二匹は隣同士で住むことになった。ライオン夫婦の住まいである洞窟の、隣の洞窟に山犬夫婦が移り住んだのだ。ライオンが招いたのである。ライオンと山犬は、家族ぐるみで仲良くなったのだ。そして、お互いに協力し合って獲物を獲るようになっていた。お互い助けあって、平和で豊かに暮らしていたのだった。 しかし、それは表面的なものだった。ある日、ライオンの妻が苦情を言いだしたのだ。 「もう我慢できないわ」 「何がだ?」 「なんで百獣の王である私達が、あんな山犬と助け合わなきゃいけないの」 「おれの命の恩人だぞ。それに彼らは何かと助けてくれるじゃないか。おかげで我々は豊かで平和だ」 「わかってます。でも、山犬がいなくても豊かで平和に暮らせるわ。山犬に協力してもらって獲った肉なんて食べられません」 「何を言ってるのだ。あの山犬のどこが気に入らないのだ」 「身分が違うといっているのです。私たちは百獣の王、あいつらは・・・・卑しい山犬でしょ」 「でも命の恩人だ。わしを助けた」 「その恩返しはもう終わったでしょ」 「そうかもしれないが・・・わしはあの山犬の心を尊敬しているのだ」 「ふん、あなたは騙されているのよ」 「ちがう。あいつはこういったんだ。『これまで何度も裏切られてきた。もう裏切られるのは嫌だ。だから助けたくない。でも、助けたときのすがすがしい気持ちは、裏切られたときの哀しい気持ちよりもずっと重いものだ。だから、助ける』とな。あいつは、何度も裏切られてきた。今回も裏切られるかもしれないという危険を冒してまで、わしを助けたのだ。その心は汚れ一つないのじゃないか。そうは思わぬか?」 「裏切られるかもしれないけど、助けてあげたい・・・・。裏切られてもいいから助けてあげたい・・・・」 「そうだ。それがお前に出来るか?。わしは、そういうところに惚れ込んだのだ。だから、いつまでも一緒にいるつもりだ」 ライオンの妻は、涙を流してうなずいた。 「私が間違っていました。身分で他を判断するなんて・・・。私の心は汚れています」 「それがわかればいいのだ。さぁ、食事にしよう」 ライオン一家と山犬の一家は、その後も仲良く付き合っていたそうである。 さて、この中にはたくさんの教えが含まれていますよね。他人を助ける気持ち、もちろん見返りなど求めない、それどころか裏切られる可能性があるものを助ける・・・。ちょっとできないことですよね。 人は、たいていの場合、助ける代わりに・・・という代償を求めるものです。見返りなく助けるなどとは、なかなかできることではありません。ましてや、裏切られた経験があると、その後は他人を助けるなんてしたくなくなります。何度裏切られても人助をしてしまう、貧乏くじを引いてしまう・・・そんな人を世間では「お人よし」と嘲るんですね。 でも、ちょっと考えてみてください。菩薩はどうでしょうか?。 菩薩は見返りを求めず、助けを求めたものを助けます。もちろん、そのあとお礼参りをしろ、などとは言いません。二度とその菩薩にお参りしなくても怒ったりはしません。嘆いたりもしません。哀れに思うことはあるかも知れませんが・・・。 そう、菩薩は裏切り続けられているのかもしれませんよ、人間に。 「助けてください。助かったらお礼します」 「今度こそは、心入れ替えてやり直します。ですから助けてください」 「助けてください。今後は、精進努力いたします。迷わず、精神修養します。生活を改めます」 こんな言葉を何度菩薩は耳にしていることでしょうか。そう考えれば、人間はいかに裏切り行為をするか、よくわかりますよね。人間は裏切るものです。 でも、その裏切りにも負けずに、「人を救うことの喜び」を優先するのです。それが菩薩なのです。ああ、そうだ、子供に裏切り続けられている親も一種の菩薩ですな。ま、それは親の期待などという邪心がありますけどね。なので、菩薩の心とは比較できませんが・・・。 ともかく、この山犬は菩薩なのです。菩薩の心境を語っているんですね。ですから、物語がライオンに山犬が食われてしまっていても、山犬は満足したことでしょう。 もう一つ。ライオンの妻と、ライオンの言葉です。身分の差、貧富の差で付き合いを拒む妻。それをたしなめる夫。世の中ではよく見られる構図ですね。もちろん、逆の場合もありますよ。付き合いを拒む夫、諭す妻とかね。 とかく人は身分や貧富の差を持ち出し、付き合いを計るところがあります。その人の心の美しさで付き合うのではなく、経済的力や名誉などで付き合いを決めるんですね。それが愚かなことだとは気付かないんです。 いくら財力や名誉があっても心が歪んでいては、付き合う相手ではありません。そんな者と付き合えば、自分も心が歪んでしまいます。財力がなくても、名誉がなくても、心正しきもの、美しい心を持ったものと付き合えば、こちらも心が洗われますよね。付き合う相手を財力や名誉だけで選んではいけませんよ。 ライオンの妻の間違え、それを正した夫。素直に受け入れた妻。どちらもいい人なのです。 何度も裏切られても、それでも助けたいと思った山犬・・・菩薩・・・がお釈迦様の前世です。 ⑨ジャータカ176 「サルと一粒の豆」 昔、ブラフマダッタ王がバーラーナシーの国を治めていたときのこと。国境の部族が反乱をおこした。 季節は雨季で、長雨が続いていた。大雨で川はあふれ、田畑の作物も家も流されてしまうくらいであった。しかし、王は反乱軍を抑えるため、雨の中軍隊を出動させることにした。 王の側近に賢い大臣が一人いた。その大臣は出兵には反対だったが、進言しても聞きれてもらえないことがわかっていたため、機会が来ることを待っていた。 王の率いる兵隊がたくさんの豆を蒸し、軍馬に与えた。するとそのとき、一匹の飢えたサルがやってきて、豆の入った馬のエサ桶から豆を両手いっぱいに握りしめて木に登っていった。 サルは枝に腰を下ろし、一粒一粒食べ始めた。ふと、サルの手から豆が一粒落ちた。 「あっ!」 サルはそう叫ぶと、豆を拾おうとして枝から飛び降りた。その瞬間、両手いっぱいの豆は散らばり、叫んだため口の中の豆も飛び散ってしまった。慌てたサルは、こっちの豆そっちの豆と拾い集めようとしたが、大雨で豆は見る見るうちに流されてしまったのだった。仕方がなく、サルは肩を落として木に登っていき、恨めしそうに見下ろしていた。 それを見ていた王は 「なんなのだ、あのサルは。いったい何をしたいのだ。どうしたというのだ」 と大臣に尋ねた。大臣は 「王様、あのサルは、落としてしまった一粒の豆を拾おうとして、手に持っていた多くの豆を失ってしまったのです。小さなことにとらわれ、大きなことを見失ってしまった愚かなサルなのです。そして、すべてを失くしてしまったのです」 「おぉ、なんと愚かな・・・・。そうか、そうか・・・。わしはあのサルと同じだな」 「その通りです。小さなことに欲張っていると、もっと大きな大事なものを失くします。国も同じかと・・・・」 「わかった。このまま軍を進めたのでは、わしは国を守る大事な軍を失うことになるだろう。そういうことだな?」 「はい、その通りです」 「危ういところだった。よし、兵を戻すぞ!」 こうして王は、軍隊を戻したのであった。反乱を企てた部族も、大雨と王の出兵の噂だけで消え去ってしまっていた・・・。 「小事にとらわれ大事を失くす」 ということです。これって、意外とやっていることですよね。 人は、とかく目の前のことしか考えられない場合が多いのです。目の前のことにとらわれ、その奥にある大事なことを見逃している場合が多いんです。で、後になってわかるんです。「しまった!」と。 このサルのことは笑えません。どなたも似たようなことをしてますから。特に目の前の欲にとらわれて、友人を失くしたり、信用を失ったり・・・なんてことは、よく耳にしますからね。 あまり欲張らないで、こうなったらこうなる、そうしたらこうなる、で次にこうなってしまう・・・・というように、よく考えてから行動したいものです。サルのように慌ててはいけませんよね。 ⑩ジャータカ291 「魔法のびん」 昔、ブラフマダッタ王がバーラーナシーの国を治めていた時のこと。 この都に一人の商人がいた。その商人は人々にものを施すなど、善い行いをたくさんしたため、死後に帝釈天に生まれ変わることができた。 この商人には一人息子がいた。その息子は、父が残してくれた財産を引き継いだ。ところがこの息子は大酒飲みの怠けものだった。しかし、息子は、ただ遊び呆けるのはよくないと思い、大きな料理店を作った、が、料理店を経営するのではなく、毎日のように自分が飲んで食べて歌い踊り遊んでしまったのだった。息子は、毎日遊んだ。酒・女・博打・・・ありとあらゆる遊びをし、ついには破産してしまったのである。 すっかり財産を失くし、一文無しになってしまった息子はぼろを身にまとい、物乞いをする日々を過ごしていた。 帝釈天となった父親は、落ちぶれた息子を見て哀れに思い、天界からやってきた。そして、魔法のびんを息子にさしだしたのだ。 「おい、息子よ。お前がしっかりとこのびんを守っていったなら、財産はなくなることはない。よいか、この魔法のびんを決して壊さぬよう、しっかり守るのだ」 いくら怠け者で愚かな息子でも、びんを守ることくらいはできると考えたのだ。親心である。 一方、息子は、父親の愛情が嬉しかった。帝釈天となった今、本当ならば自分息子一人を贔屓にしてはならぬはずであった。それなのに、自分の身を案じてくれる・・・・。その愛情の深さに感謝したのだった。 「父上、ありがとうございます。何があってもこのびんだけは守り通します」 息子は、そう誓った。 帝釈天の魔法のびんのおかげで、再び大金持ちになってしまった息子は・・・・また遊び呆けるようになってしまった。毎日のように女を抱き、酒をくらい、歌い踊り、騒ぎっぱなしの日々であった。 ある日のこと、ベロベロに酔っぱらった息子は、魔法のびんを弄んでいた。 「あははは、これさえあれば、俺は一生遊んで暮らせる。いいものをくれたぜ。あははは、ほらよっと、おっとどうだ」 そう言いながら、息子は魔法のびんを放り投げて遊んでいた。 「しまった!」 すっかり酔いは冷めていた。魔法のびんは粉々になっていたのだった。 その後、その息子は再び物乞いの生活をするようになり、ついには食べものを得ることができず、野垂れ死んでしまったのである。 これもよくある話です。財産家の放蕩息子が家を潰す・・・・。昔からよく聞きますよね。この話の場合、一度はチャンスを与えられているのです。しかし、そのチャンスも大事にしなかったために失ってしまうんですね。 そもそも、働かないということがいけません。一度、辛苦を味わったのですから、心入れ替えて働けばいいものを・・・。が、今だってそんな話はよく聞きますよ。財産家の息子じゃなくてもね。 一生懸命働こう!、そう決意しても、いつの間にか家の布団の中でゴロゴロ・・・・。確かに一週間前働くことを決したはずだったんだが・・・。そう思う自分が布団の中にいる。そんな人って、結構いるんじゃないでしょうか。 まだ、帰る家があるうちはいいですよ。寝させてくれる家があるうちはいいですよ。しかし、そんな怠惰な生活をしていたら、やがて寝ることができる家も失ってしまうことでしょう。 怠けずこつこつと働く。働いた分で生活をする。そうすれば借金なんてできないし、家を失うなんてこともないでしょう。欲望に負けない自制心が大事なのです。 借金で生活が苦しい・・・という人の話を聞いていると、たいていが贅沢なんですよね。働いて頂ける賃金以上の生活をしてしまっているんです。安月給なのに豪華なTVがある。大きな車がある。ブランド物のバックや服がある。貴金属を持っている。暇があればパチンコ三昧・・・。 悪くはないですよ。好きな生活をすればいいですよ。でもね、範囲ってものがあるでしょう。借金してまで贅沢はしてはいけませんよね。ちゃんと自制しなきゃ。 自分の欲を上手にコントロールすること。それが大事なのですよ。あれもこれもといって、何でも手に入るものではありませんからね。 自制心。それがないと、この放蕩息子のように何もかも失うことになるのです。そうなれば、いくら先祖がよくても助けてはくれませんからね。お気をつけてください。 ⑪ジャータカ272 「荒らされた森」 昔、ある森に二人の樹神が住んでいた。その森には狂暴なライオンやトラもたくさん住んでいて、多くの獣を獲って食べていた。食べ飽きると、死体をそのあたりに捨ておいたので、森は動物の腐った死骸の匂いが立ち込めていた。その森には人間は誰一人として近づかなかった。 ある日、一人の樹神がもう一方の樹神に言った。 「この森は腐った動物の死骸のせいで臭くてかなわない。毎日が不愉快だ。あんたはどう思うか知らないが、わしはあのライオンやトラを追い出そうと思う」 「それはやめたほうがいい。彼らのおかげでこの森は人間の手から守られている。彼らを追い出せば、人間がここにやってきて木を伐り、畑を作ってしまう。そうなれば君も住まいを失くすぞ」 そして、歌を唱えた。 「悪友を選べば、平和は壊される。善い友を選べば、平和は増す。平和を呼ぶ友を選ぶ知恵こそ生きる道。我らの暮らしを守る善い友を選ぶべき・・・・」 ライオンやトラを追い出そうといった樹神は、この歌を聴いても意味がわからなかった。 それからしばらくったある日、一人の樹神は神通力を使って、ライオンやトラを森から追い出してしまった。 すると、森の中からライオンやトラがいなくなったことを知った人間が大勢でやってきて、木を伐採し始めたのだった。樹神は慌てた。そこでライオンたちを追い出すことに反対した樹神にどうすればいいか相談した。賢い樹神は 「彼らは隣の森にいる。戻ってきてもらうように頼んできなさい」 そう言われて住まいを失くした樹神は、隣の森に行ったが、ライオンたちは 「何を今さら。勝手なことを言うな」 と、冷たい態度だった。ついに樹神は住まいを失くしてしまった。 「だから忠告したのだが・・・。私は天へ帰るとするか」 賢い樹神は、天へと昇っていったのだった。 こうした物語を読んでいると、「バカだねぇ、愚かだねぇ、普通はこんなことしないだろう」と思うことでしょう。しかし、意外とこの愚かな樹神のようなことをやっているんですよ。 よ~っく自分の人生を振り返ってみてください。自分を応援してくれていた人に背を向けたことはないですか?。自分の味方になっていてくれた人と袂を分かつようなことはありませんでしたか?。共存共栄と気がつかず、けんか別れしてしまい後悔したことはありませんか?。 案外、ちょっとしたことで、本当は自分にとっていい友達だった人と仲違いしてしまった・・・・なんてことは、あるんじゃないでしょうか。誤解が誤解を生んで、まったく勘違いで、いい友人を失ってしまう、というのはよく聞く話です。 悪い友やつまらぬ噂話に翻弄されることなく、自分にとって大事なものはなにかということを見極めてから行動したいですね。 ⑫ジャータカ427 「スパッタの最後」 昔、霊鷲山(りょうじゅせん)の山頂に鷹の王が住んでいた。名をスパッタといった。彼は、力も強く威厳があり、偉大であった。数千もの家来を従えていたのだった。彼の力は日に日に増しており、家来の誰ひとりついていけない程、高く舞い上がることができた。そんなスパッタを見て、前王である両親は心配した。 「よいかスパッタ。あの大空には私たちが決して行ってはいけない場所があるのだ。あまり高く舞い上がり過ぎてはいけない。私たちは鳥に過ぎない。身の程をよくわきまえて、調子に乗ることなく、自分が飛んでいい範囲を知ることが大切なのだ。よいか、スパッタ。この大地が丸いお盆のように見えたなら、すぐに戻ることだ。それ以上飛び上がると、ベーランバというすさまじい風にあおられ、吹き飛ばされてしまう。よいか、ベーランバに捕まったら、帰ってくることはできない。くれぐれも高く飛びすぎないようにな・・・・」 スパッタは、 「わかりました。心配しないでください。ちゃんとわきまえていますよ」 と答えたのだった。 ある日のこと、数千の家来を連れて上空高く飛んでいたスパッタは 「ふん、誰ひとりついてこれないじゃないか。バカバカしい。どいつもこいつも情けない奴ばかりだ」 と言い放つや、さらに上空高く舞い上がった。 「俺にとっては、こんなことくらい何でもない。ベーランバかなんか知らないが、俺のこの羽根の力が負けるものか」 スパッタはどんどん高く舞い上がり、ついには大地が丸いお盆に見えるところまで到達してしまった。 「きれいだ。大地は丸いんだな。それに青い。まるで宝石だ。空気が冷たい。気持ちがいい・・・・」 そう思った瞬間だった。 「あぁぁぁぁ・・・・」 スパッタは身動きができなくなってしまった。それどころかどんどん流されていた。そして、あっという間もなく、すさまじい風に巻き込まれ、大空の彼方へ飛ばされてしまったのだった。 スパッタ王が帰ってこないことを知った家来や前王は、彼がベーランバに巻き込まれたことを知ったのだった。 このお話は「自惚れの戒め」です。読んでの通りです。しかし、こういうヤツっていますよね。実力もないくせに、背伸びして痛い目にあったり、信用を失ったり・・・・。身の程を知りなさい、と思うのですが、当人は勘違いしていますから、他人の忠告は耳に入らないんですね。スパッタと同じです。 過小評価や優柔不断もいけませんが(石橋を叩いて叩いて叩いて、結局渡らないなどというのも愚かです)、自己過信や過大評価、うぬぼれも、無謀の謗りを免れません。自己を客観的に、冷静に評価できる眼を持ちたいですね。 ちなみに、驚かされるのは、この物語ができたころに、地球が丸い、青い星である、とインド人は知っていた、ということです。高く高く上がると、大地が丸い青いお盆のように見える・・・というのですからね。インド人に驚かされますねぇ・・・。なぜ、知っていたのでしょうか?。 ⑬ジャータカ304 「竜の兄弟」 昔、ヒマラヤ山のふもとに竜王の一族がいた。竜王には息子が二人いた。弟竜は乱暴者で、いつも竜宮の女官をいたぶったりしていた。見かねた竜王は、兄竜に弟竜の追放を命じた。兄竜は弟竜に謝らせ、弟竜を許してもらった。しかし、弟竜の気性の激しさは改まることはなく、三度目の騒ぎのとき、ついに竜王の怒りは爆発した。 「お前はなぜ弟をかばうのだ。お前も大ばかものだ。お前も同罪だから弟と一緒にここを出ていけ!。バーラナシーの都の最も臭い便所の中に三年間住んでいろ!」 王の命令により、兄弟竜は竜宮を追放されたのだった。 兄弟竜は、王の命令通り、バーラナシーの都で最も臭い便所に住むことになった。それは、都のはずれの貧しい村の便所だった。兄弟竜は、その村の便所の糞尿溜まりに住みついたのだった。弟竜はいつも怒っていた。 「こんな臭い所に住むなんて・・・・クッソ~、竜王のせいだ。怨んでやる。いつか復讐してやる」 そんな弟竜を宥め諭すのが兄竜の役目だった。 ある日のこと、村の子供たちが便所の糞尿溜まりに二匹の竜が住んでいることに気付いた。村の子供たちは竜を木の棒でつついたり、石を投げたりしていじめ始めた。弟竜は牙をむき出して怒り始めた。 「お前ら、俺の猛毒で殺してやる」 兄竜は弟を押さえつけて、歌を唱えた。 「国を追われた我々は、他国に暮らす身の上だ。悪口雑言吐かれても、それを丸ごとしまい込む、大きな蔵を作るのだ。他人の素性人の徳、誰も知らぬが当たり前。知らない人ともに住み、自分が偉いと思い込む、それは無意味な高慢だ。追放された身の上だ、たとえ自分が正しくとも、愚かな人の罵りは、強く耐えねばならぬのだ・・・・。 よいか、弟よ。そもそもは、お前のその短気が原因なのだ。すぐに怒り出す、その性質を改めるのだ。そうでないと、どこにも住む場所はなくなるのだよ」 兄竜の言葉に弟竜は強く耐えしのんだのであった。 その後、弟竜は、時たま怒り出すこともあったが、兄の忠告に従い、暴れ出すことなく便所の中で三年間を過ごした。そして、竜王の許しもあり、竜宮にもどった。父竜の亡きあとは、兄竜が王となり、弟竜は兄を助けたそうだ。 ちょっとしたことですぐに怒り出す人はよく見かけます。なんでそんなことで・・・と思うようなことに引っ掛かってイライラしている人って案外多いですよね。私の周りにもかつていましたから。 短気は損気・・・と昔の人はいいましたが、まさにその通りです。気が短いのは損です。他人の言うことなどどうでもいい、と思っていれば、怒ることはないのですけどねぇ。 しょっちゅうイライラしていると、そのうちに誰にも相手にされなくなります。そんな人とは誰も付き合いたくないですからね。楽しくありませんからね。短気は孤立を招きます。わがままも大概にしておいたほうが身のためですね。 ⑭ジャータカ207 「甲虫になった王妃」 昔、カーシ国のポータリにアッサカという王がいた。王には妃がたくさんいたが、中でも第一王妃のウッパリーを愛していた。ウッパリーは大変美しく、魅力的で、他の妃は誰もかなう者がいなかった。 そんな美しい王妃であったが、ある日急病になり、あっけなく死んでしまった。王は悲しみのあまり、王妃の身体に香油をぬり、棺に納め、土を入れて自分の寝室に安置した。これを見かねた大臣たちが 「そのままでは王妃の御遺体は腐ってしまいます。どうか埋葬を・・・」 と勧めたのだが、王は頑なに拒否し、棺とともに部屋に引き籠ってしまったのだった。そうして、何日かが過ぎていった。 そんなある日のこと、ヒマラヤ山中に住む仙人が神通力により、アッサカ王の現状を知るにいたった。 「おぉ、あの王を救わねばならん」 仙人はそういうと、神通力で王宮の庭に下り立った。そして、庭にいたバラモンに言った。 「私はヒマラヤ山中に住む仙人だ。国王の現状を知り、王を救いに参った。もし、王が望みとあらば、亡くなられた王妃と会わせることができるのだが・・・・」 それを聞いたバラモンは、早速このことを大臣に告げ、大臣は国王の耳に入れた。この話を聞いた国王は大喜びし、 「すぐにその仙人に会う」 といって、引き籠っていた部屋を飛び出し、庭まで出てきたのだった。そして、王は仙人に尋ねた。 「あなたが仙人様ですか。ウッパリーは一体どうなりましたか」 「もうすでに生まれ変わっておる」 「いったい何に生まれ変わりましたか。きっと何に生まれ変わっても美しいのであろう。あぁ、早く会いたいものだ」 「王様、残念ながらウッパリー王妃は、美しい者には生まれ変わっておりません。生前、王妃は御自分の美しさを鼻に掛け、周囲を見下しておりました。国王にはどうだったかは知りませんが、周囲にはそれはひどい仕打ちを・・・・。さらには、善い行いなど一つもしていませんでした。そのため、王妃はこの王宮の庭にいる牛の糞を食らう甲虫に生まれ変わっております」 「な、何を言う。バカにするのもいい加減にしろ。そんなくだらない話は聞きたくない。わしは王妃のもとへ帰る」 「お待ちなさい、国王様。今、あなたの大事なウッパリー王妃をここへ呼んでみせましょう」 そういうと仙人は呪文を唱えた。すると牛舎のほうから甲虫が二匹飛んできた。 「国王様、なんなりとご質問ください。この甲虫、人の言葉を話せるようにしましたので・・・・」 仙人の言葉に半信半疑ながらも国王は質問をした。 「お前は、前の世ではなんという名前であったか」 すると一匹の甲虫が答えた。 「わたしはアッサカ王の第一王妃ウッパリーでしたという名前でした」 なんと、その声は生きていた時のウッパリーと同じ声だった。驚いた王は、続けて質問した。 「お前はなぜ牛フンを食らうような甲虫になったのだ」 「生前、美を誇っていて、周囲の者たちの醜さを笑ったからです。そして、わがままほうだいをしたからです。それで、このような醜い姿になりました」 王はうなだれた。 「一緒にいるもう一匹の甲虫はなんなのだ」 「これは今のわたしの夫です」 「お、お前はこのアッサカ王が愛しくないのか?。今の夫が好きなのか」 「前の世では国王に愛され幸せでした。でも、それは前の世でのこと。前世のことなどわたしには何の意味もありません。今は、この夫といることのほうが幸せです」 そういうと二匹の甲虫は仲良く連れ立って飛んで行ってしまった。あとに残された国王は、ふらふらと立ちあがると、 「部屋の王妃の棺を処分しろ。なんと虚しいことだ・・・・」 その言葉を聞いた仙人も、安心してヒマラヤに帰っていった。 国王は、その後立ち直り、別の妃を第一王妃とし、国を正しく治めるようになったそうである。 ちょっと突拍子もない話ですが、ジャータカにはこう言った話はよく出てきます。生まれ変わった虫や動物が人と話をする、という、まあ荒唐無稽な話なのですが、大事なことはその内容にあるので、設定はどうでもよいことですね。 人は亡くなくなってしまえば、骨になってしまいます。そして、違う世界に生まれ変わっていることでしょう。ひょっとしたら、身近な生き物に生まれ変わってきているかも知れません。ですから、いつまでも亡くなった人のことを追いすがってはいけないのです。忘れるのではなく、生まれ変わった世界で楽しく幸せに生きていることを願うのですね。それが先祖供養でもあるわけです。 ところが、たまに亡くなった方のことをいつまでも追い続け、メソメソしている方がいます。これはいけません。泣かれる側、つまり亡くなった側も、あまりメソメソしていると、困ってしまいます。かえって亡くなった方に迷惑を掛けることになるんですね。 生あるものは必ず死にます。いつか、必ず死ぬのです。それを認識して、たとえ愛しい人であっても、その死に直面したならば、素直に受け入れましょう。 なお、美しい方、男女を問わず、あまりに自分の美を誇りに思い、周囲を「ブス」だの「醜い」だの「見るに堪えない」などといって、バカにしないほうがいいですね。自分の美しさを誇るあまり、超ワガママになるのもいけません。歳をとれば、どんなに美しい人もイケメンも、ジジイにババアです。「別に」なんて気取っていると、来世は糞転がし・・・かも。お気を付け下さい。 なお、ここで紹介した物語は、「すずき出版 仏教説話大系4」から抜粋し、多少省略したりアレンジしたりして掲載させていただきました。興味のある方は「仏教説話大系」を読んでみてください。合掌。 |