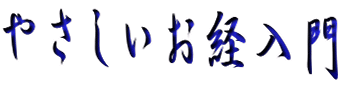
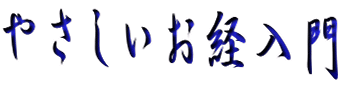
ばっくなんばぁあ~20
第 六 章
「大乗経典」
| *浄土三部経 ①大無量寿経(仏説無量寿経) 4 前回に引き続き、48誓願の残りの解説をいたします。 36、十方世界の諸仏の国土の菩薩たちが、私の名を聞いたならば、寿命が終わったあとも常に修行して仏道を成就するでしょう。そうでないならば、私は如来にはならない。 すべての菩薩が修行を止めないで、必ず如来となる、そういう浄土なのですね、西方浄土は。ということは、このころ、菩薩行を途中で放棄する人がいたのでしょう。迫害を受けたり、辛かったりもしたのでしょうね。で、西方浄土では、そうした途中でくじけるようなことがない環境にあるということですね。当時は、菩薩行をするには、環境が悪かった時代だったと思われます。 37、十方世界の諸仏の国土の天人や人々が、私の名を聞いて五体投地し礼拝し、歓喜し、信心を起こし、安楽し、菩薩の修行をしたならば、あらゆる天人も世人もその人を敬うでしょう。そうでないならば、私は如来にはならない。 どの世界の人々でも、天人でも、南無阿弥陀仏と唱え、五体投地という礼拝をし、喜びを感じ、信心を起こし、心が安楽となり、修行までしたならば、どこの世界の神も人々も、その南無阿弥陀仏と唱えた人を尊敬する、と言っているのですが、そりゃそうだと思いますよ。そりゃ、敬うでしょう。ただ単に南無阿弥陀仏と言って礼拝するだけじゃないんですよ。心から喜び、信心を起こし、安楽になって、さらに修行をしないといけないんですよ。そんな人がいたら、尊敬します。 この教えがまとめられたころ、南無阿弥陀仏と唱えていた大乗仏教のグループは、相当な迫害を受けていたのではないかと、想像できますよね。ここまでやっても、きっと尊敬されなかったのでしょうから。だからこそ、別次元の浄土を用意する必要が出てきたのでしょうから。ま、いつの世も、新しいことを始めると、迫害を受けるものですねぇ。 38、私の浄土の人々は、衣服を得ようと思ったらそれはすぐに得られ、しかも如来の意にかなった衣服となるでしょう。衣服を裁縫したり、染めたり、洗ったりする必要はない。そうでないならば私は如来にはならない。 いいですねぇ、極楽世界は。この誓願がもととなり、極楽では衣服もいらないし、不自由もしない、という話が生まれてきました。当時、衣服に事欠くような人々がたくさんいたのでしょうね。大乗仏教グループは、そうした人々に生きる希望を与えたかったのでしょう。 39、私の浄土の人々や天人が受ける快楽は、煩悩の全くない快楽であり、聖者が受ける快楽と同じである。そうでないならば私は如来にはならない。 神々や人々が受ける快楽には、煩悩がつきものです。というか、煩悩をもととして得られるのが快楽ですね。ところが、如来の快楽は、いわゆる快楽とは異なります。愉悦とでもいいましょうか、この上ない喜び、なのです。そこには、苦しみもなければ、辛さもともないません。単なる快楽とは全く異なるのです。言葉では表現しにくいですね。そうした煩悩を伴わない、悩ましい快楽ではない快楽が得られるのが、極楽浄土なのですね。 40、私の浄土の菩薩は意に従って十方無量の浄土を見たいと思えば、それに応じて悉く見ることができる。それは素晴らしく磨き上げた鏡に己を写すように明らかである。そうでないならば私は如来にはならない。 西方浄土では、菩薩であってもすべての浄土を見通すことができるんですね。しかし、これ31の誓願とちょっとかぶってます。31は、西方浄土からすべての浄土が見える、というものでした。ここでは、西方浄土の菩薩が、と限定しています。わざわざ、なぜ限定?。だって、西方浄土にいれば、誰でも他の浄土を見ることができるのに・・・・。 前の誓願を忘れてしまったのですかねぇ・・・・。なぜ、これがここで・・・・、よくわかりません。 41、他方の国土の菩薩たちが私の名を聞いたならば、その菩薩は悟りを得るまで身体は完全で不自由はない。そうでないならば私は如来にはならない。 他の仏国土の菩薩についての誓願です。たの仏国土・・・すなわち他の大乗仏教グループ・・・の菩薩であっても、阿弥陀如来の名を聞いたならば、身体に不自由はなくなる、ということを言っているのですが、当時は身体に不自由がある人々は、相当な迫害を受けていたのでしょうね。そうした人々にとって、西方浄土、極楽浄土というのは、理想の地だったわけです。そこへ生まれ変わるという希望を胸に、生き抜くことができたのでしょうね。 42、他方の国土の菩薩たちが私の名を聞いたならば、皆ことごとく清浄なる解脱の境地に至るであろう。この境地に至れば願えば無数の諸仏を瞬時に供養することができ、禅定の境地は損なうことがない。それができないならば、私は如来にはならない。 他の仏国土、すなわち、他の大乗仏教グループの修行者でも、阿弥陀仏の名前を聞いただけでも、悟りを得らる、というのですね。つまり、他のグループよりもこっちは優れているぞ、と主張しているわけです。こうした、「こっちはすごいぞ」という言葉は、どの経典にもあることなので、驚くことでもありませんし、当然の主張と言えば、当然ですね。 43、他方の国土の菩薩たちが私の名を聞いたならば、その菩薩の寿命が終わった後、その菩薩は尊い家に生まれ変わるであろう。そうでないならば、私は如来にはならない。 あれ?、悟るんじゃなかったのでしょうか?。前の誓願と矛盾してない?。と思えるような誓願です。っていうか、尊い家に生まれ変わるって、それを言いますか?。身分の差なく、悟りを得られるのが仏教でしょう。しかも、42の誓願で、清浄なる解脱の境地に至ってるんですよ。そうした者は、どこへ生まれ変わろうとも、平気なはずだし、そもそも解脱すれば生まれ変わらないし・・・・。この誓願を入れた理由がわからないです。よほど、貧しい家の信者が多かったのか・・・・。 まあ、こうした誓願があるからこそ、日本において、貧しい人々の間に阿弥陀信仰が爆発的に広まったわけでもあるのですが・・・・。どう考えても、人気取りの誓願?、としか思えません。ある党のマニフェストみたいに・・・・。ときどき、こうした変な誓願が出てくるんですよねぇ。 44、他方の国土の菩薩たちが私の名を聞いたならば、歓喜し菩薩の行を修め、徳を身につけるであろう。そうでないならば私は如来にはならない。 いい加減、同じような内容の誓願ばかりが出てきて、ちょっと食傷気味ですね。もういい、って感じになって来てます。やはり、先に48があったのでしょうねぇ。で、内容を作るのに限界がやってきた、という感じは否めません。かなり、苦しいようです。 惜しいかな・・・。 45、他方の国土の菩薩たちが私の名を聞いたならば、皆ことごとく無量の諸仏を同時に礼拝することができる境地を得るであろう。また、この境地に常にいて、自らが如来となるまで常に一切の諸仏を見ることができよう。そうでないならば私は如来にはならない。 いや、もういいっす、って感じですね。そもそも、悟りを得たならば、自由自在となるはずです。前に、何度も如来の境地を得る、と言っているのですから、あえて、どこまで見えるとか、どういうことができるとか、こと細かく説く必要はないのですよ。如来と同じ境地に至る、だからどんなこともでもできる、と同じ誓願の中で語ればいいことなのですね。本当に、底をついて来て、苦し紛れの誓願、としか思えなくなってきます。きっと、苦労したんだろうな、この経典の編纂者は・・・。 46、私の浄土の菩薩たちは、その志や願いに従って聞きたいと思う教えを自然に聞くことができよう。そうでないならば私は如来にはならない。 これも前に出てきたような・・・・。まあ、そういうことです。自由自在に教えを聞くことができる、ということですね。 47、他方の国土の菩薩たちが私の名を聞いたならば、決して退くことのない堅固なる心を得るであろう。そうでないならば私は如来にはならない。 そりゃそうでしょ。他のグループのものだって、解脱できるのですから、堅固な心くらいは得るでしょう。順序が逆ですよね。先にこの誓願を出すべきですよね。 48、他方の国土の菩薩たちが私の名を聞いても悟りの境地に至ることができず、また決して退くことない心を得られないならば、私は如来にはならない。 今までの誓願が成就しないならば、如来にはならない、と言っているのですね。おかしいですよねぇ、これも。まあ、まとめの誓願、と言えばそうなんでしょうけど。1~47の誓願が成就したならば、私は如来となる、と言っているわけで、それは当たり前のことであって、だいたい、他の誓願の一つでも成就しなければ如来にはならないのですから、あえてこれは必要ないわけで・・・・。まあ、まとめの誓願としか言いようがありません。苦しかった・・・・というのが本音でしょうか。 というわけで、苦しみながらも48の誓願を造り上げ、それを成就するために修行に励んだのですよ、法蔵菩薩は。で、なんとか、すべてを成し遂げたのですね。で、阿弥陀如来となって極楽浄土を築き上げた・・・・。 ちょっと待ってよ。おかしいじゃないですか。先に浄土がなくてはならないでしょ、この誓願を見てみると。「私の浄土では・・・・」と言っているのですからね。 普通、如来になって初めて仏国土をもつことができます。あるいは、如来になれるけど、人々を救うためにあえて如来にならない菩薩であれば、浄土をもつことができます。たとえば、観音様のような補陀落山(ふだらくさん)のように(ここは蓮の花で囲まれた浄土だそうです)。まあ、法蔵菩薩もそういう状況であったと、解釈すればいいわけですが・・・・。 まあ、なにはともあれ、誓願は成就されたのです。誓願通りの極楽浄土がつくられたのですな。 こうした誓願を法蔵菩薩が立て、それを成就したと話を説いているのは、お釈迦様です。忘れてはいませんよね。こういう菩薩がいて、こういう誓願を立てた、というところまで、お釈迦様が説いたわけですね。なので、お釈迦様の言葉に戻ります。 少々、略してあります。 「・・・・・阿難よ、法蔵菩薩は、これら48の誓願を成就し、すでに悟りを開き、如来となっている」 「えっ、この誓願を成就されたのですか。では、法蔵菩薩は今どこにいらっしゃるのでしょうか」 お釈迦様は、西の方の空を仰ぎ眺めると目を閉じた。しばらく瞑想をしていたが、ふと眼を開き、優しい眼差しを人々に向けたのだった。 「阿難よ、ここから西に向かって十万億の仏国土を過ぎたところに、極楽浄土と呼ばれる世界がある。その極楽浄土で、法蔵菩薩は阿弥陀如来となり、多くの菩薩や弟子に法を説いているのだ。この極楽浄土こそ、法蔵菩薩が理想の国土として掲げた国土であり、法蔵菩薩は厳しい修行の末、築くことができた浄土なのだ。法蔵菩薩は、この浄土を造り上げるのに気の遠くなるような時間を要した。そして、この極楽浄土が完成してからも、すでに気の遠くなるような時間が過ぎている」 「その極楽国土は48誓願にあるように、光り輝くものであり、あらゆる財宝でできているのでしょうか」 阿難の質問に、お釈迦様は 「よろしい、極楽国土のことを説こう」 といい、極楽浄土の素晴らしさを紹介したのであった。 「極楽国土は、広さに制限がない。空気は澄み渡り、いつも心地よい風が吹いている。そこにいる人々は老いることがない。美しく咲いた花はしぼむことがなく、その中を色とりどりの鳥が美しい声を響かせる。それはまるで妙なる音楽を聴く様である。大地は金・銀・瑠璃・玻璃・珊瑚・瑪瑙・しゃこの七宝からできている。それらは互いの光で輝き合い、まばゆく光っている。それらは清浄で、その荘厳さはどこの浄土にもない。また、大地だけでなく、木々も七宝でできている。一つの木がいろいろな宝でできているという木もある。そうした木々には、花や実が過不足なく付いている。乱れた姿はなく、調和がとれている。目も眩むばかりに美しく輝き、また風が吹けば、木の葉がすれ合う音が、妙なる音楽を奏でるのだ。 ここにはひときわ大きい道場樹という木があり、この木はありとあらゆる宝で出来上がっている。どこからともなく風が吹き、この道場樹の葉が触れ合うと、妙なる音が響き、それは教えを説く声となるのだ。その声は、十方に響き渡り、他の諸仏の国土まで響くのだ。 極楽浄土には、七宝で造られた楼閣や宮殿がある。それらもまばゆく光り輝いている。宮殿や楼閣の周りには、池がある。その池の水は八功徳水という八種の優れた特性をもつ水であふれているのだ。そのほかの建物も自然も、すべて七宝でできており、極楽浄土は絶えず光り輝いているのだ。池の中には、色とりどりの蓮の花が咲いている。この池の水の深さは自在である。足首までの深さを望めば水の深さは足首までとなり、膝の上までと思えばひざ上となり首まで池の水に浸りたいと望めば首まで深くなるのだ。また水温も思うがままである。冷たい水を望めば冷たくなり、温かい水がよければ温かくなるのだ。水面に立っているさざ波は、望む音に変化する。教えが聞きたいと思えば教えの声になるし、静かなる音を望めばそのような音となるのだ。 極楽浄土で食事を望めば、七宝でできた器にこの世では見ることができないような御馳走が盛られて出てくるのだ。しかし、一切の執着をなくしている極楽浄土の人々は、その食事を食べることもなく、見て香りをかいだだけで満腹となる。 また、極楽浄土には山や谷といったでこぼこがない。起伏がなく、まっ平らな台地となっている。しかし、もし山が見たい、谷が見たいと望むならば、目の前に素晴らしい山々が現れる。見たいと思う景色や風景が自然に現れるのだ。さらに気候も穏やかで、暑くもなく、寒くもない。気候の不順もなければ、嵐もないのだ。それが極楽浄土なのだ」 お釈迦様の話に、人々は、極楽浄土の素晴らしさを胸に描いたのだった。 この内容に元に、平安時代後期の貴族たちは、この世に極楽浄土を実現しようとしました。その代表的な建築物が宇治の平等院です。平等院鳳凰堂は、まさにこの経典に従って、造られたそうです。極楽浄土にあこがれ、生きているうちに極楽浄土の世界を味わいたかったのでしょうねぇ。極楽国土がどんなところか、想像できない方は、宇治の平等院を御参拝ください。 ここに説かれているように、極楽浄土は理想世界です。暑くもなく、寒くもなく、嵐もなく、山もなく、谷もなく、すべては宝石でできており、輝いている。食事の心配も衣服の心配もない。生きることにおいて、心配事などないのですね。ただ、如来の教えを聞いていればいい。ここに生まれ変わる者は、すでに深い信心をもっているものですから、仏の教えを疑う者などいません。また、性もありませんから、そうしたことで悩む必要もないのですね。なんとまあ平和な。理想国家であります。 が、退屈なのは言うまでもありません。何もすることがないのですから・・・・。 しかし、こうした世界が望まれるということは、いかに当時は苦しみが蔓延していたか、ということなのです。食事も満足に得られず、衣服も満足に得られず、暑さに苦しみ、寒さに苦しみ、山を越え、谷を分け入って食べ物を得たのでしょう。そうした苦しみから、誰もが解放されたい、と思っていたのでしょうね。そうした人々から思えば、極楽浄土は絶対に行きたい場所NO.1となることは間違いありません。苦のない世界なのですから。 そう思えば、今は平和なのでしょうね。特に日本は・・・・。平和すぎて、他人の苦しみが理解できないくらいになっています。いったい日本人は、どこまで堕落していくのでしょうか・・・・・。 今回は、ここまでにしておきます。合掌。 ①大無量寿経(仏説無量寿経) 5 お釈迦様は極楽浄土の状況を人々に説いた後、阿弥陀如来についても語ります。阿弥陀如来がどんな如来か、ということですね。 「阿難よ、人々よ、これより阿弥陀如来について説こう。 阿弥陀如来は、その身から光明を発する。その光明はあらゆるものの中で最も尊く、他の諸仏の及ぶところではない。あるときは百の仏を照らし、あるときは千の仏国土を照らす。それは阿弥陀如来にとって自在なことである。そのため、阿弥陀如来のことを無量光如来・無辺光如来・無礙光仏・無対光仏などと呼ばれる。 また阿弥陀如来の光を浴びたものは、貪りや怒り、愚かさが消え去り、心は安らかとなり、喜びで満ち溢れ、教えを学ぶ心が起こるのである。さらに、地獄・餓鬼・畜生に生まれたものでも、阿弥陀如来の光明を見たならば、苦しみはたちまちに消え、平安な風が吹いてくるのだ。そして、その者たちが寿命を終えた時には、それらの者は必ず極楽浄土に生まれ変わるのである。また、この光明の功徳を聞き、阿弥陀如来の名を日夜唱えたものは、必ず極楽浄土に往生するであろう。 阿難よ、阿弥陀如来については、どんなに多くを語っても語り尽くせないのだ。 阿難よ、阿弥陀如来の寿命について教えておこう。その寿命は、知りつくすことができないのだ。したがって、阿弥陀如来のことを無量寿如来ともいう」 そのとき、霊鷲山は夕日に赤く染まった。 「あの夕陽の向こう、はるか西方に極楽浄土はある」 お釈迦様がそういうと、人々はお釈迦様を礼拝し、そして西に向かって礼拝したのだった。 おおよそ、こんな感じで大無量寿経(仏説無量寿経)は終わります。多少はしょってありますが、ご了承ください。 重要な事柄は、阿弥陀如来の光明は無量であり、素晴らしいものである、ということと、寿命がとてつもなく長い、ということです。そのために、阿弥陀如来のことを「無量光如来」とか「無量寿如来」ともいう、ということですね。 一たび阿弥陀如来の光明に照らされれば、誰の心にもある「貪り」や「怒り」、「愚痴」、「妬み」、「恨み」、「羨み」、「愚かさ」という「心のマイナス要素」がたちまちに消え去ってしまう、と説いています。これはありがたいですね。人間は、常にこの「心のマイナス要素」に苦しんでいます。 いろいろなものを欲しいと思う心、あれがしたいこれがしたいと思う心、もっともっとという心、怠けたい遊びたいさぼりたいという心・・・・こうした心が貪りですね。 他人に対して怒ったり、苛立ったり、妬んだり、恨んだり、羨んだり、グチグチと不平不満を持ったりもします。またそうした考えが間違えだよということを理解しない、理解しようとしない、理解しても直せない愚かさがあります。 これらが、誰もが抱える「心のマイナス要素」です。みな、誰しも、このマイナス要素に苦しむんですね。自己嫌悪に陥ったり、生きていくのが辛くなったり、嘆いたり、苦しんだりするのです。 そうした苦しみも、たった一度だけでも阿弥陀如来の光明に照らされれば、たちまち消えてしまうのです。心はすっきりですね。悩んできたのが嘘のよう。それが阿弥陀如来の功徳なのです。 しかし、阿弥陀如来の光明に照らされる、といってもどうすればいいのか分かりません。阿弥陀如来に会えないのですから。実際に目の前に阿弥陀如来がいるわけではないのですから。 では、どうすればいいのか・・・・・。 答えは最後の部分に隠されているのですよ。 阿弥陀如来はどこにいるのか?。そう、西方です。西方極楽浄土が阿弥陀如来がいらっしゃる世界です。それは遥か西の方、ずーっと、ずーっと西の方なのです。 真西に太陽が沈む時はいつでしょうか?。そう、春分の日と秋分の日、ですよね。このときは、真西に太陽が沈みます。真西がわかる日でもあります。 その日、太陽が沈みゆく方向には、極楽浄土があります。阿弥陀如来がいらっしゃいます。人々は、真西に沈みゆく太陽を通して、極楽浄土を見たのでしょう。感じたのでしょう。また、阿弥陀如来の姿を、夕日に重ねて見たのでしょう、観じたのでしょう。 真西に沈みゆく太陽に向かって、静かに手を合わせてみましょう。心を一つにして、南無阿弥陀仏と唱えてみましょう。すると・・・・。 太陽の光が、実は阿弥陀如来の光・・・光明であるかもしれません。いや、阿弥陀如来の光明であると信じることが大切なのです。阿弥陀如来の御光が、今私に注がれている、と感じることが大切なのです。それこそが、「信心」であり、極楽浄土へ行くための「切符」になるのです。ここを疑うものは、極楽浄土への切符は手に入らないのです。 貪りや怒りや愚痴、愚かさと言った「心のマイナス要素」は、きれいさっぱり無くならないかも知れません。しかし、一心に礼拝した後は、きっと清々しいものです。なぜか、心が晴れ晴れとしています。ただ、それが持続できないだけです。 でも、いいんです、それで。持続できなくてもいいのです。マイナス要素が溜まってきたら、また西に向かって手を合わせればいいのですから。その繰り返しでいいのです。 そうやって、人々は阿弥陀如来を信じ、極楽浄土に往生することを信じて、生きてきたのですね。だからこそ、昔の人は、心が折れにくく、強かったのです。 現代。信心はどこかへ捨て去られたかのようになっています。純粋な信心はどこかに置き忘れてしまったかのようです。流行っているのは、霊能者を目的とした新興宗教やサロン的新興宗教くらいで、純粋な信心などどこかに置き忘れているのです。 お寺に人が訪れても、それは観光であって、心からの信心参りではないでしょう。「縁結びを祈りに来た!」という若い女性でも、半分は遊びの気分があるのではないでしょうか?。「もしかしたらラッキーがおこるかもしれないでしょ」程度なのではないでしょうか?。 阿弥陀信仰が流行った当時、人々にはそんな余裕がなかったのです。本当に心から極楽浄土に往生することを願わねば生きていけなかったのです。それほど辛い時代だったのですね。 今は、本当に豊かです。平和です。抱えている悩みだって、いわば贅沢な悩みなのです。 もちろん、だからといって、昔のような時代と比較して君たちは贅沢だ、などとナンセンスな説教をするつもりはありません。そうではなくて、どんな悩みであろうと、悩みであることには変りはないのですから、昔の人がしたように心から祈ってはどうだい?、と提案しているのですよ。 悩みがあるなら、西に向かって、沈む夕日に手を合わせてみるのもいいんじゃないかと思うのです。そこから何か光明が見えてくることもあると思うのですよ。 悩んでないで、信心してみるのもいいのではないでしょうか。それを説いているのが、この無量寿経なんだと思うのです。 さて、我ながらうまくまとまったということで、無量寿経については今回で終わりです。次回からは、「観無量寿経」に入ります。これは、あの有名な話が出てきます。どんな話か?。それは次回のお楽しみです。合掌。 ②観無量寿経 1 今回から、浄土三部経のうちの2番目、観無量寿経に入ります。このお経、簡単にその内容をいいますと、それはあの有名な「ダイバダッタの策略」に絡めて、阿弥陀浄土や阿弥陀如来を観想する教えを説いています。ですので、みなさんも聞いたことがあるかもしれないような話が出てきます。物語になっていますので、ある程度は省略しまして、また、わかりやすいように足りない部分はつけたしなどしまして、読みやすくわかりやすくしておきます。 お釈迦様の晩年に差しかかったころのことである。その日、お釈迦様は霊鷲山(りょうじゅせん)でいつものように教えを説いていた。そこへ、マガダ国の使いの者が走ってやってきたのだった。弟子の者が 「今は法話中です」 と止めたのだが、尋常ではない様子にお釈迦様が、その使いの者に 「何事か」 と尋ねた。その使いの者は、 「アジャセ王子が・・・・アジャセ王子が、謀反を起こしました」 と告げたのだった。 マガダ国王のビンビサーラは、人々に信望の厚い国王であった。また妃のバイデーヒーも国民から慕われていた。二人にはアジャセ(アジャータシャトル)という息子がいた。マガダ国は平和であった。アジャセにあの男が取り入るまでは・・・・。 アジャセにはダイバダッタという出家者の友がいた。ダイバダッタは仏陀釈尊(お釈迦様)の従弟に当たる。年は釈尊よりもずいぶんと下であった(ダイバダッタの年齢については、お経によって「一つ年下」、「数歳年下」、「かなり年下」という設定がある。ひょっとすると、ダイバダッタと思われる人物は何人もいたのかもしれない)。 ダイバダッタは、ある日のこと大勢の弟子に囲まれて説法をしている仏陀世尊の前に進み出て、 「世尊よ、世尊はずいぶんと年をとられました。見るからに衰え、力も弱り、人生の晩年に差し掛かっております。これでは、多くの弟子を指導していくのは難しいでしょう。世尊よ、この際指導者の立場を引退し、弟子の指導から解放され、安楽な晩年を過ごされてはどうでしょうか。教団のことは、この私にお任せいただければいいのです。私は今まで以上にしっかりと教団を率いていきます」 と声高らかに言ったのだった。世尊は 「ダイバダッタよ、そのようなことはいってはいけない。心を落ちつけ、よく考えよ」 と諭した。しかし、ダイバダッタは世尊の言葉を受け入れず、再び同じことを言った。世尊よ、引退せよ、と。 世尊も再び戒めた。が、三度、ダイバダッタは同じ言葉を繰り返した。世尊も同じように戒めた。が、ダイバダッタは聞き入れようとはせず、 「老体なのだから、引退すればいいのです。教団は私が率います。私の方がうまく教団を率いることができます」 と大声で言ったのだった。それを聞き世尊はダイバダッタに厳しい口調で叱った。 「ダイバダッタよ、私は優秀な二大弟子と言われるシャーリープトラやモッガラーナにすら教団を譲る気はない。ましてやその二人に及ばない汝に譲ることなどありえない。ダイバダッタよ、お前は権威や権力に執着し過ぎている。私はよく知っている。おまえはアジャセ王子に取り入るため、神通力を使って幼児になり、アジャセ王子の膝元で戯れたり、王子のたらしたよだれさえ飲み込んだであろう。何のためにそこまでしたのか。何の野心があるのだ。よだれを飲むまでして、権威が欲しいのか。私はそのような者に教団を任せる気はない。ダイバダッタよ、このようなことをする自分自身、恥ずかしくはないのか。もし、少しでも恥ずかしいと思うのなら、これ以上のことを私に言わせるではない。静かにこの場を立ち去るがよい」 ダイバダッタは、世尊の前で両手を強く握りしめて立ちすくんだ。彼の腹の中は怒りで燃えていた。 (くっそ、何もそこまで言うことはないだろう。大勢の前で恥をかかせやがって・・・・・。くっそ、こうなったら・・・・アジャセをそそのかすしかないな) ダイバダッタは、無言で世尊の前を立ち去ったのだった。 ダイバダッタは、すぐさまアジャセ王子のもとへと向かった。 「王子よ、御機嫌は如何かな」 「おぉ、ダイバダッタ尊者。今日はどんな神通力を見せてくれるの?」 「王子よ、今日は大切な話があってきました。とても重大なことですから、よくお聞きください」 「いったいどうしたというのですか、ダイバダッタ尊者」 ダイバダッタの真剣な表情に、アジャセ王子も緊張したのだった。 「いいですか王子、あなたの父上ビンビサーラ王は、連日のようにこの国の宝物を車に山のように積み上げ、世尊とその弟子たちに貢いでいます。このままだと、この国の宝物庫は空になり、国が滅んでしまうでしょう。それを防ぐには、ビンビサーラ王を止めなければなりません。それには、アジャセ王子、あなたが早く王位につくことです。それが国のためになります。あなたがこのマガダ国の新しい王となり、そして世尊を教団指導者から外し、私を教団の指導者とするのです。そうなれば、この国の宝は減るどころか、益々富栄えるでしょう」 「ダ、ダイバダッタ尊者・・・・。それはいくらなんでも・・・・無謀です。父王はまだ元気ですから・・・」 (ちっ、ガキめ、俺の言う通りにすればいいものを・・・) ダイバダッタは、暗い顔をして、アジャセに尋ねた。 「王子よ、あなたは父王を優しい方だと思っているでしょう」 「も、もちろん・・・父王はとても優しい人です。私にも国民にも」 「ふん、うふふふ」 ダイバダッタは不気味に笑った。 「王子よ、あなたは御存知ない。あなたと父王の間の因縁を・・・・」 「な、なんですか、それは?。ダイバダッタ尊者、そんな話は聞いたことがありません。いったい何を隠しているんですか?。どうか、お教えください」 「いいでしょう、そこまでいうのでしたらお教えしましょう。アジャセ王子、あなたと父王は、生まれながらの仇敵なのですよ」 「生まれながらの仇敵?」 「王子よ、あなたの小指は一本折れていますね。それはいつからそうなっているのですか?」 「た、確かに私の片方の手の小指は一本折れまがっている。これは生まれつきそうなっている・・・・と聞かされているが・・・、それがどうしたというのか?。この指に何か秘密でもあるのか?」 「お知りになりたいですか、アジャセ王子?」 ダイバダッタは、アジャセ王子の目を食い入るように見つめ、そう言った。アジャセは、恐ろしさに少し身を引いたのだが、首をゆっくりと縦に振ったのだった。 「そうですか・・・聞いたことを後悔するかもしれませんが、構いませんね・・・・。わかりました。お話しましょう。 アジャセ王子、あなたの父上と母上は、長い間お子さんができませんでした。お二人は、あちこちの神に祈り、子供が生まれるように願ったのです。しかし、それでも子供には恵まれませんでした。ある日のこと、お二人の元にある占い師がやってきました。そしてこう言ったのです。 『見えます、見えます・・・・。ある山の中に仙人がいます。この仙人の寿命は尽きようとしています。この仙人の寿命が終わると、この仙人は王様の御子息となって生まれ変わってくるでしょう』 国王はこの話を聞いて大いに喜んだのです。そして、その占い師に 『その仙人はいつごろ寿命を終えるのだ』 と尋ねたのです。占い師は 『あと3年の命でしょう』 と答えました。しかし、国王は3年が待ち切れなかったのです。占い師に仙人の居場所を聞くや否や使者を仙人の元へと走らせました。そして、仙人に伝えたのです。 『占い師の言葉によると、あなたは3年後に死んで、我々の子・・・王子に生まれ変わることになっている。しかし、3年も待つことはできない。仙人よ、今すぐ死んでいただくわけにはいかないか』 と。もちろん仙人はこれを断り、使者を追い返しました。使者はすぐさま王宮に戻り、仙人の答えを国王に伝えました。国王はそれを聞き、カンカンに怒り、 『私はこのマガダ国の国王だぞ。国王がへりくだって頼んでいるのに・・・仙人め、なんというヤツだ』 と叫んだのです。あの温厚なビンビサーラ王が、ですよ。王は、改めて使者に命じたのです。 『もう一度仙人のところへ行き、早く死ぬように頼んで来い。もし、それを聞き入れないようなら・・・・殺してもかまわん。仙人が死ねばそれでいいのだ。私の息子に生まれ変わってくるのだからな。仙人として3年過ごすよりも、早く私の息子になったほうが、幸せに決まっているからな・・・・』 と」 ダイバダッタの話に、アジャセは驚きを隠せないでいた。ここまで聞けばほぼ想像はつく。だが、アジャセはダイバダッタの話の続きを待ったのだった。 「王子よ、この先も聞きますか?。そうですか・・・では続けましょう。 国王の命を受けた使者は、再び仙人の元を訪れ、早く死んでくれるように頼みこみます。しかし、仙人は首を横に振るばかりでした。使者は仕方がなく、仙人を殺そうとしました。仙人はあわてて使者を制して言ったのです。 『待ちなさい。あなたが私を殺すのはよいが、私を殺して城に戻ったら、私のこの言葉を国王に伝えてください・・・・。国王ビンビサーラは私の寿命が尽きる前に、間接的ではあるが私の寿命を奪った。私も国王の息子、王子として生まれ変わったならば、同じように間接的ではあるが、国王ビンビサーラの寿命を奪うであろう』 仙人はそう言い終わると、使者が突き出した刃物に無抵抗で刺され、亡くなったのです。その日の夜のこと、母上は妊娠する夢を見ました。やがてそれは真実となり、母上は、アジャセ王子、あなたを身ごもったのです。 国王は、占い師を呼び、妃のお腹の子が男であるか女であるかを占わせました。占い師は 『このお子さんは男の子でしょう。王子に間違いはございません。しかし・・・・』 というと、暗い顔になった。国王は、話を続けるよう促した。 『はぁ・・・なぜにこのように早く御懐妊されたのか・・・・。以前私が占った時は、確か3年後だったはず・・・。しかも、このお子さんは、なぜか国王様に恨みを抱いております。このお子さんが成長したときには、国王様に必ず害をなすでしょう』 占い師は、暗い顔をしてそう告げました。国王はその占い結果を聞き、青くなって自室に籠ってしまったそうです。そして、その日から、ビンビサーラ王の苦悩の日々が始まったのです・・・・」 ダイバダッタは、嫌な笑い顔をしてアジャセを見下したのだった。 ②観無量寿経 2 アジャセ王子は冷や汗を流していた。その顔は苦悩に満ち、蒼白であった。 (ふん、まだ驚くのは早いぜ、アジャセよ。これからが面白いところなのだよ) 不気味な微笑みをしながら、ダイバダッタは話を続けた。 「ビンビサーラ王は、悩みました。そりゃそうです。自分が命じて仙人の命を奪ったのですからね。恨まれても仕方がないでしょう。自分に対し恨みを持った子供が生まれてくる・・・・これは恐怖ですよ。毎日が地獄の日々です。お妃様のお腹は、日に日に大きくなっていくのですからねぇ・・・。 いよいよ、出産が迫ったある日のこと、国王はお妃様にとんでもないことを願い出るんです。そう、国王は 『イダイケよ、お前が身ごもった時、私はとある占い師に生まれてくる子供のことを占ってもらった。そのことは知っていよう。その時の結果は、この子供は国王である私に必ず害をなす、と言うものだった。も、もちろん、それをすべて信じているわけではない。わけではないが、もしそれが真実であったならば、国王としてそれは防がねばならない。害をなす可能性があるならば、国のためにその害を防がねばならぬのだ』 その話を聞いたお妃様は、たいそう驚き、国王にどうすればよいのか尋ねました。国王は 『イダイケよ・・・。お前は、いよいよ出産という時が来たら、高楼に上り、そこから子供を産むのだ。だ、誰にもその子を受け止めさせてはならない』 『そ、それでは生まれてくるこの子は・・・』 『あぁ、子供は地面に落ちてしまうだろう。それしか方法はないのだ。そうすればすべてうまくいくのだ。国のためなのだ』 『そ、そんな恐ろしい・・・・』 お妃様は、首を横に振ったのですが、国王に逆らうことはできません。お妃様は国王の命に従ったのです。つまり、出産の日、お妃様は高楼に上り、お子さんを生んだのです。しかし、あろうことか、その子は小指を折っただけで、命は助かってしまったのです」 そこまで聞いて、アジャセの顔色はだんだんと赤くなっていった。 「ダ、ダイバダッタ尊者よ、その話は本当か?。もし本当ならば・・・。この指にはそんな秘密があったのか・・・」 「アジャセ王子よ、これはすべて本当の話です。知らなかったのは、王子様だけです」 「そ、そうなのか・・・・。もちろん、仏陀世尊も御存知なのだな?。家臣の者も知っているのだな」 ダイバダッタはゆっくりとうなずいた。 「そうか、それで仏陀の弟子も家臣の者も、みな私にはよそよそしい態度なのだな。そうか、そういうことだったのか。ならば・・・・・」 「ならば?」 「ダイバダッタ尊者よ、よく教えてくれた。尊者よ、尊者が言うように、私は国王の座につこう。今こそ、恨みを晴らして、私が王位につこう。父王を殺そうではないか。なればダイバダッタよ、そなたも世尊を追い出すか、殺してしまえ。教団の統率者となるのだ。私はマガダ国を、そなたは教団を手中に収めるのだ。そのためにはどんな援助でもしよう」 アジャセ王子は、そういうと勢いよく立ちあがったのだった。ダイバダッタは、笑いをこらえるのに必死だった。 翌日のこと、アジャセ王子は妃のところへ駆けつけた。そして、小指を妃の目の前に突き付け言った。 「母上、この小指の秘密を教えてください」 「な、何を・・・・それは・・・・。こ、小指がどうしたというのです?」 「とぼけないでください。私は昨日、ダイバダッタ尊者から話を聞きました。この小指にまつわる話をね」 「な、なんと・・・・、ダイバダッタ尊者が・・・・なぜ、その話を」 「そのうろたえようは・・・・、尊者の話は嘘ではないのですね。嘘であって欲しかった・・・。あなたたちにとって、私は邪魔な存在なのですね。私は生まれてきてはいけなかったのだ」 「そ、そんなことはありません。た、確かに私たちはあなたを一度は亡きものにしようとしました。でも、助かったあなたを見て、国王も私も目が覚めたのですよ。私たちの過ちに気付き、あなたを失わなくて良かったと、心から喜んだのです。だからこそ、あなたを育ててきたのです。もし、本当に邪魔であるならば、あなたの命を奪う機会は何度もありました。でも、それはできなかったのです。そうしなかったのですよ。なぜなら、私たちは、心からあなたを愛しているからです」 「今さら何とでも言えますよ。ふん、あなたたちは、怖くて手を下すことができなかっただけでしょう。結局は、自分がかわいいんですよ」 「違います、それは誤解です、アジャセよ、誤解なのですよ」 「誤解ねぇ・・・。もういいです。私は・・・許さない」 そういうとアジャセ王子は自室に戻り、自分の配下である家臣に命じた。 「国王が乱心した。私を殺そうとしたのだ。今すぐ国王を幽閉せよ!」 国王乱心の言葉は、あっという間に宮中に広まった。国王側近の家臣や兵までもが動揺したのだった。アジャセ王子直属の兵隊たちの行動は早かった。国王を警備する兵たちの動揺の隙をつき、あっという間に国王を捕縛したのだった。あまりのあっけなさに、国王はこの日を待っていたのではないかと、噂する者もいたのだった。 ビンビサーラ王は牢獄に幽閉された。 「何人たりともビンビサーラ元国王に近付いてはならぬ。もし、近付く者がいたならば、その場で即刻処刑する」 ビンビサーラ元国王が幽閉されている牢獄に至るには、7つの扉を通らねばならなかった。アジャセは、その扉ごとに番人をおいた。今、アジャセはその牢獄の前にいた。 「父よ、いや、父だった人よ、なぜあなたはここに入れられたのか、わかりますね」 ビンビサーラは何も答えず、牢獄の隅で結跏趺坐し、目を閉じていた。 「ふん、いつまでそうしていられるかな・・・・」 アジャセは、そういうと、 「誰も通すな」 と番人にいいつけて牢獄をあとにした。 一方、国王幽閉の知らせを聞いたイダイケ夫人も、妃の部屋に閉じ込められていた。部屋の前には兵士が立っていた。夫人は、部屋から一歩も出られなかったのであった。しかし、ビンビサーラ元国王とは違い、食事も運ばれてくるし、室内では自由に振舞うことができた。 「このままではいけない。国王が飢えてしまう。なんとか国王を助けなければ・・・・」 ビンビサーラ国王が幽閉されて3日ほどたったころ、イダイケは行動に出たのだった。 夫人は、まず沐浴をして身を清浄にした。そして、全身に、牛乳と蜂蜜と麦の粉を混ぜて練ったものを塗りつけたのだ。夫人は、その上に清潔な衣をはおった。また、いつものように宝石類で身を飾った。王妃の冠の内側には葡萄酒を詰めた革袋を隠し、髪の毛でそれを覆った。首飾りの宝石類で、中が空洞になっているものにも葡萄酒を詰め、穴を蝋でふさいだ。こうして、身につけらるだけの食料を身につけ、扉の前の兵士に「アジャセ新王に挨拶をする」といって通してもらった。 夫人はアジャセの前にはいかず、そのまま牢獄へ向かった。各扉の番人には「アジャセ新王から許可をもらっている」といって、通してもらい、7つの扉を通過していったのだった。そして、夫人は牢獄の番人にも 「アジャセ新王からの許可はもらっている。鍵を開けて、私が入ったらすぐに閉めなさい。私が合図するまで、扉の外で待っていてください」 と告げたのだった。こうして、イダイケ夫人は、ビンビサーラ国王と面会できたのである。 ビンビサーラ王は、結跏趺坐のままの姿でやつれていた。 「国王よ、アジャセは・・・なんということを・・・」 「嘆くな、イダイケよ。アジャセは悪くはない。こうなったのも、すべては私自身が原因なのだ。この三日間、私は私の犯した罪について懺悔していた。こうした懺悔も大事なことだ。それにな、ここにいるのもいいものなのだ。この窓から世尊のおられる霊鷲山(りょうじゅせん)が見えるのだ。こうして結跏趺坐をし、窓の外の霊鷲山を見ておれば、何の辛いこともない。ただ、空腹なだけだ・・・・」 「そう思いまして、ほれ、このように・・・・」 イダイケ夫人は衣服を脱いだ。そして、身体に塗ってあった麦の粉を丸めて団子のしたのだった。 「ここには葡萄酒が・・・」 そう言って冠をはずし、葡萄酒の入った革袋を出した。ビンビサーラ王は、葡萄酒を一口飲んだ。 「あぁ、生き返った。ありがとう・・・・。しかし、こんなことはいつかは発覚する。そうなれば、イダイケよ、汝の命も危ない。これ以上、アジャセに罪を犯させてはならぬ。私のことはいいから、アジャセを許してやってくれ・・・・」 「ビンビサーラ様、あなたはこのような状態になってもアジャセのことを・・・・なぜそこまで・・・・・」 「アジャセは我等の子だ。しかも、このマガダ国を背負っていかねばならぬ。国王になる者に、これ以上に苦しみを与えてはならぬ。さぁ、もう帰るがよい。そして、二度ときてはならぬ」 「国王様・・・・」 「あ、いや、待ってくれ。その前に水を汲んで来てくれ。その水で、口をすすぎ、身体を清めたい。私は、この場で、ここから、世尊にお願いして、八斎戒(在家の戒律で、毎月8日・14日・15日・23日・29日・30日に限って出家者と同等の生活をするという戒律)という戒律を授けてもらおうと思っているのだ」 「わかりました。今すぐ水を持ってまいります」 イダイケ夫人は、牢獄の番人に、飲むための水ではなく、清めの水を欲しいと頼んだ。番人は、飲み水でなければ問題ないだろうと、鉢に水を満たして持ってきた。 「さぁ、イダイケよ、もう戻るがよい。そして、二度と来てはならぬ」 ビンビサーラの言葉に、夫人は 「今日は戻ります。しかし、明日もきます。必ず来ます。いいえ、心配なさらないでください。アジャセには、これ以上罪を犯さすようなことはさせません。大丈夫です。うまくやりますから」 と言い残し、牢獄をあとにしたのだった。 夫人が牢獄を去るのを見届けると、ビンビサーラは鉢の水で口をすすぎ、残った水を身体にかけた。そして、窓の外に見える霊鷲山に向かって三礼し、願いを口にした。 「世尊よ、私の願いをどうか聞き届けてください。私は今、宮中の牢獄に幽閉されています。こうなったのもすべては私自身の罪によるものです。深く深く我が罪を懺悔いたします。・・・・世尊、私は明日をも知れぬ命です。どうか、私に八斎戒を授けてください。また、できることならば、目連尊者や富楼那(ふるな)尊者の話をお聞かせください」 その願いは瞬く間に世尊に伝わった。仏陀世尊は、すぐさま目連尊者と富楼那尊者をビンビサーラの元に遣わし、目連尊者には八斎戒を与えさせ、富楼那尊者には教えを説かせたのであった。 こうして、ビンビサーラは八斎戒を受け、一般の在家信者よりも一歩進んだ信者となったのだった。 翌日から、目連尊者と富楼那尊者がビンビサーラの元を毎日訪れるようになっていた。毎日、ビンビサーラのために法を説いて聞かせていたのだった。また、イダイケ夫人も毎日ビンビサーラの元へと通っていた。おかげで、ビンビサーラは、国王時代の時よりも顔色は良く、健康であり、充実した毎日を過ごしていたのだった。 一方、アジャセは、国王の仕事の引き継ぎに追われる毎日であった。他国へ国王が代わったことも知らせねばんらないし、国の政治に関しても覚えることがたくさんあった。 「はぁ・・・国王がこれほど大変だとは・・・・」 と嘆く毎日であった。アジャセが国王について・・・・ビンビサーラが幽閉されて・・・・3週間が過ぎた日のことだった。やっと、国政の引き継ぎにめどがついたアジャセは、 「どれ、久しぶりに父の様子でも見に行ってくるか。もう死んでいるかな。それともカスカスになっているか・・・・」 アジャセは鼻歌交じりに牢獄へ向かった。そして、牢獄の中の父を見て驚いたのだった。ビンビサーラ王は、ぴんぴんしていたのだ。いや、それどころか、国王のときよりも健康そうだったのだ。 「な、なんということだ。いったいどうなっている!。おい、番兵、番兵、これはどういうことだ!」 アジャセは番兵に問いただした。番兵は仕方がなく、イダイケ夫人のことを話したのだった。 「なんと、母上め、そんなことを・・・・・。くっそ~してやれた。私の目を盗んで、そんなことを!」 アジャセは、すぐさま母親の元へ駆けていった。 「母上、私を愚弄したな!」 そういうと、アジャセは腰に差してあった剣を抜くや否や、イダイケ夫人に切りかかったのであった。 ②観無量寿経 3 アジャセ王子は母親であるイダイケ夫人に、こともあろうか剣を向けたのであった。かろうじて剣をよけたイダイケ夫人は、驚きのあまり叫び声をあげていた。その声を聞いた家臣の月光と医者のジーバカが駆けつけてきた。 「おやめ下さいアジャセ王子、いえ、アジャセ国王様!」 そう叫びながら月光がアジャセ王子とイダイケ夫人の間に立ちふさがった。また、同時にジーバカがアジャセ王子を後ろから羽交い締めにした。 「おやめ下さい、アジャセ王よ。落ち着いて、落ち着いてください」 「放せジーバカ。早く放せ!」 「アジャセ王、落ち着いてください。剣を手放してください!」 大声で月光が叫んだ。 「うるさい!、お前たちは何をしにここに来たのだ。お前たちには関係のないことだ。母は・・・この女は・・・・私の考えに背いたのだ。国王の私に逆らったのだ。成敗して何が悪い!」 「アジャセ王よ、落ち着いて私の話を聞いてください。お願いですから・・・・話を聞いてください。まずは私の話を・・・。皇后様も逃げることはできません。腰を抜かされたようですから。ですから、ここは一旦、剣を納めてください。私の話を聞いてから、正式に罰を与えるのかどうかを検討されては如何でしょうか」 月光は、優しくそう言ったのだった。しかし、月光の眼差しは鋭く、アジャセはその目を見た途端、力が抜けたのだった。それでも、アジャセはまだ剣を納めることはしなかった。 「お、お前の話など・・・・聞きたくはない・・・」 力なくアジャセは言った。 「いいえ、聞いていただきます。アジャセ王よ、今、あなたは何をなさろうしているのか、わかっているのでしょうか?。尊いベーダ聖典の中に、世界の初めから現在に至るまで、心得違いを起こし欲にかられた悪王のことが説かれています。その中でも、大恩ある父王を殺して王位についた者が1万8千人いると説いております。しかし、未だかつて母親を殺した王はいないとも説いています。あなたは今、そのいまだかつてない、非道の母親殺しをしようとしているのです。それはこのマガダ国を・・・この国の王族の名を汚すこととなるのです。私はそのようなことを許せません。もしも、それでもあなたが母親を殺そうとするのでしたら、あなたは国王でも何でもありません。あなたをこの宮殿にとどめ置くことはできません。今すぐ、私たちはあなたを国外に追放するでしょう」 気がつくと、月光の周りには多くの家臣や兵が集まっていた。どの家臣も、兵隊たちも、アジャセを諭している月光でさえも、みな腰に下げた剣に手がかかっていた。 アジャセは、剣を捨てた。そして力なく後ろを振り向き、ジーバカに問うた。 「ジーバカよ、お前たちはなぜ父上や母上の心配ばかりするのだ。なぜ、私のことを心配してくれない・・・・。なぜ私のことを親身になって考えてくれないのだ」 ジーバカは、手を緩め、アジャセから離れていった。 「王子様、私たちは王子様のことを心配しているがゆえに、こうして止めているのです。ひと時の激情に駆られて、大きな罪を起こしてはなりません」 「ジーバカよ、月光よ、母上を殺すことは止めよう・・・・しかし、私は、どうしても父も母も許すことができないのだ。あの二人がした仕打ちを・・・許すことができないのだ」 「どうしても許すことはできないと・・・」 月光は優しく尋ねた。 「月光よ、ジーバカよ・・・・もうこれ以上、私を苦しめないでくれ・・・・・」 そう言い残し、アジャセは肩を落としてその場を立ち去り、自室へと向かったのだった。 アジャセ王子は、イダイケ夫人の処刑を止めることにした。しかし、どうしても両親を許すことはできず、父のビンビサーラは引き続き地下の牢に、母親のイダイケ夫人は宮殿の奥まった部屋に幽閉することにした。 「殺されたほうがよかった・・・。こんなところに閉じ込められるくらいなら、我が子に殺されたほうがよかった・・・・」 イダイケ夫人は毎日そうつぶやいていた。その姿は、かつての美しさのかけらもなく、ガリガリにやせ細り、顔色は悪く、あたかも死人のようであった。 冷たい床に横たわっていた夫人の脳裏に釈尊の姿が横ぎった。 「そうだ・・・世尊は・・・。主人も世尊を礼拝していると言っていた・・・」 イダイケ夫人は身体を起こし、たった一つの小さな窓から外を見た。そこには、遠く霊鷲山が見えていたのだった。 「あぁ、世尊がいらっしゃる霊鷲山が見える」 イダイケ夫人はそう言うと、手を合わせて祈ったのだった。 「世尊よ、世尊は以前、私が悩んでいた時に阿難尊者を私の元に遣わして下さいました。あの時の喜びは今でもはっきりと覚えております。あの時、私はずいぶん救われました・・・・。世尊よ、ごらんください。私は今、我が子の手によってこのような暗い部屋に閉じ込められています。もう以前のように、間近に世尊を礼拝することも、お話を伺うこともできなくなりました。あぁ、もう一度、もう一度でいいですから、世尊のご尊顔を拝みたい・・・・。いえ、それはとても怖れ多いことでしょう。ですから、できることでしたら目連尊者と阿難尊者を私の元にお遣わしください。女人が一人住まう部屋に聖者を遣わすのは、問題があることなのかもしれませんが・・・・どうかわたしを憐れんで、お二人を遣わして下さい・・・・」 イダイケは涙ながらにそう祈ったのだった。 イダイケのこの願いは、瞬時に霊鷲山の釈尊に伝わった。釈尊は直ちに目連と阿難を呼び寄せ、王宮に向かうように命じた。そして、自らも神通力によってその場から消えたのである。 まばゆい光にイダイケは顔をあげた。そして、彼女は驚きのあまり「あっ」と声をあげていたのであった。そこには、光に包まれた釈尊の姿があった。 釈尊は身から金色の光を放ち、多くの宝で飾られた蓮華台に座り、左に目連尊者を、右には阿難尊者を従えていた。また、頭上には梵天や帝釈天などの神々が、天界の花を降らせて釈尊らを讃えていた。 釈尊は優しく慈愛に満ちた目でイダイケを見つめていた。イダイケは釈尊に向かい、五体投地して礼拝した。 「せ、世尊・・・世尊よ、ありがとうございます。お姿を・・・・ありがとうございます。・・・・世尊よ、お尋ねしたいことがあります。私は前世でどのような悪業を重ねたのでしょうか?。どのような悪業によってアジャセの如き、あさましい子の親となったのでしょうか。それに・・・怖れ多いことですが・・・・世尊にはどのような因縁があって、ダイバダッタのような従弟がいるのでしょうか?。あのダイバダッタさえいなければ・・・・如何に我が子が悪いといえども・・・・我が子を・・・・アジャセを苦しめることはなかったのでしょう。ダイバダッタさえいなければ・・・・アジャセも罪を犯すことなどなかったのでしょう。あのダイバダッタが、こともあろうに世尊の従弟とは・・・・」 イダイケの気持ちは伝わった。釈尊は、慈愛に満ちたまなざしをイダイケに向けていた。しかし、未だ釈尊の口は開かれることはなかった。イダイケは続けた。 「世尊よ、私はもうこのような苦しみには耐えられません。このような苦しみの世界で生きることはできません。この世は汚れそのものです。この世は地獄のようなものです。人は自分のことだけを考え、そのためには大恩ある親でも殺そうとする。私はもはやこのような世界を見たくはありません。世尊よ、なにとぞ、私のために、惑いや憂いや悩みのない清浄なる世界をお示しください」 イダイケは、再び深く深く釈尊を礼拝したのだった。 そのとき、釈尊の口がふと動いた。 「イダイケよ、汝の願う、清浄なる世界・仏国土を示そう・・・」 釈尊はそう言うと、眉間から金色の光を放った。その光はあまねく十方の世界を駆け巡り、それぞれの世界を照らし出した。その光は釈尊の頭上に戻ると、巨大な山のような黄金の台の形を作ったのである。 その黄金の台の中に、清浄なる様々な仏国土が現れた。ある国土は七宝でできており、ある国土は蓮華ばかりでできていた。ある国土は天界の宮殿のようなものがあり、ある国土は水晶の鏡でできていた。そのほかに多くの仏国土が現れ、そのきらびやかな荘厳は手に取るようにわかったのである。 イダイケは、手を胸の前で堅く握りしめ、感動に震えていた。 「世尊よ・・・・。私は今、多くの荘厳なる諸仏の国土を見ることができました。どれもが清浄であり、光明に満ち溢れ、とても優れておりますが、私はその中でも特に阿弥陀仏の極楽国土に生まれ変わりたいと願います。世尊よ、願わくば、阿弥陀仏の極楽国土に生まれ変わるにはどうしたら良いのか、私にお教えください」 釈尊はほほ笑むと、口から五色の光明を放った。その光は、地下の牢に閉じ込められているビンビサーラ王の元にも届いた。ビンビサーラ王は、その光に包まれると心眼が開き、牢の中からでも釈尊の姿をとらえることができた。やがて、ビンビサーラ王は、迷いのない境地に達することができたのだった。ビンビサーラ王を導いた後、釈尊は再びイダイケに話しかけた。 「イダイケよ、西方の極楽浄土を心に思い浮かべよ」 「世尊よ、その素晴らしい世界は想像もつかないほど遠くにあるのでしょうか」 「イダイケよ、極楽浄土は遥かかなたにあり、また遥かにあらず身近にあるものだ。なぜならば、距離は遠く離れていても阿弥陀仏を念じる者は常に阿弥陀仏と通じ合い、阿弥陀仏や極楽の菩薩が常に念じる者を守るからだ」 「あぁ、安心いたしました」 「イダイケよ、今汝のために、また生きとし生ける者のために、極楽浄土に生まれ変わるための清浄なる行を説こう」 釈尊は、すっと背筋を伸ばし、イダイケを見つめ直したのであった。 ②観無量寿経 4 釈尊は教えを説き始めた。 「極楽浄土に生まれたいと願う者は、三福の行をおさめねばならない。三福とは三つの善行のことだ。第一に、世俗の教えに従って父母に孝養を尽くし、師と年長者を敬い、謹んで十善業を修することである。十善業とは、殺生をしない・盗みをしない・淫らな異性関係を行わない・ウソをつかない・ふざけた言葉遣いをしない・悪口を言わない・二枚舌を使わない・貪らない・怒りや憎しみや妬みの気持ちをもたない・間違った考えをしない、ことである。これらが三福の第一の行だ。 次に第二の行とは、仏法僧に帰依し、戒律を守り、すべての立ち振る舞いを正すことである。そして第三の行は、悟りを求める心を起こし、深く因果の道理を信じ、大乗仏教の経典を読誦し、多くの人々が救われるよう教化することである。イダイケよ、この三福を行うことにより、極楽浄土に生まれ変わることができるのだ。この行は、私が説くだけでなく、過去・現在・未来の諸仏が、皆悟りを開く前に修行し、またはこらから修行する清浄なる行なのである。 阿難よ、よく聞くがよい。そして思念せよ。また、これから説くことを多くの人々に伝えよ。私は、イダイケと多くの生きとしける者のために西方極楽浄土を見る方法を説こう。 イダイケよ、凡俗にある汝は天眼通を得ておらず、自分の視界以上のものを見ることができない。しかし、汝は今、諸仏の力のおかげで極楽浄土を見ることができた。極楽浄土を見るのは、自分の力ではなく、諸仏の力にすがることによるのだ。それにより、明鏡に向かって己の顔を映すように、明らかに極楽浄土を見ることができるのだ。そして、心は歓喜に包まれ、真理を体得することができるのだ」 このとき、イダイケが不安そうに尋ねた。 「世尊よ、天眼通を得ていない私は、今は世尊の力によって極楽浄土を拝むことができました。しかし、世尊よ、もしも世尊が入滅されてしまったならば、その後の人々はいくら極楽浄土を見たくても、世尊の不可思議な力がないため、極楽浄土を見ることができません。そのようなときは、如何すればよろしいのでしょうか」 「イダイケよ、阿弥陀仏の極楽浄土を見るためには、まず心からあらゆる雑念を除いて西方をしずかに思うのだ。すなわち、西に向かって正座し、落日の光景を見るのだ。日が西の地平に沈もうとするそのときの、大空においた太鼓のような夕日の状態を思い浮かべよ。このようにして、日が静かに残光をとどめて西の地平に沈んだ後、目を閉じても開けても、その日輪が鮮やかに見えて忘れられないとき、それが観想のが成し遂げられた証である。これを日想といい、初観という。 次に水を観想せよ。すなわち、清く澄みきった水を明瞭に思い浮かべ、次にその水が氷になったことを思い、それが瑠璃に変じたと思うのだ。そして、それが極楽浄土の瑠璃の大地となると思いなさい。これが水想といい、第二観という。 次に眠るとき以外は、目を閉じていても開いていても、極楽浄土の瑠璃の大地が見えるように思い浮かべよ。このような状態を進めていき瞑想に入ったならば、極楽浄土の大地はますますはっきりと見えるであろう。これを地想といい、第三観という。この観想を修めるものは、塵のように積もった罪が除かれ、死後に必ず清らかな国に生まれ変わるであろう。 次に極楽浄土の宝の木を観想せよ。根と幹と枝と小枝と葉と花と実が、宝でできており、それらが調和できた美しい木が立ち並んでいる。その木の高さは測ることもできず、こずえの先は空の彼方に吸い込まれている。葉と葉の間には七宝の花が咲き、七宝の実がなり、葉一つ一つには千の色と百の模様があり、空を彩っているのだ。遥か上方は、妙なる真珠で飾られた巨大な網が上に向かって七重に木の上を覆っている。その網と網の間には、美しい花で飾られた宮殿があり、天人たちがその中で自然の音楽を楽しんでいる。その天人たちは、五百億の宝珠の飾りをつけており、その宝珠は百億の太陽と月を合わせたほどに光り輝き、遠くを照らしている。これはたった一本の木であるのだ。その木が何十本・何百本と立ち並んでいるのだ。一本の木の観想を終えたならば、次々と木を観想し、すべての木の観想を終えよ。これを樹想といい、第四観という。 次に極楽の宝の池の水を思い浮かべよ。極楽浄土には八つの宝の池がある。これらの池は、七つの宝の成分でできており、池の中にある宝珠から湧き出ているのだ。一つの池からは14の川が流れ出ており、それらはそれぞれ七宝に輝いている。それらの川の溝は黄金でできており、そこには金剛の砂がある。その砂からは七宝の蓮華が咲き出しているのだ。流れる水の音は、妙なる音楽のようであり、よく聞くとそれは真理の法を説き、菩薩の修行を説き、諸仏を讃嘆しているのだ。また、水源になっている池の中の宝珠は金色の光を放ち、その光は空中で宝の鳥へと変ずるのである。その鳥は静かで優雅に鳴き、絶えず仏法僧を称賛している。これを八功徳水の想といい、第五観という。 次に極楽浄土の五百億の楼閣を思い浮かべよ。それぞれの楼閣は宝石でできており、その中には無数の天人がいて、妙なる音楽を奏でている。また楽器が宙に浮かび、誰も弾く者がいなくても自然に音をだしている。それらの音はすべて仏法僧を念ずることを説いているのだ。このような観想ができた者は、この楼閣から先ほどの宝の大地や宝の木、宝の池も見ることができるので、この観想を総の観想といい、第六観というのだ。 阿難よ、イダイケよ、これらの法は、迷いの世界に沈没し、そこから出ることができない人々を救うための教えである。これらの法を忘れずに保持し、広く人々のために説くべきである」 釈尊がそこまで話した時、あたりはまばゆいばかりの光に包まれた。イダイケが何事かと思い顔をあげると、そこには阿弥陀仏が立ち現われていたいたのであった。 阿弥陀仏は、左に観世音菩薩、右に勢至菩薩を従え、火の玉のような光明に包まれていた。その光は、あまりにも眩いため、イダイケは目がくらみ三尊の姿がはっきりと見えないほどであった。イダイケは深々と頭を下げ、阿弥陀仏の足に額をつけたあと、言った。 「世尊よ、私は今世尊のお力により、阿弥陀仏だけでなく、観世音菩薩・勢至菩薩のお姿も拝むことができました。私にとってこれ以上の喜びはありません。しかし、世尊が入滅されてしまったら、後世の人々はいったいどのようにすれば、三尊を礼拝することができるのでしょうか」 「イダイケよ、阿弥陀三尊を礼拝しようと思うのなら、次のような観想をするのだ。まず前に説いた七宝の池の上に蓮華があると思うがよい。その蓮華の一つ一つの花びらには百種の宝の色があると思うのだ。さらに、その花びらには八万四千の筋があり、その一つ一つの筋には八万四千の光明がある。イダイケよ、これらがはっきりと見えるように観想するのだ。 次に、このような花びらがさらに八万四千あり、その花びらと花びらの間には意のままに宝を出す宝珠が百億あり、蓮華の花を飾っていると思い浮かべよ。その一つ一つの宝珠は千の光を放出しているのだ。その光は天を覆う蓋のごとく空中に照り輝き、七宝の光を放っているのだ。 イダイケよ、宝石によって作られた蓮華のうてなを思い浮かべよ。そのうてなは様々な宝石によって飾られている。そのうてなには、4本の柱が立ち五百億の宝珠で飾られた幕が張り巡らされている。さらに、その宝珠の一つ一つには、八万四千の光があり、その光は様々に変化しながら美しい輝きを見せている。 イダイケよ、もしも西方の阿弥陀仏を礼拝したいと思うのなら、このように阿弥陀仏の蓮華のうてなを見ることである。なぜならば、蓮華のうてなは阿弥陀仏がお座りになっているところだからである。これを華座想といい、第七観というのだ。 阿難よ、このような妙なる華は、阿弥陀仏が法蔵菩薩であったときに起こされた偉大なる誓願によってできたものである。だから、もしも阿弥陀仏を念じようと思うのなら、このように華座を観想することである。それは順序よく観想することだ。まず、一つ一つの花びらを観じ、次に花びらと花びらの間にある宝珠を観じ、次に宝珠から放つ光明を観じ、次に蓮華のうてなを一つ一つ細かく感じ、次にうてなの上の幕を観じ、それらがしっかりと見えるようにするのだ。それはまさに鏡に己の姿を映すのを見るように見なければいけないのだ。この観想を完成した人々は、あらゆる罪がすべて取り除かれ、必ず極楽浄土に生まれ変わるであろう」 釈尊はさらに続けた。 「華座を観じ終わったら、次に仏の姿を心に思い浮かべよ。仏を観想すれば、仏は必ずその人の心の中に現れ、その人はその場に居ながらにして、仏を礼拝することができるのだ。 イダイケよ、人々が心に仏を礼拝できるのもできないのも、その人が心に仏を思うか思わないかにかかっているのだ。従って、人の心がすなわち仏であり、心が仏を作るのである。なれば、一心に阿弥陀仏を観想することが大切なのだ。 イダイケよ、目を閉じていても開いていても、金色に輝く仏の姿が見えるように思いを凝らすのだ。そして、宝の大地、宝の木、宝の池などの極楽浄土の美しさを思い、蓮のうてなの上に座っている仏を思うのだ。さらに、その左の大きな蓮華の上には観世音菩薩が、右の蓮華の上には勢至菩薩が金色の光を放って座している姿を思い浮かべよ。三尊の光明はもろもろの宝樹を照らす。その一本一本の木の下には、また三つの蓮華が現れ、それぞれに一仏と菩薩が座っていると観じるのだ。すなわち、極楽浄土はこのように三尊の姿で満ちているのだ。このような感想が成就すれば、その人は水の音や光明、また木々や鳥たち妙なる法を説いている声を聞くことができるようになるであろう。瞑想中に聞いた妙なる法は、瞑想から覚めても記憶からは消えることはない。これを像想といい、第八観という」 釈尊がそう説き終わると、阿難が尋ねた。 「世尊、この第八観を得た者は、どのような利益を得るのでしょうか」 「阿難よ、人々は何億年にもわたり生まれ変わり死に変わりを繰り返し、無数の罪を犯している。第八観を成就した者は、その無数の罪が除かれ、現在の身をもって仏を見ることができ、また仏を念じた時、心の安楽を得るのである。 阿難よ、イダイケよ、観想はまだまだ奥があるのだ」 釈尊は、さらに奥深い観想を説こうと、さらに自身の光明を放ったのであった。 ②観無量寿経 5 釈尊は教えを説き続けた。 「イダイケよ、仏を観じ終わったならば、次には真の阿弥陀仏の姿と光明の働きを観ぜよ。阿弥陀仏の身体は尊い金色で、その背丈はとても測ることができないほど高い。眉間の白毫は丸く右に回っており、五つの大きな山を合わせたほどの大きさがある。目は大海のように広く、瞳は涼やかに美しく澄み渡っており、秋の中天にかかった満月のようである。身体のすべての毛穴からは光明が放たれ、後光は大きく鮮やかに輝き、すべての世界を包み込むほどである。その後光の中には、無数の仏の分身がおり、さらにその分身の仏の一つ一つを菩薩たちの分身が侍者となって取り囲み守っている。 阿難よ、阿弥陀仏から放たれる多くの光明は、その一つ一つがあまねく十方世界を照らし、念仏するすべての人々をおさめとり、捨てるということはないのだ。 以上の観想をするならば、それは十方の一切の諸仏を見て、念じたことと同じである。それゆえに、この観想を念仏三昧と名付け、また一切の仏身を見る観法とも名付けるのである。 阿難よ、仏身を観ずることができれば、仏の心も見ることができるのだ。仏の心とは、阿弥陀仏のあらゆる生きとし生けるものを救うという大慈悲のことである。この観想をなすものは、命が終わった後に諸仏の前に生まれ、真実の悟りを得るであろう。だから常に心に阿弥陀仏を深く観想しなければならないのだ。 阿難よ、これを遍観一切色身想(へんかんいっさいしきしんそう)と名付ける。すなわち、一切の仏を見たことになるということである。そしてこれが第九観である」 釈尊は、続いて阿弥陀仏の左の脇時である観世音菩薩の観想・・・第十観・・・を説き、さらに右の脇時の勢至菩薩の観想・・・第十一観・・・を説いた。続いて、浄土をあまねく合わせて観想し、自分がその浄土に往生するということを観じる普観(ふかん)・・・第十二観・・・を説き、次いでこれらの諸観想を総合して観想する雑観想・・・第十三観・・・を説いたのであった。 釈尊が説き終えると、阿難が釈尊に尋ねた。 「世尊よ、私たちは今、極楽浄土に生まれるという十三の観想の教えを聞きました。しかし、人々にはいろいろな能力や素質があり、今説かれたことができる者もいれば、できない者もいます。もし、十三の観想ができなければ、阿弥陀仏を見ることはあきらめなければならないのでしょうか」 釈尊は、一度うなずくと、質問に答え始めた。 「阿難よ、いい質問である。汝が言うように、生きとし生けるものには様々な能力や素質がある。それを九品(くほん)に分けて考える。すなわち、 上品上生(じょうぼんじょうしょう)、上品中生(じょうぼんちゅうしょう)、上品下生(じょうぼんげしょう) 中品上生(ちゅうぼんじょうしょう)、中品中生(ちゅうぼんちゅうしょう)、中品下生(ちゅうぼんげしょう) 下品上生(げぼんじょうしょう)、下品中生(げぼんちゅうしょう)、下品下生(げぼんげしょう) の九つである。 このうち中品までに位置する者は、善を修め、戒律を守り、世間の道徳を守れる人々である。そのような人たちは、臨終にあたって仏や菩薩の来迎を受けて極楽に往生し、または往生してから間もなく菩薩たちにまみえることとなる」 その言葉を聞き、阿難は再度尋ねた。 「世尊よ、それは恵まれた人々だと思います。しかし、多くの者は善を修めることもできず、戒律を守ることもできず、道徳心にも欠けています。世尊よ、そのような多くの人々は、極楽浄土に往生できないのでしょうか」 「阿難よ、そのような人々はたくさんいるのは確かだ。しかし、阿弥陀仏の誓願はすべての人々を救うことである。従って、阿難よ、少しも心配には及ばない。これより、そのような人々も必ず極楽浄土に往生し、悟りを開くことができるということを説き明かそう」 釈尊の言葉に、阿難もイダイケも歓喜の表情を浮かべたのだった。 釈尊は、静かに語り始めた。 「生きとし生けるものの中には、生きていくうえで悪を犯さざるを得ないようなことがたくさんあろう。罪を犯さずに生きることができればそれに越したことはないが、それは難しいことである。しかし、だからといって、人々は犯した罪を反省するかといえば、必ずしもそうとはいえないであろう。大乗仏教の経典を誹謗するほどではないが、悪行を犯して自らの罪を少しも恥じることなく、また他人に注意することもなく過ごしている人は多いものである。そういう者は、死後に自分が犯した罪の報いを受けることも忘れ、毎日を事もなげに暮しているのだ。 しかし、このような人であっても、命が終わろうとするときに、自分を正しい仏道に導き入れてくれるよき友に会うことができて、そしてその人から大乗経典の名を聞かせてもらえば、長い間にわたって作ってきた重い罪も取り除かれるのである」 その言葉を聞き阿難が尋ねた。 「そういう人もすぐに救われるのですか」 「阿難よ、そうではない。それだけのことでは、まだまだ生死の苦海を離れることはできないのだ。よいか阿難、そのよき友が南無阿弥陀仏と唱えよと教えてくれれば、今まさに死なんとする人は、その教えに従って念仏するであろう。そうすれば阿弥陀如来はそれを知って、観世音菩薩と勢至菩薩を伴い、光明とともにその分身を差し向けてくれるのだ。その者は、聞くであろう。 『よくぞ我が名を唱えてくれた。それによってこれまでの諸々の罪は悉く消えた。私はすぐにお前を極楽浄土に迎えよう』 と。 その阿弥陀仏の声により、その人はこの上ない喜びに包まれ、息絶えると同時に、直ちに宝の蓮華台に乗って仏たちに従っていくのである。そして彼は、極楽浄土の宝の池に生える蓮華の中に生まれるのだ。蓮華はまだつぼみであるが、四十九日の明け方、その蓮華は静かに開き始める。蓮華が開き終わると、観世音菩薩と勢至菩薩が光明を放ちながら現れ、自他共に救われる経典を説いてくれるのだ。その人は、法を聞き、悟りを求める心を起こし、長い間の内に悟りを得るための条件を身につけていくのである。阿難よ、このような人を下品上生の人と名付くのだ。 次に、下品中生のものはどうか。 この者は、下品上生の者に比べ、もっとひどい罪を犯している。戒を破るにとどまらず、僧団の財物を盗んだり、僧に供養するはずの食べ物を食べてしまったり、または自分の名誉や利益のために仏の教えだといって法を説いたりしても少しも恥じることなく、様々な悪行を犯しながら他人を悪しざまにののしったり、自分は少しも悪くないと主張する。こうした人々が下品中生のものである。 このような人々は、その悪のために必ず地獄に落ちる。息絶えようとするその時に、数々の地獄の猛火が一時に攻めてきて、その者を焼こうとする。しかしこのとき、彼に正しい道を示してくれるよき友があって、阿弥陀仏の威徳と偉大さを説き、阿弥陀仏の光明と不思議さを説き聞かせれば、それを聞き終わったその人からは、長い間生死に迷うべき罪が取り除かれるのである。そして攻めてきていた地獄の猛火は、たちまち涼風となり、その風に乗り空から色とりどりの花が降るのだ。その花一つ一つには、仏の分身や観世音菩薩の分身、勢至菩薩の分身が乗っているのを見ることができよう。そして七宝の蓮華に乗せられ、そのまま極楽浄土の宝の池に生える蓮華の中に生まれるのだ。 先の下品上生の人は、四十九日で蓮の花が開いたが、下品中生の人はもっともっと長い年月がかかる。しかし、蓮の花は必ず開くのだ。そして次第に花が開くと、観世音菩薩と勢至菩薩が自他共に救われる経典を説き示してくれるのである。それを聞き終わると、その人はすぐさま悟りを求める心を起こすことができるのだ。 次に、極悪の罪を犯す下品下生の人たちのことを説こう。この者たちは、五逆(父を殺すこと、母を殺すこと、聖者を殺すこと、仏の身体を傷つけて出血させること、教団を破壊し分裂させること)や十悪(十善戒を犯すこと)は言うに及ばず、その他のあらゆる不善の罪を犯すために、必ず地獄に落ち、無限にも近いほどの間、苦を受け続けなければならない者である。この人たちは、命の終わるときに正しい仏道に導いてくれるよき友に出会えて慰められ、南無阿弥陀仏の名号の功徳を説き聞かせられながらも、苦しみに迫られてとうてい心静かには念じることはできないであろう。しかし、もしよき友が、さらに勧めて、 『苦しさの余り心を静めて仏を念ずることができないのであれば、口に南無阿弥陀仏と唱えよ』 と道を指示してくれれば、その人は苦しさの中にありながら声を振り絞って、南無阿弥陀仏と十遍ほど念仏を唱えるのだ。さすれば、その一声一声に、重罪も消え、苦しい中でありながらも、空中から降りて近付いてくる金色の蓮華を見ることができるのだ。 太陽のように輝くその蓮華が静かに止まり、その人を乗せるであろう。するとその人は、極楽浄土の宝の池に生える蓮華の中に生まれるのである。その蓮華が花開くには、下品中生の人よりは長い時間がかかるが、必ず花は開くのだ。そして花が開けば、観世音菩薩と勢至菩薩が自他共に救われる経典を説き示してくれるのである。それを聞き終わったあと、その人は悟りを求める心を起こすのだ。 阿難よ、この下品上生・下品中生・下品下生の往生を観ずることを下輩生想(げはいしょうそう)といい、第十六観と名付けるのだよ」 釈尊は、このように説いたのであった。この話を聞き、イダイケをはじめ、多くの者が大いに喜んだのだった。いつの間にか、宮殿の500人もの侍女たちの耳にも釈尊の声が聞こえていたのだ。イダイケだけでなく、侍女たちも、釈尊の話を聞き、極楽浄土に生まれ変わりたいという心を起こしたのであった。 その時であった。阿難が立ち上がって釈尊の前に進み出ると 「世尊よ。わたしたちは世尊の偉大なる慈悲によってこの未曽有の法を聞くことができました。この説法をこれから後、どのような名でお呼びすればよいのでしょうか」 と尋ねた。釈尊は 「阿難よ、これを『観極楽国土無量寿仏観世音菩薩大勢至菩薩』と名付ける。この法は阿弥陀仏の極楽浄土、阿弥陀仏と二菩薩とを観ずることを説いた教えだからである。また『浄除業障生諸仏前(じょうじょごうしょうしょうぶつぜん)』とも名付けよう。なぜならば、罪を除いて阿弥陀仏の御前に生まれることを説いた教えであるからだ」 と教えたのだった。阿難は続けて願い出た。 「世尊よ。今一度、この教えの要を説き示してはもらえないでしょうか」 「よろしい、阿難よ。要を説こう。 心に仏を見る観想を行う者は、現在この世にありながら阿弥陀仏および観世音菩薩、勢至菩薩を見ることができる。もしもそのように見るに至らないまでも、阿弥陀仏および観世音菩薩、勢至菩薩の名を聞く者は、それだけでも長い間の罪が除かれるのだ。従って、阿弥陀仏を心から信じる者が多くの利益をこうむることは、今さら説くことでもないであろう。 念仏する者を観世音菩薩、勢至菩薩は誠によき友達、優れた友達だと讃嘆している。人中に咲く白蓮華であると褒め称えている。そのうえに、未来は成仏を約束された座について阿弥陀仏の極楽浄土に生まれることができるのだ。 阿難よ、汝はこの言葉をしっかりと自分の胸におさめ、信じて忘れず、生きとし生けるもののために説き広めるがよい。この言葉とは、すなわち阿弥陀仏の名である」 釈尊はそういうと、目連と阿難を従え、虚空に舞い上がり、霊鷲山へと帰っていったのであった。イダイケはその後ろ姿に手を合わせ、釈尊の言葉を繰り返していた。その心には、かつてない喜びが湧いてきたのであった。 牢内のビンビサーラ王も小さな窓から釈尊たちの姿を目で追いかけていた。そして深々と合掌礼拝したのだった。その姿は囚人ではなく、気高いものであった。 以上、観無量寿経 完。 これで観無量寿経の内容を終えます。次回からは、この内容について解説いたします。 つづく。 |