鬼の子・1
1
都大路を歩いていた男はふと顔を上げた。
風はまだ冷たい。
身を切るような冷たさに誰もが足早に歩いていく。
だが男だけは、唐突に湧き上がった自分自身の不安感が拭い去れぬというように北風にその身をさらしながら、ゆっくりと空を見上げた。
不気味な暗雲が、大津の都を覆っている。
男はその状景に見覚えがあった。
出来れば一生思い出したくもない、忌まわしいあの日の空だ。
…その雲は遠く大江山から流れて来たのではあるまいか。
男は知らず自分がそう呟いてしまった事に恐怖を覚えた。不意に恐ろしくなって辺りを見回す。
だが、男が懸念していたような類の者は、そこにはいなかった。その代わり、いつの間にか、この道を通っている者がほとんどいなくなっている事に気がついた。
その閑散とした道の中で、男の目にふと捉えられたのは、年の頃なら十五、六と思われる少年の姿だった。
年に能わぬ鍛え上げられた体躯と、ただ歩いているだけでも解る堂々とした立ち居振舞いとは裏腹に、少年の容貌はまだ幼く、男の目にはそれが奇妙な違和感として写し出されている。
先ほどから吹き付ける冷たい風も、少年には何の苦でもないのか、彼はは上掛けすら着ていない。
それらの違和感に誘われた訳ではないが、男は少年から目を放せずにいた。
その視線を捉えたのか、少年は立ち止まって男を見た。
「おい、そこの男」
呼ばれた途端、男は己の背筋から一気に恐怖が駆け抜けていくのを感じた。それは以前にも感じた暗い記憶でありその恐怖が何を意味しているかは男にとって考えるまでもない事だった。
先程までの不安感はこれであったのか。
だが、少年の瞳には男の変化を捉えた様子はなかった。少なくとも男の目にはそう見えた。
そこで男は何とか声が震えそうになるのを堪えながら少年の問いかけに答えた。
「…何か?」
普段の自分からは想像も出来ない情けない声であったが、今の男にはその言葉を絞り出すので精一杯であった。
幸い、少年はその事にも少しも注意を払っていないようだった。すっと、滑らかな動きで腕を上げ、ある建物をその細く長い指で示した。
「大王(おおきみ)のいる城というのはあれに相違ないか?」
少年の指し示したそこは、この都で一番の高さを誇る大霊院であった。神の使いと言われる永遠の火を祀ってある二対の塔の内の一つ、都の人々にとっては、彼等の「神」が残してくれた唯一つの崇拝の対象である、神聖な社であった。
だがその畏れ多くも無知なる少年の態度よりも、男には少年の発した言葉の方が怖しかった。
疑念は瞬時に確信へと変わっていた。…そしてこの少年の素性も正体も何もかも、男の中で繋がっていった。
最早男は先程からの震えを止められずにいた。だが気丈にも男は少年に向き直り、あらんばかりの声を張り上げた。
「お、お主、鬼であろう!あの忌まわしい呉葉の産み落とした児であろう。あやつ、身篭っておったから、。どうじゃ!図星であろうが!!」
呉葉、という言葉に反応して少年の瞳が紅の輝きを帯びた。
口元を醜く歪め、嘲るように男を見る。
「ほう、その名を知っているのか…」
少年はぞっとするほどの怖ろしい声で呟いた。心なしか、その声には嬉しげな響きさえ感じられる。
少年はいまだ小刻みに震える男の右腕を掴み、一気に捻り上げた。
ぐきり、と嫌な音がして、男の右肩は呆気なく壊されていた。
激痛が男の体中に走り、男は耐え切れず悲鳴を上げた。
少年はその様子を可笑しげに見ている。自分の壊した男の苦しむ様を、さも楽しげに。
「苦しいか?痛いか?そうだろうさ、肩の骨がイカレちまってるからな」
それから怒気を含んだ声でこう付け加えた。
「確かに、俺は鬼だ。鬼の児だ。貴様らの言う、この世で最も忌まわしき生き物の血を継いでいる。だがそれがどうした?お前らの王はその鬼と交わったのじゃないのか?最も忌むべき生き物と床を共にしたのだろうが。そんな男今でものうのうと王に推したてられているのに、俺の事を忌まわしいと言える気か?俺は貴様らのご大層な王の子でもあるんだぞ」
少年はそこまで言い切ると、ようやく男の肩から手を離した。
「さあ、それじゃ案内してもらおうか。貴様らの忌まわしき大王の所に」
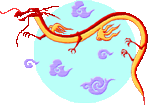
2.
彼と王との接見は王の私室で行われた。
王にどれほどの権限があろうと、それを公式な謁見とする事が禁忌だという事実は揺るがし様もない。
だが、それを強要された少年は、その事に対してさほど嫌悪を覚えた様子はなかった。
「そなた、名は何と申す」
王は緊張に声を震わせているようだった。その声の響きには抑えようのない喜びが溢れている。
それとは対照的に、少年は冷徹な面持ちで王の顔を見ていた。
そこには何の感慨も現れてはいない。
ただ目の前の男を値踏みするような無遠慮な視線を浴びせているだけだ。
「紅丸」
一言だけ答える。その声の無機質さにも関らず、王は彼が己に対して言葉を発してくれた事がさも一大事件であるかのように、喜びに顔をほころばせた。
「紅丸と申すのか。それは呉葉がつけた名か、お主もそろそろ元服の年だと思うが、まさかそれが正式な名ではあるまい」
呉葉、という名に反応して、紅丸のこめかみがピクリと動いた。
先程までと違い、明らかに不快を顕にしている。
だが王の方はそんな紅丸の変化には気付かなかったようだ。ただひたすら我が子に会えた喜びを無邪気に溢れさせている。どうやらそんな王の態度が、余計に紅丸を苛立たせているようだった。
「貴様、陛下御自らが直々に貴様に謁見を許してやっているというのに、何なのだ!その不遜な態度は!!」
紅丸の傲慢さに業を煮やして叫んだのは、王の傍に控えていた老いた男であった。
「まあ、そう声を荒げるな」
王がそれをたしなめる。だが、男の怒りは収まらない。
「しかし陛下、こやつ、陛下の前でありながら…」
「私の息子だ」
そう言った王の言葉には有無を言わさぬ響きがあったので、男はそのまま黙り込んでしまった。だが、紅丸を不審そうに見る視線は外さない。
「すまなかったな、紅丸よ。気を悪くせんでくれ」
王がそう取り成すのを紅丸は黙って聞いていた。
別にどちらでも構わないといった鷹揚な態度が男には見てとれたので、諌められた男は悔しくてならなかったが、今の王には何を言っても無駄だと考えたので口を挟むことはしなかった。
明日にはお考えを改めてくれるであろうかとも考えたが、それも希薄な願いのように思えた。
「して、呉葉はどうしておるのじゃ? 今は何処に住んでおる?…元気で、暮らしておるのか?」
紅丸は立て続けに発せられた質問に耐えかねたのか、割れんばかりの大音声で、王に返事を返した。
「母は今大江の館に住んでおる!鬼の長である兄上の家だ!毎日鬼どもを叱咤するほどの元気ぶりで、とばっちりを喰らう者どもが辟易しておるほどだ!…それから」
ここで少年は言葉を途切らせた。余程、腹に据えかねていたのだろう、大きく息を吸い込んで吐き捨てた。
「わが母の名は紅葉だ!鬼女紅葉!それが俺の母の名だ!金輪際”呉葉”等という名で呼ぶな!…打ち殺すぞ」
最後の言葉は低く脅すように囁かれた。
その呪いの言葉を吐く紅丸の眼が一瞬だけ紅く光ったのを、側近の男は見逃さなかった。怒鳴られた王はただ驚愕の眼差しを一編に態度を豹変させた息子に向けて呆然としている。
不甲斐ない王に代わって男は意を決して紅丸に尋ねた。
「おぬし、そこまで陛下を嫌うのならば何故山を下りてこの都まで参った。鬼は鬼らしゅう大江に篭っておれば良いものを」
紅丸は未だ怒りの収まらぬ瞳を男に向けた。
その瞳に射竦められた時、この幾多の戦をくぐり抜けてきた経験を持つ老兵は、いまだ自分が恐怖を感じる対象が存在していた事を思い知らされた。
「俺だとて山を下りて貴様らのような軟弱な人間どもと顔を突き合わしたくなんぞなかったわ」
心底憎々しげにそう言う。紅丸がどれ程の屈辱を感じてこの前に座っているのか、ギリ、と歯噛みしたその音からも感じ取る事が出来た。
「母上が俺に降りろと言うたのだ、俺は山で暮らしていてはいかんのだと」
その言葉に、男はまじまじと紅丸を見つめた。
鬼がよもや政なんぞに関心を持って、この少年を送りつけたとは到底考えられなかった。
山を下ろされたのだという、紅丸の悔しげな横顔を見ていると、確かに鬼の荒くれどもの中で暮らしてゆくには、余りに少年は人間に近すぎる感はある。十四にしては逞しすぎる体躯も鬼の中に混ざっておれば華奢でひ弱に映るだろう。
改めて、火の一族の血の濃さというものを考えさせられた。
「ではお主、このまま都に留まるつもりか?」
そう問う男に紅丸は投げやりとも思える答えを返した。
「嫌ならとっとと出ていくまでだ。別にここでなくとも暮らせる所は幾らでもある」
だが都を追い出した所で帰る場所を持たないこの少年が何をやり始めるか、結果は火を見るより明らかだ。夜盗か追剥か、どのみちろくな事にはならないだろう。
仮にも火の都を統治する陛下の、その血を分けた者がそのような不名誉な行為を行うなど以っての外だ。その可能性故に、男は不承不承という形で紅丸に言った。
「誰もお主に出て行けとは言うてはおらぬわ。正式に、という訳にはいかぬが都に留まることは許してやろう。西の端ににワシの持っておる屋敷がある。後で案内させてやるから、庭ででも待っておれ。一つ言うておくが庭の松には手を触れるでないぞ。陛下が丹精こめて育てられておる松ばかりだからな」
「覚えられていたらそうしてやる」
そう言って、紅丸は部屋を退出した。
それを見送ってから男は未だに驚愕から覚めやらぬ主君に向かい、紅丸の今後の身の振り方について意見を述べた。
まず一つは、けして彼を息子として扱わぬ事。
そしてもう一つは彼に対して常に監視の目を怠らぬ事。
『あのような禍々しき者が都に入り込むなど、本来あってはならぬ事。なにやら不吉な気がしてならぬ。陛下がこのような状態ではわしがしっかりしなければ…』
彼の懸念など嘲笑うかのように、風が木立を駆け抜けていった。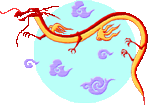
![]()