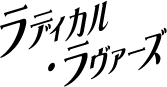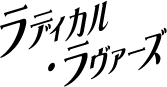|
その日、若島津は珍しいことに酔っていた。かなり、相当の勢いで酔っていた。
でもまあ、それも仕方がない。本日、いや日付けも回りかけてもうすぐ昨日、Jリーグ・セカンドシーズン晴れて優勝。しかも最終戦にまでもつれこんでの優勝カップだ。テレビカメラも入った祝勝会で、人間、羽目を外さずにいつ外すとゆーのか。
おまけに実質功労者の一人とあっては、酒を勧める手も途絶えなかった。また本人、自覚があったのでほいほい受けた。頭に被った量ほどには胃にも入った。プラス、人にもぶっかけまくった。それも若島津にしたら珍しい。
「あんまり、飲めない人かと思ってたのになぁ」
今年のルーキーに勧められたシャンパンを一気にあけると、彼はどうしてだか残念そうに呟いた。
「何考えてんだ。飲めないと思って勧めたのか、お前」
「えーと、そういうのも面白いかなって」
空けたグラスを逆にもたせて、若島津は笑ってシャンパンを縁から溢れるまで注いでやった。
「10年早い」
普段、怒鳴られこづかれている先輩に対する意趣返しなのだとしたら、随分と自分も舐められたものだ。カメラがこっちを向いたのを目の端にして、ついでに瓶に残った半分ばかしのシャンパンをルーキー君の頭に降り注ぐ。いきなり過ぎて目に入ったらしく、彼は悲鳴を上げて首を振った。
「なァに、若さん独占してんだよぅッ」
これも何だか呂律が怪しいベテランDF氏が、後ろから若島津の首を抱えて割り込んでくる。普段は冷静沈着でならしてるクセに、意外とこの人の酒グセが悪いことを周囲の人間は知っている。
「すげェな、城山さん。もうどのくらい飲んじゃったんですか」
「おー、そんなにしゅごいー?」
「しゅごいしゅごい。ぐちゃぐちゃに出来上がっちゃってますよ。中継、まだあるんでしょ。だいじょーぶかな」
「あ、それなの。そのことで来たの、俺は。そろそろ隣ホールに雛壇出来たらしいぞーい。主要なヤツは集まれってさっ」
地元ホテルで行われている優勝祝勝会だが、東京のスタジオと繋がる形で、深夜サッカー番組の生中継が入る手筈になっている。最後にもう一杯シャンパンを空けて、「んではッ 行きますか!」と若島津は側にいたルーキー君の肩も叩いた。
「え、いやっ オレはいいっす! オレ場違いですよっ」
「バーカ、何言ってんだ! お前も後半出てただろー!」
「そうそう、お前のパスからパスに繋がり、俺が後ろからダイレクトに決めた! ンー最高だっ! いい試合だった!」
城山さんも手伝ってくれて、二人でルーキー君の襟首掴んで引きずって行く。うへーっ、とか、マジすかーっ、とか叫んで慌てふためく彼を見て、普段は仏頂面のイタリア人監督も、言葉は分からないながら向こうでゲラゲラ笑い転げる。その隣にいたお雇い外国人・金髪FW氏からは、「ヘーイ! カンパーイ!」と微妙なイントネーションでのシャレた仕種が飛んできた。オーイェー、ハインツ氏、今期あなたの多大な功績にも敬意を表してカンパーイ!
───ふふふ、楽しくって仕方がない。
凄いぞ、羽目を外している自分すら面白い。
ハイになってる頭の理性・三割部分で「でも俺、これ後になって我に返ったらかなり恥ずかしいんだろうなぁ」なんて若島津は思いながら、前髪から零れるアルコールを振り払った。
タクシーを降りてマンションを見上げると、自分の部屋に灯りがついているのにすぐ気付いた。念のため数えてみる。下から4番目、右から2番目。やっぱり自分の部屋だ、間違いない。
なるほどー?、と深くは考えずにエントランスをくぐる。考えるも考えないも、実を言えば合鍵渡してる相手なんか一人しかいない。正確には『渡した』のじゃなくて『脅し取られた』に近いが。『脅される』理由がある自分に当初はうんざりしたものだったが。
エレベーター出て廊下を歩いて、ドアの前で鍵を出しかけて苦笑する。だから開いてるんだよ。でなくてもチャイムを鳴らせばそれで済むんだ。なんだ、酔いは全然醒めてない。
「ただいま」
いつもしろと言ってるのに、予想通りにチェーンも鍵もされていなかった。普段はかけない声をかけながら玄関口で靴を脱ぎ、応えて奥のリビングから覗いた顔はもちろん、
「───お帰り」
「お前、来るなら電話しろって言ってるだろー?」
「合鍵持ってる意味ねーじゃねえか、それ」
そうだよ、渡したくなかったよ、俺は。恒例で一応はぼやいてみせ、だけど機嫌がいいので、若島津は自分から日向の胸ぐら掴んでぶつかるようなキスをした。
「…わっ 酔っぱらい!」
「ただいま」
「聞いた。2度目だよ」
「そうだっけ? ンー、今何時だ」
2時、と腕の時計を見て言い、「思ったより早かったな」と日向は付け足しのように呟いた。
「そうかな」
「朝帰りかと思ってた」
「じゃあ何でここで待ってたんだよ」
ちょっと眉をしかめただけで、それには日向は答えなかった。代わりに、もたれかかっている若島津の髪に鼻を寄せ、「酒くせーっ」と非難がましい声を上げる。
「安酒じゃないぞー」
「関係ねえよ、そんなの。あんた、せっかく奇跡的に質のいい髪の毛してんのに…」
奇跡的、と日向が言うのは、若島津がほとんど自分の髪に構わないせいだ。トレードマークになっていて半端なこの長さを切るに切れずにいるが、特に手入れらしい手入れもしていない。下手すりゃ洗ったっきり、リンスも忘れてシャワーを済ませる。
「風呂入れよ、風呂!」
「一応、すすいで来たんだけどなあ…」
「匂うんだからダメ! 入んなって!」
引きずるように脱衣所に連れて行かれて、覗いた風呂場にお湯がちゃんと張ってあるのに驚いた。こいつは家政婦さんか。人の家に勝手に入って、勝手に風呂の用意をして待ってるなんて。
「終身雇用で、雇ってもらえんならそれもいいかもな。──ホラッ 服! 着たまま行くなよっ」
お世話されるのも何だか楽しい。簡単に剥かれて風呂場に突っ込まれて、シャワーを浴びてもまだ気分はハイだ。
「あっつー。お前の温度設定、熱すぎるよ…」
「へーへー。すいません、次から気を付けるよ。って、おい、風呂桶ン中で寝るなよ。死ぬぞ!」
|