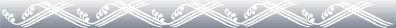
空間に剣戟が満ちた。 激しく打ち込んでくる緋村の剣は、通常とは比べ物にならないくらい速い。しかしそれでさえも蒼紫の目には、はっきりと見えていた。代々受け継がれた細作としての資質なのか、蒼紫は動体視力に優れている。 「何度斬り込んでも無駄だ。防御に徹した時の俺の小太刀は、小銃の弾丸とて防ぎきる」 緋村の刃を小太刀で二度受け止める間に、こちらの拳打は二十発以上奴の身体に食い込んでいる。擦った拳が、緋村の血に赤く染まった。 拳の勢いに押されて、床を滑るように倒れ込んだ緋村に、蒼紫は無造作な声を投げた。 「──立て。倒れている者にとどめを刺すのは、俺の好みじゃない」 少々拍子抜けする思いで、緋村の小柄な身体を見下ろす。幕末の最強とはこの程度なのか。それともこの十年の間に、腕が鈍ったとでもいうのだろうか。……そんな筈はない。もしそうだったなら、般若が倒された訳がない。 心の中で眉をひそめた蒼紫の前で、緋村がゆらりと立ち上がる。弥彦の必死な叫びに、平静な声で答えるだけの余裕もあるようだ。 「大丈夫でござるよ。これしきでやられては、恵殿に申し訳ないし、薫殿にあわす顔もない。左之にはなんと言われる事やら……」 苦笑含みのその言葉は、やはり彼がまだ本気ではなかった事を示している。蒼紫は手加減なしに拳を入れた。それをあれだけ受けてたいした影響が出ないとしたら、恐ろしく打たれ強いか、拳打の威力を受け流していたかでしかない。入ったと確信していた拳が、ほとんど受け流されていたとしたら──この相手に、拳は有効な攻撃方法とはいえない事になる。 考え込んだ蒼紫の前で、緋村はとんでもない事をぽつりと呟いた。 「それに、やっとあの小太刀を、防ぐ手段が見えてきた所でござる……」 蒼紫の瞳が硬質な光を宿した。 「ハッタリ……と言いたい所だが、お前はそんな事を言う性格ではないな……」 ついと歩を踏み出し、緋村の瞳を正面から見詰める。いまだ穏やかともいえるその色に、語られた言葉が真実である事を確信した。 特殊な場合を除いて、剣撃の勝敗はその速度で決まる。緋村の飛天御剣流もまた、速さと高さにおいて他の流派を上回るが故に、一振りで三人を倒せるという無敵の伝説を残しているのだ。無論、流派に見合うだけの実力があってこその話であるが。 そして同じくらいの速さを誇る者同士での闘いは、武器の優劣が大きく影響する。不殺を誓う緋村にとって、この際切れ味は関係ない。問題は刀の長さの方だ。逆刃刀は小太刀と比べるとかなり長い。小回りが利かないのは当然である。 相手が戸惑っている間に自分の間合いに持ち込み、そこを拳法で攻撃する。攻守の釣り合いの取れたこの戦法を、いったいどういう手で破るのか。 「見せてもらおうか、その手段とやら」 そう呟いて、無造作に歩を進める蒼紫と、緋村の間で緊張が高まる。殆ど、手の届くぐらいの距離まで近づいたとき、緋村は気合と共に逆刃刀を振り下ろした。 「遅い!」 これでは先程と全く同じ──そう思って繰り出した蒼紫の小太刀は、即座に打ち返された。返す刀もまた、同じように弾かれる。何が起こったか理解らず、驚いて緋村を見詰めたその目に、信じられない光景が飛び込んで来た。 緋村の手が刃の鍔元を握っている。 いくら切れ味の鈍い鍔元とはいえ、刃を直接握ればどうしたって怪我をする。刀を握ったその手からは、かなりの量の赤い血がだらだらとこぼれ落ちていた。 驚愕したほんの一瞬の間を突いて、緋村の剣の柄が飛んでくる。気が付いたときには避けようもない距離にあったそれは、凄まじい勢いで蒼紫の喉元にめり込んだ。 刹那息が詰まった。 あまりの衝撃に、半ば弾かれるように後ずさった蒼紫へ、緋村は一つ息をついてから声を掛けた。 「蒼紫、お前の強さの秘訣は、相手の“間合い”を完全に制する事にある」 流石に息が上がっている緋村は、それでも淡々と言葉を続ける。 「単純に考えると刀を持つ拙者が有利の様だが、長い間合いにはどうしても懐に死角が生じる。それをついて小太刀で刀を封じると同時に、拳で攻撃してくる。ならばこちらも、同じ小太刀の間合いに切り替えれば」 刃を直接握って、長さを調節して……? 「死角は自ずと消滅する」 確かに──死角は消滅するだろう。だが、戦いの最中の利き腕の怪我がどんなに不利であるか。守りの戦いが全てである御庭番衆には、そこまで捨て身になる事はできない。いや、できなかった……今までは。 驚愕を押し隠し、感情を込めずに呟いた。 「……成程。日本刀は引くか押すかして斬る事によって、初めて真の切れ味を見せる。握るだけでは、まして切れ味の最も悪い鍔元なら、骨に喰い込むまではいかない」 ……とは言っても、実際にするとなると恐ろしいものだ。己の信念に賭け、勝つためならこの身が滅びることも厭わない。それこそが幕末を支配した狂気であり、抜刀斎の心の奥に巣喰っているものなのだろう。 だが、もう幕末ではない。今、この場で──その身を犠牲にしてまで、緋村は何を守ろうというのか。 高荷恵? 観柳のようなクズに喰い物にされる人々? それとも……。 こちらを見詰める瞳の中に、微かな哀れみを見つけた気がして、蒼紫はそそけ立った。同情などいらない。そんなものが欲しいのではない。 「肉を切らせて骨を断つ……か。人斬りの真髄、しかと見せてもらった」 瞬時、沸き上がった怒りと悲しみの分、蒼紫の瞳が不吉にきらめく。凄みを増した呟きから、表に出ない感情が微かに漏れ出した。 「返礼として、御庭番衆御頭の真髄で仕留めてやろう」 初めて──本気で緋村を殺そうと思った。 ゆったりとした動きで攻撃を仕掛ける蒼紫に、緋村は戸惑ったようだった。さもあらん──先程までの勝負は、ほんの少しの刀の長さが問題になるほど、ただひたすらに速さの勝負だったのだから。 あの動きに、奴の目が慣れてしまっている今こそ、この攻撃は最大の威力を発揮する。静動のはっきり別れる通常の剣術に対して、緩急自在の流水の動きを取り入れたこの……。 「剣舞!?」 その正体に気付いた緋村が、焦って繰り出した剣は蒼紫に擦りもしない。ただ、緩慢に回るような動きに見えて、その実、剣を振り下ろした時もうそこに実体はない。ゆらゆらと水の中を漂うように、相手の攻撃を躱す事ができるのだ。 必死に攻撃を繰り返す緋村に、うっそりと言葉を投げる。 「やめておけ。静動のはっきり分かれる剣術に慣れているお前では、この緩急自在の流水の動きは捕らえられまい」 防御に徹する流水の動きが、一瞬の動をもって攻撃に変わる。緋村の側面に回り込んだ蒼紫は、その一言に理不尽な思いの、全てを込めて囁いた。 「死ね」 振り返った緋村の胸に、三度、確実に小太刀の刃が食い込んだ。吹き出した血で空間が赤く染まり、声もたてずに緋村が倒れる。まったく受け身を取れていない、無防備な倒れ方だった。 殺した。 そう思った時、蒼紫の心の中で何かが壊れた。元々、殺したかった訳ではない。ただ、何故か魅かれた。会って話してみたかった。強いというならば、闘ってみたかった。 だが、もうこれは終わってしまった事……回転剣舞をまともに食らって、生きている者はいない。緋村は死んだのだ。 「剣…心…」 倒れた緋村を呆然と見詰める弥彦が、かすれた声でポツリと呟く。その横顔に、蒼紫は感情のこもらない声を掛ける。 「おわりだ、小僧。緋村抜刀斎は死んだ」 「うるせえ」 振り返った弥彦が、泣きそうな声で叫んだ。 「……次は俺が相手だ! 刺し違えても、てめえは必ずブッ倒す!!」 敵う相手ではないと判っているだろうに。刺し違えても蒼紫を倒すという程、緋村が死んだのが辛かったのか……心は痛むが、ここから先に行かせる事はできない。と、いって殺してしまうのも気が引ける。 「いい気迫だ。ここで殺すのは少し惜しいな」 小さく呟いた後ろで、何かが動いた気配がした。ピクリと頬を引き攣らせた蒼紫と泣きかけている弥彦に向かって、割合に平静な声が投げかけられる。 「……弥彦は神谷活心流の大事な後継者でござる。こんなところで死なせはせぬよ」 「剣心!」 あわてて振り返った二人の前で、緋村はゆっくりと立ち上がった。その胸には、確かに三本の鋭利な傷が刻まれている。 「それに拙者もまだ、こんなところで死ぬ訳にはいかぬ…!」 「不死身か……! 貴様」 こんな筈はない。確かに、斬ったという手応えがあったのだから。だが、その答えは程なく解明した。何故か、胸元まで引き上げられていた緋村の鞘の先が、かん高い音をたてて幾つかに割れたのだ。 ため息のように緋村は漏らした。 「……回転剣舞か……鉄拵えの鞘を丸太の様に斬るとは……」 「……そうか。とっさに鞘を引き上げ、身代わりにして威力を半減させたのか……」 鉄拵えの鞘──手応えがあった訳だ。驚きが納得に変わるにつれて、蒼紫の中に喜びが沸き上がってきた。 ここまで、蒼紫の技を躱した者は今までいない。闘い甲斐のある、求めてもなかなか得られないような男だ。そして、それとは少し別の次元で、何故か殺したくなかった。殺すのがもったいなかった。 「──大した男だ。確かに最強と言われるだけの事はある。いや、俺自身も心から認めよう。そして改めて」 この感情が何なのかは、まだよく理解らない。だが、気持ちに値するだけのものが、確かに緋村の中にある。 殺したい訳ではない。しかし、 「最強の称号を御庭番衆のものにしたくなった…!!」 この手で倒してみたいのだ。 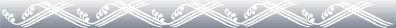
流石に荒い息を吐く緋村の回りで、もう一度回転剣舞の構えを取る。今度は殺す気はない。だが、しばらく動けなくなるくらいの衝撃は、与えるつもりだった。 ひたすらに、蒼紫の動きを目で追うだけの緋村に向かって、平静に言い放つ。 「言ったろう。この流水の動きは、お前には捕らえられない。ましてや満身創痍で動きも鈍い」 そしてもう、鞘を身代わりにする事はできない。また蒼紫とて、同じところに打ち込む訳もない。 剣舞が防御から攻撃へ移るその一瞬、緋村の瞳がきらめいたような気がした。 「終わりだ! 緋村抜刀斎!!」 横薙ぎに打ち込んだつもりの刃と交差して、逆刃刀が宙を飛ぶ。そして、小太刀の刃は緋村の合わされた手のひらに、がっちりと挟まれていた。 「……お前の流水の動き、確かに拙者には捕らえられぬ。だが、回転剣舞で攻撃に転ずる一瞬の“動”の動きなら、話は別でござるよ」 ──真剣白刃取り……ただ、手で挟まれているだけなのに、その刃、押すも引くもかなわない。完全に動きを封じられてしまった。 「剣術五百余流派通じて、唯一の徒手空拳技。拳法だけが、徒手空拳技ではないって事でござる」 今度ばかりは、驚愕を押し隠すのも間に合わない。あっけにとられた蒼紫に向かって、緋村は淡々と言い諭すように続けた。 「──蒼紫。最強の称号、そんなに欲しければいくらでもくれてやる。そんなもの拙者にはうざったいだけ……」 挟まれた刃が、凄い力で引かれる。信じられない事だが、そのまま柄を握った蒼紫の手をもぎ離そうとしている。当然、必死で抵抗はしたが、長続きはしなかった。 「今の拙者には、拙者の助けを待つ人と帰りを待つ人の方が、何万倍も──大事でござる!」 次の瞬間、奪い取られた小太刀の柄頭が、間髪入れずに蒼紫の喉元を強襲した。 「!!」 喉の内部での出血が、口から勢いよく吹き出してくる。これは先程、逆刃刀の柄頭で突かれた場所と同じ……人間の急所の一つでもある喉を、こうも強く突かれれば、いくらそれが刃物でないといっても無事ですむ訳はない。 刹那遅れて、激痛が脳天を駆け登った。同時に失血に因るものか……目の前が真っ暗になっていく。このまま意識を失えば、間違いなく蒼紫の負けだ。 ここまで──緋村を追い詰めていたというのに。 「無理するな、退け! いくらお前とて、喉笛を二度──」 気遣うように掛けられた声が、消えかけていた意識を一瞬戻した。しかし、それからの動きは意図的に行った訳ではない。半ば反射のようなものだった。 「まだだ……!!」 叫びと共に残った力の全てを込めて、緋村の頬を張り飛ばす。だが、それが精一杯だった。殴られた緋村が吹っ飛ぶのを微かに認め、蒼紫の意識は完全に暗闇に覆われた。 |

