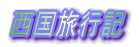
2005年10月から11月にかけて、西国33観音巡礼の旅に出た。
ここでは、今回の巡礼の旅のうち、3分の1ほどのウェイトを占める観光部分を旅行記風にブログにしたものを纏めてみた。巡礼記としては、別のページに掲載している。
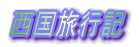
2005年10月から11月にかけて、西国33観音巡礼の旅に出た。
ここでは、今回の巡礼の旅のうち、3分の1ほどのウェイトを占める観光部分を旅行記風にブログにしたものを纏めてみた。巡礼記としては、別のページに掲載している。
第1回(その2) (2005.10.24〜10.27)
3日目 10月26日(水)

朝の勤行のため、5時半起床。6時半より本堂へ、本尊は阿弥陀如来。お勤めの僧は三人、我々は焼香のみ。参加者の半数は外人。焼香を勧めたが、断わられた。

続いて、表の護摩堂で、護摩行にも参加。規模は小さいが、本物を目の当たりにした。
朝食後、一の橋の方、裏口から奥の院へ。歩いている人も少ないと思っていたが、御廟前まで行ったら、大勢の団体客に圧倒された。それでも、団体客の後ろについて、般若心経など、一通りの読経をすませ、納経する。これでやっと、年を越してしまったが、四国88ヶ所巡礼のお礼の高野山参りも出来たとの喜びが沸いた。一寸だけ、あまりの混雑に辟易してはいたが。



一の橋の参道入り口付近 参道途中にある「父母恩重碑」 御廟橋前にて



信長墓所 参道脇の紅葉 バス停前の入り口


 帰りのケーブルカーと電車にて
帰りのケーブルカーと電車にて
9:40のバスに乗り、橋本,北野田で乗換え、 中百舌鳥から和泉中央へ。
コンビニでお握りを買ってタクシーに乗りこんだ。
運転手と路線バスがなくなったことや、その後のことなどを聞いた。仕方がないので、タクシーで往復する人や、山上のお寺から携帯でタクシーを頼む人など、いろいろいるとのこと。私も、登りで疲れたら、帰りお願いするよ、と言ってタクシーを降りた。
さあ、この坂を登って、第4番札所施福寺へ。施福寺というよりも、槙尾山であろうか。
駐車場近辺は、店もあり、なんだか人が大勢いるという感じだった。外れから急に舗装道路が急坂になっていて、ここにお寺の標柱が立っていた。傍のベンチでは、老婦人が、山に向かって祈っている。恐らく、登りきれないのを知っている方だろうとは、想像に難くなかった。これから先のことを予感させる光景だった。
舗装道路の勾配は、秩父の札立峠の登り初めと同じような感じだ。かなりきつい。ここを汗をかきながら、背中の荷物の重さを気にしながら、何とか登った。
 参道登り口
参道登り口 山門
山門 参道
参道
そこにあるのが、立派な山門。ここだけ少し勾配が少なくなっていて、ホッとするが、案内書ではここから30分とある。元気を出して、登らなければと思うが、足取りは一向に進まない。休み休み行くうちに、年上の人にも置いていかれる。
愛染堂にたどり着いたときは、もう少しという気持ちだけ。カメラを構えるが、傍へ行くとか、いい角度で撮ろうとかいう気持ちは少しも湧いてこない。
上の境内に着いた時には、ホッとして、もう取敢えず休憩。茶店の前から、下界の写真を撮ったり、33観音堂を覗いたりしてから、やっと、呼吸を整えてお参りした。  磨崖佛
磨崖佛  本堂
本堂
所が、この休憩中に、何人もの団体に抜かれていて、朱印を貰うのに、20分近く並ぶ始末。友達のいる人たちは交代で並んでいたが、こちらは座りたくなる程の疲労感の中で、やっと立っていた。かなり、いらいらしていたのだろう。朱印を貰った後は、帰りの下り坂のことしか頭になかったし、更に、その先のバス停までの道のりばかり考えていた。
従って、後で気がついたのだが、このお寺には大師堂や護摩堂もあるのだが、本堂の後ろに隠れていたのをすっかり見逃してしまった。山寺にはあるだろう不規則な堂宇の並び、それをすっかり失念していたというわけだ。苦労して登っただけに、なんとも残念なことだった。
帰りの下りは、想像していた通り、足に来ることおびただしく、注意しながら下った。
 バス停への道
バス停への道
駐車場から先は、更に3キロ。坦々とした道を歩く人はいない。少し下っていて、苦労はないが、荷物の重さは堪えた。何台もの自動車が追い抜いていくが、止まって「乗りますか」とは聞いてくれない。手を上げれば、止まってくれたかも知れないが、それはためらう気持ちが強かった。達成感が激減するような気がしたから。
1時間足らず歩いて、バス停にやっと着いた時、バスが出たばかり。それから30分ほど地べたに座り込んでバスを待った。
4日目 10月27日(木)
朝7時から、フリーの食事は有難い。少しだが、早めのスタート。
第5番札所藤井寺は開いていて、出勤途中のサラリーマンが立ち寄り、お参りしている。

 二つの門
二つの門
駅から近い方の門は小さいが、四脚門は立派な造りであった。
本堂で立ってお経を上げたが、後から来た人は座っていた。成る程、じゅうたん敷きだ。
邪魔されず、ゆったりお参りできた。
取って返す電車は、通勤電車。近鉄は満員。しかし、地下鉄はもう座って行けた。
第24番札所中山寺も町の中。
参拝者は多いが、団体がいないので助かる。エスカレーターなどついていて、参拝者の便を図っている。


 境内にて
境内にて
高みにあるので、宝塚からの町並みが見える。新しい雰囲気のお寺だった。
少し早めに回っていたが、勝尾寺行きのバスは一日三本。たっぷり時間があった。昼食を食べるところを探したが、結局、パンを買って広場で食べた。バスに乗って何分か、車窓に見える千里の町はどこまで行っても同じ雰囲気の感があった。どこか無機質な、造られた市街地の中をバスが走る。バスは満員、年寄りが4、50分を立って乗っていた。
第23番札所勝尾寺は、山門付近も工事中で、新しげなお寺。商売をやっている雰囲気もあって、あまり好きになれない。大きな本堂も、外からは何もなく、その前で読経するしかない。内陣へは、供養を頼んだ人だけが入れる。
 二階堂を望む
二階堂を望む 
帰りのバスは、往復一緒の人がいた。満員で立ったまま。
第22番札所総持寺も街の中。方向だけ決めて歩くが、街に埋没していて、迷子になったかと思った。もっと大伽藍かと思っていたが、立派なのは、寺務所だけ?かな。今回の最後なので、ゆっくりフルコースで読経。最初で最後の鐘も撞いた。大師堂でも般若心経を。

 左本堂、右閻魔堂
左本堂、右閻魔堂
30分ほど早くお参りできたので、1本早いひかりで帰京。さすがに疲れ、新幹線の中ではよく寝た。
第2回に続く 前のページに戻る