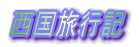
2005年10月から11月にかけて、西国33観音巡礼の旅に出た。
ここでは、今回の巡礼の旅のうち、3分の1ほどのウェイトを占める観光部分を旅行記風にブログにしたものを纏めてみた。巡礼記としては、別のページに掲載している。
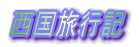
2005年10月から11月にかけて、西国33観音巡礼の旅に出た。
ここでは、今回の巡礼の旅のうち、3分の1ほどのウェイトを占める観光部分を旅行記風にブログにしたものを纏めてみた。巡礼記としては、別のページに掲載している。
第2回 (2005.11.7〜11.10)
1日目 11月7日(月)
夜来の雨が、早く上がったようで、表に出ると青空が広がっていた。少し残った雲に朝日が当たって、今回の旅の幸運を感じる。
長い新幹線の旅、倹約をして「ひかり」に乗ったのだ。名古屋を過ぎると、流石に寝疲れてきた。日除けを少し上げて、外を見る。
関が原辺りでは、点々と見える紅葉がきれいだ。
姫路は、立冬というのに、暑いくらいで、シャツになって、袖をまくる。すぐにバス乗り場が見つからなかったので、近くでびらを配っている若い女性に尋ねたが、分からないと言う。仕方なく大通りの両側に点在するバス停をしらみつぶしに見て歩いたが、ない。もう一度、駅に戻って、聞いてみようと思ってロータリーの反対側に来たら、ありましたーーバスはそこそこ込んでいて、思いがけないほど、狭い道を曲がりくねって走った。20分以上走って、想像していたような終点、書写山ロープウェー下に着く。
ロープウェーを降りると、そこはもう第27番札所圓教寺の寺領なのであろう、志納所がある。少し登ったところで、小休止して、バス停を探しながら買った、お握りの昼食とした。紅葉が、少しずつ始まっていた。




参道途中からの風景、山門、路傍に並ぶ33観音像
参道は苦労なしで本堂までたどり着けるのかと思っていたら、33観音像を拝みながら、それなりの急な東坂を登り、仁王門に着く。趣のある、好い門だ。寿量院を過ぎると、道はだらだらと下り、やがて、湯屋橋に出る。 ここから摩尼殿を仰ぎ見ると、さすがの造りという感がある。舞台造りの摩尼殿の舞台から下を見ると、人がいなければ、時代を勘違いしそうな景観だ。
ここから摩尼殿を仰ぎ見ると、さすがの造りという感がある。舞台造りの摩尼殿の舞台から下を見ると、人がいなければ、時代を勘違いしそうな景観だ。 


 笠塔婆
笠塔婆 露座仏
露座仏 常行堂舞台
常行堂舞台
山道を少し歩いて、映画で有名になった三つのお堂の前に出る。大講堂、食堂、常行堂はそれぞれの風格を持っている。建物としては、大きいという感覚以外は、驚くようなことはないのだが。更に、開山堂、鐘楼から、人影の少なくなった弁慶の井戸の方まで回った。




境内にあるお堂群 法華堂、金剛堂、護法堂、観音堂


 鐘楼
鐘楼
弁慶の護法石、鏡池(弁慶は7歳から10年ここで修行した)
今は、昔の山岳信仰の道場という面影よりも、ハイキングコースとか観光地の様相を呈しているようだが、広大な敷地の中に、これだけのものを残しているということはすごいことだ。大きければ好いというものではないが、33の札所の中では、満足の出来るお寺だと思う。
まだ、時間があったので、バスで戻る途中、姫路城に立ち寄った。何回も外からは見ていたのだが、中に入るのは始めて。時に、団体の後ろについて、説明を聞いたり、興味のある所を遠回りしてみたり、ゆっくりと、天守閣まで上った。特に、西の丸の渡櫓を歩いたのが面白かった。
2日目 11月8日(火)
8時過ぎに南口の駅レンへ。何も問題なくスタート。最初は慣れない車に少し緊張気味だったが、車の数も多くないし、道幅も問題ない。只、黄色でもお構いなしなのが怖かった。ルートナビで調べてあった道はやめて、車のナビを信じて走ることにした。非常にスムーズ。次第に国道の車の数も少なくなった頃に、右折し、山に分け入った辺りにお寺第26番札所一乗寺はあった。
入り口に車を止め、境内に入る。右手のかえでの美しさに目を奪われた。 何も装飾のない佇まいが好きだ。人影のない石段を登ると、正面が本堂だが、現在改修中。
何も装飾のない佇まいが好きだ。人影のない石段を登ると、正面が本堂だが、現在改修中。  仮本堂 左手の常行堂が仮本堂になっている。仮とは言え、立派なお堂である。お堂の前の、これはまさしく仮のプレハブの中で、朱印を頂く。
仮本堂 左手の常行堂が仮本堂になっている。仮とは言え、立派なお堂である。お堂の前の、これはまさしく仮のプレハブの中で、朱印を頂く。
 境内
境内  奥の院へ
奥の院へ
一番上に、建築中の本堂があり、奥の院へ通じる道もあったが、朝の冷気が漂う山内を、ぐるっとひと周りして、石段下まで降りてきた。この辺りに来て、やっと一組の参拝者と出会った。
 ここ第25番札所清水寺のある社町は、以前、ここの集乳所に友人がいた関係で、覚えている町だ。国道とは言え、殆ど渋滞のない道路を走り、国道から分かれた道を更に側道へと入る。有料の自動車道を行くと大きな駐車場があった。少し前に着いたらしい夫婦連れが、仁王門の前で写真を撮っていた。美しい山門だが、何故か,仁王様は金網に守られていた。薬師堂にある十二神将のうち、丑年の分をカメラに収めた。大講堂で読経して、根本中堂へ。中に入れるようになっていたので、中に入り座る。深閑として、誰もいず、静寂と荘厳な雰囲気の中で、再び読経した。何故か、度々災害に遭っているお寺のようで、台風被害の爪痕も残っていた。再建された堂宇が多いにも拘らず、山中にあって、雰囲気のいいお寺だった。
ここ第25番札所清水寺のある社町は、以前、ここの集乳所に友人がいた関係で、覚えている町だ。国道とは言え、殆ど渋滞のない道路を走り、国道から分かれた道を更に側道へと入る。有料の自動車道を行くと大きな駐車場があった。少し前に着いたらしい夫婦連れが、仁王門の前で写真を撮っていた。美しい山門だが、何故か,仁王様は金網に守られていた。薬師堂にある十二神将のうち、丑年の分をカメラに収めた。大講堂で読経して、根本中堂へ。中に入れるようになっていたので、中に入り座る。深閑として、誰もいず、静寂と荘厳な雰囲気の中で、再び読経した。何故か、度々災害に遭っているお寺のようで、台風被害の爪痕も残っていた。再建された堂宇が多いにも拘らず、山中にあって、雰囲気のいいお寺だった。



本堂、宝匡印塔、本坊




境内の紅葉、こん浄水、仁王、十二神将
清水寺から三田まで、ナビの言う通りに走った。JRに沿った道から、車が走っていない、素晴らしく良い道を通り、県道から取り付け道路を上る。勾配のきつい参道の上に小さな駐車場があった。
すぐ横に番外花山院山門がある。規模は全てこじんまりとしている。巡礼中興の祖である花山院が崩御した場所である。本堂の向かいにある、御廟所に供養塔が立っている。境内から、有馬富士や千丈寺湖など周辺の景色が良く見えた。

 本堂、薬師堂、大師像
本堂、薬師堂、大師像



有馬富士、鐘楼、境内にて
朱印を貰った時、お車ですか?と尋ねられ、[はい]と答えて、維持費を支払った。
三田では、駅レンの入り口が見つからず、GSで聞いてから返却。2時間のアヘッド。予定を変更して第9番札所南円堂に行くことにした。予定外のことで、乗換駅を間違えそうになったが、無事に鶴橋から快速急行に乗れて、30分で奈良へ。
近鉄奈良駅前は奈良公園に向かう人と戻る人で混雑していた。
 奈良公園
奈良公園
人の流れに従って、南円堂へ曲がる道を一つやり過ごし右折、国宝館、東金堂を横に見て五重塔へ。五重塔からは正面に南円堂が見える。相変わらずの人ごみだが、ゆったりとした感じが好い。手を洗い、荷物を置く場所を探していると、一匹の鹿がすっと近づいてきて、じっとしている。まるで写真を撮ってくれと言うようだったので、カメラを取り出し、南円堂をバックに写真を撮った。その間、鹿はじっと待っていてくれた。ひょっとしたら、私に安らぎをくれる仏の鹿かも知れない。

観光客の邪魔にならないように、横から経を上げる。この環境ではなんとも落ち着かない。まあ、観光地なんだから止むを得ないかとあきらめ納経所へ。納経をする人は少なく、朱印はすぐに貰えた。
 仮金堂
仮金堂  南円堂
南円堂
ここで、北円堂の開扉があり、是非見ていきなさいと勧められた。北円堂は外から見ても、静かで味のある佇まいをしていた。300円を払って、堂内へ。正面の弥勒如来像。さすがと思わせる運慶の作品だ。加えて、無著・世親菩薩像。すっかり開け放たれた扉にも拘らず、薄暗い堂内で、暫しの時間を過ごした。これだけの作品を、300円の拝観料で拝見するのは、申し訳ないようだった。  北円堂
北円堂  猿沢の池から五重塔を見る
猿沢の池から五重塔を見る
北円堂を出て、三重の塔から猿沢の池に行く。ここは有名な撮影スポット。しかし、夕べの気配が濃くなりつつあり、好い写真は無理のようだった。興福寺を大きくもう一回りして、駅に向かった。
特急で、西大寺から橿原神宮へ。 古い看板の宿を見て、これはこれは、昔懐かしい和風の宿だった。